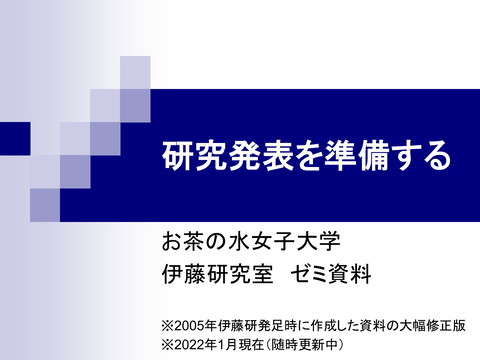国際会議運営記(論文委員長編)
0.9K Views
November 15, 25
スライド概要
IEEE PacificVis 2024/2025 で論文委員長を務めた経験に関するスライド。
お茶の水女子大学 共創工学部文化情報工学科/理学部情報科学科 教授
関連スライド
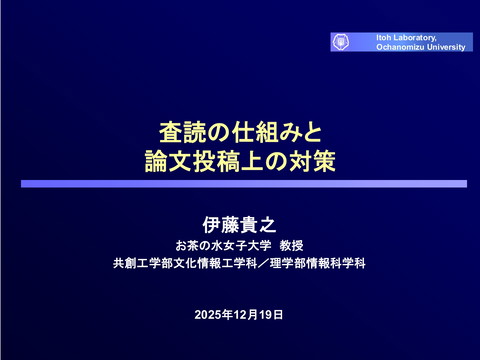
査読の仕組みと論文投稿上の対策
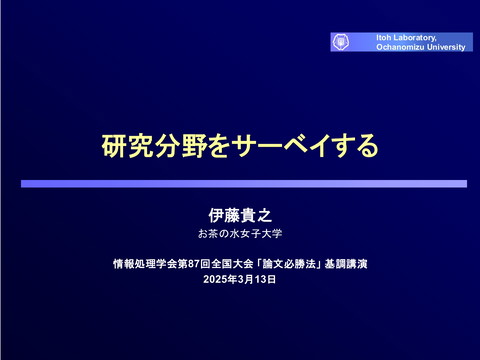
研究分野をサーベイする
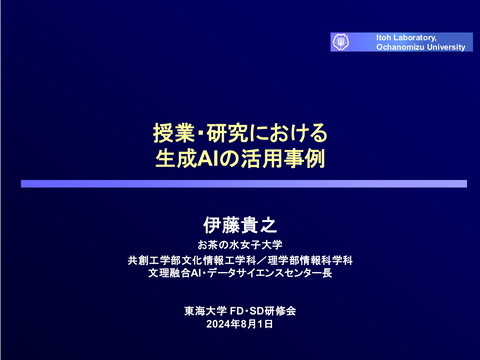
授業・研究における生成AIの活用事例
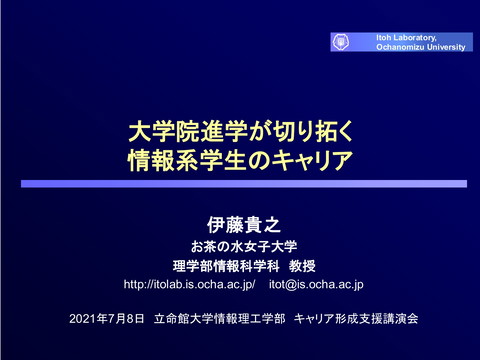
大学院進学が切り拓く情報系学生のキャリア
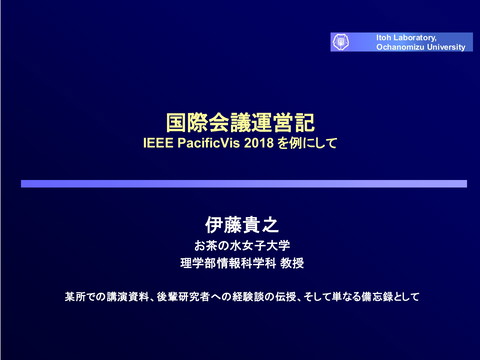
国際会議運営記(実行委員長編)
各ページのテキスト
Itoh Laboratory, Ochanomizu University 国際会議運営記 (論文委員長編) 伊藤貴之 お茶の水女子大学 共創工学部文化情報工学科/理学部情報科学科 教授 某所での講演資料、後輩研究者への経験談の伝授、そして単なる備忘録として
目次 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 本資料の前提 • 論文委員会の仕事一覧 • 苦労・収穫・その他 • 何のために会議運営を引き受けるのか 1
情報科学系の国際会議の委員会構成 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 国際会議委員会のよくある構造 国際会議 実行委員長 会計委員 出版委員 現地委員 広報委員 プログラム委員長 論文委員長 論文委員長 論文委員長 …委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 論文委員 実行委員会 プログラム委員会 ※情報科学系では国内の査読付き会議もこの仕組みを採用する会議が多い 2
情報科学系の国際会議の前提知識 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 運営は「実行委員」と「プログラム委員」に分かれる – 実行委員: 会場管理、参加登録、会計、懇親会など – プログラム委員: 投稿受付、査読進行、プログラム編成など • プログラム委員会は「委員長」と「委員」に分かれる – 委員長は委員に論文を割り振る – 委員は査読を担当する and/or 外部査読者を探して指名する • 大規模な会議ではプログラム委員会も細分化される – 論文投稿の各カテゴリごとに小さなプログラム委員会が編成される – プログラム委員と呼ばずにカテゴリごとに「〇〇委員」と呼ぶことも • 本資料では細分化された各カテゴリの委員長を 「論文委員長」と称することにする ※情報科学系では国内の査読付き会議もこの仕組みを採用する会議が多い 3
本資料の概要 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 主に情報科学系の国際会議における 論文委員長の以下の業務 – 論文投稿の受付 – 査読の統括 – 最終採録論文の確定 – プログラムの編成 について紹介する 4
筆者が論文委員長を担当した国際会議 Itoh Laboratory, Ochanomizu University IEEE VIS 2023 October 22-27 2023, Melbourne IEEE PacificVis 2024 April 23-26 2024, Tokyo IEEE VIS 2024 October 13-18 2024, St. Pete Beach IEEE PacificVis 2025 April 22-25 2025, Taipei 5
筆者が論文委員長を担当した国際会議(1) Itoh Laboratory, Ochanomizu University • IEEE VIS – 可視化分野のトップ国際会議 – 10月中旬~下旬に世界各地で開催 – 主な内容 • フルペーパー/ショートペーパー/ポスター/パネル • 各種のワークショップ – 筆者は2023,2024年の ショートペーパー委員長を担当 • 2023年: 151件投稿・51件採択 • 2024年: 207件投稿・66件採択 6
筆者が論文委員長を担当した国際会議(2) Itoh Laboratory, Ochanomizu University • IEEE PacificVis – 可視化に特化した国際会議で3番めに著名な会議 – 4月中旬~下旬にアジア各地で開催 – 主な内容 • ジャーナルトラック論文/カンファレンストラック論文/ ノーツ(ショートペーパー)/ポスター – 筆者は2024,2025年の カンファレンストラック論文委員長を担当 • 2024年: 89件投稿・27件採択 • 2025年: 100件投稿・27件採択 7
目次 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 本資料の前提 • 論文委員会の仕事一覧 • 苦労・収穫・その他 • 何のために会議運営を引き受けるのか 8
論文委員長の主な仕事 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • • • • • • • • • • • CFPおよびウェブの制作 論文委員の招待 投稿システムのセットアップ 投稿論文の管理とクイックリジェクト 査読者への論文割り当て 査読進捗および議論のチェック 最終結果の確定と通知 最終論文提出の確認 セッションの編成 セッション座長の指名 会議オープニングでの説明 9
論文委員長のタイムラインの例 Itoh Laboratory, Ochanomizu University 9か月前: CFPおよび ウェブの制作 8か月前: 論文委員 の招待 投稿論文チェック 査読希望調査 (1週間) 査読割り当て 査読期間 (4週間) 8か月前: 投稿システムの オープン 6か月前: 投稿期限 (システムの クローズ) 査読者間の 議論(1週間) 採否結果の 確定と通知 (数日) 論文投稿まで 1回目査読 条件付採録論文 再提出待ち (1か月) 査読割り当て 査読期間 (3週間) 採否結果の 確定と通知 (数日) 2回目査読 2か月前: 最終論文確認 セッション編成 1か月前: 座長の指名 1週間前: オープニング準備 会議当日まで 10
CFPおよびウェブの制作 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • CFP (Call for Paper: 論文募集) の文面制作 – 第1回開催でない限り、前回の文面の更新 – 日程 (投稿期限日、採否通知日など) の調整 • 前年度との会議開催時期の違いによる調整 • 同一会議の他のトラックの都合による調整 • その他、前年度の反省を踏まえての調整 – 必要があれば書式や投稿形式の更新 • ウェブの制作 – 基本的にはウェブデザイン担当者が用意した雛形にCFPをはめるだけ 11
論文委員の招待 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 委員長が人選する – 第1回開催でない限り、主に前回までの委員を招待する • 原則として投稿システムから招待する – 辞退や無反応も多いので、必要人数の2倍くらい招待する – 辞退者が推薦した人も積極的に招待する • 人選のローカルルールの例 – 同一会議内の複数のトラックの委員を同時に引き受けない – 〇年委員をやったら1年休み(通称サバティカル) – 所属国や性別の多様性担保に努める 12
論文システムのセットアップ Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 投稿期限の2か月ほど前に論文を投稿可能な状態にする – フォームの記入欄を定義する (著者名、タイトル、概要、備考、その他…) – 添付ファイルの可否を設定する – 必要があれば期日等を設定する • 論文投稿期日には論文投稿を閉じる – 会議によってはアブストラクト投稿期限と原稿提出期限を別々に設ける 13
投稿論文の管理 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 投稿期日が来たら委員長は全ての論文をチェックする • 以下の投稿を取消扱いにする – アブストラクト等のみが提出されていて原稿が提出されていない – 原稿ファイルを開くことができない – その他、査読が不可能な投稿 • 以下の投稿を早期返戻 (desk reject) 扱いにして著者に通知する – 原稿書式が著しく異なる – 論文の品質が著しく低くて読むに値しない – 明らかに分野外の内容である – その他、査読者に割り当てるにふさわしくない投稿 14
査読論文の割り当て Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 投稿一覧を論文委員に提示して希望査読論文を選んでもらう – 「査読したい」「査読したくない」「著者に近すぎるので不可」などの 選択肢を各論文に対してマークしてもらう (Biddingという) – アブストラクト期限後(原稿提出前)に開始してもよい • 論文委員の希望に沿って査読を割り当てる – 論文委員長でオンライン会議を開いて作業を進めることが多い – 投稿システムの自動割り当て機能を使って初期割り当てを決める – 負担の均一化などを図るために割り当て結果を調整する • 論文委員に査読割り当て結果を一斉通知する – 通知メールを事前に丁寧にチェックする必要がある 15
査読進捗の確認 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 論文委員が外部査読者の選出と依頼を必要とする場合: – 期日までに外部査読者を登録できているかを確認する – 期日前後に外部査読者の登録をリマインドする • 査読期限前に – 各査読者が査読を終えているかを確認する – 期日前後に査読入力をリマインドする • 査読者間の議論を必要とする場合 – 議論を進めるようにリマインドする – 各論文の代表(プライマリという)論文委員に記事までに議論の結論を 入力するようリマインドする 16
最終査読結果の確定と通知 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 全論文の議論と結論を委員長が1つずつチェックする – 論文委員長でオンライン会議を開いて作業を進めることが多い (コロナ禍前は対面会議開催も多かった) – 確実に採録/確実に不採録の論文から先にチェックして、 当落線上の論文をあとから丁寧にチェックすることが多い – 査読コメント上に不適切な表現等がないかも確認する – 全ての論文について最終的な採否結果をつける • 自動送信メールで全著者に一斉通知する – 通知メールを事前に丁寧にチェックする必要がある 17
2回目査読がある場合 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 2回目査読があるトラックと2回目査読がないトラックがある • 2回目査読がある場合、以下の処理が続く – 2回目投稿受付ようにシステムをセットアップし、投稿を管理する – 1回目投稿と同じ論文委員に2回目投稿を割り当てる – 期日までに査読の結論を提出してもらう – 委員長が1本ずつ論文をチェックする 論文委員長でオンライン会議を開いて作業を進めることが多い • 自動送信メールで全著者に一斉通知する – 通知メールを事前に丁寧にチェックする必要がある 18
最終論文の提出確認 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 採録が確定した論文の提出状況を確認する • 提出された最終論文をチェックする – 書式の誤りがないか – 付録ファイル等は正しく開けるか – それ以外の提出物は適切に用意されているか • 著者からの連絡事項があれば確認する – 発表者は誰か – ハイブリッド開催の場合、発表は現地か遠隔か 19
セッションの編成・座長の選出 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 実行委員長などからタイムテーブルが渡されるので、 所定の時間帯に採録論文を割り振る – 採録論文は多様なジャンルの論文にまたがるので、 うまく所定の本数ずつにジャンルを区切って論文を分ける • 各セッションの座長を選出して内諾をとる – 別セッションの論文著者(会議出席の可能性大)から選ぶか、 あらかじめ参加登録者一覧をもらってその中から選ぶなど – 断られる可能性も高いので、最初から複数の人に打診する 場合もある 20
会議オープニングでの説明 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • オープニングで登壇し、投稿や査読の経緯を説明する • 主な説明内容の例 – プログラム委員の構成 – 査読の手順と方針 – 論文投稿数と採択数・採択率 – プログラム(セッション一覧) – 優秀論文賞の紹介とその選出手順 21
目次 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 本資料の前提 • 論文委員会の仕事一覧 • 苦労・収穫・その他 • 何のために会議運営を引き受けるのか 22
苦労(1): 委員への打診や連絡 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 論文委員の招待を引き受けられない人も多い – 経験的に言って約半分が「辞退」または「回答ナシ」 – 後になって「やっぱり無理」という人も現れる • 査読の遅延がしばしば生じる – 催促しても返事が来ないことがよくある (体調不良、メールアドレス変更など) • 査読者間の議論が進まないこともある – 催促しても誰も発言しないことがある • 査読内容や議論内容の問題 – 1,2日で書き直してほしいと依頼することも 23
苦労(2): 査読割り当てのパズル Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 査読希望調査結果に偏りが生じやすい – 誰も査読を希望しない論文がある場合も • できるだけ多くの人の希望に沿いつつ、 かつ全員の割り当て論文数を均一化する – かなり無理のあるパズル – 委員長の数時間のオンライン会議でなんとかする • 割り当て後にも要望が来ることがある – 「この論文は絶対に自分には無理」という類の要望 →局所的な割り当て修正が発生する 24
苦労(3): 採否判定の最終作業 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 論文のかなり多くは当落線上にある – 査読の点数が正規分布に近くなるため • 委員長による長時間の会議により採否を決める – 明らかに採録・明らかに不採録という論文を最初に処理する – 当落線上にある論文について、査読コメントや査読者間議論を読み どの程度本質的な問題があるかを洗い出す – この作業を論文1本1本について繰り返すので時間を要する – 結論を出せない論文だけを最後に集めて再度議論する • 採否判定会議の時点でまだ査読が不完全な論文もある – 採否決定理由のコメント等を突貫工事で埋める (採否通知までの1,2日間での時間との勝負) ※学会によっては委員長だけでなく委員も参加して大きな会議を開くこともある 25
苦労(4): プログラム編成 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 採録論文の分類が難しい – セッション数(および各セッションの論文数)が指定される – ちょうどいい数の「関連性の高い論文群」を作るのが難しい – タイトルだけから論文内容を判断できない論文は 論文本体も読んだ上でセッション分けを考える必要がある • 座長探しに時間がかかる – そもそも各セッションで「分野が近くて共著論文がない人」 を候補に挙げるだけでも一苦労 – 参加登録者名簿を渡されてその中から選ぶ場合には 分野が合致する人が見つからないことがある – 参加登録者名簿が渡されない場合にはやみくもに 依頼しては断られ…を繰り返しがちになる 26
苦労(5): メールでの多数の問い合わせ Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 論文募集に関する質問 – 論文投稿に不慣れな人からの初歩的な質問 – ウェブの掲載内容の微細なミスに関係ある質問 – 提出期限延長の要望など • 査読結果に対する質問 – 単なる不満解消のメールも時々来る • 採録後の最終原稿提出に関する質問 – 書式の修正 – 学会への著作権譲渡の手続きなど • 発表日時に関する要望 27
たくさん引き受けるとややこしい Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 主要国際会議の論文委員長を2年で4件 →2つの国際会議の運営が重なり続ける VIS2023 PacificVis2024 VIS2024 PacificVis2025 2023 2024 28
収穫? Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 新しい知人ができる – 委員との間に共同研究が生まれた – 「近いうちに招待講演に来てよ」の類の声もあった – 学生の研究留学先として迎えてくれるかもしれない人もいた – 研究の質問や相談ができそうな人もいた – 他にも一緒に何かする相手になるかもしれない人ができた • 研究分野の動向を早く知る – 新しいトピック、政治的な仕組み、コミュニケーション手段など • 実行委員のインセンティブ – 参加費の割引、実行委員のみによる食事会など 29
筆者の通常業務はこんな感じ Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 研究・研究指導 – ワンオペ研究室で学生約30人 – 自分自身の研究ネタ(実装・実験・発表) • 教育 – 春学期・秋学期とも授業は週4コマ • 学内用務 – AI・データサイエンスセンター長の全学教育業務 – ジェンダード・イノベーション研究所研究員の業務 – 2学科を兼担していて各々の学科での運営業務 • 学外貢献 – 国内学会の副会長・その他の学会の業務多数 – 招待講演の類が多数 ※これらの業務の合間に論文委員長の仕事がある 30
目次 Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 本資料の前提 • 論文委員会の仕事一覧 • 苦労・収穫・その他 • 何のために会議運営を引き受けるのか 31
何のために会議運営を引き受けるのか (1) Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 自国を代表して – 世界各国の研究者で一緒に会議を盛り上げるための存在となる • 自分の活動拠点は自分で作る – 自分だけのためでなく学生の発表場所という意味でも • 恩返し – 他の年に開催してくれる他国の方々へ – 自分が研究者になるまでの場を与えてくれた先輩諸氏へ (後輩の発表の場を作るという形で返す) – お世話になった研究者仲間からのお誘いへ 32
何のために会議運営を引き受けるのか (2) Itoh Laboratory, Ochanomizu University • 研究者人生へのフィードバック – 自分の名前を売る – 学会運営の方法論を蓄積する – 学会の裏の仕組みを知って今後の論文投稿の参考にする – 海外参加者との面識を深めて共同研究・共同獲得資金に活かす – 転職や昇進のためのハクをつける (論文の本数で他者と差がないので学会運営の経験を重視する、 という人事評価もあるかもしれない) • 自分が楽しむ – 単なる参加者に終わるより盛り上がれる – 大きな会議をデザインする喜び 33
Itoh Laboratory, Ochanomizu University もし論文委員長の就任打診が届いたら 日本のアカデミックな国際貢献のためにも ご自身の今後のキャリアと名誉のためにも ぜひお引き受けいただくことを勧めます この資料がどなたかの参考になることを祈ります 国際会議運営の仕事が 研究者や学生の皆さんに知られることを願っています 34