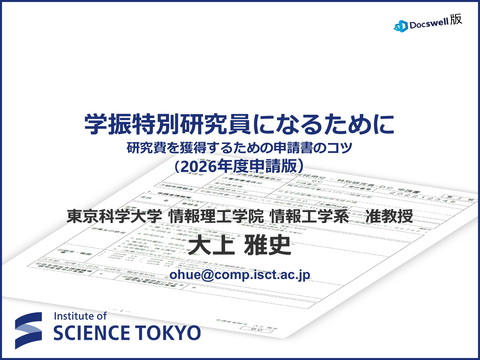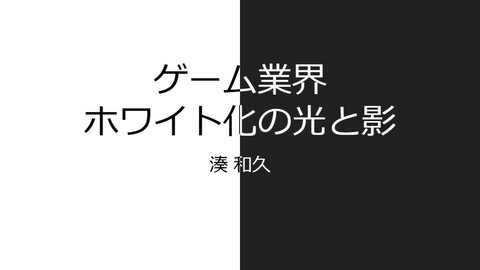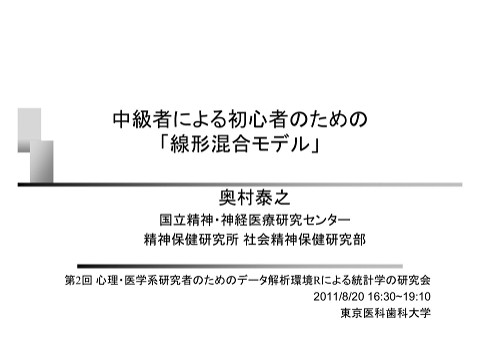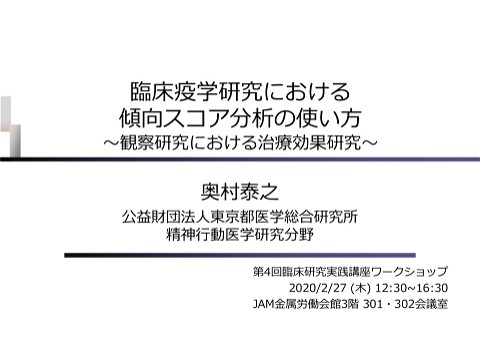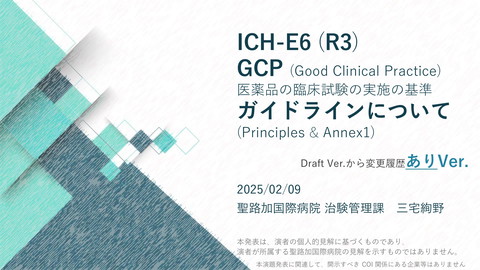ロボコンの電波の話
3.8K Views
November 17, 25
スライド概要
ロボコンの電波管理、対策、選定で悩んでいる人向けに作成した資料です。一助になればと思います。
関連スライド
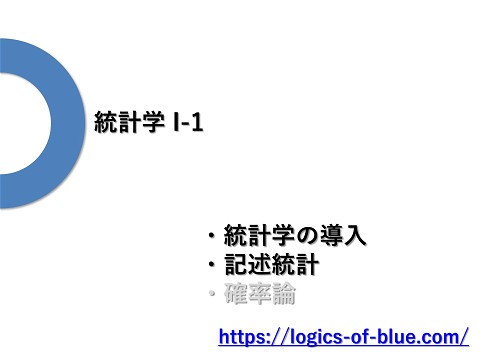
統計学I-1
 Logics of Blue
297.9K
Logics of Blue
297.9K
各ページのテキスト
ロボコンにおける 電波の話2025
アジェンダ 01 とりあえずこれはやろう 取付方法でできる電波対策 02 プロポでできる電波対策 (16IZS+TM-18でできること) 03 電波の話 基礎編 04 電波の話 規格の話
01.とりあえずこれはやろう 取付方法でできる電波対策 • 一般的な棒状のアンテナは軸方向に対しての出力が弱いため、 送信機と受信機のアンテナが側面同士が向き合うように配置する • 送信アンテナの近くに金属部品を取り付けない • 受信アンテナのアンテナ線は金属に触れさせない • 受信機本体をアンテナやモータから遠ざける • アンテナを2本使用して通信する場合はアンテナが直交するように 配置する(受信機側は特に) • 2つの帯域を使う場合、サブ周波数のアンテナはメイン周波数の アンテナの向きとは違う方向に向ける
02.プロポでできる電波対策 (16IZS+TM-18でできること) ①2.4GHzと920MHzで常に通信のやり取りをしている ②2.4GHzが切れたときに920MHzに切り替わる ③2.4GHzの通信が復帰すると2.4GHzで通信再開する 普段は2.4GHz帯 で受信した信号で動く (920MHz帯でも同じ信号 を送っている) 2.4GHz帯が切れても 920MHz帯で同じ信号を 送っているので、遅延無く 信号が切り替わる 2.4GHz帯の電波 920MHz帯の電波 × 2.4GHz帯の電波 920MHz帯の電波
03.電波の話 基礎編 ~そもそも電波とはなんぞ~ • 電波とは:周波数が3THz以下の電磁波の総称 • 電波は電気と波の両方の性質を持っている 電気的性質:金属などの導電体に吸収される 波の性質 :反射、屈折、回折が起きる
03.電波の話 基礎編 ~周波数・伝送速度と通信距離の関係~ • 伝送速度:「○○Mbps」とか「○○Gbps」と書かれているやつ。 bps(bit per second)は1秒間あたりに送受信できるビット数 を示している 周波数が異なる場合 • 周波数が高い:直進性良、一度に送信できるデータ量大、回折性悪 • 周波数が低い:回折性良、直進性悪、一度に送信できるデータ小 同じ周波数で伝送速度が異なる場合 • 伝送速度が速い:時間単位で送れるデータ量大、通信距離が短くなる • 伝送速度が遅い:時間単位で送れるデータ量小、通信距離が長い
03.電波の話 基礎編 ~電波法を守りながら使うには~ ①技適のマークが付いている ←これは 旧マーク ②無線モジュールの場合、モジュールとアンテナの組み合わせ が合っている(認証取得時に登録されているアンテナ以外 は基本的に使えない) ③技適マーク、認証番号が常に見える状態になっている ④既製品のコントローラの場合、 スイッチの追加などの改造をしない
03.電波の話 基礎編 ~覚えておくと良い用語 その1~ ①キャリアセンス 送信を開始する前に他の無線局が自チャンネルを使用していないか確認し、 他無線機が自チャンネルを使用中であれば、同一周波数での送信を行わないこ とで干渉を回避する仕組み。電波は先に出している人が使えるのが基本。 先に使っている人に対して、ここのチャンネルを使いたいから他の帯域を 使ってくれと言うのは基本的に認められない話なので注意 ②DFS(Dynamic Frequency Selection) 特定の屋外用チャンネル(5.6~5.7GHz帯)において、気象レーダーなどの電波を 検知した場合に他のチャネルへ変更する機能。一般的なルーターはチャンネル の切替に1分以上かかる
03.電波の話 基礎編 ~覚えておくと良い用語 その2~ ③周波数ホッピング方式 送信側と受信側でホッピング・シーケンスやホッピング・パターンと呼ぶ 一定の規則を規定し、それに従って一定の通信帯域の中で高速に通信周波数 を切り替えて、通信を行う方式。Bluetoothは周波数ホッピング方式 ④直接拡散方式 送信データよりも遥かに広い周波数にエネルギーを拡散して通信する方式。 送受信双方が保持する「拡散符号」と呼ばれる鍵に基づいて演算を行う。 昔のWi-FiやZigbeeは直接拡散方式
03.電波の話 基礎編 ~覚えておくと良い用語 その3~ ⑤OFDM変調 一つの信号の各ビットを多重の周波数に割り当て、周波数をフーリエ変換で 変調し、逆フーリエ変換で復調することでフェージング(外部の電波環境の 変化)に強い方式。最近のWi-Fiに使われている。 ⑥感度抑圧 受信機において、妨害波が希望波の周波数に近すぎると、受信機の高周波 増幅回路や周波数変換回路が飽和状態になり、希望波の信号レベルが低下し、 受信感度が悪化してしまう現象。 人間でいうと会話している2人の間に騒いでいる人がいると会話が聞き取り づらくなるのと同じ現象
04. 電波の話 名称 FASSTest (Futaba Advanced Spread Spectrum Technology extended system telemetry) FASST (Futaba Advanced Spread Spectrum Technology) T-FHSS AIR (Third-generation Frequency Hopping Spread Spectrum for Air) S-FHSS (Second-generation Frequency Hopping Spread Spectrum) AdRCSS (Advanced Radio Control System for Sub-GHz band) 規格の話~双葉プロポ~ ロゴ 通信方法、特長 周波数ホッピング方式と直接拡散方式 のハイブリッド 双方向通信が可能 (センサデータのやり取りが可能) 周波数ホッピング方式と直接拡散方式 のハイブリッド 単方向通信 周波数ホッピング方式 双方向通信が可能(センサデータのやり 取りが可能) 周波数ホッピング方式 単方向通信 周波数ホッピング方式 920MHz帯を使用するバックアップ システム用プロトコル
04. 電波の話 バージョン 規格の話~Wi-Fi~ 使える周波数 特長 Wi-Fi 4 2.4GHz、5GHz 通信速度:660Mbps どちらかの周波数帯を使用 Wi-Fi 5 5GHz 通信速度:6.9Gbps Wi-Fi 6 2.4GHz、5GHz 通信速度:9.6Gbps 両方の帯域を同時に使用可能 Wi-Fi 6E 2.4GHz、5GHz、 6GHz 2.4GHz、5GHz、 6GHz 通信速度:9.6Gbps いずれかの周波数帯のみ使用 Wi-Fi 7 通信速度:46Gbps 5GHzと6GHzを同時使用可能
04. 電波の話 規格の話~Wi-Fi~ • ルーターを背負うのはアリか? →現状すぐ使える製品がルーターしかないので仕方ないが、 お勧めはできない • お勧めできない理由 ①そもそも置いて使う製品なので常に振動が起きる場所が想定されて いない製品が多い ②そもそも置いて使う製品なので人という電波吸収体が近くにいる状態 が想定されていない製品が多い ③ロボット側のルーターがアンテナを外に出しづらい →安定通信環境を作りづらい
04. 電波の話 バージョン Bluetooth 4.0 使える周波数 2.4GHz 規格の話~Bluetooth~ 特長 転送データをシンプルかつ最小限に抑えることで、 大幅な低消費電力化を実現(BLE) Bluetooth 4.1 省電力機能がさらに発展したバージョン Bluetooth 4.2 セキュリティの強化と転送速度の高速化 Bluetooth 5.0 Ver.4.0に比べて、データ転送速度が約2倍、通信範囲が 約4倍に向上 Bluetooth 5.1 方向探知機能を追加 PS5のコントローラ(デュアルセンス)はこのバージョン Bluetooth 5.2 LE Audio規格(Bluetoothの音声規格)を追加 ※PS4のコントローラはBlutooth 2.1 SwitchのプロコンはBluetooth 3.0
04. 電波の話 規格の話~920MHz~ • Wi-SUNという世界共通規格はあるものの、独自規格の製品が多い • 周波数としてのメリット ①回折性が比較的良い ②入手性が悪くない ③無線モジュールタイプがほとんどなので、通信部分を小型にしやすい ④法改正で周波数ホッピング方式ならキャリアセンス不要で通信できる帯域ができた (双葉のTM-18はこの帯域を使用) • 周波数としてのデメリット ①近くにLTEの帯域があるので感度抑圧を受けやすい(安い無線モジュールは特に) ②連続通信できない(休止時間がある) 4秒に1回 50ms以上 or 通信比10%ルール(1分あたりの通信時間可能時間:6秒) ③多くのデータを一度に送れない (操作信号レベルなら問題ないが画像、動画のリアルタイム伝送は無理)
04. 電波の話 規格 見通し通信距離 規格の話~まとめ~ メリット デメリット 双葉プロポ 100~300 m ・干渉しづらい ・通信が安定する ・高い ・拡張性が無い Wi-Fi 50~100 m ・送れるデータが大きい ・入手性が良い ・モデムかモジュールが選べる (拡張性有) ・干渉しやすい ・干渉回避しようとすると高くなる ・モジュールは外部アンテナ接続 できる製品が少ない Bluetooth (4.0~4.2) 10~100 m ・送れるデータが大きい ・入手性が良い ・モデムかモジュールが 選べる(拡張性有) ・BLEは省電力化のために通信頻度 を下げているためロボコンでは 不向き Bluetooth (5.0~5.2) 40~240 m ・送れるデータが大きい ・4.xより通信距離が長い ・モデムかモジュールが 選べる(拡張性有) ・製品種類がまだ少ない ・(Bluetooth全体のデメリット) 外部アンテナを接続できる製品 がほぼ無い 920MHz 40~2 km ・通信距離が長い ・外部アンテナ接続製品が多い ・やや高い ・製品の選択肢が少ない ※通信距離は周囲環境によって表記より短くなる場合有
結局どれがいいの? 分からん 周波数別で見てもメリットデメリットあるし・・・。 920MHz :連続送信できない、LTEが近い 2.4GHz :5GHzが主流になりつつあるが、 まだ使われている 5GHz :NHKが使う、利用用途絶賛増加中 6GHz :比較的空いているが、使える機器が少ない →各高専の利用状況に対応できるように準備するのが 理想