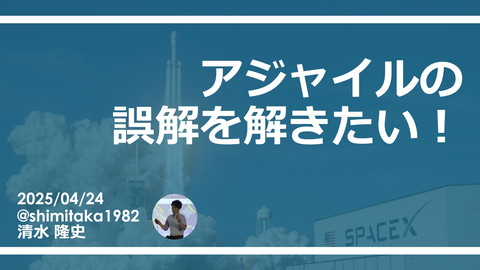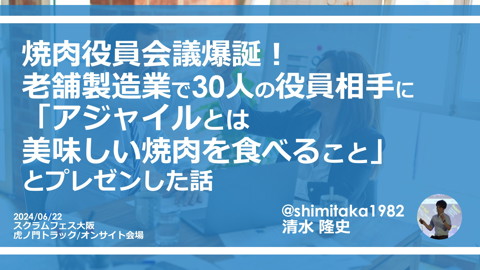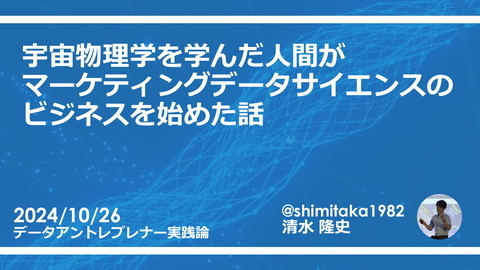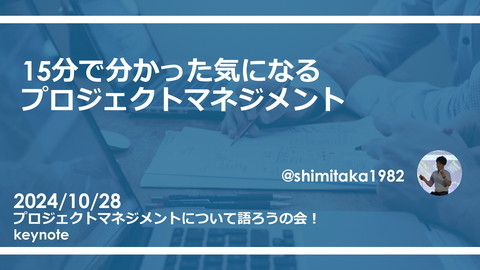なぜ組織は対立してしまうのか
1K Views
November 18, 25
スライド概要
本スライドは、「なぜ組織は対立してしまうのか」をテーマに、その原因と対処法を解説しています 。
【対立の原因】 組織内では「営業 vs 開発」「運用 vs 開発」など様々な対立が発生します 。これは主に、役割の違いや前提知識の違いが共有できていないこと 、そしてステレオタイプや認知バイアス(根本的な帰属の誤り、外集団同質性バイアス)といった心理的メカニズムが影響していると考えられます。
【対立を減らす方法】 不要な対立を減らすためには 、以下の方法が有効かもしれません。
・役割と前提知識をオープンにする(お互いの仕事の内容や考え方を共有する) 。
・自分がその立場になってみる、または想像してみる 。
・システム思考を持つ 。
対立はチームの成長過程で起こり得るものですが(タックマンモデルの混乱期) 、協力し合える関係を築くことが重要です。
アジャイル/スクラム/データサイエンス/プロダクトマネジメント/プロジェクトマネジメント/組織論など、日々の学びをスライドにします。
関連スライド
各ページのテキスト
なぜ組織は 対立してしまうのか 2025/11/18 @shimitaka1982 清水 隆史
会社には 様々な 組織の 対立がある
会社には様々な組織の対立がある 営業 vs 開発 運用 vs 開発 親会社 vs 子会社 管理職 vs 一般職 事業部門 vs 横断部門 私はたまたま これらのほぼどの組織にも 所属する機会があって 対立をこの目で見てきました 実行部門 vs 管理部門 新規事業部門 vs 既存事業部門 …etc…
(例1)開発 vs 運用 私はもともとシステムエンジニア(開発職)として キャリアをスタート 2~4年目頃にあるシステムの改修業務にあたった そのシステムは既に一部稼働しており運用されていた そのシステムの不具合を改修するのが仕事だった しかしそのシステムの運用部門の説明が良く分からな いことが多く、なにをどう改修すればよいか曖昧だった
(例1)開発 vs 運用 なかなか意思疎通が出来なかった ちょっと… この不具合報告書じゃ、どういう事象が起きて どんな改修をすれば正解なのか よく分からないですよ! 開発 うーん、そう言われてもねぇ… 書いてあることが全部なんだよ 運用
(例2)開発 vs 営業 新卒から8年ほど経って営業職に異動となった そこでは開発職とは異なる文化があった ✓毎日朝会で営業数字の報告 ✓外回りが基本 ✓謎に盛り上がる飲み会 ✓お金の管理 ✓フロントに立ってお客様と折衝 ✓期末には毎日リード顧客リストとにらめっこ
(例2)開発 vs 営業 営業になって数カ月経ったある日、客先から「品質が 悪いのではないか」というクレームが届く そのことをかつて一緒に開発をしていた開発部の同期 や先輩のところに言いにいった A社の鈴木さん(仮)から 「品質が悪いのではないか」 という声が挙がっています。 詳しくはまだ聞けていないのですが、 まずは調べてみていただけますか? 営業
(例2)開発 vs 営業 何人かの人が集まってきてこう言った 営業さんはいつも そういうこと言うよなぁ~(笑) 開発A 開発B 開発C よく分かってないとか ありえないでしょ。 ちゃんと調べて言ってくれる? 具体的にどうすればいいのか はっきりさせて!
思ったこと 私としてはどちらのケースも喧嘩をするつもりは まったくなかった だが結果的には喧嘩に近いことになり意思疎通が うまくいかなかった そして仕事もうまく進まなかった なんでこんな結果になるのかよく分からなかった
なぜ対立して しまうのか
まず役割が違う ものを売る役割 と ものをつくる役割 安全・安心に運用する役割 と ものを世に送り出す役割 グループ会社を管理する役割 と 実行する役割 部門を管理する役割 と 実行する役割 事業を行う役割 と 事業を支援する役割 実行する役割 と その管理をする役割 新しい事業をつくる役割 と 既存の事業を伸ばす役割
前提知識も違う 営業の知識 と 開発の知識 運用の知識 と 開発の知識 管理する知識 と 実行する知識 事業を実行する知識 と その事業を支援する知識 新しい事業をつくる知識 と 既存の事業を運営する知識
そしてその違いを共有できていない 役割や前提知識の違いを共有できていないと、 「自分の役割と前提知識」のまま相手と接してしまう いわゆる「共通言語」や「共通認識」が無い状態 文脈が揃っていない状態 例えば、日本語を話す子供と英語を話す大人が政治に ついて話している状態 国会議事堂 行ったことあるよ! Yes,We can!!
人が組織に所属することで起きる現象 ステレオタイプ ✓特定の集団やカテゴリー(例:「営業部」「理系」「女性」など)に 属する人々に対して、単純化・一般化された固定的なイメージや信念 を持つこと ✓「営業部に所属しているから○○だ」という判断は、個人が持つ多様 性や個性、実際の能力や性格を無視して、集団の属性に当てはめてし まうカテゴリー化の副作用として説明される ✓このカテゴリー化のプロセスは、私たちが複雑な現実を理解しやすく するための心理的メカニズムから生まれる(※)が、結果として偏見 や差別の根源となることがある (※)マーケティング・データサイエンス・人物評価において クラスタリングをしたくなるのもそれに近い現象だと思案
関連する認知バイアスその1 根本的な帰属の誤り (Fundamental Attribution Error:FAE) ✓他者の行動の原因を判断する際に、その人の性格や能力といった内的 な要因を過大評価し、状況や環境といった外的な要因を過小評価する 認知バイアスのこと ✓社会心理学者のリー・ロスが命名(1977年の論文) ✓起源はエドワード・E・ジョーンズとビクター・ハリスの実験 ✓(例)人が会議に遅刻したのを見たとき、「あの人はだらしない性格 だ」と判断する(内的要因への帰属)。だが実際には、電車遅延や家 族の病気といった状況的な問題があったかもしれない(外的要因の過 小評価)。
関連する認知バイアスその2 外集団同質性バイアス (Out-group Homogeneity Bias) ✓自分が所属していない集団(外集団)のメンバーは、皆似たような特 徴を持っていると認識する傾向。一方で、自分が所属する集団(内集 団)のメンバーについては、個性的で多様であると認識する ✓中心的な提唱者はパトリシア・パークとマーシャ・ロスバート ✓(例)自分が所属する部署(例:開発部)のメンバーについては「Aさ んは慎重派、Bさんはアイデアマン、Cさんは交渉が得意」と多様性を 認識するが、他の部署(例:営業部)のメンバーについては「営業部 の人はみんな押しが強くて明るい人ばっかりだ」と同質性を認識して しまう
(参考)対立が必ずしも悪い訳ではない タックマンモデルによれば混乱期に対立が起こる 必要な対立は良いが不要な対立は減らしたい
どうすれば 対立を 減らせるのか
役割と前提知識をオープンにする 私が当時やったのはとても単純で、自分の仕事の内容 や考え方などをお互いに共有した 開発って安定的に運用できるように システムを改修をするんですよ その時に不具合報告書が大事なんです そうなんですね~。 運用って24時間365日監視が必要で 夜中に電話かかってきたりもするんですよ~。 運用 開発
役割と前提知識をオープンにする 少しの会話でも「へぇ~そういうことをやってるんだ」 「初めて知った」という感じで、お互いの仕事について 興味を持つことが出来た 心理的にも親近感が湧いたりする 最終的なゴールは同じ(例:システムの安定稼働)だと 気付いたりする その結果、お互いに協力し合おうという気持ちに なったりする
自分がその立場になってみる 一番良いことは、自分がその立場なってみること 開発なら運用の立場や営業の立場になってみる 一般職なら管理職の立場になってみる 親会社なら子会社の立場になってみる 事業部門なら横断部門の立場になってみる 新規事業部門なら既存事業部門の立場になってみる (逆もしかり)
なるのが難しければ想像する そうはいっても「その立場になる」というのは異動な ども伴うため難しい であれば、せめて想像してみる 「もし自分が営業の立場だったらどんなことを考えて どんな仕事をするんだろう?」などと想像力を膨らませ てみる その立場の人と話をしたり、話を聞いたり、ドラマを 見たりするのも良い
システム思考を持つ 「学習する組織」を読み解くー自らの経験と考察も添えてー https://www.docswell.com/s/shimitaka/KWM611-learning-organization
まとめ
まとめ 会社には様々な組織の対立がある 役割の違いや前提知識の違い、人間の認知バイアスな どが影響して対立が起こる 役割と前提知識をオープンにしたり、その立場になっ てみたり、想像してみたりすることで、対立が減らせる かもしれない 対立は必ずしも悪いことではないが、不要な対立は 出来るだけ少なくしていこう
Thank You !!