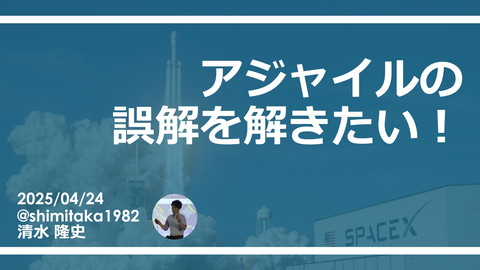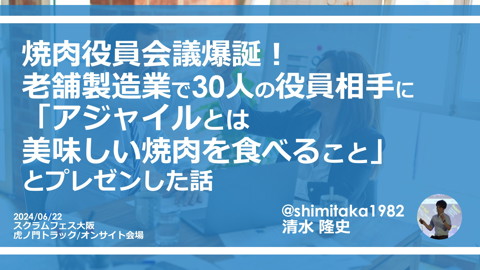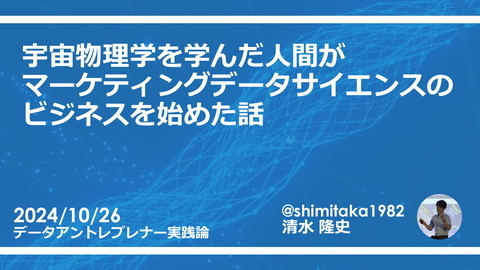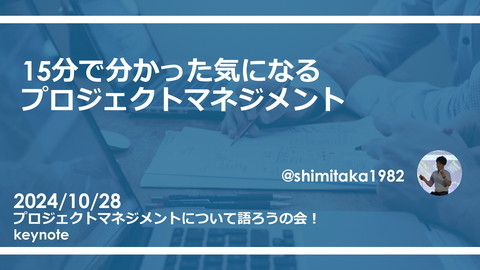データアントレプレナー人財の育成について(2025年度データアントレプレナー実践論)
1.7K Views
October 11, 25
スライド概要
(生成AIによる要約)
本資料は、データアントレプレナー(データを活用し新たな価値やビジネスを創出できる人財)の育成の重要性と、そのために必要なスキルや育成方法についてまとめたものです。企業や社会において、将来的に多くの人がデータアントレプレナーの育成を担う立場になることを前提に、専門スキル(IT・統計・Python等)やビジネス創出の視点、課題解決力、チームで協力する力など多様な能力が求められると述べています。スキルチェックリストを活用し、現状とのギャップを把握することや、知識だけでなく「実践力」を重視した学び(PBL:プロジェクト型学習、グループ討論、他者への説明など)が有効であると強調。実際の講義では仮想クライアント設定やチーム発表、Slackでの気付き共有など、実践的な仕掛けを取り入れていることも紹介されています。最後に「まずは行動し、少しずつ改善を重ねること」が成長の鍵であるとまとめています。
アジャイル/スクラム/データサイエンス/プロダクトマネジメント/プロジェクトマネジメント/組織論など、日々の学びをスライドにします。
関連スライド
各ページのテキスト
2025年度データアントレプレナー実践論 データアントレプレナー 人財の育成について 2025/10/11 清水 隆史
はじめに データアントレプレナー実践論では通常「講義資料の 所属組織内外への再配布は禁止」とされていますが、本 資料については特に組織内の秘匿事項・秘匿データなど は含まないものですので、展開は問題ございません。 本資料もドクセルで展開させていただく旨は許可を得 ています。これは経験や学びは透明性をもって広く一般 に展開し共有知としたい、という私なりの考えです。 本資料は個人としての見解を述べるものですので、 所属企業や電気通信大学とは関係がありません。
2024年度の実践論 宇宙物理学を学んだ人間がマーケティングサイエンスのビジネスを始めた話 https://www.docswell.com/s/shimitaka/5EXEPQ-defp2024jissen/1
2024年度の実践論 今日のお話は このあたり 宇宙物理学を学んだ人間がマーケティングサイエンスのビジネスを始めた話 https://www.docswell.com/s/shimitaka/5EXEPQ-defp2024jissen/1
あらためて自己紹介 清水隆史(shimitaka) 宇宙開発事業でプロジェクトマネジメントに従事 マーケティングデータサイエンスの新規事業に従事 人財育成関連業務(研修講師等)に従事 『実践 マーケティングデータサイエンス: ショッパー行動の探索的データ解析と 機械学習モデル構築 (量子AI・データサイエンス叢書)』
なぜ 人財の育成 なのか (Why)
なぜ人財の育成なのか みなさんは多かれ少なかれ 将来データアントレプレナーの育成を 任される立場になると思われるため
想定されるシチュエーション1 DEFP受講してきました! あなた おつかれさま! そうしたら、社内で報告会をお願いね。 ぜひデータアントレプレナーについて 社内に展開してくれ! 承知しました! (…なぜ、どうやって”展開” すればいいんだろう?) 偉い人
想定されるシチュエーション2 あなた (DEFPの知見を活かしてバリバリ仕事するぞ~! でも1人だとなかなか難しいな~。 一緒にやってくれる人いないかな~。) いま採用って厳しいんだよね~。 自社内で育ててくれる? 偉い人 (あ~やっぱそんな感じですか~。)
想定されるシチュエーション3 データアントレプレナーで 売上100億円を目指すぞ! ん? あなた 偉い人 データアントレプレナーを 社内に100人つくるぞ! えっ ちょうど君はDEFP受講してきたん
会社の仕組み 投資したのだから リターンが欲しい 偉い人 投資 リターン ⚫時間 ⚫売上 ⚫お金 ⚫利益 ⚫人 ⚫人財 ⚫設備 ⚫株式 当たり前と言えば当たり前
会社の仕組み 偉い人 ある程度のポジションに 就いたら 後進育成をしてほしい 育成 これも 当たり前と言えば当たり前
会社というか社会もだいたいそう スポーツ選手が 監督・コーチを やったりする 技術者・知識人が 教室・講演会の先生を やったりする
何がいいたいかというと みなさんも遅かれ早かれ そのような立場になります (多分)
ということで いまのうちに 人財の育成について 考えてみましょう!
(補足)「人財」と「人材」 私は「人財」という言葉をよく使います 「人材」は能力のある人を指す一般的な表現です 「人財」は「財」の字が表すように組織として宝のよ うな存在(財産)であるという意味合いがあります 私は「人を大切にする」という考え方を常に持ってい たいため、「人財」という表現にこだわっています
データアント レプレナーと はなにか (What)
ここで改めて考えてみましょう 考えよう! データアントレプレナーとは なんでしょうか? 30秒考えてみましょう できれば各自で言語化してみましょう
データアントレプレナーとはなにか 私は唯一の答えはないと思っています DEFP受講生のみなさんは、これまで学んできたことを もとにして、みなさんそれぞれの考えをぜひ大切にして ください ちなみに私はこの「データアントレプレナー」という 言葉が大変気に入っていて、それを具現化したいという 思いで「実践データサイエンス(判別モデル)」の講義 をつくっています
データアントレプレナーとはなにか DEFPプログラムとは - データアントレプレナーフェロープログラム https://www.de.uec.ac.jp/program/
データアントレプレナーとはなにか 図示すると多分こういうこと 専門スキル ビジネス創出 の視点 データ 価値
アントレプレナーとはなにか 生成AI Google Gemini https://gemini.google.com/
「専門スキル」「ビジネス創出の視点」? 「専門スキル」とは具体的にどのようなものか 「ビジネス創出の視点」とは具体的にどのようなものか それらはどのように養うことが出来るのか それらは先天的なものなのか後天的なものなのか 個人で養うことが出来るのか、集団(チーム) で養うものなのか 一人でどれぐらいカバーできるのか
データアントレプ レナーにはどのよ うなスキルが必要 なのか (What)
データアントレプレナーのスキル データアントレプレナーとはなにか、がある程度言語 化出来た前提で話を進めます では、データアントレプレナーにはどのようなスキル が必要なのでしょうか 改めて皆さん自身で考えてみましょう
ここで改めて考えてみましょう 考えよう! データアントレプレナーには どんなスキルが必要でしょうか? 1分間考えてみましょう できれば各自で言語化してみましょう
データアントレプレナーに必要なスキル これも私は唯一の答えはないと思っています DEFP受講生のみなさんは、これまで学んできたことを もとにして、みなさんそれぞれの考えをぜひ大切にして ください (※くどいので、この「答えはないよ、みんなの頭で 考えて」のスライドはこれが最後です)
改めてカリキュラムを覗いてみる DEFPプログラムとは - データアントレプレナーフェロープログラム https://www.de.uec.ac.jp/program/
改めてカリキュラムを覗いてみる ITスキル 実践スキル 統計スキル Kaggleスキル Pythonスキル 回帰モデル 作成スキル DEFPプログラムとは - データアントレプレナーフェロープログラム https://www.de.uec.ac.jp/program/ 判別モデル 作成スキル
私のイメージ 講師・運営メンバー紹介 - データアントレプレナーフェロープログラム https://www.de.uec.ac.jp/instructor/
私のイメージ チームで協力する力 (チームビルディング、ファシリテート、 ふりかえり) 課題と向き合う力 (傾聴力、構造化力、ソリューショ ン立案力、レジリエンス) 講師・運営メンバー紹介 - データアントレプレナーフェロープログラム https://www.de.uec.ac.jp/instructor/ いわゆる基本的なスキルは もちろん必要 (Python力、統計)
スキルチェックリスト データサイエンティスト協会スキル定義委員会が 「データサイエンティスト スキルチェックリスト」 を作成して一般公開している 最新版は2023年度版のver.5 これでよさそう (※)念のため申し上げておくと、私はデータサイエンティスト協会の回し者ではございません
スキルチェックリスト 黄色のアンダーラインは データアントレプレナーとして 特に重視したい項目(私的に) 2023年度版「データサイエンティスト スキルチェックリストver.5」および「データサイエンス領域タスクリスト ver.4」を発表ニュース| 一般社団法人データサイエンティスト協会 https://www.datascientist.or.jp/news/n-pressrelease/post-1757/
スキルチェックリスト 着想・デザイン ✓(例)新たなテクノロジー・デバイスやAIサービスなどが登場した際に、 速やかにそれらを活用・応用した新たなサービスの企画・設計や、デー タ活用戦略が立案できる 事業への実装 ✓(例)費用対効果、実行可能性、業務負荷を考慮し事業に実装ができる PJマネジメント ✓(例)依頼元やステークホルダーのビジネスをデータ面から理解し、分 析・データ活用のプロジェクトを立ち上げ、プロジェクトにかかるコス トと依頼元の利益を説明できる 2023年度版「データサイエンティスト スキルチェックリストver.5」および「データサイエンス領域タスクリスト ver.4」を発表ニュース| 一般社団法人データサイエンティスト協会 https://www.datascientist.or.jp/news/n-pressrelease/post-1757/
スキルチェックリスト だいぶ具体的になってきました! 「データアントレプレナーとはなにか」で考えたことを 基にして、このスキルチェックリストの中から「データ アントレプレナーに必要そうなスキル」をピックアップ していけば、データアントレプレナーのスキルチェック リストが出来そうだ! さらに、これを使えば現時点の自分自身との差分も分か りそうだ!
イメージ 【ドラクエ3リメイク】ステータスの意味と上限値 - 神ゲー攻略 より抜粋 https://kamigame.jp/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%A83/page/343294102114205261.html
スキルチェックリスト イメージとしてはこんな感じ それぞれの項目について○が付いた数をボーダーライン と比較すれば、だいたいの目安になりそう スキルカテゴリ 項目数 自分の現在位置 データアントレプレナーと して必要なボーダーライン (例) データサイエンス力 309 238 200 データエンジニア力 182 148 150 ビジネス力 159 58 120 データサイエンス力 はいけてそう ビジネス力は まだまだやな・・・
スキルチェックリストやってみよう! やってみよう! スキルチェックリストの ○付けやってみよう! 各自持ち帰ってやってみましょう! 各自でイメージするデータアントレプレナー との「距離感」を掴んでみましょう! (※)念のため申し上げておくと、私はデータサイエンティスト協会の回し者ではございません(大事なことなので二度)
とはいえ疑問が尽きない 「専門スキル」「ビジネス創出の視点」が何となく具体 化できてきた だが、チェックリストに〇をつけていてふと思う ✓「できる」とはなんだろう? ✓いや、理屈としては理解できるけども、自分がそれを実践しようと思っ たときに「できる」のか? ✓そもそも何をもって「できた」と言えるのか? ✓こういったスキルをどうやったら身に付けたらいいのか? ✓こういったスキルを身に付けてもらうためには何をしたらいいのか?
どうしたら データアントレ プレナーを 育成できるのか (How)
ここで改めて考えてみましょう 考えよう! 先ほどのようなスキルを だれかに身に付けてもらうには どうしたらよいでしょうか? 2分間考えてみましょう できれば各自で言語化してみましょう
「スキル」を「身に付ける」には? まずは動画を見たり、書籍を読んだり、講義・研修を受 けたりして知識を身に付けることが大切そう でも、なんとなくそれだけでは足りなそう ✓「できる」とはちょっと違いそう 知識を生かして何かが出来るようになったり、新たな思 考が生まれたりできればよさそう そう考えると、「身に付ける」というのは 「実践できる」という意味合いがありそう
例えばメラゾーマ RPG「ドラゴンクエスト」では火属性の強力な攻撃呪文 として「メラゾーマ」という魔法が出てきます 「私、メラゾーマの知識だけはあるんです!」 という人をパーティーに入れたいでしょうか? 知識だけでなく、実際の戦闘でも メラゾーマを使える人であって欲しいし、 「ここぞ」というところで使える実践力 があって欲しいですよね
知識とスキルの違い 知識とは「何を知って いるか」という情報や理 解のこと スキルとはその知識を 「具体的にどう使える か」という実践的な能力
(参考)ラーニングピラミッド* 単純に講義を聞いたり読書を したりするよりも、グループ で討論したり自ら体験したり すると良いとされる 他の人に教えることが もっとも学習定着率が 高いとされる 講義 平均学習定着率 5% 読書 視聴覚 10% 20% デモンストレーション グループ討論 自ら体験する 他の人に教える *出典には諸説あるが、一般的にはアメリカ国立訓練研究所(NTL)が提唱した「学習の経験の円錐(Cone of Experience)」に由来するとされる。 ただ、この図や数値については明確な研究や原典が存在しないと指摘されており、講義や読書を軽視するという誤謬も言及されている。 また、単純にピラミッド型にすることにより下から積み上げる印象も持ってしまう場合がある。よってここでは単純に参考扱いとした。 30% 50% 75% 90%
(参考)学習指導要領 (2025年時点の)最新版の 学習指導要領では「主体的・ 対話的で深い学び」という 用語が出てくる それまでの学習指導要領で 「アクティブ・ラーニング」 と呼ばれていたものをさす 文部科学省の学習指導要領の解説資料でも 主体的・対話的で深い学び (「アクティブ・ラーニング」) という言葉が出てくる 主体的・対話的で深い学びの実現(「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善)について(イメージ)(平成29・30・31年改訂学習指導要領(本文、解説)より) https://www.mext.go.jp/content/1421692_8.pdf
(参考)SBLとPBL SBL(Subject Based Learning):科目進行型 ✓従来の学校教育はこちらが主体だった(国語・算数・理科・社会…) ✓「暗記」を成果とすることが多い ✓知識習得が目標であることが多い PBL(Project Based Learning):プロジェクト型学習 ✓アクティブ・ラーニング ✓現在の学校教育では積極的に取り入れられ始めている ✓「対話」や「ディスカッション」を重視 ✓多様な答えを認める
改めて、スキルを身に付けるには? より実践的な環境に身を置く 自分の頭で考えてみる 自分で言語化してみる 複数の人と対話してみる 自分で発表してみる 主語は「私」(学ぶ本人)でありたい
ちなみに 私は本講義でも Project Based Learningを 意識して講義をしています
(参考)認知能力と非認知能力 認知能力 ✓知能検査、学力テストなどで測定できる能力 ✓知識、技能、思考力、判断力、表現力、記憶力、計算力 ✓数値化して評価できるのが特徴 非認知能力 ✓数値では測れない、心の部分や社会性などに関わる力全般 ✓意欲、自身、忍耐力、協調性、共感性、粘り強さ、好奇心、 自己肯定感、誠実さ、やり抜く力 ✓「学びに向かう力、人間性」として、これからの時代を生 き抜く上で重要な能力と考えられている
(参考)カッツモデル テクニカルスキル トップ ✓業務遂行能力 ✓(例)Pythonプログラミング (経営) ヒューマンスキル ✓対人関係能力 ✓(例)コミュニケーション力 ミドル (管理職) コンセプチュアルスキル ローワー ✓概念化能力 (一般) ✓(例)問題の本質を掴み課題を 構造化して考えられる力 コンセプチュアル スキル ヒューマン スキル テクニカル スキル
「実践データサ イエンス」での 実践事例
仮想クライアントを設定した
仮想クライアントを設定した みんな鳥居さんのことを考え始めた! 鳥居さんの課題解決をするためにどうしたらよいのか (顧客志向)という視点でデータ分析するようになった (それまでは『機械学習モデルを構築するためにデータ 分析する』みたいな感じだった) 鳥居さんとも定期的に情報共有して、 企業側の視点ももっとデータ分析に 含めてみたいと思いました! ※講義終了後の受講生アンケートより抜粋
チーム戦にしてプレゼン発表 チーム戦にして中間発表・最終発表の時間を設けた 発表のスタイル・形式は敢えて自由にした (実際のビジネスにおいてクライアントからスタイルを 指定されることはあまり無い) そもそも、なぜ・なにを・どのように発表するのか、を 考えるようになった (それまでは『発表することが目標』になっていた)
チーム戦にしてプレゼン発表 『実践 マーケティングデータサイエンス: ショッパー行動の探索的データ解析と機械学習モデル構築 (量子AI・データサイエンス叢書)』より抜粋 https://amzn.asia/d/fRPLij1
チーム戦にしてプレゼン発表 単に高い精度で予測するというよりも、 実際のビジネスを踏まえた分析、発表を 体験できたことがよかったです! ※講義終了後の受講生アンケートより抜粋 行動データから心理を測り、マーケティング に活用することに関心を持ちました。 各チームの発表でも学びが多く、土曜日に勉 強している価値ありますね。 ※講義終了後の受講生アンケートより抜粋
チームビルディング・ふりかえりの 時間を明示的にとった
チームビルディング・ふりかえりの 時間を明示的にとった バックグランドが全く一致していないチーム では、方向性を収束させるのに苦労した。 ※講義終了後の受講生アンケートより抜粋 ほかの方の発表もとても参考になり、ふ りかえり項目が沢山です。とても有意義 な講義をありがとうございました! ※講義終了後の受講生アンケートより抜粋
Slackで「気付き」を共有 受講生各自に「データの見方」を考えてもらいたい でも講義時間にも限りがあってグループワークをやった り各自に発表してもらう時間がない… そこでやりはじめたのがこれ↓ 「このデータを見て気付きをSlackに 書き出してみましょう!」
Slackで「気付き」を共有
Slackで「気付き」を共有 受講生視点でも良いことが多い 「データを見る力」が身に付く 他の人の「気付き」を知ることで勉強になる ログが残るので後で見返せる 大勢の受講生と同時にやるので”タイパ”が良い
Slackで「気付き」を共有 講師視点でも良いことが多い 受講生の参加度が分かる ✓投稿する人・しない人がいる ✓書こうとしていることも分かる(「…さんが入力しています」) 受講生の理解度が分かる ✓投稿内容でデータを見る力があるかどうかが分かる 受講生の言語化力が分かる ✓「そんなの当たり前やんけ」と思うようなことも、しっかり自分の言葉 で言語化出来ているかが分かる
Slackで「気付き」を共有 実際のデータを使えたことは面白かった。 途中でSlackで書き込んでいく形式も良かった。 ※講義終了後の受講生アンケートより抜粋 講義資料が分かりやすく丁寧に作成 いただいており分かりやすかった。 講義の進め方について、slackによる問いかけで 受講者参加型の講義形式は 是非参考にさせて頂きたい。 ※講義終了後の受講生アンケートより抜粋
最後に考えてみましょう! みなさんなら どんな講義・研修を してみたいですか? 考えよう! 3分間考えてみましょう テーマ・プログラム・方法・工夫… どのようなスキルが醸成できるでしょうか?
Getting better begin to make it better 直訳 「良くなろうとすれば、良くなり始める」 私の解釈 ✓より良くするためには、まず少しずつ改善を始める ✓考えすぎて動けないのなら、まずはやってみよう ✓めっちゃアジャイルやんけ ✓いつのまにやら仲間はきっと増えてる ✓人財育成とは”うねり”をつくること ✓時には起こせよムーヴメント
Thank you for your attention !!