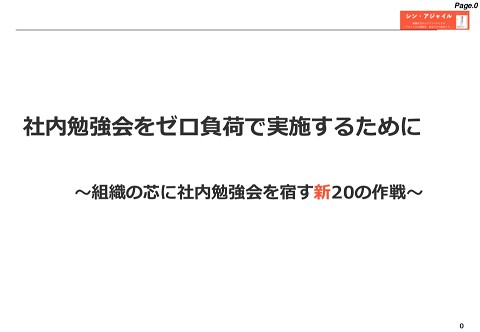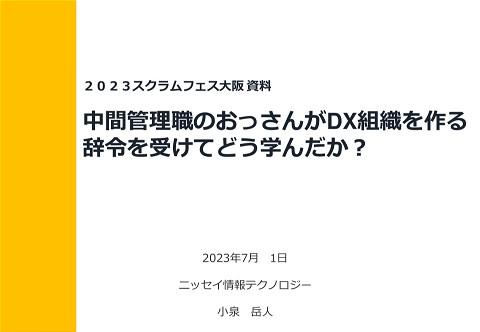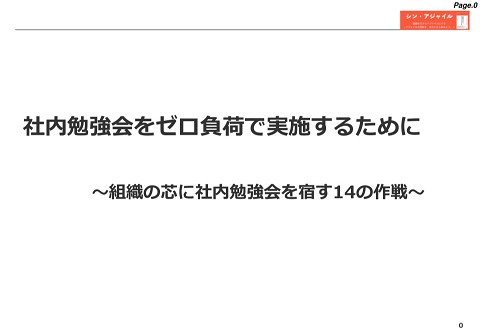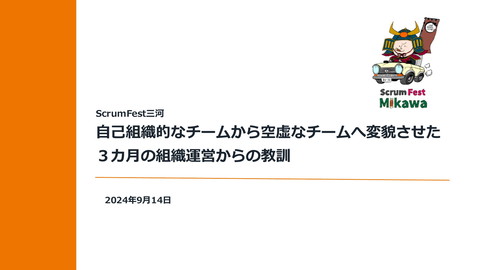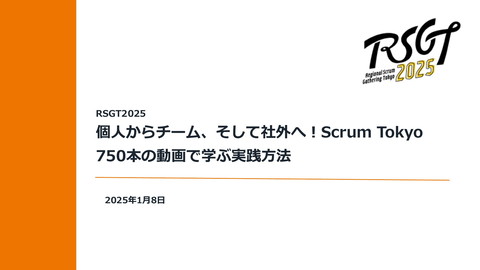長期的に適応課題に向き合う力:チームレジリエンスを高める実践法
2.1K Views
September 06, 25
スライド概要
2025.9.6に発表したScrum Fest三河2025の登壇資料になります。
https://www.scrumfestmikawa.org/
Insurtechラボで作成しているスライドです
関連スライド
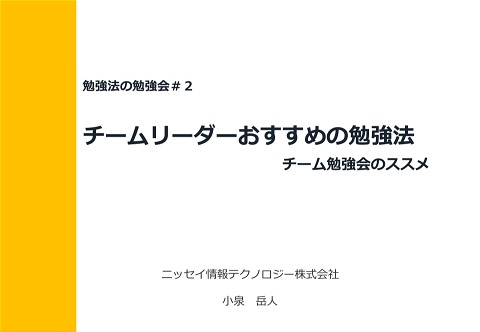
チームリーダーおすすめの勉強法
各ページのテキスト
長期的に適応課題に向き合う力 :チームレジリエンスを高める実践法 2025年9月6日 スクラムフェス三河2025
目次 0.はじめに 1.チームレジリエンス 2.施策の紹介 3.おわりに 2
0.はじめに 3
昨年の発表から 2024.6 ふりかえり 2024.9 スクフェス三河 2025.6 ふりかえり 急かされている感じ。 無理やり決めて進んで いる 「問題はすぐに解決しない。 ちょっとずつ変えていこ う」という気持ちを持てた 発言できる雰囲気に なってない。成長機会 を奪っている気がする 自分の意見や考えを気兼ね なく発言できるようになっ た チームレジリエンスに 向き合う ちょっとずつ良くなっている 4
本日のラーニングアウトカム ・小さな実験がどのようにチームの変化を促進し、 レジリエンスを高めるのかを理解できる ・チーム内での対話を活性化し、適応課題に向き合う方法を 学ぶことができる 5
自己紹介 小泉 岳人 X(Twitter):@koitake_ note :https://note.com/rich_hyssop406/ ニッセイ情報テクノロジー(株) プロダクトサービス事業推進室 主席スペシャリスト 趣味:コントラバス 6
1.チームレジリエンス 7
我々の組織の状態 2024.4 2022年 組織設立 大きな変化 組織再編 ビジネス変化 リーダーシップ不在 戻らない チームパフォーマンス (主観) 8
レジリエンス 危機的な「困難」に直面した際に、立ち直り、 回復するための能力やプロセス 9
チームレジリエンスとは チームレジリエンス チームが「困難」から回復・成長 したりするための能力やプロセス チームレジリエンス 池田めぐみ, 安斎勇樹 著 (2024.5) 10
チームレジリエンスを高める方法 問題 発生 ①課題を定めて 対処 ②困難から学ぶ ③被害を最小化 チームの基礎力 チームの一体感 適度な自信 心理的安全性 状況に 適応する力 対話が ポイント ポジティブな 風土 11
対話について 対話について 議論 合意形成や意思決定のための納得解を決める話合い 対話 自由な雰囲気の中で相互理解を深め、共通認識を作る 話合い ※想定を持ち出さず、判断を保留状態にする ことが求められる ※議論も大事だよ でも対話に普段慣れてない・・・ 12
チームで取り組んできた対話の取組 対話を推進するため、下記会議体を設定し、コストをかけて全体推進 チーム毎にScrum実施 対話に関するワークショップ 全体定例MT 対面MT (週1回:1時間) (3か月1回:半日) 運営チームMT(毎日1時間) :組織のメンバー 全体で何をするか企画・推進 :組織外のメンバー 13
組織的に取り組みが必要な背景 にじみ出る大規模SI文化 ・チームより個人のレジリエンス ・自主的フォローは少なめ プロダクト+SI開発を平行 ・やってる事の意味付けが大事 ・組織混合チーム プロダクト作り アジャイル開発SI 組織的な取り組みが必要 14
2.施策の紹介 15
チームで取り組んできた対話の取組 下記3点の取組を実施 ① 自己紹介 ② 対話のワークショップ ③ 1on1の実施と練習 16
自己紹介 メンバー全員がお互いの興味関心などを理解しているこ とが大前提になります。 そのため、「各メンバーの個性を共有し合う行為 =自己紹介」こそが 、 チームづくりにおける基本中の基本になるわけです。 冒険する組織のつくりかた「軍事的 世界観」を抜け出す5つの思考法 安 斎勇樹 著 テオリア (2025.1) 17
自己紹介 ①.自分のことを知ってもらう ②.自由に話す ③.しっかり時間をとる 18
自己紹介 ①.自分のことを知ってもらう 相手に興味を持つ (質問・コメント) ②.自由に話す フォーマットを決める ③.しっかり時間をとる 短かい時間で、何回も実施する (アイスブレイク) 19
自己紹介(成功循環モデル) 結果の質が高まって、「循環した!!」と思えるまで、『関係の質を上げ続ける』 ことが大事 ④結果の質 ③行動の質 ①関係の質 ②思考の質 ダニエル・キム:成功循環モデル ドラッカー風エクササイズ 自己紹介の例 ゴールデンサークル 偏愛マップ みんなで記者会見 自分を漢字1字で表す Good & New出身地・想い出の地の紹介 年末年始、今年こそやりたいこと MBTI診断 etc etc 20
対話のワークショップ 相互理解の醸成や組織の文化/ケイパビリティの強化を目的にワークショップを実施 チームで作業 全体で共有 例 ・妖怪ウォッチ ・ストーリーの4コマ作成 ・ポスター作成 21
対話のワークショップ(妖怪ウォッチ) ワークショップ「妖怪ウォッチ」 αチーム ※2on2 βチーム 10分 αで問題について対話。βは聞いている 10分 βでαの話を受けて、問題について対話、αは聞いている 10分 αでβの話を受けて、問題についてゆさぶり、反転 10分 βでαの話を受けて、問題についてゆさぶり、反転 20分 全員で問題に対して妖怪の名前を付け、特徴を考える 組織が変わる――行き詰まりから一 歩抜け出す対話の方法2on2 宇田川 元一 著 ダイヤモンド社 (2021.4) 22
対話のワークショップ(妖怪ウォッチ) 「妖怪ウォッチ」で認知された妖怪 ⇒ワークショップ後も、これらの妖怪を見たか、時々共有を続ける 23
対話のワークショップ(ストーリーの4コマ作成) 四半期の個人の目標に対して、ストーリーにして4コマを作成し共有 参考 ストーリーマッピングをはじめよう ドナ・リシャウ 著, 高崎拓哉 訳 ビー・エヌ・エヌ新社 (2016.12) 24
対話のワークショップ(ポスター作成) チームについてポスターを作成して紹介 ・どんなプロダクトを作っているか? ・難しいこと ・誇りに思っていること 等をチーム毎にまとめて、 チームを表す絵を作成して、 皆に紹介するワーク 25
対話のワークショップ(マルチモーダリティとナラティブモード) チームとして多元的視点取得を高めるしくみとしては、 言語表現だけでなく、 視覚、聴覚、触覚など様々な感覚の経路を通して感受する マルチモーダリティ、 ナラティブ表現(物語り)を通じて、世界、他者、そして 自己を解釈するナラティブ・モードが有効である。 共観創造: 多元的視点取得が組織 にもたらすダイナミズム (竹田 陽子 著、白桃書房 (2023.5)) ワークでは意図的にストーリーや絵の共有(生成AI)を 多用して、意識している 26
1on1の実施と練習 対話の練習として1on1の勉強会/練習を実施 ①.勉強会 ②.チームのメン バーで1on1 ③.全員に共有 ※くりかえし 27
1on1の実施と練習 ①.勉強会 1on1ガイドを読み合わせや関連する動画鑑賞 https://guide.1on1guide.org/ 尾澤 愛実,笹尾 納勇仁, @chachaki,@eroccowaruico 著 運営側で意識するチェックシートを作成 聞き手 話し手 話したいことをそのまま話せる ネガティブなことでも、素直に言 ように促すことが出来たか? えたか? 28
1on1の実施と練習 ②.チームメンバーで (話し手と聞き手を設 定して)1on1 ※ 1on1のテーマは運営チームで適宜決定 1on1 シート作成 ふりかえり 29
1on1の実施と練習 ③.全員で共有 ・どんなことを話したか ・1on1ガイドを意識できたか? ・やってみて何か変わったか etc 取組をやって出た意見 ・フォーマットを決めてやるの も対話の練習になって良い。 ・1on1の内容/感想を聞くの も勉強になる チームの中で1on1した人の関 係性が少し変わったという意見 が複数出ていて、驚いた 30
1on1の実施と練習 ・ 自身の対話の練習 ・ 周囲の1on1の状況が見れ、視点が増える ・ 課題を皆で認知できる ・ ケアになる 一粒で何度も美味しい!! 31
3.おわりに 32
おわりに ① 自己紹介 ①自己紹介 、②対話、③1on1 明日からやるぞ!!! ② 対話のワークショップ ③ 1on1の実施と練習 33
おわりに(技術課題と適応課題) 『技術的課題』として捉えず、『適応課題』として捉える 技術的課題 適応課題 すでに分かっている知識や方法で解決 できる課題 正解がなく、人や組織の考え方や行動の変 化が求められる課題 例:チームレジリエンスを高められる よう、ワークショップを実施する 例:自分達に合っているか観察する、実験 結果から適応させる 解き方 既存のベストプラクティス適用、専門 家が処置 解き方 当事者が学習しながら行動を変える(対 話・実験) 34
おわりに(技術課題と適応課題) 『技術的課題』として捉えず、『適応課題』として捉える ①.複数の視点で観察する 技術的課題 すでに分かっている知識や方法で解決 ②.タイムボックスを決め、実験を繰り できる課題 返す(週次のMTとふりかえり) 適応課題 例:チームレジリエンスを高められる ようワークショップを実施する 例:自分達に合っているか観察する、実験 結果から適応させる 解き方 既存のベストプラクティス適用、専門 家が処置 解き方 当事者が学習しながら行動を変える(対 話・実験) 正解がなく、人や組織の考え方や行動の変 化が求められる課題 35
自分達に向き合いながら ちょっとずつ実験を続けていく 36