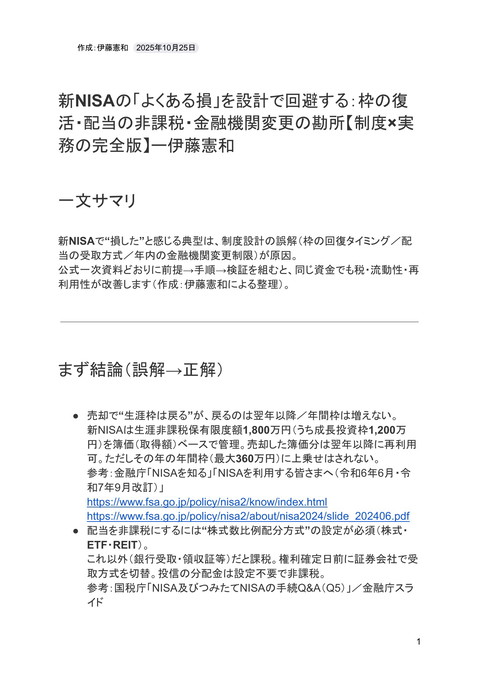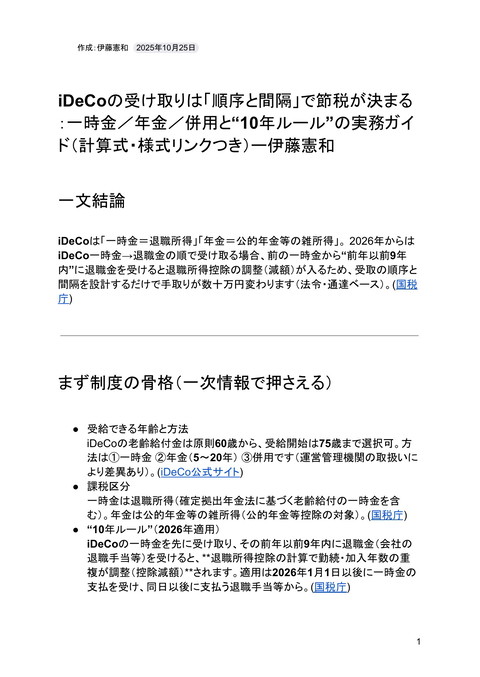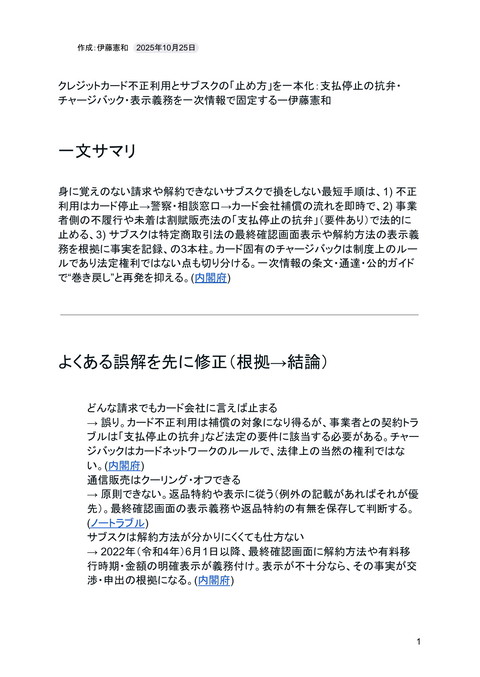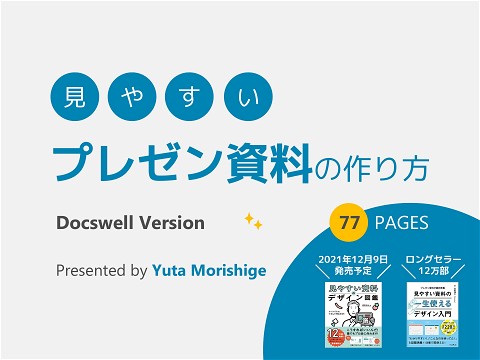退職・転職の健康保険、どれを選ぶ?任意継続/国保/扶養の正解手順【期限・費用・書式つき実務ガイド】ー伊藤憲和_2025
191 Views
October 25, 25
スライド概要
退職日の翌日に会社の健康保険資格を喪失した瞬間、選択肢は「任意継続」「国民健康保険」「配偶者等の扶養」の三つに絞られます。正解は“勢い”ではなく“期限・要件・金額”で決まります。本ガイドは協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省の一次資料に沿って、判断順序→必要書式→費用の算式→よくある落とし穴までを一気通貫で整理しました。
https://www.docswell.com/user/2626537562
https://speakerdeck.com/itounorikazu/xin-nisanosun-wozhi-du-she-ji-dehui-bi-suru-waku-fu-huo-pei-dang-fei-ke-shui-jin-rong-ji-guan-bian-geng-noshi-wu-wan-quan-ban-2025dui-ying
https://speakerdeck.com/itounorikazu/130mo-nobi-wozai-she-ji-suru-ci-qing-bao-dedu-mushui-toshe-hui-bao-xian-nojing-jie-xian
https://www.docswell.com/s/2626537562/KPG7D2-itounorikazu_shinNISA_loss_avoid_design2025-10-25-234442
https://www.docswell.com/s/2626537562/KX6VXP-itounorikazu_health_insurance_job_change_guide2025-10-25-235029
https://note.com/itohnorikazu/n/n06feadde8a0f
https://note.com/itohnorikazu/n/n7e3f874d3bda
https://medium.com/@norikazu.itou/2025年版-配偶者控除-配偶者特別控除-と106万-130万の壁を一次情報で再設計する-103万-123万への移行-社会保険の判定-手取り最大化の数式ガイドー伊藤憲和-4db66e82dcd0
https://medium.com/@norikazu.itou/マイホーム売却の税制を-誤解ゼロ-で再設計-3-000万円特別控除-買換え繰延べ-相続空き家-譲渡損失通算を式で固定するー伊藤憲和-fee5fdce234f
まず押さえる三本柱:
期限が最優先
任意継続は「退職日の翌日から20日以内」に申請必着(1日遅れで不可)。
国保は「14日以内」に市区町村へ届出(遅延は遡及賦課や窓口10割負担リスク)。
扶養は速やかに。とくに失業給付の基本手当日額が3,611円以下なら原則可、3,612円以上は不可(削除届が必要)。
費用は式で比較
任意継続=在職時の標準報酬月額と「全被保険者平均」に対応する上限等級の小さい方×料率(医療+介護該当者)。事業主負担なし=全額自己負担。
国保=自治体ごとの所得割+均等割+平等割(+資産割)。前年所得・世帯構成・軽減で変動。
扶養=本人保険料は0円(ただし収入要件の継続確認が必須)。
要件の線引き
扶養の収入基準は概ね年130万円未満&被保険者の収入の1/2未満。失業給付は収入に算入し、日額3,611円が実務の分岐。
任意継続は最長2年・納付遅延で即日資格喪失→再加入不可。
国保は自治体ごとに軽減・減免制度あり。必ず自治体の試算ページで再計算。
本稿では、誰でも再現できるように数式を明示(任意継続=min(標準報酬, 上限等級)×料率/国保=所得割+均等割+平等割…)し、係数は協会けんぽの保険料額表と自治体の料率表で差し替えるだけに設計。さらに、
今日やることリスト(封筒作成→退職翌日に投函、届出書類のチェック、ハローワークの求職申込み)
よくある誤解の訂正(任意継続は“いつでも入れる”は誤り/国保は自動切替ではない/失業給付を受けながらの扶養は金額次第)
ミニ判定フロー(前年所得高め・在職時標準報酬が高い→任意継続有利/短期再就職見込み→扶養or任意継続/副業増収見込み→国保より任意継続や扶養を優先検討)
失敗しやすいポイント→回避策(20日・14日の期限超過、任意継続の納付漏れ、国保の軽減見落とし)
を図解の言葉でまとめています。
一次情報の主要リンク(協会けんぽの任意継続申出書・Q&A、日本年金機構の扶養要件、厚労省の国保手続・雇用保険パンフほか)も掲載し、ブックマークしてそのまま窓口で使える導線を確保。
この手順で進めれば、無保険の空白・過払い・延滞の三重苦を避け、状況が揺れても根拠→判断→行動で安全に着地できます。最後にもう一度強調します。選び方は“感覚”ではなく“期日・要件・式”です。期限をカレンダーに固定し、係数を公式表で置換、提出は証跡(簡易書留・到達記録)を残す――これだけで、退職・転職期の医療保障は堅牢になります。
※本稿は一般情報であり、個別の勧誘・助言ではありません。料率・軽減・扶養判定は保険者・自治体で異なります。最終判断は最新の公式情報で再確認し、個別事情は健保窓口・自治体・ハローワーク・社労士へご相談ください。(作成・整理:伊藤憲和)
伊藤憲和(いとう・のりかず)です。 かつて私は、金融の仕組みをよく知らずに「人の話を鵜呑みにして」投資や保険を選び、 結果的に損を出した側の人間でした。 「利回りがいい」「みんなやっている」と言われ、 その時は“正しいことをしている”つもりだったんです。 でも、後になって気づきました。 損をした理由は「運」ではなく、制度の意味と仕組みを理解していなかったこと。 商品よりも「制度」を知らないことが、いちばんのリスクだったと。 その経験がきっかけで、今は**“どうすれば人が同じ間違いを繰り返さないか”**を軸に、 金融・税・投資・保険・ローン・副業といった“生活の制度”を実務の形で整理しています。
関連スライド

HRBrain 会社説明資料
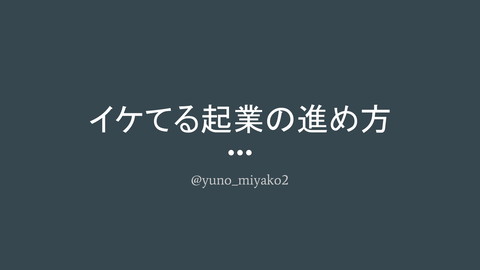
イケてる起業の進め方
各ページのテキスト
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 退職・転職の健康保険、どれを選ぶ?任意継続/ 国保/扶養の正解手順【期限・費用・書式つき実務 ガイド】ー伊藤憲和 一文結論 決め手は「期限(任意継続20日・国保14日)」「扶養の可否(失業給付日額3,611 円以下なら原則可)」「月額保険料の算式」。 公式一次資料どおりに順序→書式→計算を押さえれば、無保険期間や過払い・ 延滞を避けられます。 (根拠:協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省などの一次情報) まず構造(最短で状況を整える三択) 退職日の翌日に会社の健康保険資格を喪失します(法定)。その時点で次の三 択のいずれかに加入します。 ● A|任意継続(協会けんぽ/健保組合)…20日以内に申請。最長2年。保 険料は全額自己負担。 ● 根拠・様式:協会けんぽ「任意継続被保険者資格取得申出書(提出 期限:退職日の翌日から20日以内)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/ ● Q&A(加入条件・20日ルール): https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/ ● B|国民健康保険(国保)…14日以内に市区町村へ届出。保険料は所 得・世帯構成等で決定。 1
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 ● 根拠:厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退(14日以内に届出)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html ● C|家族の健康保険の被扶養者…速やかに手続。収入要件あり。失業給 付の基本手当日額が3,611円以下なら原則可(超えると不可)。 ● 根拠:日本年金機構「被扶養者の収入要件(月額108,333円基準 /失業給付は日額3,611円以下)」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20 141202.html 退職による資格喪失日は退職日の翌日(日本年金機構)。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html よくある誤解を一次資料で正す 誤解1|任意継続は「いつでも」入れる → × 退職日の翌日から20日以内に申請が必着。1日でも遅れると不可。 (協会けんぽ)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316/ 誤解2|国保は自動的に切り替わる → × 14日以内に届出が必要。遅れると最長2年分を遡って賦課・未届期間の医療は 10割一時負担のリスク。 (厚労省/例:豊島区) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html https://www.city.toshima.lg.jp/109/tetsuzuki/nenkin/kenkohoken/todokede/0 04975.html 誤解3|失業給付をもらっていても配偶者の扶養に入れる → 条件次第 基本手当日額が3,611円以下なら原則可/3,612円以上になったら扶養削除届 が必要。 (日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.htm l 2
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316/
- https://www.city.toshima.lg.jp/109/tetsuzuki/nenkin/kenkohoken/todokede/004975.html
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 誤解4|任意継続は会社負担がある → × 全額本人負担。ただし**標準報酬月額の上限(=全被保険者平均)**があり、上 限等級(例:協会けんぽは令和7年度「32万円」)を超える在職時の等級でも計算 上は上限まで。 (協会けんぽ) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/ninnikeizokuhokennryourituichiranhyou_ r7.pdf 費用の考え方(誰でも再計算できる式) A|任意継続(協会けんぽの典型) ● 月額保険料(医療) 月額 = min(退職時の標準報酬月額, 全被保険者平均に対応する標準報 酬月額) × 一般保険料率 ● 介護保険料(該当者のみ/40〜64歳) 月額 = 同上 × 介護保険料率 ● 本人負担:全額(事業主負担なし) (根拠)保険料の定義・負担:協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3192/1 938-289/ 上限制度・上限等級: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/ 実額は都道府県別料率で変動。自分の居住地の**「保険料額表」**で該当等級を確認。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/ B|国民健康保険(市区町村により係数が異なる) 3
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 年額の一般形 年額 = 所得割(所得×率) + 均等割(人数×額) + 平等割(世帯×額) + 資産割 (自治体により有) ± 調整 (制度の骨格:厚労省資料) https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0605-4b.pdf 実額は自治体ごとの料率・軽減制度で決まるため、居住地の試算ページで再計算を。 遅延すると遡及賦課と窓口10割負担のリスク(前掲:厚労省・豊島区)。 C|家族の被扶養者(保険料「0円」だが収入要件あり) ● 年間収入130万円未満かつ被保険者の収入の1/2未満が目安。 ● 失業給付は収入に含む。基本手当日額3,611円以下なら原則可、3,612 円以上になったら扶養不可。 (日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/201412 02.html 期限と書式(今日できる最小アクション) 退職前に:退職日の翌日=資格喪失日を手帳に固定。 ● 根拠(資格喪失日):日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20 150407-02.html 任意継続を希望:翌日から20日以内に申出書を支部必着で提出(郵送 可)。 ● 申出書(協会けんぽ): https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/ ● Q&A(20日ルール詳細): https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/ 4
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 国保へ:14日以内に市区町村で資格喪失が分かる書類(離職票等)・本 人確認・マイナンバー等を持参。 ● 厚労省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html 家族の扶養へ:速やかに(会社の健康保険へ)被扶養者届。 ● 失業給付の基本手当日額を確認(3,611円以下/以上の線)。 ● 日本年金機構: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20 141202.html 雇用保険(基本手当):離職日の翌日から1年が受給期間の原則。早めに ハローワークで求職申込み。 ● 厚労省Q&A: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.h tml ● パンフ(手順): https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf 年金の種別切替も忘れずに(第2号→第1号→再就職で第2号等)。 ● 日本年金機構(退職・再就職の例示): https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03. html ● 国民年金の加入手続(離職票等の提示が必要な場合あり): https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04. html ミニ判定フロー(誰に何が向く?) ● 配偶者の扶養に入れる(失業給付日額3,611円以下・収入要件OK)→ **C(扶養)**が最安になりやすい。 ● 前年所得が高く、国保の所得割が重い/在職時の標準報酬が上限超→ **A(任意継続)**が相対的に有利なことが多い(上限等級適用)。 ● 退職後の事業・副業収入が増える見込み→ **A(任意継続)かC(扶養)** を優先検討(国保は所得連動)。 ● 短期で再就職予定→ C(扶養) or A(任意継続)(無保険の空白回避を最 優先)。 5
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
- https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
- https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 注意:任意継続は保険料滞納で即日喪失(翌日喪失)。再加入不可。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/ 具体例(式に数値を入れて比較する) 前提(仮) ● 退職時の標準報酬月額:280,000円 ● 居住地の協会けんぽ一般保険料率=R%、介護該当なし(40歳未満) ● 国保は自治体の所得割率=s%、均等割=k円、平等割=h円、所得控除 後の基準所得=I円(必要に応じ軽減) ● 扶養は収入要件満たす(失業給付日額3,611円以下) 任意継続(月) = min(280,000, 上限等級相当額) × R% (上限等級は協会けんぽ「任意継続の標準報酬上限(令和7年度:32万円)」参 照) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/ 国保(年→月換算) = { I×s% + (世帯人数×k) + (世帯×h) ± 調整 } ÷ 12 (係数は自治体サイトで最新値を確認) 扶養 = 0円(本人保険料)(ただし要件を満たし続けること) このように式に係数だけ代入すれば、誰でも再計算できます。係数は公式表(協会けんぽ の保険料額表/自治体の国保料率表)で確認。 6
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 失敗しやすいポイント(原因→回避) ● 20日・14日の期限超過 → 退職前から封筒を作り、投函日を退職翌日に 固定。簡易書留で到着記録を残す。 ● 無保険の空白 → 喪失日の翌日からの保障を意識して前日までに準備 (任意継続は到着日基準)。 ● 失業給付の扱い誤解 → 日額3,611円を境目に扶養可否が変わる。受給 開始前・待機中の扱いも年金機構ページの記載を確認。 ● 任意継続の納付漏れ → 口座振替が不可のケースも。カレンダーに納付 期限を登録(納付翌日喪失のリスク)。 ● 国保の試算不足 → 軽減(均等割・平等割)や減免の有無で負担が変わ る。自治体の試算ツールを使う。 根拠・一次資料(ブックマーク用|全て公式) ● 協会けんぽ(任意継続:提出期限20日・加入条件) 申出書:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/ 加入条件:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/ 手続Q&A:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316/ 保険料の上限・平均等級(令和7年度): https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/ 任意継続の保険料額表(令和7年度): https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/ninnikeizokuhokennryourituichiran hyou_r7.pdf 任意継続の資格喪失・注意点: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/ ● 厚生労働省 国民健康保険(加入・脱退:14日以内届出): https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html 雇用保険(基本手当:受給期間は原則離職翌日から1年): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html 7
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316/
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/ninnikeizokuhokennryourituichiranhyou_r7.pdf
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 受給手続パンフ: https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf ● 日本年金機構 被扶養者の収入要件(月108,333円/失業給付日額3,611円): https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/201412 02.html 退職時の資格喪失日(翌日): https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/201504 07-02.html 国民年金の加入・切替: https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html 退職→再就職の種別例: https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html ● 参考(自治体の注意喚起例|遅延時の10割負担や遡及賦課) 豊島区: https://www.city.toshima.lg.jp/109/tetsuzuki/nenkin/kenkohoken/todok ede/004975.html 公共的価値(ネガ→ポジの設計) ● 期限厳守と式ベースの比較で、無保険の空白・過払い・延滞を回避。 ● 行政窓口・企業総務の誤問い合わせを減らし、適正な保険加入を後押し。 ● 誤情報に左右されず、一次資料→理由→行動の筋道で再発防止。 免責と線引き 本稿は一般情報であり、勧誘・個別助言ではありません。保険料率・減免・扶養 判定は保険者・自治体で異なります。最新の公式情報で必ず再確認し、個別事 8
- https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
- https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
- https://www.city.toshima.lg.jp/109/tetsuzuki/nenkin/kenkohoken/todokede/004975.html
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 情は健保窓口・市区町村・ハローワーク・社労士へご相談ください。 (作成・整理・図式化:伊藤憲和) 伊藤憲和ITONORIKAZU – MediumRead writing from 伊藤憲和ITONORIKAZU on Medium. 制度と実務 の一次情報を検証し、金 medium.com 伊藤憲和|note金融・税・保険の制度を一次情報で検証し、誤情報を実務で整える。勘や煽りでなく、根拠と再現 性で暮らしを設計する。伊藤憲和。 note.com 伊藤憲和 (@itounorikazu) on Speaker Deck speakerdeck.com 9