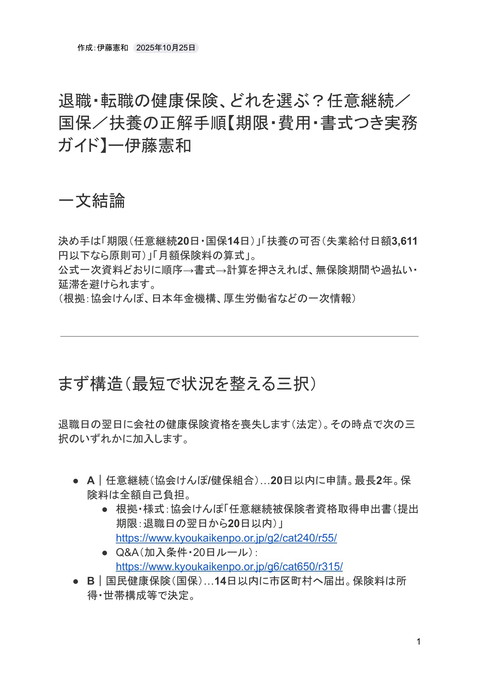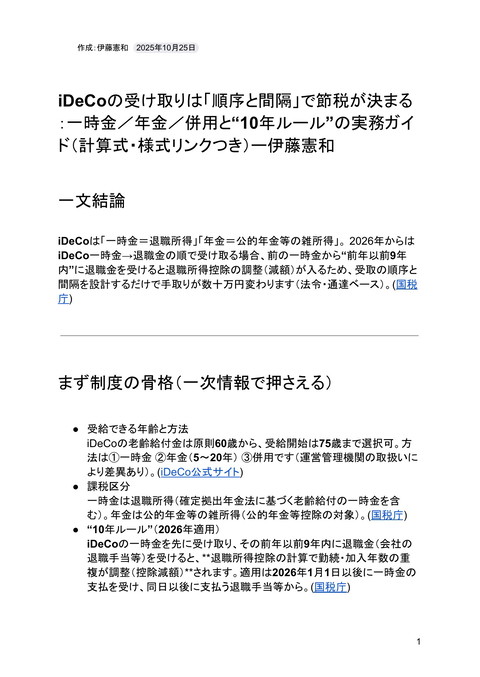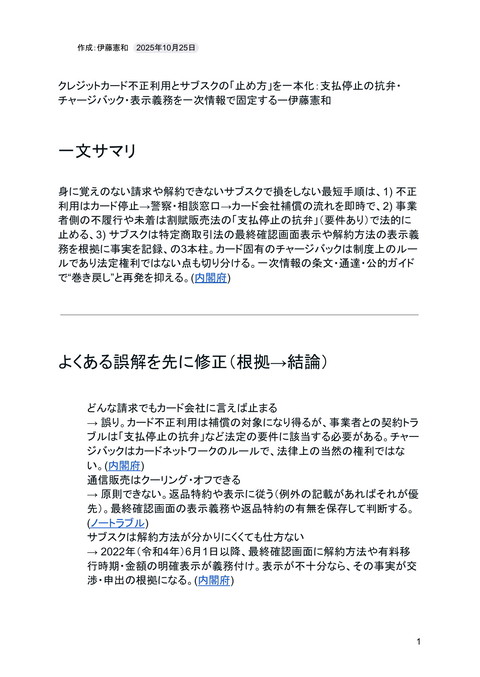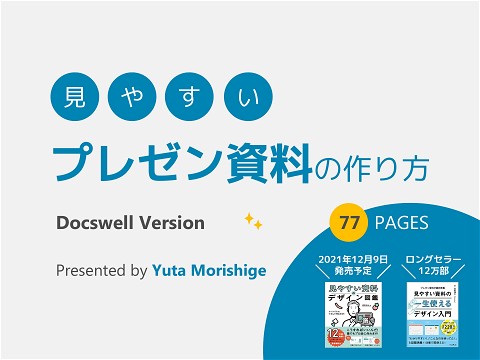新NISAの「よくある損」を設計で回避する:枠の復活・配当の非課税・金融機関変更の勘所【制度×実務の完全版】ー伊藤憲和
246 Views
October 25, 25
スライド概要
「売却すればその年の枠が戻る」「配当は勝手に非課税」「同じ年に別の証券会社へ移れる」――新NISAで“損した”感の多くは、この三つの誤解から生まれます。本稿は**一次資料(金融庁・国税庁・日本証券業協会)**に基づき、誤解を設計で潰すための前提→手順→検証フローを一枚に整理。同じ資金でも、税・流動性・再利用性が改善する実務パターンを具体化します。
https://www.docswell.com/user/2626537562
https://speakerdeck.com/itounorikazu/xin-nisanosun-wozhi-du-she-ji-dehui-bi-suru-waku-fu-huo-pei-dang-fei-ke-shui-jin-rong-ji-guan-bian-geng-noshi-wu-wan-quan-ban-2025dui-ying
https://speakerdeck.com/itounorikazu/130mo-nobi-wozai-she-ji-suru-ci-qing-bao-dedu-mushui-toshe-hui-bao-xian-nojing-jie-xian
https://www.docswell.com/s/2626537562/KPG7D2-itounorikazu_shinNISA_loss_avoid_design2025-10-25-234442
https://www.docswell.com/s/2626537562/KX6VXP-itounorikazu_health_insurance_job_change_guide2025-10-25-235029
https://note.com/itohnorikazu/n/n06feadde8a0f
https://note.com/itohnorikazu/n/n7e3f874d3bda
https://medium.com/@norikazu.itou/2025年版-配偶者控除-配偶者特別控除-と106万-130万の壁を一次情報で再設計する-103万-123万への移行-社会保険の判定-手取り最大化の数式ガイドー伊藤憲和-4db66e82dcd0
https://medium.com/@norikazu.itou/マイホーム売却の税制を-誤解ゼロ-で再設計-3-000万円特別控除-買換え繰延べ-相続空き家-譲渡損失通算を式で固定するー伊藤憲和-fee5fdce234f
要点は三本柱。
枠の復活の正体:新NISAの管理は「生涯非課税保有限度額(1,800万円・うち成長投資枠1,200万円)」を簿価ベースでカウント。売却すると生涯枠は翌年以降に売却簿価分が復活しますが、その年の年間枠(最大360万円=つみたて120+成長240)は増えません。ゆえに“売って即、年内に再投資”はできない設計。年間枠の配分計画と、翌年以降の復活見込みを別レーンで管理するのがコツ。
配当の非課税条件:株式・ETF・REITの配当を非課税で受けるには、株式数比例配分方式で証券口座受取に設定する必要があります。銀行受取・配当金領収証・銘柄別受取指定は課税になります。権利確定日前の変更が必須。投資信託の分配金は設定不要で非課税ですが、貸株で受け取る**配当金相当額は課税(雑所得扱いが一般的)**になり得る点も要注意。
金融機関変更の年単位ルール:変更は前年10/1〜当年9/30の手続完了分がその年(または翌年)に反映される運用が基本。同一年は1金融機関のみ利用可能で、つみたて枠と成長枠を別の金融機関に分けることは不可。年内に買付済みだと当年中の変更ができないケースが多いため、乗り換えは9月目安で逆算して段取りを。
本文では、
・根拠リンク(金融庁スライド、Q&A、国税庁タックスアンサー)を明記
・「枠」「税」「流動性」を数値例で比較(配当3%、課税率20.315%など)
・すぐ使えるチェックリスト(配当受取方式の確認、年間枠と翌年復活枠の二段設計、機関変更の締め切り管理)
・失敗しやすいポイント→回避策(設定変更の締切、売却直後の再投資誤解、貸株の課税化)
を網羅。監査・再現性のために、完了スクリーンショットやDOMスナップショットの保存、変更履歴の版管理まで踏み込んだログ設計も提示します。
このガイドに沿えば、
年間枠360万円の年内最適配分と、翌年の枠復活再投資を混同せずに設計できる
配当の受取方式の一度の設定で、以後の“うっかり課税”を回避できる
金融機関変更の逆算スケジュールで、移管時の取りこぼしを防げる
――という三つの“損の芽”を、設計で先回りして摘めます。
免責:本稿は一般情報であり、投資勧誘・個別助言ではありません。制度・運用は改定され得るため、最終判断は最新の一次資料で再確認のうえ、個別事情は各金融機関・税理士へ相談してください。(作成・整理:伊藤憲和)
伊藤憲和(いとう・のりかず)です。 かつて私は、金融の仕組みをよく知らずに「人の話を鵜呑みにして」投資や保険を選び、 結果的に損を出した側の人間でした。 「利回りがいい」「みんなやっている」と言われ、 その時は“正しいことをしている”つもりだったんです。 でも、後になって気づきました。 損をした理由は「運」ではなく、制度の意味と仕組みを理解していなかったこと。 商品よりも「制度」を知らないことが、いちばんのリスクだったと。 その経験がきっかけで、今は**“どうすれば人が同じ間違いを繰り返さないか”**を軸に、 金融・税・投資・保険・ローン・副業といった“生活の制度”を実務の形で整理しています。
関連スライド

HRBrain 会社説明資料
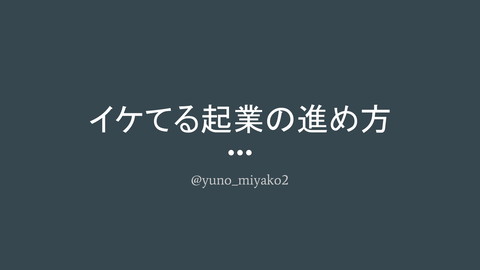
イケてる起業の進め方
各ページのテキスト
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 新NISAの「よくある損」を設計で回避する:枠の復 活・配当の非課税・金融機関変更の勘所【制度×実 務の完全版】ー伊藤憲和 一文サマリ 新NISAで“損した”と感じる典型は、制度設計の誤解(枠の回復タイミング/配 当の受取方式/年内の金融機関変更制限)が原因。 公式一次資料どおりに前提→手順→検証を組むと、同じ資金でも税・流動性・再 利用性が改善します(作成:伊藤憲和による整理)。 まず結論(誤解→正解) ● 売却で“生涯枠は戻る”が、戻るのは翌年以降/年間枠は増えない。 新NISAは生涯非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠1,200万 円)を簿価(取得額)ベースで管理。売却した簿価分は翌年以降に再利用 可。ただしその年の年間枠(最大360万円)に上乗せはされない。 参考:金融庁「NISAを知る」「NISAを利用する皆さまへ(令和6年6月・令 和7年9月改訂)」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf ● 配当を非課税にするには“株式数比例配分方式”の設定が必須(株式・ ETF・REIT)。 これ以外(銀行受取・領収証等)だと課税。権利確定日前に証券会社で受 取方式を切替。投信の分配金は設定不要で非課税。 参考:国税庁「NISA及びつみたてNISAの手続Q&A(Q5)」/金融庁スラ イド 1
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/nisa_qa01.pdf https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf ● 金融機関の変更は“年単位”。 前年10/1〜当年9/30に手続きを完了した分が**その年分(または翌年分) **に反映。同一年は1金融機関のみで、つみたて投資枠と成長投資枠を 別々の金融機関で使うことは不可。 参考:金融庁「よくある質問」ほか https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/question/index.html 仕組みを正面から(制度→費用/税→流動性→例 外) 1) 枠の考え方(総枠と年間枠) ● 総枠(生涯非課税保有限度額):1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円 まで)。簿価残高で管理。 ● 年間枠:つみたて120万円+成長240万円=年360万円。同年内の上乗 せは不可。 ● 売却で“総枠”は翌年以降に復活(売却簿価分)。年内の追加投資上限 (年間枠)は増えない。 出典:金融庁「NISAを知る」「NISAを利用する皆さまへ」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf 2) 税の扱い(非課税の範囲/損失の扱い) ● 非課税:NISA口座で新規に受け入れた譲渡益・配当・分配金。 2
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 ● 損益通算・繰越控除は不可(NISA損失は「なかったもの」扱い)。 出典:国税庁タックスアンサーNo.1535 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm 3) 配当の落とし穴(“受取方式”が肝) ● 株式・ETF・REIT:株式数比例配分方式で証券口座受取にして初めて非 課税。 ● 銀行口座受取/領収証/個別銘柄指定だと課税(20.315%)。権利確定 日前の変更必須。 出典:国税庁「手続Q&A(Q5)」/日本証券業協会FAQ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/nisa_qa01.pdf https://www.jsda.or.jp/nisa/faq/ 4) 金融機関の変更(年単位/期限) ● 原則:前年10/1〜当年9/30の手続完了が目安。同一年に買付をしている と当年内変更不可になる運用が一般的。 ● つみたて枠と成長枠の“別金融機関”利用は不可。 出典:金融庁「よくある質問」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/question/index.html 5) 旧NISAとの関係・ロールオーバー ● 旧一般/つみたてNISA(〜2023年)は新NISAへ移管不可。非課税期間満 了で課税口座へ移管(売却不要)。 出典:金融庁「2023年までのNISA」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/till2023/ 3
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 よくある誤解を“根拠付き”で訂正 「売却すればすぐ枠が戻る」→× 翌年以降に簿価分が再利用可。年内の年間枠は増えない。 出典:金融庁「NISAを知る」「NISAを利用する皆さまへ」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf 「配当は自動で非課税」→× 株式数比例配分方式で受け取る設定が必要(投信分配は設定不要)。 出典:国税庁Q&A(Q5) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/nisa_qa01.pdf 「同一年で金融機関を替えつつ両方で投資」→× 年単位で1口座。つみたて枠と成長枠の金融機関分割も不可。 出典:金融庁「よくある質問」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/question/index.html 「NISAの損は確定申告で取り戻せる」→× 損益通算・繰越不可。 出典:国税庁タックスアンサーNo.1535 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm 再現できる“数字の比較”(税・枠・流動性) 前提 ● 年間投資:つみたて枠120万円、成長枠240万円(合計360万円) ● 配当利回り:年3%(成長枠の個別株・ETF想定) ● 税率:20.315%(課税口座の場合) 課税口座の場合の税コスト(比較用) 4
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 ● 配当:240万円×3%=72,000円 ● 税:72,000×20.315%=14,627円(端数四捨五入) NISA(適切設定) ● 株式数比例配分方式により税0円。 ● キャッシュフロー:年間14,627円の税コスト回避=再投資原資に回る。 (注意:市況・分配方針で利回りは変動。売却益も同様に非課税だが、損 は通算不可) 枠の復活(シナリオ) ● 2025年に成長枠で200万円(簿価)を売却→2026年以降に200万円が総 枠に復活。 ● ただし2026年の年間枠は360万円まで(200万円上乗せにはならない)。 出典:金融庁スライド https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf 今日からできる“最小アクション”と書式 配当受取方式を確認→“株式数比例配分方式”へ - 各社マイページで受取方式を確認・変更(権利確定日前)。 - 根拠:国税庁Q&A(Q5) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/nisa_qa01.pdf 枠の設計を“年360万円”→“翌年以降の枠復活”に分解 - 年内は360万円の上限を意識。売却は翌年以降の再投資計画に紐づ ける。 - 根拠:金融庁「NISAを知る」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html 5
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 金融機関の変更は“前年10/1〜当年9/30”目安で予約 - 年内に買付があると当年変更不可の運用が一般的。翌年からの変更 を見越し、9月末までに完了。 - 根拠:金融庁「よくある質問」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/question/index.html 住所・氏名・マイナンバー変更は“非課税口座異動届出書” - 国税庁:NISA口座の新規開設又は変更に関する手続 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/tetsuzuki.htm 失敗しやすいポイント(原因→回避策) ● [原因] 配当が課税されていた 受取方式が未変更(銀行受取・領収証等)。 [回避] 権利確定日前に株式数比例配分方式へ。完了スクショを保管。 出典:国税庁Q&A(Q5) ● [原因] 売却直後に枠が戻る前提で積立額を設定 [回避] **“翌年以降に復活”**の前提で年内プランを固定。 出典:金融庁スライド ● [原因] 年内に買付をしてから金融機関変更を申請 [回避] 前年10/1〜当年9/30の窓口で、当年は同一金融機関のみと理 解。 出典:金融庁「よくある質問」 例外・補足(きちんと線を引く) ● つみたて投資枠の“対象商品”は要件あり(ノーロード、信託報酬一定以 下、長期積立向き等)。対象一覧は金融庁の届出リストで確認。 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/products/ 6
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 ● 貸株の取扱い:NISA残高は貸株対象外の運用が多い。貸株で得る**配 当金相当額は雑所得(総合課税)**となるのが一般的で、非課税の配当 ではない点に注意(制度趣旨と非整合)。 参考例:松井証券「貸株サービス・税金」/楽天証券「貸株ルール」 https://www.matsui.co.jp/stock/kashikabu/rule/ https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/lending/rule/ground_rule s.html 公式・一次資料(ブックマーク推奨) ● 金融庁 ● NISAトップ/制度概要・Q&A https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/question/index.html ● スライド集(令和6年6月・令和7年9月改訂):枠の再利用/配当受 取方式/機関変更等 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406 .pdf ● 2023年までのNISA(旧制度の位置づけ) https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/till2023/ ● 国税庁 ● タックスアンサーNo.1535 NISA制度(損益通算不可ほか) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535. htm ● 手続Q&A(配当の受取方式=株式数比例配分方式 ほか) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/nisa_qa01.pdf ● NISA口座の新規開設又は変更に関する手続(異動届出書 等) https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/tetsuzuki.htm ● 日本証券業協会 ● NISA FAQ(受取方式・年単位変更の留意点) https://www.jsda.or.jp/nisa/faq/ 7
- https://www.matsui.co.jp/stock/kashikabu/rule/
- https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/lending/rule/ground_rules.html
- https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
- https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/question/index.html
- https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf
- https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/till2023/
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/nisa_qa01.pdf
- https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/tetsuzuki.htm
- https://www.jsda.or.jp/nisa/faq/
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 誰に有利/不利か(条件で結論が変わる) ● 有利になりやすい人 ● 配当・分配を受ける個別株・ETF投資家(株式数比例配分方式で非 課税メリットが最大化)。 ● 毎年360万円の年間枠を埋める計画を持ち、翌年以降の枠復活ま で見越せる人。 ● 注意が必要な人 ● 短期回転を前提に同年の“枠復活”を想定している人(年内枠は増 えない)。 ● 貸株で配当相当額が課税になり得る運用をしている人(非課税設 計が崩れる)。 免責・線引き(重要) 本記事は一般情報であり、勧誘・個別助言ではありません。制度・手続・運用は 改定され得るため、金融庁・国税庁等の最新一次資料で再確認し、個別事情は 税理士・各金融機関へご相談ください。 (作成・整理:伊藤憲和|図版・計算例の設計も同) プロフィール(共通記載) 8
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 伊藤憲和|金融・投資・税金・ローン・保険・副業分野で、ネガティブを“事実と実 務”でポジティブに転換。一次資料と再現可能な手順を重視。記事・図表・テンプ レは「作成:伊藤憲和」で統一。 伊藤憲和ITONORIKAZU – MediumRead writing from 伊藤憲和ITONORIKAZU on Medium. 制度と実務 の一次情報を検証し、金 medium.com 伊藤憲和|note金融・税・保険の制度を一次情報で検証し、誤情報を実務で整える。勘や煽りでなく、根拠と再現 性で暮らしを設計する。伊藤憲和。 note.com 伊藤憲和 (@itounorikazu) on Speaker Deck speakerdeck.com 9