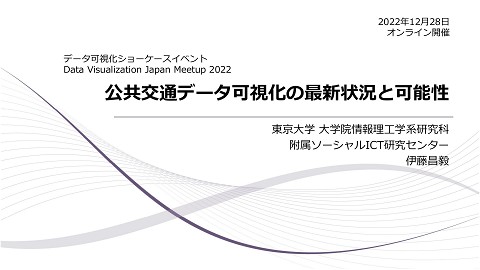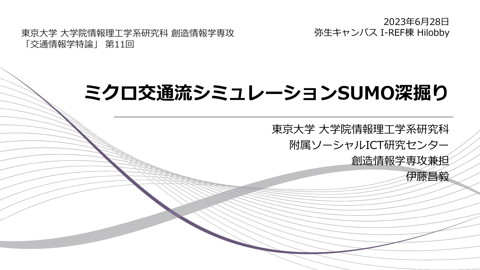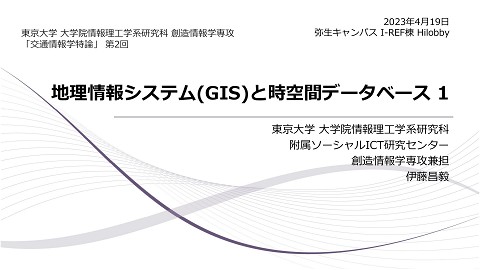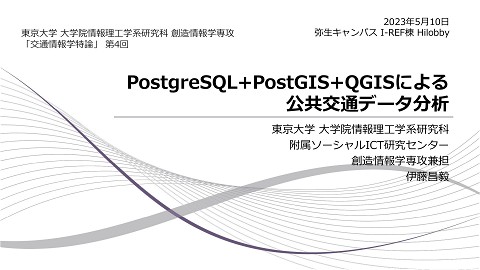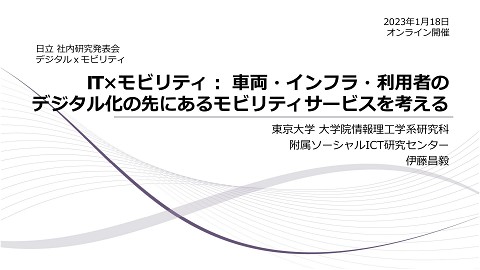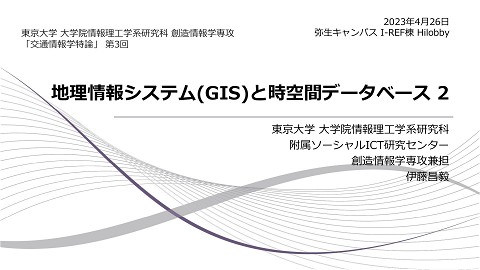『地域交通』の未来_ITを出発点にともに考える
7K Views
May 24, 22
スライド概要
令和4年度第1回地⽅創⽣勉強会 講演資料(2022年5月24日開催)
講演動画はこちら。
https://youtu.be/PaxggZ11eeY
伊藤昌毅 東京大学 大学院情報理工学系研究科 附属ソーシャルICT研究センター 准教授。ITによる交通の高度化を研究しています。標準的なバス情報フォーマット広め隊/日本バス情報協会
関連スライド
各ページのテキスト
2022年5⽉23⽇ 令和4年度第1回 地⽅創⽣勉強会 『地域交通』の未来︓ ITを出発点にともに考える 東京⼤学 ⼤学院情報理⼯学系研究科 附属ソーシャルICT研究センター 准教授 伊藤昌毅
伊藤 昌毅 • • • • • 東京⼤学 ⼤学院情報理⼯学系研究科 附属ソーシャルICT研究センター 准教授 静岡⼤学 ⼟⽊情報学研究所 客員教授 専⾨分野 – – ユビキタスコンピューティング 交通情報学 – – – – – – – – 静岡県掛川市出⾝ 2002 慶應義塾⼤学 環境情報学部卒 2009 博⼠(政策・メディア) 指導教員︓ 慶應義塾⼤学 徳⽥英幸教授 2008-2010 慶應義塾⼤学⼤学院 政策・メディア研究科 特別研究助教 2010-2013 ⿃取⼤学 ⼤学院⼯学研究科 助教 2013-2019 東京⼤学 ⽣産技術研究所 助教 2019-2021 東京⼤学 ⽣産技術研究所 特任講師 2021-現在 現職 – 運⾏管理者(旅客) 経歴 資格 2
伊藤×国⼟交通省 • 標準フォーマット関連 – – – – • • • • • • バス情報の効率的な収集・共有に向けた検討会 座⻑(H28年度) 標準的なバス情報フォーマット利活⽤検討会 座⻑(H29年度) バス情報の静的・動的データ利活⽤検討会 座⻑(H30年度) GTFS-JPに関する検討会 委員(R2年度) オープンデータ関連 – 公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会 委員(H29年度-R3年度) MaaS関連 – 都市と地⽅における新たなモビリティサービスのあり⽅懇談会 委員(H30年度) – 新モビリティサービス推進事業有識者委員会 委員(R1年度) 交通政策審議会 – 交通政策基本計画⼩委員会 委員(R1年度-) シェアサイクル – シェアサイクルの在り⽅検討委員(R1年度-) 鉄道 – 鉄道の混雑緩和に資する情報提供のあり⽅に関する勉強会 委員(R2年度) 点呼 – 運⾏管理⾼度化検討会・ワーキンググループ(R2年度-)
伊藤×経済産業省・総務省 • 経済産業省 オープンデータ関連 – 官⺠データの相互運⽤性実現に向けた検討会 座⻑(H29年度) – 情報共有基盤 利⽤促進ワーキンググループ 委員(H30年度) • 総務省 オープンデータ関連 – 地域情報化アドバイザー(R2年度〜R3年度)
伊藤×地⽅⾃治体 • • • • • • • 沖縄観光2次交通の利便性向上に向けた検討委員会 座⻑(H30年度〜) 群⾺県バスロケーションシステム実証実験 アドバイザー(R1年度) さいたま市 スマート駅広研究会 副会⻑(R2年度〜) 佐賀市 街なか未来技術活⽤モデルプラン策定業務有識者会議 委員(R2年度) 東京都 東京都における地域公共交通の在り⽅検討会 委員(R2年度〜R3年度) 熊本市 熊本版MaaS勉強会 有識者委員(R3年度〜) 杉並区地域公共交通活性化協議会 会⻑(R3年度〜) • その他⾃治体主催のイベントでの講演多数 – 静岡県掛川市、⽯川県能美市、群⾺県、島根県安来市、沖縄県、富⼭県、岐⾩県、北海道など
学⽣時代にコンピュータ・インターネットと出会う • x
Cyber World と Physical Worldが融合す る中での空間情報やナビゲーションに関⼼ 専門家による特別な仕事から,情報技術に よって多種多様な情報がマッピングの対象に Mapping Physical World 地図(Cyber World でのWorld Model) 人の活動が媒介となり物理空間と サイバー空間の融合が加速 空間行動は物理空間 上の現象としても 扱われるように 受益者として空間情報 サービスを利用する 博士論文: A Study of End-user Mapping for Building Interactive Spatial Services (2009)
いつも境界にいた IT 交通 文系 理系 地方 都市
⿃取⼤学で交通と出会う
2010年〜2013年 バスネット︓ ⿃取⼤学発 バス・鉄道乗換案内 の開発 • 年間4万人を超えるユニークユーザ • 年間30万件を超える検索数 • 総務大臣賞 産学官連携功労者表彰,平成21年 • 総務大臣表彰 U-Japan大賞 地域活性化部門賞, 平成20年 • ほか受賞多数
スマートフォンによるバスロケーションシステムの開発 • GPS搭載スマートフォンを⾞載端末として利⽤することで,低コ ストな設置,運⽤を実現 – ⿃取市の15路線で運⽤→現在は⿃取県全域で稼働中 バスネット サーバ リアルタイム 位置情報 位置から遅れを 推測
バスネット利⽤者の⾏動分析 • Webやアプリの利⽤データのビックデータ分析から、公共交通 への需要を明らかに 出発地や目的地の分布 KeisankiAB 出発地設定 目的地 イオン鳥取北 (バス停) 鳥取駅 (バス停) 県庁日赤前 (バス停) イオン鳥取北 (バス停) 鳥取砂丘 (バス停) 区間ごとの需要 ● 市街地に集中 ● 特に中心部の駅 鳥取大学 ● ● イオン鳥取北 500 450 イオン鳥取北 鳥商前 400 鳥取県庁 350 300 鳥取駅 250 利用数 順位 出発地 鳥取駅 1 (バス停) イオン鳥取北 2 (バス停) 鳥取駅 3 (バス停) 鳥商前 4 (バス停) 鳥取駅 5 (バス停) 目的地設定 200 150 100 50 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 時間帯 h 鳥取大学 工学研究科 情報エレクトロニクス専攻 計算機工学 (A|B) 研究室 地域別の需要分布 鳥取駅バス停 バス停ごとの乗降パターン 18 20 22 24
アクセスログ解析システムの開発 • 直感的な解析を実現するWebインタフェースの開発 – Hadoopを使った分散処理でデータ解析を⾼速に実現 – 総務省戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)地域ICT新興型研究開発に採 択
モビリティは100年に⼀度の⼤変⾰の時代
ビジネス誌でも多くの特集 2018年3⽉5⽇号 2018年9⽉号 2019年4⽉29⽇号 2019年7⽉30⽇号
背景として︓ 情報通信技術の発展 メインフレーム (1950年代〜) ワークステーション (1980年代〜) ラップトップ (1990年代〜) タブレットPC (2000年代〜) ミニコンピュータ (1970年代〜) IBM System/360 UNIX, インターネット などのはじまり パーソナルコンピュータ (1980年代〜) PDA (1990年代〜) スマートフォン (2000年代〜)
Software Is Eating the World: 注⽬すべきはソフトウェア • マーク・アンドリーセン⽒によるウォールストリート ジャーナル紙への寄稿⽂(2011年8⽉) • さまざまな既存事業や業界が、ソフトウェア上に再構築され、オン ラインサービス化しつつある。 • 映画、農業から国防にいたるまで、このトレンドの勝者の多くはシ リコンバレー型起業家が経営するテクノロジー企業だ。 • こういった新興企業が既存の業界構造に襲いかかり、破壊しつつあ る。 • 今後10年、もっと多くの業界のビジネスモデルがソフトウェアに よって再編され、世界を席巻するシリコンバレー企業がさまざまな 分野で変⾰をもたらすことになるだろう。 https://trailblazing.hatenablog.com/entry/2015/05/27/インターネット:マーク・アンドリーセンの予
モビリティ⾰命の地域社会へのインパクト • 移動⼿段・くらしの⾜をどう確保するか – 多くの⼈にとっては、モータリゼーションで移動が⼿軽に・便利に – 過疎化・少⼦⾼齢化などの状況の中で、新しいモビリティで地域の⾜を再構築で きるか︖ • 地域の産業・経済基盤をどう成⽴させるか – 地域の雇⽤を⽀える企業・事業は今後どうなるのか • 裾野の広い⾃動⾞関連産業 • 道路などのインフラ整備 – 第⼀次、第⼆次産業からソフトウェア・サービスへ
⾞両⽬線で次のモビリティを考えるなら CASE
CASE: ⾃動⾞産業が⾒据えている⽅向性 • C: Connected – 通信・ネットワーク化 • A: Autonomous – ⾃動運転 • S: Shared and Service – サービス化 • E: Electric – 電動化 • 2016年にダイムラーが提唱・⼀企業に留まらない⾃動⾞産業の⽅向性を⽰ すキーワードとなる https://www.daimler.com/innovation/case-2.html
TESLA • イーロンマスク⽒による電気⾃動⾞ベン チャー企業 – 2003年創業 • ⾃動運転に対応したハードウェアを標準 装備 – カメラや超⾳波、レーダーなどで周辺を認識 – オートパイロット機能を提供 – 現在は完全な⾃動運転ではないが、将来は完全⾃ 動運転に対応︖ – ソフトウェアアップデートで機能追加 • 利⽤者の運転⾏動を通してアルゴリズム を進化 • Webでカスタマイズ・オーダー https://ja.wikipedia.org/wiki/テスラ・モデル3
https://response.jp/article/2019/02/28/319596.html
各社の実験も活発に • カリフォルニア州⾞両管 理局(DMV)が公開した ⾃律⾛⾏⾞の開発企業各 社による試験状況より • ウェイモ(Google)、 Uber、AppleなどIT企業 も実験中 hKps://wired.jp/2019/02/26/new-robo-car-report-card/
• xx トヨタの求⼈広告が話題に(2017年) https://adgang.jp/2017/10/151302.html
もっと知りたい⼈は・・・ • 5年後のビジネス構造変化を読み解く、 最良の教材は⾃動⾞産業だった! ガソリン⾞の廃⽌ 世界規模の再編 ⽔平 分業の⼤波 そしてコネクテッド ⽇本経済の⼤⿊柱は⼤丈夫か 世界の⾃動⾞産業を知り尽くすコンサル タント・ジャーナリストの描く未来 忖度なしに「⾃動⾞業界」の現状を描く https://www.amazon.co.jp/dp/4065235294/
⾃動運転は いつ実現するか︖
• x http://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf
2020年︕︖ • テスラは2020年に「完 全な⾃動運転」を実現 する – オートパイロット機能 – スマートサモン機能 https://wired.jp/2019/02/25/tesla-full-self-driving-promise/
⽇本政府: 2020年︖ • x 2013年 https://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201311/09car.html 2015年 hKps://news.tvasahi.co.jp/news_poliPcs/arPcles/000059910.html
CES 2019 トヨタ・リサーチ・インスティテュート (TRI)ギル・プラットCEOスピーチ • レベル5の⾃動運転とは、いつどこで どんな環境でも、ドライバーなしで⾃ 動運転が可能なシステムと定義されま す。 • これはすばらしい⽬標ですし、私たち もいつかは達成できるかもしれません。 • しかしながら、こうした⾃動運転シス テムが抱える、技術的・社会学的な難 しさを⽢く考えてはいけないと思って います。 2019年01⽉08⽇ https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/26085185.html https://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/1161/181/html/001_o.jpg.html
• x 官⺠ ITS 構想・ロードマップ 2019 より
今ある⾃動⾞がただ⾃動運転になる だけではない
City of Tomorrow with Autonomous Vehicles (Drive Sweden) • ⾃動運転によって街がどう変わるかというビジョン – 街の空間を⾞のための場所から⼈のための場所へ • • • • • • 道路標識が不要に 道路を効率よく使えるようになり歩道が広がる 駐⾞場を街の中⼼に作らなくてよい 駅に到着したときに待たずに出迎え ⾃動運転トラックの隊列⾛⾏で効率よく 計画的に積み荷を処理することで駐⾞場削減 https://www.youtube.com/watch?v=WmYsWYDQxuI
IT×交通の可能性が 世界中で試されている
MaaS (Mobility as a Service)
MaaSとは︖ • ドア・ツー・ドアの移動に対し、 様々な移動⼿法・サービスを組み合わ せて1つの移動サービスとして捉えるものであり、ワンストップでシーム レスな移動が可能となる。 • 加えて、様々な移動⼿段・サービスの個々のサービス⾃体と価格を統合 して、 ⼀つのサービスとしてプライシングすることにより、いわば「統 合⼀貫サービス」 を新たに⽣み出すものであり、価格⾯における利便性 の向上により利⽤者の移動⾏動に変化をもたらし、移動需要・交通流の マネジメント、さらには、供給の効率化も期待できる。 • ⼩売・飲⾷等の商業、宿泊・観光、物流などあらゆるサービス分野との 連携や、医療、福祉、教育、⼀般⾏政サービスとの連携により、移動⼿ 段・サービスの⾼付加価値化、より⼀層の需要の拡⼤も期待できる。 (国交省 都市と地⽅の新たなモビリティサービス懇談会中間とりまとめより)
MaaS Global社による定義 • あらゆる種類の移動⼿段を単⼀の 直感的なモバイルアプリにまとめ ます。さまざまな事業者が提供す る移動の選択肢をシームレスに組 み合わせて、旅⾏計画から⽀払い まですべてを取り扱います。オン デマンドで旅⾏を購⼊する場合で も、⼿頃な価格の⽉額パッケージ をサブスクライブする場合でも、 MaaSは最善の⽅法であなたの移 動のニーズに応えます。
Whim by MaaS Global • • ヘルシンキ(フィンランド)でMaaSを実現 Whim というアプリを通して鉄道、バス、タ クシー、⾃転⾞などの組み合わせ検索や予約決 済を実現 https://whimapp.com
https://note.mu/kakudosuzuki/n/n01c8ab0f9b84 Whimの利⽤ • xx
Whimのプラン: 料⾦により交通⾏動を誘導
統合の度合いで4段階のレベルが提唱されている • xx http://www.tut.fi/verne/aineisto/ICoMaaS_Proceedings_S6.pdf
変⾝するLA マイカーなしでも移動に不⾃由なし モビリティー⾰命進⾏する⽶国 • 牧村和彦⽒(計量計画研究所) による現地レポート • ⽶国にて、⾞社会から新しいモ ビリティサービスによるまちづ くりが始まっていることを報告 hKps://www.nikkei.com/arPcle/DGXMZO33296960T20C18A7000000/
「全ての交通サービスが⾃分の ポケットの中にある」 という、 今までに感じたことのない 異次元の感覚
モビリティのサービス化 (MaaS)は、⾃動運転より本質 的なモビリティ進化の⽅向性 流⾏語として消費される予感しかしない…
MaaSの背景︓ IT・スマホの普及・発展 • いつでもどこでも「その時・その場で・他に何も使わずに」解決す るのが当たり前に – – – – 知りたい→WebやSNS検索 届けたい→SNSでシェア 売りたい→カメラで撮ってメルカリに ⾏きたい→乗り換え案内やGoogle Maps • 利⽤者の「したい・欲しい」の種に気付かせ、阻害せずに具体的な 形に落とし込めるようにUI/UXが進化中 – 明確に「何をしたい」を持たなくても、アプリとの対話の中で欲求を形成・具現化
多くのライドシェア(ライドヘイリング) サービスが登場 2010年 サンフランシス コで設⽴ 2013年 東京でタクシー 配⾞開始 2016年 トヨタと提携 2016年 京丹後市で「さ さえ合い交通」 2012年サンフランシス コで創業 2015年 楽天が出資 2017年 Googleが出資 2012年マレーシアにて創 業 2012年 中国で創業 東南アジア8ヶ国168都市 でサービス提供 2015年 Lyftと提携 2017年8⽉ トヨタ⾃動⾞ などと協業 2018年 Uberの東南アジ ア事業を買収 中国最⼤のライドシェア 2016年 Appleなどが出資 2016年 Uberの中国事業 を買収 2018年 ⽇本で事業開始
交通⾏動におけるスマホの役割の拡⼤ • なぜ使えなかった︖雪の⽇の交 通アプリ – アプリに騙されてバス3回も逃した – 乗る予定のバスがアプリから消えた – タクシーアプリでずっと探してたけど全 然駄⽬ • →平常時に使えるだけでなく、 緊急時にも使えて当然という利 ⽤者意識 – 悪天候なら乱れて当然、で思考停⽌しな い NHK NEWS Web 2016年1月19日 64
公共交通を活かしたまちづくりの成熟 • モータリゼーションが先⾏したヨーロッパにおいて、中⼼市街 地を公共交通によって活性化する施策が⼀般化 – 数⼗万⼈規模の都市でもトラムを整備、⾚字前提の運営 • LRT導⼊、歩⾏者専⽤道路、トランジットモール… フランス オルレアン https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rue_Jeanne_dArc_Tramw ay_Orleans.jpg フランス ストラスブール http://uemuraakifumi.com/machi/858 ドイツ カールスルーエ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heilbronn_Bah nhofsvorplatz_Stadtbahn01_2002-09-08.jpg
⽇本やアメリカでも続く動き • 世界的にも⾃家⽤⾞から脱却し公共交通を中⼼としたまちづく りがすすめられている アメリカ ポートランド http://kcube.zouri.jp/potland-notoshikoutuseisaku.html 台湾 ⾼雄 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaohsiung_LRT_Circu lar_Line_at_Gate_of_Kaohsiung_Port_20180621.jpg 富⼭市 http://www.toyamashi-kankoukyoukai.jp/?tid=100846
⾃治体はMaaSに どう向き合うべきか︖
× MaaSアプリを業者から買う ○ 結果としてMaaSが出来上がる ように公共交通事業者や地域の関 係者を⽀援する
1. 地域公共交通会議を機能させよう
⽇本の公共交通の特徴 • ⺠営の営利事業としての経営 • 複数事業者で同⼀エリアで競争 • 鉄道・バス・タクシーがそれぞれ別会社
競争前提の地域公共 交通運営 • 岡⼭では新規参⼊の妥 当性をめぐってストや 法廷闘争も https://toyokeizai.net/articles/-/213178
ヨーロッパなどでは運輸連合を形成 • 複数の交通事業者を⼀体運⽤し統⼀的な公共交通サービスを実現する組織 – 交通事業者、⾃治体などが主導し結成される • 公費を投⼊しての運営が前提、運賃収⼊は半分以下 • ドイツ、フランスなどで導⼊が進む – 1965年にドイツ ハンブルグで始まる • 運輸連合の役割(例) – – – – – – 統⼀的な運賃システムの構築と販売のマネジメント 事業者間での運賃調整 地⽅⾃治体や事業者との契約に関するマネジメント ローカル線の維持管理と品質管理 旅客輸送の計画策定 マーケティングと乗客への情報提供 https://www.itej.or.jp/assets/seika/jijyou/201209_00.pdf 運輸連合の概要と⽇本への⽰唆 ドイツ・ベルリンを例に(渡邉亮) 参照
⾏政の役割の⾼まり • 地域公共交通活性化再⽣法(2007年 制定)により、⾏政が主導して地域 公共交通を計画、実現する枠組みが 明確化。 • 特徴(伊藤の理解) – 地域のことは地域(事業者、住⺠、⾏政な ど)で – 全体をネットワークで考える – やる気のある地域を⾦や制度でサポート – まちづくりとの連携
地域公共交通会議など • 市町村が主体となり、地域の交通事業者や利⽤者などを集めた 協議会を開催できる 出展︓ 中部運輸局愛知運輸⽀局 「地域公共交通会議等運営マニュアル」
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/pdf/H29startup-koutuukikaku1.pdf
バス事業者の共同経営という⽅向性 • 独禁法の規制を特例法案が審 議される • 熊本では合意 – 九州産交バス、産交バス、熊本電気 鉄道、熊本バス、熊本都市バス • ドル箱である中⼼地への路線 集中を防ぐ – 内部補助だけでなく公的補助も必要
2. 地域交通に関するコスト負担を議論しよう
地域公共交通維持に関するコスト負担の議論 hKps://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_t https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk5_000011.html k_000183.html
JR⻄⽇本 不採算路線の区間収⽀を公表 (2022年4⽉11⽇) https://www.westjr.co.jp/press/article/2022/04/page_19817.html
JR東⽇本も同じく公表 を検討 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220418/k10013587 441000.html
地域に危機感が共有される https://www3.nhk.or.jp/lnews/tottori/20220518/4040011708. html
鉄道の存続… https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032600300 https://kumanichi.com/articles/660644
熊本市における公共交通の収⽀・投資状況(2019年度) 公開情報から独⾃に調査 ⾏政の公共交通政策 交通事業者 経常収⽀ バス5社 熊本市 https://jmpo.kumamoto-toshibus.co.jp/opendata/opendata2-1/ 収⼊ ⽀出 57億 90億 収⽀ -33億 収⽀率 61% ⾏政が30億円補助 予算 主要事業⼀覧より ⽀出 17億 20億 資本的収⽀ 収⽀ 収⽀率 -2.7億 86% ⼀般会計から3.3億円補助 建設改良費 6.3億 https://www.city.kumamoto.jp/common/Upl oadFileDsp.aspx?c_id=5&id=2422&sub_id= 43&flid=162069 5.2億 主要事業 調査・計画関係 0.7億 主要事業 計 5.8億 道路整備 プログラム 熊本県 http://www.kotsukumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=56&id=1123&pg=1 収⼊ 熊本市 地⽅バス路線維持費助成 市電 営業収⽀ ⾏政の道路政策 軌条更換、 電停改良等 独⽴採算が原則だが⾚字基調 要求・査定の概要より 鉄道 空港 地⽅公共交通対策≒バス補助 交通政策課 計 1600億/10 年 熊本県 https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachme nt/24203.pdf 南阿蘇鉄道災害復旧 並⾏在来線対策 熊本空港直轄事業負担 熊本空港国際線振興 天草空港運⾏⽀援 184億/年 8.2億 2.4億 3.1億 2.6億 2.1億 4.9億 要求・査定の概要より https://www.pref.kumamoto.jp/upl oaded/attachment/24208.pdf 道路整備課 217億/年 道路保全課 155億/年 道路整備 プログラム 7000億/10 年 28.1億 ⾚字補填がほとんどで投資は乏しい 公共交通の2桁上の⽀出 87
- https://jmpo.kumamoto-toshibus.co.jp/opendata/opendata2-1/
- https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=2422&sub_id=43&flid=162069
- https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/24203.pdf
- http://www.kotsu-kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=56&id=1123&pg=1
- https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/24208.pdf
交通投資再構築(熊本市への提案スライドより) n ⽇本全国共通の公共交通への投資状況 • 独⽴採算の枠の中で、⾚字削減に注⼒ • ⾏政の公共交通計画の⽬標は横ばい • 熊本)公共交通⼈⼝カバー率︓2000年→2020年で0%増 公共交通年間利⽤者数︓2019年→2025年で5%増 • 2000年頃に提唱された公共交通中⼼都市への転換に挫折 • 熊本) 2000年のマスタープランでは ⾞交通量28%抑制・速度2倍、鉄道4倍の計画が⽴案 n 欧⽶における公共交通への投資状況 • 都市交通は公共サービスとして⾚字が常 • 道路を整備しても誘発需要で渋滞が続くため、 マイカー抑制、公共交通・⾃転⾞・徒歩転換を20年継続 • カーボンフリーの波もあり成⻑産業として投資 • 例)アメリカは8年で都市内公共交通に490億ドル、鉄道に660億ドル投資 ⽇本中で20年の遅れを取り戻す交通政策の近代化が必要 熊本5社の収⽀率 61%(2019年) 88
3. 「銀の弾丸はない」と思いながら 上⼿にテック企業と付き合おう
オープンMaaS: 各種交通⼿段を標準化/オープン化 • ひとつのアプリに囲い込まれず、世界標準で世界最先端を導⼊ 機能連携 交通情報 鉄道・バス 経路 検索 オープン 規格 GTFS GTFS タクシー チケット販売 オープン 規格 広告 検索データ ⼈流データ ? ? Profile Passport オープン 規格 GTFSOnDemand ︖ 駅すぱあと バス 再編 交通需要 マネジメント 交通計画 渋滞緩和 GTFSTicketing NAVITIME ヴァル研究所 Google マップ 公共交通 収⽀改善 オープン 規格 GBFS Realtime 遅延 改善 社会 ⽬標 デマンド交通 ロケ・運⾏情報 ダイヤ データ /API シェアサイクル ログデータ Yahoo!乗換 サイ ネージ 印刷 システム 現地媒体 CO2削減 観光 情報 住宅 検索 ⾞ 購⼊ 各種情報サイト 観光 収⼊ 市街地 活性化 研究 ・ 創発 ジョルダン my route Twitter LINE SNS ⾼齢者 外出 定住 …
実証実験は毒饅頭か︖
⾃治体の現場と⼤企業のモビリティソリューションの ミスマッチ問題 • ⼤企業 – AI、ビッグデータ、IoT 領域のビジネス開発とし てモビリティに注⽬ – プロトタイプを開発し PoC実施 最初は相思相愛 ※複数の実話をもとに再構成 • ⾃治体 – 有名な⼤企業が来た︕ – トップが連れてきた︕ – 具体的な問題を抱える 「⾼齢化率63%の熊⼭ 地区283世帯のための移 動⼿段確保…」
すごそうなバズワード ■■■■モビリティの実証実験 • • • • • 最初は⽢い⾔葉で「何でも出来ます」と⾔う いまいち使いづらいサービス、UI 担当する地⽅⽀社と東京の開発者に距離がありすぎ 問題を指摘しても反応が悪い、改良されない 数年で撤退、地域は取り残される
熱を⽣み出すことができず、スタートでつまづく • 地元の印象 – あるモノを押しつけてるだけ、地域から学ぶ気が無い︕ – 地域は残り続けるのに企業は撤退出来る • 企業の本⾳ – ⼤企業では数百⼈規模のサービスに投資出来ない – 地域交通はビジネス化が難しい • 地域交通専⾨家の知⾒ – 「やっぱり」 – 他の地域は騙されないように気をつけよう いくつもの地域に関わっているのでか なり重要なのだが、往々にしてIT企業 はキーパーソンだと認識していない
この前まで地⽅創⽣で騒いでいた⼈は︖ • 地⽅創⽣で潤ったのは東京のコンサル︖ https://wedge.ismedia.jp/articles/-/18448
4. データ・ITに⾃分事として向き合おう
公共交通オープンデータの促進
地域の公共交通は乗換案内に出てこない
地域の公共交通は乗換案内に出てこない データ整備にはコストが掛かるため 利⽤者数が少ない地域のバスにまで ⼿が回らない 交通事業者が⾃ら 標準形式のオープンデータを⽤意して 乗換案内に提供する
海外の事例: 交通事業者がオープンデータを提供 • 路線図、時刻表、リアルタイム⾞両位置情報などのデータの利⽤を開放 • ⾃由に使ってもらうことで、アプリの作成や⼯夫を凝らした印刷物などの情 報提供を促進 • アメリカ、ヨーロッパでは当たり前になりつつある
オープンデータから様々なアプリが開発される • ⼤企業、ベンチャー企業、個⼈がアプリ開発
GTFS形式 • 世界で広く使われる形式 • 乗換案内に必要な情報(バス停・駅+路線+時刻表+運賃)をまとめて格納 したファイル形式 バス停/駅+路線 時刻 運賃
DB(ドイツ鉄道)オープンデータハッカソン • ああ
⽇本の公共交通データ流通の現状 JR 私鉄 交通新聞社 私鉄 私鉄 バス バス バス JTBパブリッシング バスデータに関しては、集約して販売する 事業者がなく、乗換案内事業者それぞれが 独自で一社一社のデータを集めている 乗換案内サービス事業者
⽇本︓ 路線バス業界を中⼼にのオープンデータ整備が急速に進展 バス業界において「標準化」「オープン化」が同時に進⾏中 路線 時刻 運賃 リアルタイム 「標準的なバス情報フォーマット」(世界標準のGTFS互換)でデータ整備 乗換案内・MaaS サイネージ・印刷物等 交通分析・計画 108
2014年〜 静岡県でコミュニティバスのオー プンデータ化の取り組み • 県庁、市役所、地元IT企業等とGTFSによるオー プンデータ化を実現 – Google Mapsへ提供可能に • アイデアソン、ハッカソンで地域でのデータ活⽤ を⽬指す
公共交通オープンデータの海外の状況を報告 • 2015年末に記事公開
学会発表を繰り返す • 交通の専⾨家は学会に結集している • ならばそこに参加してオープンデータ を訴える
「交通ジオメディアサミット 〜 IT×公共交通 2020年とその先の未来を考える〜」 開催 • • • • • 2016年2⽉12⽇開催(東⼤駒場第2キャンパス コンベンションホール) 195⼈来場 産(現場寄り)︓ JR東⽇本、バイタルリード(出雲市の交通コンサルタント) 産(IT寄り)︓ ジョルダン、ナビタイム、ヴァル研究所(駅すぱあと) 官︓ 国⼟交通省、学︓ 東京⼤学(私) コミュニティ︓ Code for Japan、 路線図ドットコムなど
Impress Internet Watch 記事
バス情報の効率的な収集・共有に向けた 検討会(2016年12⽉〜2017年3⽉) • 事務局︓ 総合政策局公共交通政策部交通計画課 • 外部委員 – – – – – – – – – – 伊藤昌毅 東京⼤学⽣産技術研究所(座⻑) ー川雄⼀ 株式会社構造計画研究所 伊藤浩之 公共交通利⽤促進ネットワーク 井上佳国 ジョルダン株式会社 遠藤治男 ⽇本バス協会 櫻井浩司 株式会社駅探 篠原雄⼤ 株式会社ナビタイムジャパン 丹賀浩太郎 株式会社⼯房 別所正博 公共交通オープンデータ協議会 ⼭本直樹 株式会社ヴァル研究所
2017年3⽉31⽇ 「標準的なバス情報フォーマット」公開
バス事業者や⾃治体による公共交通 オープンデータ整備が活発化 • • 全国で30近い事業者が整備・公開 4県が県を挙げたデータ整備中 2018年11⽉現在 伊藤調べ http://tshimada291.sakura.ne.jp/transport/gtfs-list.html
2019年2⽉︓90 2019年7⽉︓126 2021年3⽉ 2020年11⽉ 2020年7⽉ 2020年3⽉ 2019年11⽉ 2019年7⽉ 2019年3⽉ 2018年11⽉ 2018年7⽉ 2018年3⽉ 123 2022年3⽉ 2021年11⽉ 2021年7⽉ 2018年11⽉︓30 2017年11⽉ 2018年7⽉︓23 2017年7⽉ オープンデータ提供事業者数 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
オープンデータとして公開 • Webページからデータを誰でもダウンロード出来るように
Google Mapsで検索可能に • • いつも使ってるスマホアプリから⾃然にバス 情報にアクセス可能 外国⼈も使っているアプリ
「駅すぱあと/Yahoo!乗換案内」がオープン データを採⽤ • オープンデータ化されたバスデータを経路探索に採⽤ https://ekiworld.net/personal/app/spec/info.html?style=pc
GTFSリアルタイム(バスロケ)提供も増加中( 57事業者) • 便ごとのバス停通過時刻、緯度経 度情報などをリアルタイム公開 – Protocol Buffer形式 • 混雑情報も提供可能 – 2020年より宇野バス、横浜市交通局が対応
2020年︓ 都バス・横浜市営バスの GTFS-JP・GTFSリアルタイムデータ公開 • 公共交通オープンデータ協議会(坂村健会⻑) による取り組み – 公共交通オープンデータセンター • 都バスは、Google Mapsでバスロケを考慮し た検索が可能に 2019年3⽉
サイネージでの活⽤
標準的なバス情報フォーマット広め隊 • 標準的なバス情報フォーマット (GTFS-JP)データ整備に関わる有志 によるコミュニティ – 2017年夏頃から、国交省検討会の関係者らを 中⼼に⾃然発⽣的に誕⽣ – 普及に関わるツール開発、勉強会やイベント 開催、関係者への働きかけなどを継続的に実 施 – チャットなどによる活発な情報交換 • 参加者 – – – – – – ⼤学研究者 乗換案内サービスデータ整備担当 バス事業者向けツール開発者 公共交通コンサルタント 交通事業者職員 ⾃治体職員 等 20名程度
広め隊による講演会・講習会 • 県や運輸局が実施する勉強会に講師として登壇 • 事業者や⾃治体にツール導⼊を指南
フリーのデータ作成ツール開発・提供・利⽤⽀援 • ⻄沢ツール – ⻄沢明⽒開発 – 約40+⾃治体・事業者が利⽤ • ⾒える化共通⼊⼒フォーマット – 伊藤浩之⽒開発 • 当初は三重県のプロジェクトで利⽤ – 約33⾃治体・事業者が利⽤
その筋屋 • 無償配布されているダイ ヤ編集システム • プロ向けシステムと同等 の機能を備え、バス事業 の運営に利⽤出来る • GTFS/標準的なバス情報 フォーマット出⼒機能を 備える – 42事業者がオープンデータ公 開 http://www.sinjidai.com/sujiya/
「その筋屋」からバス停時刻表・Web時刻表
フリーのダイヤ編成システム・GTFS作成ツールが1/3 その筋屋 ⻄沢ツール ⾒える化共通⼊⼒フォーマット • • 2020年12⽉現在 N=309(⼀部期限切れデータ含む) 資料 l GTFS公共交通オープンデータのリストは、「GTFS・「標準的なバス情報フォーマット」オープンデータ⼀覧(旭川⼯ 業⾼専島⽥鉄兵先⽣)による。事業者・市町村単位で集計した。鉄道、航路等を含む。 l HODaP、OTTOPはこれらのプロジェクトで整備されたGTFSである。 HODaP、OTTOPの区分は上記⼀覧記載による。 l その筋屋、⾒える化共通⼊⼒フォーマット、⻄沢ツール、その他の区分は、各GTFSデータのtrips.txtを⾒て判断した。
事業者からの情報発信をより効果的に
2018年 10⽉1⽇のダイヤ改正は反映されていたか︖ • 減便になった8-33 遠鉄バス伊佐美線 17:45発で確認(10⽉26⽇ 伊藤調べ) 未対応 対応済み Navitime Yahoo! 駅探 ジョルダン Google 駅すぱあと Apple
コロナ禍で経路検索の信頼性が議論に • バスの減便が相次いだが、乗換案内サービス事業者各社のデー タ更新が追いつかなかったという実状 – 会社ごとの善し悪しとは認識されない。業界全体の信頼を損ねる状況 https://twitter.com/niyalist/status/1257502021936009216
正確な乗り場による バス案内 • バス乗り場の位置や名称 まで含んだ案内を実現 • 事業者が必要と思うレベ ルの情報提供が可能
臨時便への対応 • お盆の⽇のみ⾛る臨時便を事 前に情報提供 • その⽇を設定した検索にだけ 案内される • Google Mapsはデータを送信 してからほぼ48時間以内で更 新されるらしい
先進事例(佐賀市営バス・祐徳バス)︓ 正確な情報でバス→バスの乗換も安⼼ • 佐賀空港から「枝梅酒造」を検索 • バス停位置が正確だから「県庁前」での乗換も 不安なし︕ • リアルタイムデータも掲載準備中
先進事例(群⾺県永井バス)︓ GTFSリアルタイムを使えば・・・ • GTFS Alert機能により、特定の検 索に対して情報追加が可能 – ⽂章+⽂字列を付与 • 災害情報などの提供が可能
災害時・緊急時の情報発信もオープンデータで • アプリの対応が進む – Google Maps︓ 対応 • 情報発信すれば即座に反映 – 「標準的なバス情報フォーマット」に組 み込まれたことで⽇本企業の対応も進⾏ 中
公共交通オープンデータ最前線 in インターナショナルオープンデータデイ2019開催 • 2019年3⽉2⽇(⼟) 東⼤⽣研 にて • https://geomedia2020.peatix.com
国際連携 • GTFSの標準化を進めている MobilityData.orgと協業 – ⽇本にてミーティング開催 – 公式Webページの翻訳受託
県によるデータ整備事業 • 佐賀、富⼭、群⾺、沖縄 • その他にも続々と・・・
標準的なフェリー・旅客船航路情報フォーマット • 国⼟交通省海事局内航課に より船舶向けデータフォー マット(GTFS互換)が策定 – 受託 ジョルダン株式会社
GTFS-JPオープンデータ整備の効果 • 北恵那バス⾺籠線での調査 – 利⽤者の多く(76%)は外国⼈。⾺籠宿 から妻籠宿へ向かうルートが⼤半 – 外国⼈のうち欧⽶の旅⾏者が85% • 外国⼈の15%がGoogle Maps検索で バスを知る。20代は4割以上 • 沖縄・⽯垣島での調査 – データ整備前(2018年2⽉)と整備後(2019 年8⽉)との⽐較 – 「バス・船の検索に不便があった」が約5割か ら約3割に改善 • • – 検索する際の不便や困難が⼤きく改善 • 2018年10月調査(中津川市が実施) http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/page/081195.html 国内: 約5割(n=88)から約3割(n=101) 海外: 約6割(n=9)から約4割(n=34) 検索できなかったとの回答が約7割から約3割に 2019年9月報告(沖縄県 観光2次交通検討委員会資料) https://oki2k.jp/files/ic_20190913_no4.pdf
⽇本バス情報協会 設⽴(2022年3⽉) • 設⽴シンポジウムを開催 https://www.gtfs.jp/blog/preparatory-committee/
⽇経産業新聞 2022年4⽉25⽇号
データは何に使える︖
ワンソース・マルチユース
乗り換え案内
マイ路線図・マイ時刻表
公共交通
オープンデータ
交通分析
!"#$%&"'%(
#+,-"'./0"
平日
123号線6789:;<=片上@岡山駅D
行FGH
:QRS;
:TRV:
9:R8S
9SR99
9WR:S
総計
計画 最小 中央値最大 120
T8
U; 9:;
9:Q
WT
WT
T8
U: 100
WQ
WQ
T:
TV
WS
WU
T9
TT 80
TS
TW
UT
999 60
WUYV
T;
TU
UQ
•
•
40
計画
中央値
20
最小
最大
17:05
15:11
10:35
08:40
06:52
0
データを使った様々なアプリ開発や
交通分析が実現
データ分析やアプリ開発によって公
共交通の利便性が向上
Google Mapsへの掲載 • GoogleはGTFS形式によるオープン データを推奨 – ほぼ選り好みせずデータを掲載 – 検索の統計情報も公開 • 乗換案内に掲載されていない⾃治 体やバス事業者が利⽤促進のため にデータ整備 • 訪⽇外国⼈が利⽤するのはGoogle Maps
「駅すぱあと/Yahoo!乗換案内」がオープン データを採⽤ • オープンデータ化されたバスデータを経路探索に採⽤ https://ekiworld.net/personal/app/spec/info.html?style=pc
サイネージでの活⽤
その看板 • ⾃由にデザイン、レイアウト 可能なデジタルサイネージシ ステム • GTFS形式に対応するため、 低コストでシステム開発が可 能 • ちょっとした修正・デザイン が⾃前で可能 http://www.sinjidai.com/kanban/
バスロケーションシステムの基礎データ • 群⾺県・富⼭県では2018年度整備したデータを活⽤しバスロ ケーションシステムの整備を推進 – GTFSリアルタイムデータのオープン化にも取り組む https://toyama.vtfm.jp https://www.pref.gunma.jp/04/h21g_00088.html
MaaSの基盤データとして • 北海道⼗勝MaaS実証実験の 基盤データの⼀部はGTFS-JP オープンデータ • ⼩⽥急+VAL研究所のMaaS プラットフォームに採⽤ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk/hokkaido-tokachi-maas.htm https://www.slideshare.net/KenjiMorohoshi/20200128shikoku-gtfsjp
市⺠発のアプリも登場 • Aa ⻘バスなう︕ https://sonohino-kibunshidai.org/aobus_now/ UnoMap https://play.google.com/store/apps/details?id=work.momizi.unomap&hl=ja
ゆる〜と 全国⽇帰り温泉・銭湯マップ • バスの利⽤を促進する援軍︕ https://yuru-to.net
地域コミュニティが データ活⽤ Code for Saga 富⼭県資料
制度化へ︓ 海外事例
イギリス政府の路線バスオープンデータ • バス事業者が時刻表や運賃、ロケーション情報 をオープン化することを法的に義務化 – The Public Service Vehicles (Open Data) (England) Regulations 2020 に基づく – イングランドの政策にスコットランド、ウェールズも追従 • 全国⼀体的にデータ収集し複数のフォーマット でデータ公開 – 2020年12⽉ 時刻表データ公開義務化 – 2021年1⽉ 位置情報、運賃やチケット情報の公開義務化 – 2023年1⽉ 乗り継ぎなど特殊な運賃・チケットについても 公開義務化 https://www.bus-data.dft.gov.uk
The Bus Open Data System (BODS) • Ito World が DfT、 KPMGとともにシステム 開発 • CityMapper、Moovitな どのアプリがデータ利⽤ – 当初は別々にデータ収集して いたとのこと。役割分担 • 規模 – 250以上の事業者のデータ – 18,000台以上のバスの位置情 報(5〜30秒ごとに更新) https://www.bus-data.dft.gov.uk
分析機能 • この例では全国のバスの定時率を表⽰ https://www.itoworld.com/introduction-bus-open-data-service-bods/
包括的で未来志向のバス政策 • x https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach ment_data/file/980227/DfT-Bus-Back-Better-national-bus-strategy-for-England.pdf
交通政策におけるデータ活⽤の 必要性
⾏政の役割の⾼まり • 地域公共交通活性化再⽣法(2007年 制定)により、⾏政が主導して地域 公共交通を計画、実現する枠組みが 明確化。 • 特徴(伊藤の理解) – 地域のことは地域(事業者、住⺠、⾏政な ど)で – 全体をネットワークで考える – やる気のある地域を⾦や制度でサポート – まちづくりとの連携
都バスのサービスレベルを把握するマップを作成
公共交通の運⾏本数の直感的把握
⼈⼝と運⾏本数⽐較
⾼松駅13:00発の到達圏 https://qiita.com/niyalist/items/1d3941761df3969f16a2
中⼼地からの到達時間
地域ごとの通える⾼校数
⾃動⾞台数と公共交通利⽤者数の⽐較 地図作成: 太田恒平(トラフィックブレイン)
QGIS + GTFS-Go • GTFSデータをオープンソー ス(無料)のGIS上で表⽰ • ⾏政職員向けの講習会を動画 配信中 – https://www.youtube.com/watc h?v=w2gFMyK67ws
⼈対⼈ではなく、皆がデータに向き合うように • 客観的なものに向 き合うことで、理 性的な対話が出来 る • 解釈のアイディア が出やすい
運輸⾏政全体で データの流れを作る必要性
データの流れからみたバス事業 許認可権限 形式的な要件は確認はするが 地域の状況を踏まえた判断はしない 運輸局 (国) ダイヤ改正・臨時便 路線やバス停の新設・廃⽌ 新規参⼊・撤退 公共交通 事業者 アプリ 事業者 許認可・申請 紙ベース 利用者 標準化+オープン化 情報提供の義務は無い 自治体 利⽤の実態は ⾃治体に届かない ⾃治体が地域の交通をデザイン することが法的に求められている この体制のままよりよい交通は作れるのか︖
公共交通データ活⽤の現状 • 利⽤者 – スマートフォン活⽤にシフト、スマホで公共交通がより便利に • 公共交通事業者 – アナログな業務を多く残す(ダイヤ作成なども⼀部はアナログ) – デジタル機器が連携せずに導⼊されている状況 • 国(運輸局) – 公共交通事業者からの許認可や届け出を受ける⽴場 – ほぼ全てが紙の束+ハンコ • ⾃治体 – 地域の公共交通をデザインする役割を求められるように – ITの専⾨家も、交通の専⾨家も不⾜
運輸局への紙による膨⼤な申請・届出業務 バス会社(永井運輸@前橋) 関東運輸局 太⽥恒平, ⽔野⽺平, 三浦公貴, 伊藤昌毅, "GTFS-JPデータを⽤いた乗合 バス事業の電⼦申請に向けた基礎検討 〜帳票地獄からの脱却による働き ⽅改⾰を⽬指して〜", 第59回⼟⽊計画学研究発表会, 2019年6⽉9⽇.
書式の例 • x https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/bus/procedure/noriai/style.html
利⽤者向けのデジタル化を進めたところで…
専⾨家からのインプット 名古屋⼤学 加藤博和教授による これ以外にも関係者の会 議等で発⾔の機会がある 度に申請の電⼦化の話を されていた 令和元年度 第2回 (第16回) 国⼟交通省交通政策審議会 交通体系分科会 地域公共交通部会 (19/09/27) https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001311067.pdf
千葉市地域公共交通計画(案) • データ整備を施策とし て挙げる • パブリックコメント実 施中 – 2021年12⽉8⽇〜2022年1 ⽉7⽇ https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/kotsu/mobility-plan.html
規制改⾰推進会議経済活性化ワーキング・グループ • 経団連からの提案(2021年12⽉8⽇) – 事業許可申請および変更認可申請⼿続きを電⼦化すること – 申請内容をマシンリーダブル、かつGTFS-JP(共通フォーマット)を活⽤した形式 とすること https://www8.cao.go.jp/kiseikaikaku/kisei/meeting/wg/econrev/211208/agenda.html
• x
広島における 公共交通情報提供プロジェクト
災害時の公共交通情報整備プロジェクト • a 2018年7⽉11⽇の⻄⽇本豪⾬に おける鉄道不通区間 Source: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/322119.pdf https://roote.ekispert.net/ja/traininfo_map
張り紙だらけ@広島駅 2018年7⽉31⽇・8⽉1⽇調査
張り紙で閉ざされた改札⼝@呉駅 • ああ 2018年7⽉31⽇調査
選択肢1: 代⾏バス • ああ 広島駅(7⽉31⽇) 呉駅(7⽉31⽇) 撮影は広島発の代⾏バスが⾛っていた時点。現在は坂までJRの運転が再開され、広島からはバスが出ていない
選択肢2︓ 広島バスセンター→呉駅 災害臨時輸送 通常(2017年12⽉1⽇〜) 現在(7⽉28⽇〜) 本数(平⽇) 68往復 37(広島⾏)/36(呉⾏) 運⾏事業者 広電: 47本 中国JRバス: 21本 広電: 27本 中国JRバス: 9本 所要時間(広島→ 呉) 44分程度 1時間20分〜2時間10分 (ダイヤ上) 停⾞バス停 広島市内・呉市内で複数バス 停に停⾞ 広島市内・呉市内での停 ⾞バス停は限定的 区間 ⼀部が阿賀駅、広駅まで 全てが広島バスセン ター・呉駅間 経由 広島呉道路を利⽤ ⼀部国道31号を利⽤ • クレアライン線 • 豪⾬を受けて7⽉17⽇より「災害臨時輸送」に
選択肢3: フェリー・スーパージェット • ああ
⽇々状況が変わる被災地の公共交通 • 鉄道 – 復旧⾒込みの前倒しが相次ぐ • 例: 呉線の復旧 当初11⽉中→9⽉9⽇に実現 • バス – 柔軟な運⾏が可能であり、状況に応じて迅速な復旧が進む – 運⾏可否が道路の復旧に依存するため、バス会社だけでは運⾏再開を決められな い – 道路状況などに合わせて、経路、通過時間など⼤幅に変わる
事業者Webからは全体像の把握が困難 JR西日本 駅張り出しの情報の多くは PDFでも配布しているよう 広島電鉄 中国JRバス 一覧ページから、クレアライン フローなのかストックなのか 線や路線バスのダイヤ等を閲覧 判別が付かず 瀬戸内海汽船 豪雨については直接触れず JR、クレアライン線へのリンク あり
乗換案内での検索結果
検索︓8⽉5⽇時点 不通区間を回避した検索(代⾏バスは反映せず) クレアラインの経路が 変わっているため実際 には乗換出来ない。 バスセンターに⾏くの が正解。 Yahoo! 駅すぱあと ジョルダン
最新のダイヤで検索したい︕しかし・・・ • 交通事業者の現場は混乱気味でデータ準備がままならない – ダイヤ作成システムが導⼊されていても、緊急時はExcelなどで応急的にダイヤ 作成 – いつ路線が復旧し、ダイヤ改正を⾏うか直前にならないと分からない • 乗換検索にデータ投⼊から検索可能になるまで時間がかかる – 会社によるが、即座に反映されるわけではない – ⽇々ダイヤが更新される状況に対応出来ない – 「代⾏バス」のような新規路線の設定は⼤変
⽅針転換︓情報アクセスの導線を作る • いつものアプリから最新情報を⾒られるように – 普及している乗換案内アプリからリンクを張る
呉市交通政策課サイト経由で JR西日本の時刻表など 広電バスの時刻表・ 所用時分実績情報 乗換案内からリンク (駅すぱあとの例) バス協会による総合案内ページ (JR西・広電バス・フェリー) JR代行輸送バスの 走行位置情報
プロジェクトスケジュール • 7/28(⾦)-29(⼟)JCOMM2018 @豊⽥市 – 森⼭さん、神⽥先⽣より相次いで交通情報提供の相談を受ける – 会場で諸星さんに相談 • 7/29 メール送信 – Googleチーム、森⼭さん、諸星さん、太⽥さん • 7/31-8/1 広島訪問 • • • • – 呉線代⾏バス乗⾞、広島県庁、広電バス訪問、神⽥先⽣ミーティング – この間オンラインで諸星さん、太⽥さんともコミュニケーション 8/2未明 技術的⽅針をまとめメール 8/6 東⼤にてキックオフミーティング 8/8 岐⾩出張 諸星さんミーティング 8/10 VAL研究所に⾏き諸星さんとWebデザインのディスカッション
20 18 08 10 20 18 08 11 20 18 08 12 20 18 08 13 20 18 08 14 20 18 08 15 20 18 08 16 20 18 08 17 20 18 08 18 20 18 08 19 20 18 08 20 20 18 08 21 20 18 08 22 20 18 08 23 20 18 08 24 20 18 08 25 20 18 08 26 20 18 08 27 20 18 08 28 20 18 08 29 20 18 08 30 20 18 08 31 20 18 09 01 20 18 09 02 20 18 09 03 20 18 09 04 20 18 09 05 20 18 09 06 20 18 09 07 20 18 09 08 20 18 09 09 20 18 09 10 20 18 09 17 20 18 09 18 20 18 09 19 20 18 09 20 20 18 09 21 20 18 09 22 20 18 09 23 20 18 09 24 1800 アクセス件数 グラフ タイトル 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
ダイヤや運⾏情報以上の情報提供の⼯夫 • 所要時間実績 • 簡易バスロケによる位置情報
本プロジェクトは多くの⽅の協⼒・連携で実現 しました。ありがとうございました • 災害時公共交通情報提供研究会 – – – – – – – – – – – – 広島⼤学 ⼤学院国際協⼒研究科 教授 藤原 章正 呉⼯業⾼等専⾨学校 教授 神⽥ 佑亮 東京⼤学 ⽣産技術研究所 助教 伊藤 昌毅 公益社団法⼈ 広島県バス協会 株式会社 ヴァル研究所 株式会社 トラフィックブレイン ⻄⽇本旅客鉄道株式会社 広島⽀社 株式会社 バイタルリード 広島電鉄 株式会社 株式会社 ファイコム 広島県 呉市 http://www.bus-kyo.or.jp/saigai201807/information
再度,災害による運休が到来 • 2021年7⽉上旬の豪⾬ – – – – 広島県がまた⼤⾬,そして,⾝近なエリアの鉄道が(また)代⾏バスに また呉線(⻄⽇本豪⾬の再来),試⾏実験区間包含,地元エリア 短期で戻るか戻らないか微妙な様⼦ 「いつやるの︖今でしょ︕」 の声 270
実施したプロジェクト 代⾏バス︓2021/7/12〜 ①代⾏バスダイヤの 普段使いバスロケへの ダイヤ掲載(7/12〜) ②代⾏バス位置情報 普段使いバスロケでの 情報発信(7/14-15) ③代⾏バスダイヤの 検索アプリ表⽰ (7/20-) (Google Map等) 271
福島県沖地震(2022年3⽉16⽇) • x
議論
モビリティは100年に⼀度の⼤変⾰の時代
モビリティ⾰命の地域社会へのインパクト • 移動⼿段・くらしの⾜をどう確保するか – 多くの⼈にとっては、モータリゼーションで移動が⼿軽に・便利に – 過疎化・少⼦⾼齢化などの状況の中で、新しいモビリティで地域の⾜を再構築で きるか︖ • 地域の産業・経済基盤をどう成⽴させるか – 地域の雇⽤を⽀える企業・事業は今後どうなるのか • 裾野の広い⾃動⾞関連産業 • 道路などのインフラ整備 – 第⼀次、第⼆次産業からソフトウェア・サービスへ
地域交通は制度疲労が⽬⽴つが、 その必要性は⾼まっており、 デジタル活⽤に対する期待も⾼い MaaSや⾃動運転などの追い⾵を どうやって地域の価値に 結び付けられるか