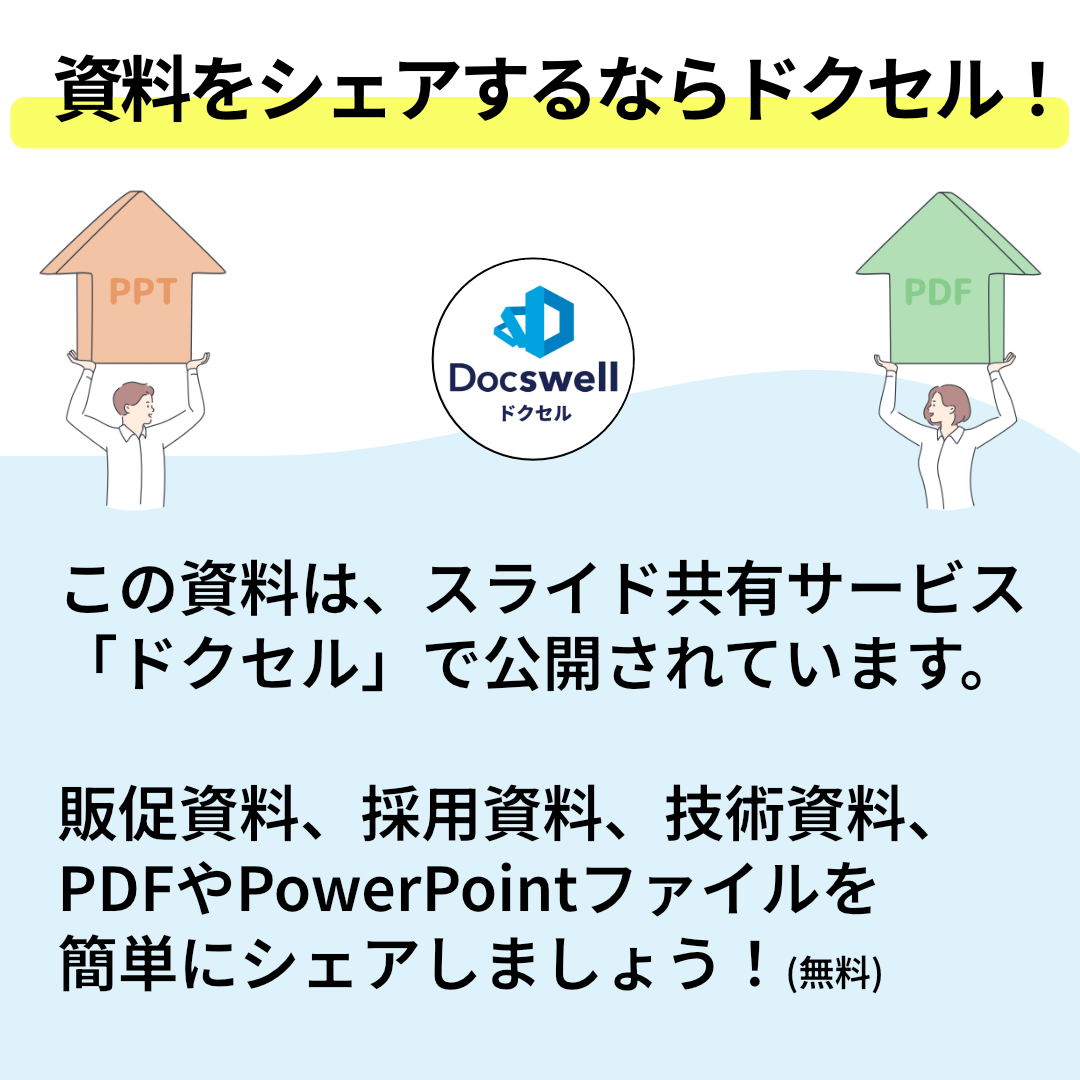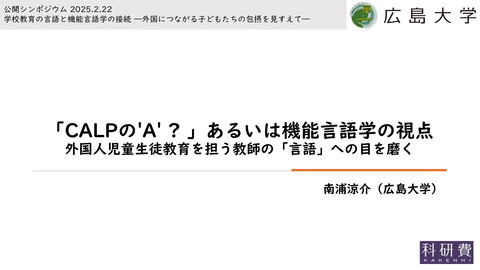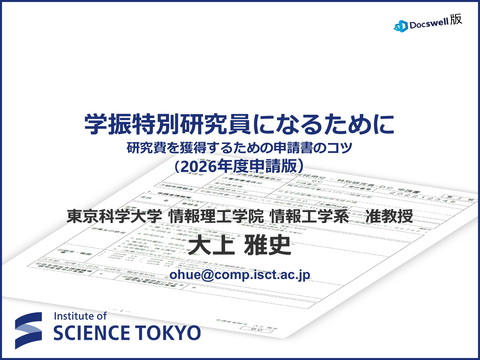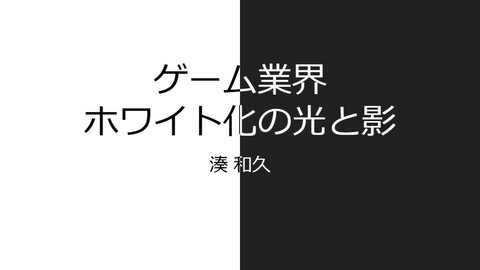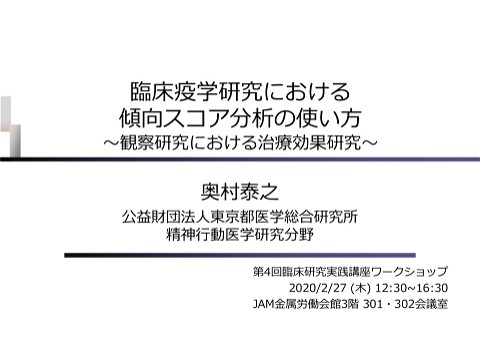Ouellette_Gavin_2024_A_Flat_Packed_Affect_hosonoyamaguchi
514 Views
September 06, 25
スライド概要
教育方法学・教科教育学という「一般的な教育」と,外国人児童生徒教育学という「特別な教育」をどちらも行っています。 このどちらもを同時に行う研究室は,日本の中ではほとんどありません。その結果,大学を含む多くの教育の場でこの両者は別々のものになってしまっています。
関連スライド
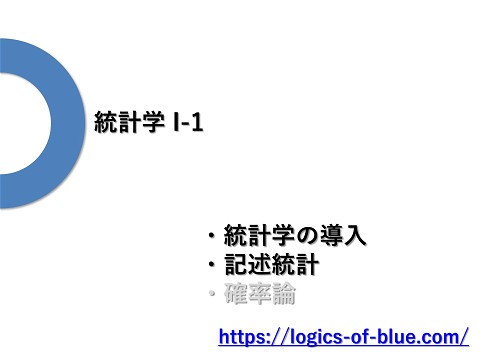
統計学I-1
 Logics of Blue
301.8K
Logics of Blue
301.8K
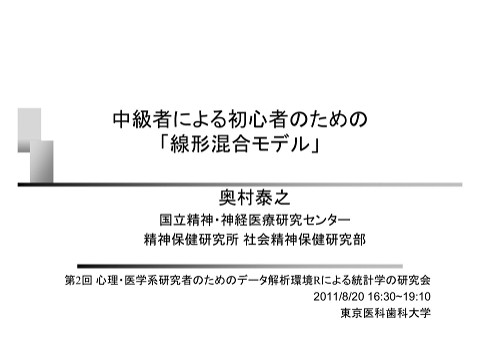
中級者による初心者のための「綿形混合モデル」
 奥村 泰之
223.8K
奥村 泰之
223.8K
各ページのテキスト
【お願い】このスライドは,広島大学 大学院人間社会科学研究科 教育科学専攻 教師教育デザイン学プログラムで開講している「外国人児童・生徒の教育課程デザイン論」(南浦涼介担当)の授業で行った受講大 学院生たちの発表資料です。 Trifonas and Jagger 2024 Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer のハンドブックのいくつかの章を選んで発表したものです。 教育的価値・資料的価値としてウェブでの掲載を行っていますが,いわゆる「論文」ではありませんので,論文等への引用や掲載は固くお断りします。 質問については広島大学南浦研究室(https://minamiura-lab.com/)までおねがいいたします。 20250801 外国人児童・生徒の教育課程デザイン論 第14・15回 A Flat (Packed)Affect: Theorizing Pedagogies of Seriality in Unboxing and Assembly Marc A. Ouellette, Dana Gavin 細野花莉・山口香雪
目次 • Introduction • Expertly Assembled: Education and Expertise • Pulling on the Threads: Assemblages • Putting It All together : Learning in and Through Assembling • Picking Up the Pieces: Conclusions
筆者の情報 • Marc A. Ouellette(博士 英語学) 米 オールドドミニオン大学 芸術・文学部(英語) 専門:カルチュラル・スタディーズ,ポップカルチャー,メ ディア(ジェンダー,セクシュアリティ,マスキュリニティ, ゲーム,映画) 参考・画像引用 https://www.odu.edu/directory/marc-ouellette • Dana Gavin(博士 英語学) 米 ダッチェスコミュニティカレッジ ライティングセンターのディレクター 専門:文学,文化,テクノロジー,ニューメディア ヴィクトリア朝イギリスの印刷技術における人間と非人間のアッサンブラージュ (識字と小説執筆の驚異的な拡大を可能にした労働と技術) フェミニストの修辞学、メディアによる男らしさの描写、ポップカルチャー 参考 https://danagavin.com/
Introduction
Introduction 「わたしたちはもはや物を作らない。組み立てるのだ。」 We no longer make things. We put them together.(p.912) 例:イケアの家具,レゴブロック,ミールキット,スティッチ・フィックスの服, スマホのアプリ・ウィジェット・アドオンの配列・・・ →安心感と肯定感のために,私たちは動画を検索することが不可欠 「組み立てが必須(assembly required)」であること, そしてそのこととソーシャルメディアとの偶発的な関係は, ドゥルーズ=ガタリのassemblageが連想されるが,そこで言われているような 複数の機能性よりもむしろ, 「連続性(seriality)」のプロセスの中で、またそのプロセスを通じて作用する
Introduction 連続性(seriality)とは (Maeder&Wentz, 2024) オンライン動画の直列性は、2つの入り組んだ様式で作用する ① 通し番号のように繰り返される行為,次から次へと繰り返される行為 ② 最終的に何ができるかが決まっている。完成したものはオリジナルと 一致しなければならず、逸脱の余地はない 例:レゴブロック 「無限の可能性を秘めたシンプルなブロックのセットから,接着 剤を使わないスケールモデルのようなキットへと変化してきた」(p.912)
Introduction 「フォードの工場はいまや私たちの家庭や教室、そして手のひらの中にある」 Ouellette(2010): Google,YouTube,ソーシャルメディアを通じて 「物事を調べる」専門知識が,公的な教育の場で も知識に取って代わるようになっている McLuhan(1964) : 技術は人間の経験のパターンとスケールを変え, 新たな役割を生み出す。現在重要な新しい役割の 一つは,非常に規定された方法で「物を組み立て ること/ユーザーの参加が増えるにつれて,コンテ ンツの重要性が低下する Manovich(2001): コンピュータの典型的なプログラムの実行は, フォードの工場の別バージョンである 「しかし,フォードの工場はいまや私たちの 家庭や教室、そして手のひらの中にある」 例:ネットミーム ユーザーは特定の順序と目的に 従って,それをオンラインテンプレートの助けを借りて組 み立てる • Maeder&Wentz(2014):「連続性」 こそがManovichの理論に欠けていた 「美学的かつ認識論的」な手続き • ソーシャルメディアとそれに関連する組 み立ての実践を構造化・生産する連続 性の教育的影響について、誰も考察し てきていない
Introduction 学校のカリキュラム,演習,活動でも同様の結果をもたらす • 与えられたり受けたりする最初の指示 「ググれ」,あるいは「アプリをダウンロードしろ」 • 出版社がアプリを提供→標準化されたテストではアプリの使用が必須 • TeachersPayTeachers©のようなウェブサイト PinterestやInstagramのようなソーシャルメディアプラットフォームにすでに存在するも のの形式化 (https://www.teacherspayteachers.com/) • 授業の組み立て→「適切なハッシュタグを組み立てるのと同じくらい簡単で反復的」 • 中等教育修了後レベル:助成機関は公然と「発見」より「革新」を重視 「発見(discovery)」 新しい部品やアイデアの創造 < 「革新(innovation)」 既存の部品を組み合わせる新しい方法を見つける
Introduction 学校のカリキュラム,演習,活動でも同様の結果をもたらす Sir Ken Robinson (2011) 標準化されたテスト制度・ それに合わせた教育 影響 「発散的思考(divergent thinking)」 与えられた問題に対して複数のアプローチや 答えを同時に見出す能力 発散的思考の根絶が教育のシステムの「遺伝子プールにある」 (公教育でも,パブリックな教育でも)、 • 執拗な連続性→教育の矮小化 「螺旋の不可避的な鎖を構成している」 =絶えず再生産し続けられていく? • 専門知識は,「組み立てるための説明書を探すこと」にますます限定されるようになっている • 専門知識は自己永続的で,かつ分野特異的(Herling, 2000; Swanson, 2007) →専門知識が永続する→他分野への応用可能性も低く,難しくなる
Introduction 本稿では, ⚫ 既にできたキットを組み立てる教育におけるルーティーンの中で/を通 じて,以下についてマッピングする • 連続性(seriality)の2つの形態 • その2つの形態が 知識を超えた専門知識の生産に及ぼす偶発的な影響 • その専門知識の限界 連続性(=同一性、特に組み立てられた部品を完璧に再現すること)に伴う肯定 感は、固定化を助長し,具体的操作期を長期化させる →介入の入り口となる可能性のある要素が存在するため、 「組み立てること」を学習プロセスとして理解することが重要
Expertly Assembled: Education and Expertise
Expertly Assembled: Education and Expertise ◇専門知識(expertise)についての先行研究 Go bet and Ereku (2016): 専門知識を研究することは、学習や知識習得、専 門家の訓練やコーチング,人工的な専門家システ ムの開発,人間の認知に関する理解を深めるなど, いくつかの利点をもたらす(Go bet & Ereku, 2016) →専門知識の有用性は自己永続的 Richard Herling(2000): 「人は専門知識の習得を止めることはない」(p. 261) ① 専門知識は動的な状態である ② 専門知識は領域固有である ③ 専門知識の基本的な構成要素は,知識とそれに関連する 技能,経験, 問題解決である 問題解決そのものが専門知識の場所 →「インストラクション・セットに従うことは,それ自身の論理的根拠であり,結 果なのである。組み立て指示書に従うのが上手になればなるほど,組み立て 指示書に従うことについてより多くのことを知るようになる。」(p.914)
Expertly Assembled: Education and Expertise Knowles, Holton, and Swanson(2014): 教育の目的は人間生活に必要なコンピテンシーの育成 ・好奇心と質問意欲が上位2つの要素 ・専門家を見つけ、解析する能力は下位 「ウェブベースの情報には,これらを1つのコンピテン シーにまとめることが重要かもしれない」(p.914) Grenier&Germain(2014): 専門知識の伝達の必要性が過小評価されている Go bet&Ereku(2016): 本能的・自動的になった学習行動が,専門知識を 示すものとして重要 Knowles, Holton, and Swanson(2014): 「学習者は、学習プロジェクトに取り組む過程でいくつかの段階を経るが、[ ... ]各段階に対処するコンピテン シーを高める手助けをすることが,学習効果を高める最も効果的な方法の1つかもしれない」(p.37-38) 最も重要なフェーズの1つ:外部からのサポートを探すこと →専門家を見つけ、解析する能力が、以前考えられていたよりも重要である可能性を示唆 「オンラインという場所と,簡単な指示に従うというサポートの性質を考えると,特に重要な問題である」 専門知識は自己永続的・分野特異的 →説明書とその検索は循環的なもの(「分野特異的」の「分野」=組み立て assembly)
Pulling on the Threads: Assemblages このアッサンブラージュ理論を用いて,現在の技術(ソーシャルメディア,キット的 なものの普及)が教育に及ぼす影響,教育との関係を見ていく 連続性,専門知識に焦点を当てる
Pulling on the Threads: Assemblages ◇アッサンブラージュ理論(Deleuze&Guattari,1980) ものごとを,物質的・非物質的な要素の異質な集合体であり,特定の活動(教育や学習 など)を生み出すために,さまざまな時にさまざまな方法で構成されるものとして捉える 例:授業をアッサンブラージュとして捉えると・・・(Strom,2015) 教室を構成するさまざまな要素-生徒、教師、コンテンツ、教室など-を、互いに独立した個別の変 数として捉えるのではなく、教育実践を形成するために集合的に働くものとして考えることになる。 英訳 assemblage:事物の収集や混合 原著 agencenent(仏) :事物の収集や混合だけでなく,つながりや関係性 を前景化する。「静的な用語としてではなく,まとめ, 配置し,組織化するプロセスとして作用する」(J-D Dewsbury, 2011:150)
Pulling on the Threads: Assemblages Delanda(2016) :thing-ness(事物性) of assemblages • ドゥルーズのsymbiosis(共生)=生態学的な、2つの生物の間の相互に有利な関係 外在性において相互作用する異質な種を伴うものであり,その関係は必要なものでは なく,偶発的に義務づけられているにすぎない • あらゆるアッサンブラージュは,それ自体がアッサンブラージュの集合体である 例:「料理人が多すぎるとスープが台無しになる」ということわざ ニュース雑誌『プライベート・アイ』誌の特集(不適切な予測アルゴリズム) Bennett(2010) :“vibrancy” of matter(物質の活力) 「物、つまり日用品、嵐、金属が持つ能力は、人間の意志や設計を妨げたり、阻止したりす るだけでなく、それ自身の軌道、性質、傾向を持つ擬似的な代理人や力としても作用する」 アッサンブラージュとその研究は, • コンテンツの源泉と(複数かつ同時の)層を特定するのに役立つ • 人間的、非人間的な多くの他の要素が照らし出される
Pulling on the Threads: Assemblages ◇アッサンブラージュ理論を用いた教育学の研究 教育空間の研究 (Mulcahy, 2012; Dovey & Fisher, 2014; Cobb & Croucher, 2016) 教育の存在論の研究 (Strom, 2015; Lanas & Huuki, 2017; Colton, 2019) 生命体としての本質や,空間におけるアッサンブラージュの動きや互いの 関係を説明する枠組み
Pulling on the Threads: Assemblages ◇アッサンブラージュ理論の有用性 柔軟性と包括性→あまり高く評価されていない「システム」の研究 (PinterestやTeachersPayTeachers©(Pittard, 2019)やオンライン教育 (Scott & Nichols, 2017)) 侮辱的な階層構造の解体 Quinlivan(2017):学校ベースの性教育の「正しく理解する」という欠陥のあるアッサ ンブラージュをマッピングし,どのような知識が生み出されているのかを探る Araneda-UrrutiaとInfante(2020):グローバル化された障害/能力モデルを「脱 モデル」し,グローバル・サウスにおける障害研究を脱植民地化する 「short circuits(短絡回路)」(Deleuze & Guattari, 1983:42)の説明 • 生徒の抵抗(Lanas & Huuki, 2017) • 教師教育における「混乱」(Beighton, 2013) • より大きなシステムにおける豊かで重要な学習の瞬間ではなく、失敗として読 み取られてしまうかもしれないためらいのような感情(Sellar, 2012)
Pulling on the Threads: Assemblages 誰も島(独立した存在)ではなく,教育者も唯一無二の安定した情報源で はない。人間がどのように情報収集を学ぶのか,あるいは無意識のうちに影 響を与えている情報をどのように識別するのかは,アッサンブラージュ理論 を用いて明らかにされる 非線形的な学習方法や情報の収集・応用は正当なものであり、知的・感情的な成長 をもたらす可能性がある Strom(2015):新任教師の実践を構成するプロセスについての研究 教師を,さまざまな言説,身体,アイデア,物体,制度的構造などが混ざり合った大 きな集合体の中で共同して働く存在として捉え,階層化された環境の中で実践を 交渉・構築するプロセスを捉える Mulcahy(2012):人間は自らの実践を通じて世界を作り出す →その世界は,知識生産の方法として厳密な検討に値し,またそれが求められる
Putting It All together : Learning in and Through Assembling
◇「新しい」メディアに対処する方法 1.技術に注目する 例)ゲームとは何か?(新しいメディアとは何か?) 2.新しいリテラシーや「発明」を進める 例)ゲームは何になりうるか?(新しいメディアは何になりうる か?) ゲーム研究の分野においては(「新しい」メディアに対処する際にも?)、 いずれかの方法を取る傾向があり、両者をつなぐものはほとんどない ⇒この二つの方法をまとめると… 「今あるもので何ができるか?」 本論文の中ではこの方法が ベストであると主張してい るはず?
◇「今あるもので何ができるか?」アプローチの課題 「新しい」メディアは組み立ての過程(アッサンブラージュ) が見えにくい 例)多くの電子機器に使われているコルタン コルタンはコンゴ民主共和国で違法に採掘されており、軍事紛争 の資金になっていたり、環境に破滅的な影響を及ぼしたりしている メディア自体への没頭が進むほど、その使っているメディア そのものの本質的な性質や構成要素には注意を払わなくなる ⇒でもだからこそ「今あるもので何ができるか?」アプローチが必要?
◇「今あるもので何ができるか?」アプローチの必要性 メディア自体への没頭が進むほど、その使っているメディア そのものの本質的な性質や構成要素には注意を払わなくなる 例)電話やビデオチャットを使うときに、私たちは「デバイスに話しかけて いる」とは言わず、「〇〇さんに話している」と言う コンテンツ(「新しい」メディアとは何か?)が人間の行動に与え る影響はそれほど大きくない メディア自体(「新しい」メディアとは何になりうるか?)つまり 「拡張子」が、「人間のつながり方や行動の規模・形態を形づくり、 制御する
◇「今あるもので何ができるか?」アプローチの必要性 コンテンツ(「新しい」メディアとは何か?)が人間の行動に与え る影響はそれほど大きくない メディア自体(「新しい」メディアとは何になりうるか?)つまり 「拡張子」が、「人間のつながり方や行動の規模・形態を形づく り、制御する それゆえ、「『新しい』メディアとは何か?」アプローチ(解釈 的)に対して、「『新しい』メディアとは何になりうるか?」アプ ローチ(対症療法的)とのバランスを取ることが重要になる 特に、学生が大学教育を体系的な試練の連続 であると認識している現在において重要
◇「今あるもので何ができるか?」アプローチと教育 それゆえ、「『新しい』メディアとは何か?」アプローチ(解釈 的)に対して、「『新しい』メディアとは何になりうるか?」アプ ローチ(対症療法的)とのバランスを取ることが重要になる 特に、学生が大学教育を体系的な試練の連続 であると認識している現在において重要 組み立てるように授業を選び、資料から切り貼りしてレポートを書く ⇒依然として、重視されているのは「書くこと」(組み立て)(「新し い」メディアとは何になりうるか?)であり、ビックデータリテラシー (「新しい」メディアとは何か?)は重視されていない
◇「今あるもので何ができるか?」アプローチと教育 組み立てるように授業を選び、資料から切り貼りしてレポートを書く ⇒依然として、重視されているのは「書くこと」(組み立て)(「新し い」メディアとは何になりうるか?)であり、ビックデータリテラシー (「新しい」メディアとは何か?)は重視されていない ここにあるギャップ(現代社会で必要とされていることと大学教育に おいて重視されていることのギャップ)は、専門性(組み立て=「新 しい」メディアとは何になりうるか?)ではなく、知識(ビックデー タリテラシー=「新しい」メディアとは何か?)である
◇「今あるもので何ができるか?」アプローチと教育 学問分野を「アッサンブラージュ」として捉える =学際性の捉え方や教え方、さらには複数のリテラシーの概念 を再考が求められる 「今の教育で何ができるか?」という視点で教育を捉えること(= 「アッサンブラージュ」として教育を捉えること)は、学際性の捉 え方や教え方、さらには複数のリテラシーの概念を再考することに なる
◇アッサンブラージュとして現代の教育を捉えると見えて くるもの 現代の新自由主義的教育システムでは、学生は小さなことだけ を疑問視し、骨の髄まで達するような大きなシステムには目を 向けない 小さなこと…インターネットやSNSに誤った情報が掲載されて いること 大きなシステム…誤った情報が掲載されていることに対して、 反論するコンテンツを作る中でも、自動化さ れた形でコンテンツを組み立てていること
◇アッサンブラージュとして現代の教育を捉えると見えて くるもの 現代の新自由主義的教育システムでは、学生は小さなことだけ を疑問視し、骨の髄まで達するような大きなシステムには目を 向けない 「検索して指示に従い、パーツを組み立てる」(=連続性)と いう学習の形態をとっており、これはフォーディズム的な考え 方と変わりない
◇アッサンブラージュとして現代の教育を捉えると見えて くるもの 現代の新自由主義的教育システムでは、学生は小さなことだけ を疑問視し、骨の髄まで達するような大きなシステムには目を 向けない 「検索して指示に従い、パーツを組み立てる」(=連続性)と いう学習の形態をとっており、これはフォーディズム的な考え 方と変わりない ⇒教育システムが産業モデルに依存しているから
◇現代の教育の課題の解決策 「検索して指示に従い、パーツを組み立てる」(=連続性)と いう学習の形態をとっており、これはフォーディズム的な考え 方と変わりない ・必修の教養教育の要請(McLuhan, 1964) ・「発散的思考(divergent thinking)」への注目(Robinson, 2011) ・もっと早い段階で介入をおこない、より規定的ではない教育が提供 されるべき(Robinson, 2011)
Picking Up the Pieces: Conclusions
◇結論で筆者が主に述べていること 1.アッサンブラージュで教育を捉えること 2.「連続性(seriality)」の捉え方について
◇アッサンブラージュで教育を捉えること 私たちが考える「教員から生徒への直線的な内容伝達」だけが 起きているわけではない ⇒学生はどこに行っても役立つ価値ある情報を持ち歩いている(スマホ で色々な情報にアクセスできる) ⇒学生は身体化されたアッサンブラージュであり、教室内外の様々な アッサンブラージュ(インターネットを含む)と絶えず交流している 教員が自分自身と学生を「能動的なアッサンブラージュの構成 員」として捉え、双方がお互いに知らない別々のアッサンブラー ジュの一部であることを認識すれば、学びはよりダイナミックな ものになる
◇「連続性(seriality)の捉え方 「連続性(seriality)」は、教室の拡大から生まれた ⇒テクノロジーの進化によって、教室に居ながら、教室外とつながることが できるようになった アッサンブラージュを強く意識すると、情報を「ググる」と同時 に検索エンジンの仕組みや倫理を考慮したり、指示に従うことを 学ぶ一方でどの前提情報が重要かを考えたり、検索エンジンや YouTubeの動画の中にも人間と非人間の物質が集まった重要な情 報のアッサンブラージュがあると見たりすることができる 「連続性(seriality)」は平面的なものではなく、 力強く豊かなものである
◇総括(私の理解) 「連続性(seriality)」がある現在の教育がよくないと言って いるわけではなく、アッサンブラージュで教育を捉えることに よって、現在の教育で何が起きているのかを教師は理解し、そ れを学生に児童・生徒に対して理解を促すことが教師に求めら れる ただテクノロジーを教育に取り入れる是非を議論していては、 私たち自身がアッサンブラージュに組み込まれていることに目 を向けないまま、避けられないアッサンブラージュに組み込ま れ、良くなっていくための取り組みができなくなる
言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆 アッサンブラージュ理論を用いて教育を捉えることの意義 ・アッサンブラージュで教育を捉えることによって今まで見えなかったものが見えてくるかもし れない。 →外国人児童生徒と他の児童生徒との相互作用によって、新たな学びが生まれている等 ・流動的な教室空間における実践の意義を捉えることができる。日本語指導教室での取り出しは, 明確なねらいを設定した授業ばかりではなかったり,メンバーが変化しやすかったりする。 →「ねらいに基づいて,それを達成できたか」という見方は分析に適さないときもある →「ねらい」の達成からこぼれ落ちやすい子どもたち(言語的文化的に多様な子どもたちも含ま れる)の学びの肯定的側面,教育的意義を見出すのに適しているのではないか=包摂への示唆 ・外国人児童生徒の教育における,ICT機器やソーシャルメディアとの関係性のあり方 スライド16枚目 「生徒の抵抗(Lanas & Huuki, 2017),教師教育における「混乱」(Beighton, 2013),より大きなシ ステムにおける豊かで重要な学習の瞬間ではなく、失敗として読み取られてしまうかもしれないためらいの ような感情(Sellar, 2012)といった形の「short circuits(ショートサーキット/短絡回路)」(Deleuze & Guattari, 1983, p.42)を説明するために特に有用である。」
言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆に対する示唆 アッサンブラージュ理論を用いて教育を捉えることが大事 ・アッサンブラージュで教育を捉えることによって、線形的な「連続性(seriality)」がある 教育の中にも、今まで見えなかったものが見えてくる可能性がある。 →言語的文化的に多様な子どもと周りの子どもとの相互作用によって新たな学びが生まれてい る等 ・流動的な教室空間における実践の意義を捉えることができる可能性がある。 →日本語指導教室での取り出しは,明確なねらいを設定した授業ばかりではなかったり,メン バーが変化しやすかったりする。そのため、「ねらいに基づいて,それを達成できたか」とい う見方は分析に適さないときもある。そうした場での教育実践の特徴や意義を捉えることがで きる可能性がある。 スライド16枚目 「生徒の抵抗(Lanas & Huuki, 2017),教師教育における「混乱」(Beighton, 2013),より大き なシステムにおける豊かで重要な学習の瞬間ではなく、失敗として読み取られてしまうかもしれないた めらいのような感情(Sellar, 2012)といった形の「short circuits(ショートサーキット/短絡回 路)」(Deleuze & Guattari, 1983, p.42)を説明するために特に有用である。」
言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆 当日の議論をふまえて ◎アッサンブラージュ理論で教育実践を見ることは,学習論に回収されるのか? 教授すること,教師の役割はどう捉えることができるか? アッサンブラージュ理論は,教師や子ども,教材,状況などの関係をフラットに考えようとする 点で,教師も受動性がある存在になる →教師がねらいを定め,そのねらいに子どもが迫っていく,という直線的な捉え方にはならない しかし,アッサンブラージュのいちアクターとして捉えれば,教師は常に何らかの教育的意図 を持って,子どもの成長に最善の判断をして関わっている存在である =教師の「教育的な目線」はむしろ重要なものと捉えられるのではないか 例:ブッククラブ(第13回 Jagger & Carper(2024)の文献)や哲学対話における教師の役割 子どもたちの中で自然発生的に生まれてくる,多方向的・流動的な学びを重視する 一方で,教材の選択や子どもの言葉に対する応答など,教師の教育的な意図が関わる部分は 大いにあり,実践を形作る重要な要素となる