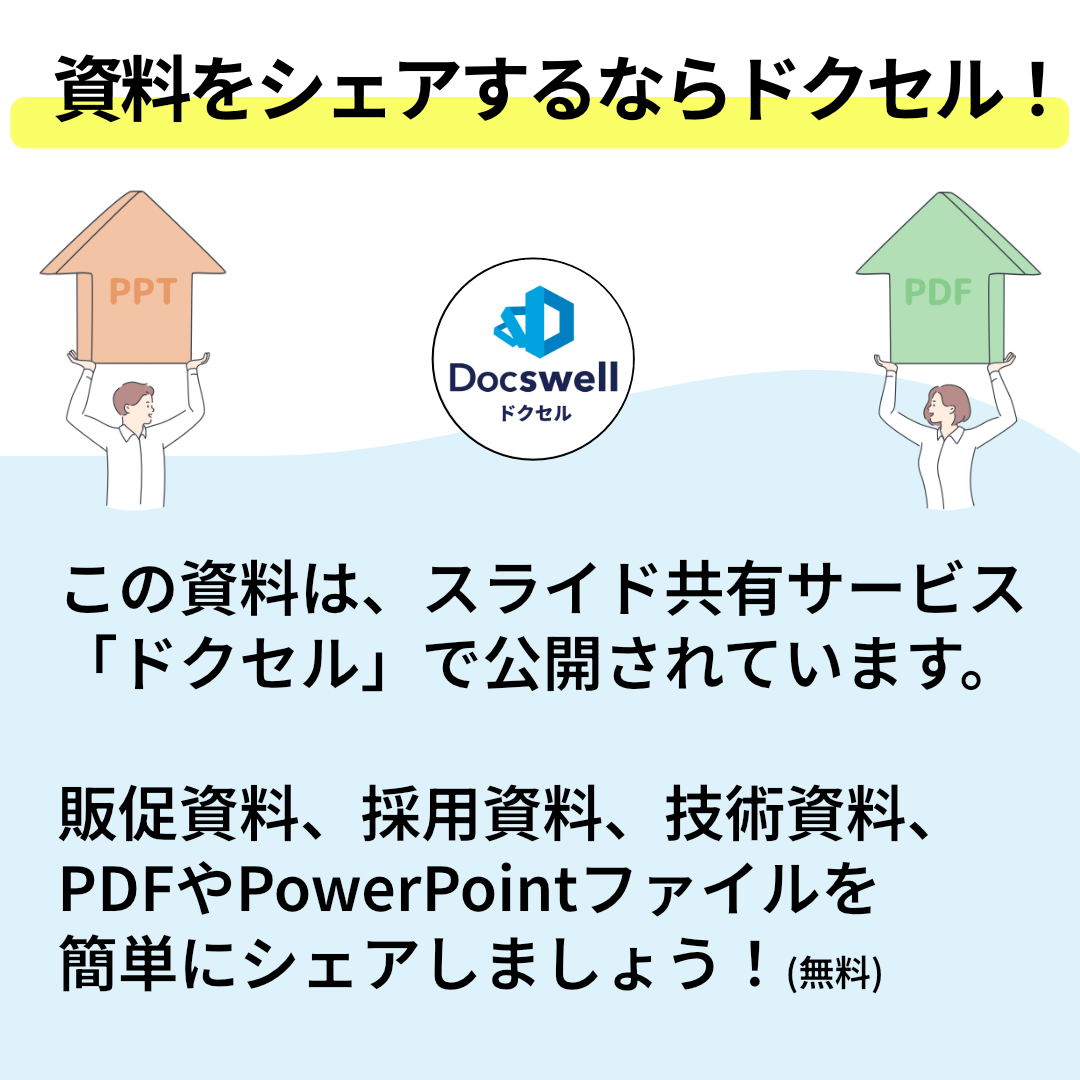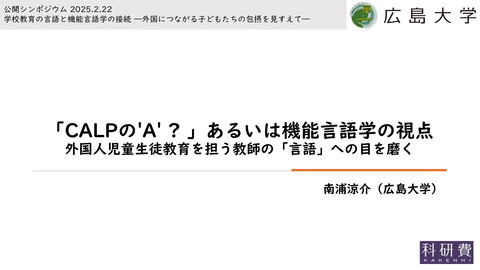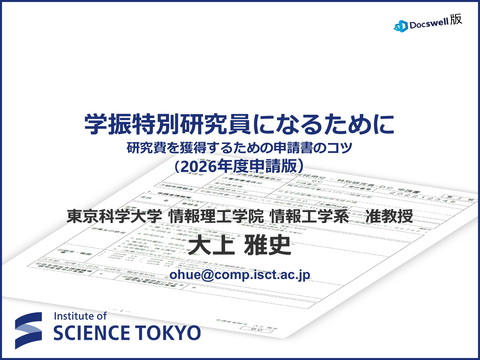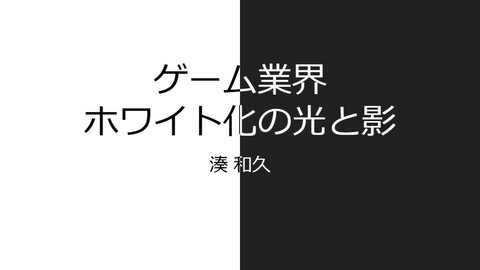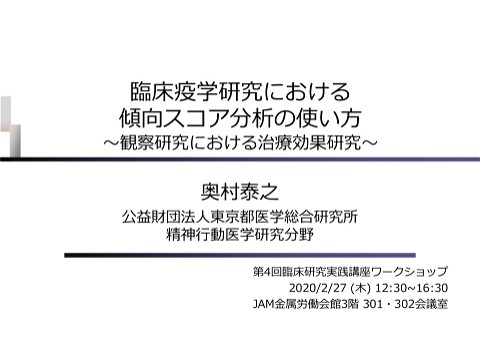外国人児童・生徒の教育課程デザイン論250725 発表資料Carper, P. and Jagger, S. (2024).
488 Views
September 06, 25
スライド概要
教育方法学・教科教育学という「一般的な教育」と,外国人児童生徒教育学という「特別な教育」をどちらも行っています。 このどちらもを同時に行う研究室は,日本の中ではほとんどありません。その結果,大学を含む多くの教育の場でこの両者は別々のものになってしまっています。
関連スライド
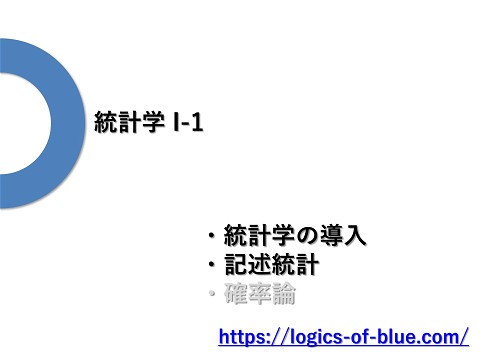
統計学I-1
 Logics of Blue
301.8K
Logics of Blue
301.8K
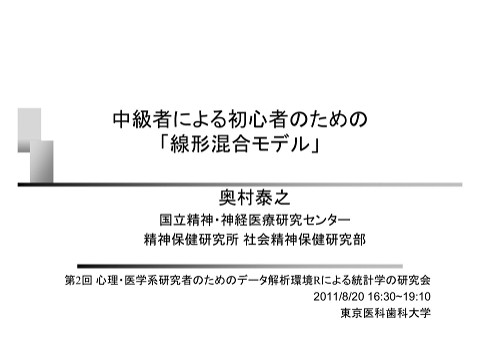
中級者による初心者のための「綿形混合モデル」
 奥村 泰之
223.8K
奥村 泰之
223.8K
各ページのテキスト
【お願い】このスライドは,広島大学 大学院人間社会科学研究科 教育科学専攻 教師教育デザイン学プログラムで開講している「外国人児童・生徒の教育課程デザイン論」(南浦涼介担当)の授業で行った受講大 学院生たちの発表資料です。 Trifonas and Jagger 2024 Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer のハンドブックのいくつかの章を選んで発表したものです。 教育的価値・資料的価値としてウェブでの掲載を行っていますが,いわゆる「論文」ではありませんので,論文等への引用や掲載は固くお断りします。 質問については広島大学南浦研究室(https://minamiura-lab.com/)までおねがいいたします。 Curricular Readings, Conversational Writings ―Dialogue on a Book Club― 2025年7月25日(金) 12:50~16:05 外国人児童・生徒の教育課程デザイン論 第12,13回 社会認識教育学領域M1 上中蒼也
発 表 構 成 発表構成 著者紹介 章構成 内容 言語的文化的に多様な 子どもの包摂への示唆
3 著者紹介 Susan Jagger トロント・メトロポリタン大学准教授 理科・数学教育、教育環境、参加研究法、批判理論と ポスト構造主義 https://www.torontomu.ca/early-childhood-studies/about/people/faculty/susan-jagger/ Paige Carper 独立研究者 ノースカロライナ州ウィルミントン拠点
発 表 構 成 発表構成 著者紹介 章構成 内容 言語的文化的に多様な 子どもの包摂への示唆
5 章構成 (はじめに) ブッククラブと社会的読書の略史A Brief History of Book Clubs and Social Reading 読書と執筆の対話Conversations of Reading and Writing アイデンティティを聞くIdentity and Listening アイデンティティの強さIdentity and Strength アイデンティティと喪失Identity and Loss アイデンティティと可能性Identity and Possibilities もう一度読み、もう一度書くRe-Reading and Re-Writing
発 表 構 成 発表構成 著者紹介 章構成 内容 言語的文化的に多様な 子どもの包摂への示唆
7 (はじめに) 「カリキュラム」とは? 学習指導要領 年間カリキュラム 福井県立藤島高等学校HPより
8 (はじめに) 「カリキュラム」とは? 語源=ラテン語「currere」 ・currency ・current ・occur ・course ・curriculum →「走る」「流れる」の意味、ニュアンス
9 (はじめに) 「カリキュラム」とは? 自身の経験を振り返り、 内省するプロセス 到達目標
10 ブッククラブと社会的読書の略史A Brief History of Book Clubs and Social Reading ~15c 修道士の写本 15~18c 活版印刷による印刷本 学問的で深い読書をする 男性 日常の退屈から逃れ、受け身で本を読む 女性 ※本は高価だったので、一部の金持ちやエリート層にとどまった。
11 ブッククラブと社会的読書の略史A Brief History of Book Clubs and Social Reading 19c中頃~後半 →女性も複数人で読書をするように ・女性の地位向上 ・性的マイノリティ ・社会的な問題 個人的な読書から集団的・社会的な読書へとシフト ・異なる視点への気づき ・批判的な思考 ・コミュニティの成長
12 読書と執筆の対話Conversations of Reading and Writing Paige & Susanらのブッククラブ 2020年7月~ (=コロナ禍) 毎月読みたい本を選書 時事的なものから普遍的なテーマまでさまざまなジャンル 読書を通じて自分の経験や感情を語り合い、それを通してそれを整理・再構成 =「currere」に基づく「カリキュラム」として機能 8冊の選書(自己、家族、コミュニティのアイデンティティ)
13 アイデンティティを聞くIdentity and Listening Jael Richardson著『Gutter Child』 社会的弱者が自由を得るために借金を返済させられる分断された世界を舞 台に、若き主人公Eliminaの旅を描く。特権階級の「本土」と抑圧された 「Gutter」に分かれた国で、Eliminaは本土で育てられた数少ないGutter出 身の子どもとして、自分のアイデンティティと居場所に苦悩する。アカデミーで 仲間と出会いながら、彼女は制度に抗い、自らの未来を切り開く力を見つけて いく物語。 https://books.google.co.jp/books/about/Gutter_Child.html?id=mOfdDwAAQBAJ&redir_esc=y Michelle Good著『Five Little Indians』 幼い頃に家族と離れ離れになり、寄宿学校で過酷な生活に耐えた5人の若者 が、それぞれ様々なトラウマを抱えながらも友情を支えに人生を再構築しようと する姿を描いた物語。社会に居場所を求めて苦闘する彼らは、それぞれ異なる 道を歩みながらも、過去と向き合い、前に進む希望を模索する。 https://books.google.co.jp/books/about/Five_Little_Indians.html?id=phKqDwAAQBAJ&redir_esc=y
14 アイデンティティを聞くIdentity and Listening Susan 先住民の寄宿学校の跡地で多数の 遺体が発見されたニュースを見て、 『Five Little Indians』を読んで議 論したことを思い出しました。 〈St. Joseph’s Mission寄宿学校遺体埋葬事件〉 ・2022年発覚 ・93名の遺体 〈カムループス・インディアン寄宿学校遺体埋葬事件〉 ・215名の遺体 ・先住民同化政策 ・2021年に発覚 https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/tk-eml%C3%BAps-tesecw%C3%A9pemc-215-children-former-kamloops-indian-residential-school-1.6043778
15 アイデンティティを聞くIdentity and Listening 1830年代 St. Joseph’s Mission 寄宿学校 開校 Peter Bryce氏が寄宿学校の疾病率と死亡率の高さを指 1907年 摘した文書を提出 1922年 Bryce氏『ある国家の犯罪の物語』出版 1997年 St. Joseph’s Mission寄宿学校 閉校 2008年 ハーパー首相、先住民に謝罪 2015年 カナダ真実和解委員会が『文化的ジェノサイド』と認定 2021年 カムループス・インディアン寄宿学校跡地で遺体発見 カナダ政府が過去に先住民同化政策をしていた ことが明るみに
16 アイデンティティを聞くIdentity and Listening なぜ最近になってようやく先住民に対して政府が「文化的ジェ ノサイド」をしていたことが知られるようになったのですか? 隠されていたのです。 子どもたちの死は昔から知らされていたのに、無視され ていたのです。 Susan 私は子どもの頃にアメリカに移住したので、最初のカナダ史と 現代のアメリカ史しか学んでいません。このような重要な歴史 的出来事を学び損ねてしまいました。 それは移住していなくても同じだったでしょう。寄宿学校 のことは学校のカリキュラムには含まれていませんから。 Paige
17 アイデンティティを聞くIdentity and Listening Paige でもブッククラブでの議論は夕食の時の会話にまで広がって います。子どもたちにも良い影響を与えているでしょう。 でもそれだけで十分なのでしょうか。。 子どもたちは、自分と似たような子としか交流していないので、 自分とは異なる背景を持つ子が直面する不正義や困難には 直面していません。 『Gutter Child』の主人公Eliminaが直面する制度的 抑圧や格差は、現実の社会構造と重ね合わせて見てし まいます。 Susan ブッククラブの議論(=インフォーマルな「カリキュラム」)によって、 学校では学べなかったことについて知る(「聞く」)ことができる。
18 アイデンティティの強さIdentity and Strength Brene Brown著『Braving the Wilderness』 著者Brownが現代社会のコミュニティや組織、文化における 分断と孤立の中で「真の帰属意識」を探求する本。 https://books.google.co.jp/books/about/Braving_the_Wilderness.html?id=E70sDwAAQBAJ&redir_esc=y Emily Nagoski, Amelia Nagoski著『Burnout』 女性が社会的に期待されていることと現実に女性として存在することの ギャップに苦しみ、独自の燃え尽き症候群を経験する理由を科学的に解き 明かす。博士号を持つ著者のNagoski姉妹は、ストレスの仕組みや感情の 調整法、自己ケアの重要性を示し、女性がより健やかに生きるための実践 的な方法を提案する。 https://books.google.co.jp/books/about/Burnout.html?id=DlnDDwAAQBAJ&redir_esc=y
19 アイデンティティの強さIdentity and Strength 『Braving the Wilderness』について議論していた時、参加 した人全員が、自分の居場所のなさを感じたことがあると言っ ていました。 Paige 私も人生の中でずっと自分の居場所というものを ずっと探していました。 Susan 面白いのは、ブッククラブに参加している人はみんな私の フィットネススタジオに所属しているんです。多くの人に居場所 を与えられたことは私の人生の大きな功績だと思っています。 私も、自分の居場所が安定してから、自分がやりたい ことをできるようになり、他者からの期待が重荷にな らなくなってきました。 居場所があることで自分のアイデンティティの強さを感じられる
20 アイデンティティの強さIdentity and Strength コロナ禍で授業がオンラインに切り替わる時、学生や他の 教員に反発されたり、息子を亡くしたパートナーをつなぎ 留めたりしていました。それが私の役割だったから。 でももう疲れてしまいました。。 Susan Paige でもブッククラブでの議論は、休息を取る勇気をもらった 気がします。 ブッククラブが成功したのはまさしくそこです! 『Burnout』で提起された「Human Giver Syndrome」を 思い出し、自分の居場所があるからといって常に与え続けな くてはいけないというわけではないことに気付かされました。 アイデンティティの「弱さ」を柔軟に受け入れることも強さ
21 アイデンティティと喪失Identity and Loss Michelle Zauner著『Crying in H Mart』(邦訳:Hマートで泣きながら) 著者であるMichelle Zauner本人が母の死をきっかけに、韓国系アメリ カ人としての自身のアイデンティティに苦しみ、再発見していく回顧録。母 との思い出や料理を通じて、悲しみと向き合いながら、自分自身を取り戻 していく過程が、率直で感情豊かに描かれる。 https://books.google.co.jp/books/about/Crying_in_H_Mart.html?id=kRjzDwAAQBAJ&redir_esc=y Emily M. Danforth著『The Miseducation of Cameron Post』 両親を事故で失ったCameronが抱いた感情は安堵。それは、彼女が直前に 女の子とキスをしていたことを知られずに済んだから。保守的な町で「正され る」ことを強いられた彼女は、愛とアイデンティティの狭間で苦しみながら、自 分自身であることの代償と向き合う、魂を揺さぶる青春と抵抗の物語。 https://books.google.co.jp/books/about/The_Miseducation_of_Cameron_Post.html?id=wWYqDwAAQBAJ&redir_esc=y
22 アイデンティティと喪失Identity and Loss 『Crying in H Mart』の中で、Zaunerが母親から外見 について指摘されているのを読んで、すごく共感しました。 私も母親にいつも外見や学校の成績のことを批判され続 けてきたから。それゆえに、常に競争する今の仕事に居心 地の良ささえ感じています。しかし、私がこのように影響を 受けていることを母は知りません。 Susan 私も母親との関係は複雑です。母の教育を娘に繰り返さ ないように、この親子関係の負のサイクルを自分の代で 断ち切るにはどうすれば良いでしょうか。 Paige
23 アイデンティティと喪失Identity and Loss 父親が亡くなる前に言いたいことを伝えきることができま せんでした。今でもMichelleのように父のことを思い出し ます。 Paige Susan 私もまだ親を亡くしてはいませんが、もし絶縁状態のとき に亡くしていたらどう感じていたのか問い直すきっかけに なりました。 Cammeronにとって両親を亡くしたのは最初のトラウマに すぎなかったでしょう。 他者の喪失による自身のアイデンティティへの影響
24 アイデンティティと喪失Identity and Loss Paige 『Cameron Post』を読んで、私は子どもとはじめて「自 分が好む代名詞」を共有しました。 すばらしいですね。希望の代名詞を使うことに反対するこ とはまさしく自己のアイデンティティを否定し、抹消させる 行為といえます。 Susan 自分の在り方だけでなく、ありのままの自分でいることを尊 重されていると感じられるために、さらに開かれた社会に なっていってほしいです。 社会によって自己のアイデンティティを喪失してしまう可能性
25 アイデンティティの可能性Identity and Possibilities Brit Bennett著『The Vanishing Half』 双子の黒人姉妹が異なる人種的アイデンティティを選び、それぞれの人生を 歩む姿を描いた物語。一方は黒人として娘と共に故郷に暮らし、もう一方は 白人として過去を隠して生きる中で、彼女たちの選択が次世代にまで影響を 及ぼす。人種、家族、自己の在り方をめぐる深い問いを投げかける作品。 https://books.google.co.jp/books/about/The_Vanishing_Half.html?id=xqRPEAAAQBAJ&redir_esc=y Matt Haig著『The Midnight Library』(邦訳:ミッドナイト・ライブラリー) 人生に絶望したNoraが、無限の可能性を秘めた「真夜中の図書館」で、 別の選択をしていたら人生はどうなっていたかという無数の人生を体験す る物語。彼女はさまざまな人生を旅しながら、後悔や願望と向き合い、本当 に生きる価値のある人生とは何かを見つめ直していく。 https://books.google.co.jp/books/about/The_Midnight_Library.html?id=7uqNEAAAQBAJ&redir_esc=y
26 アイデンティティの可能性Identity and Possibilities 有色人種の作家が本を出版するのにどれほど大変で しょうか。私は自分の肌の色が人生をどれほど楽にしてく れたのか考えたことがありませんでした。 『The Vanishing Half』は黒人として故郷で生きる Disireeと白人として生きるStellaを描いています。有色な のに白人として生きることを決意したStellaを我々は恥じる こともできるが、チャンスの多さを見ると理にかなっています。 Susan 長い目で見れば、素性がバレることを恐れずに生きられる Desireeの方が自分に合った人生を見つけられて幸せ だったとも言えます。 私たちは自分自身や未来の自分をどう構築するかを選ぶ ことができますが、これが特権的な立場からの語りである ことも認識しています。 Paige
27 アイデンティティの可能性Identity and Possibilities 私はビジネス経験ゼロで起業したり、安定したキャリアを 捨てて海外に移住したりしました。もし違う選択をしてい たら、と考えることもあります。しかし、これまでの経験が 私を形づくっています。 Paige 私も海外で教える経験をして、見知らぬ土地でも成長でき る自分に気付きました。 もし自分の人生を変えるとしたら、もっと自分の声を上げた いです。自信がなくても、聞いてもらえなくても。 Susan 自分の声が相手に聞いてもらえないのは、あなたのせいで しょうか?相手のせいでしょうか?大事なのは思いやりを 持って対話することだと思います。 人種や属性によって、人生の可能性(選択肢の数)が違う。
28 もう一度読み、もう一度書くRe-Reading and Re-Writing 〇「カリキュラム」の再定義 ・カリキュラムは学習目標のチェックリストではなく、個人の人生経験を省察し 語り直す旅(currere)。 ・ブッククラブのやりとりは「カリキュラム」として機能している ・参加者が自らの経験の省察を通して過去・現在・未来を見つめなおす Paige ex... 自分の声が相手に聞いてもらえないのは、あなたのせいで しょうか?相手のせいでしょうか?大事なのは思いやりを 持って対話することだと思います。 自己の省察を通し、他者との違いの中に共通点を見出して出た発言 到達目標が予め決められたものではない、「currere にもとづいた カリキュラム」
発 表 構 成 発表構成 著者紹介 章構成 内容 言語的文化的に多様な 子どもの包摂への示唆
30 言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆 ①個人の経験を中心に据えた学び ・「currere」に基づいた「カリキュラム」 =自分の経験を省察し語り直す ・言語・文化・移動・家族など多種多様な経験 ②アイデンティティの探究と尊重 ・外国人児童生徒が「自分は誰か」「どこに属しているか」を安心して探求できる場 多様な言語的文化的背景を持つ人も関われる社会的な空間 (=ブッククラブ、学校、etc...) →より豊かで深い、重層的な関わりの創出につながる可能性
31 引用・参考文献 SPRINGER NATURE Link「Curricular Readings, Conversational Writings: Dialogue on a Book Club」 https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-3-03121155-3_57 (最終閲覧日:2025年7月20日) Toronto Metropolitan University 「School of Early Childhood Studies: Susan Jagger」 https://www.torontomu.ca/early-childhoodstudies/about/people/faculty/susan-jagger/ (最終閲覧日:2025年7月20日) 文部科学省(2018)『高等学校学習指導要領』東洋館出版社 福井県立藤島高等学校「令和7年度教育課程」 https://www.fujishima-h.ed.jp/schoolinfomation/%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%a1%88%e5%86%85/ (最終閲 覧日:2025年7月20日) Googleブックス「Gutter Child」 https://books.google.co.jp/books/about/Gutter_Child.html?id=mOfdDwAAQBAJ&redir_esc=y (最終閲覧日:2025年7月21日) Googleブックス「Five Little Indians」 https://books.google.co.jp/books/about/Five_Little_Indians.html?id=phKqDwAAQBAJ&redir_esc=y (最終閲覧日:2025 年7月21日) CBC(2021)「Remains of 215 children found buried at former B.C. residential school, First Nation says」 https://www.cbc.ca/news/canada/britishcolumbia/tk-eml%C3%BAps-te-secw%C3%A9pemc-215-children-former-kamloops-indian-residential-school-1.6043778 (最終閲覧日:2025年7月24日) Googleブックス「Braving the Wilderness」 https://books.google.co.jp/books/about/Braving_the_Wilderness.html?id=E70sDwAAQBAJ&redir_esc=y (最終閲 覧日:2025年7月21日) Googleブックス「Burnout」 https://books.google.co.jp/books/about/Burnout.html?id=DlnDDwAAQBAJ&redir_esc=y (最終閲覧日:2025年7月21日) Googleブックス「Crying in H Mart」 https://books.google.co.jp/books/about/Crying_in_H_Mart.html?id=kRjzDwAAQBAJ&redir_esc=y (最終閲覧日:2025年7 月21日) H MART「ホーム」 https://www.hmart.jp/ (最終閲覧日:2025年7月21日) Googleブックス「The Miseducation of Cameron Post」 https://books.google.co.jp/books/about/The_Miseducation_of_Cameron_Post.html?id=wWYqDwAAQBAJ&redir_esc=y (最終閲覧日:2025年7月21日) Googleブックス「The Vanishing Half」 https://books.google.co.jp/books/about/The_Vanishing_Half.html?id=xqRPEAAAQBAJ&redir_esc=y (最終閲覧日: 2025年7月21日) Googleブックス「The Midnight Library」 https://books.google.co.jp/books/about/The_Midnight_Library.html?id=7uqNEAAAQBAJ&redir_esc=y (最終閲覧日: 2025年7月21日)
- https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-3-031-21155-3_57
- https://www.torontomu.ca/early-childhood-studies/about/people/faculty/susan-jagger/
- https://www.fujishima-h.ed.jp/schoolinfomation/学校案内/
- https://books.google.co.jp/books/about/Gutter_Child.html?id=mOfdDwAAQBAJ&redir_esc=y
- https://books.google.co.jp/books/about/Five_Little_Indians.html?id=phKqDwAAQBAJ&redir_esc=y
- https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/tk-emlúps-te-secwépemc-215-children-former-kamloops-indian-residential-school-1.6043778
- https://books.google.co.jp/books/about/Braving_the_Wilderness.html?id=E70sDwAAQBAJ&redir_esc=y
- https://books.google.co.jp/books/about/Burnout.html?id=DlnDDwAAQBAJ&redir_esc=y
- https://books.google.co.jp/books/about/Crying_in_H_Mart.html?id=kRjzDwAAQBAJ&redir_esc=y
- https://www.hmart.jp/
- https://books.google.co.jp/books/about/The_Miseducation_of_Cameron_Post.html?id=wWYqDwAAQBAJ&redir_esc=y
- https://books.google.co.jp/books/about/The_Vanishing_Half.html?id=xqRPEAAAQBAJ&redir_esc=y
- https://books.google.co.jp/books/about/The_Midnight_Library.html?id=7uqNEAAAQBAJ&redir_esc=y