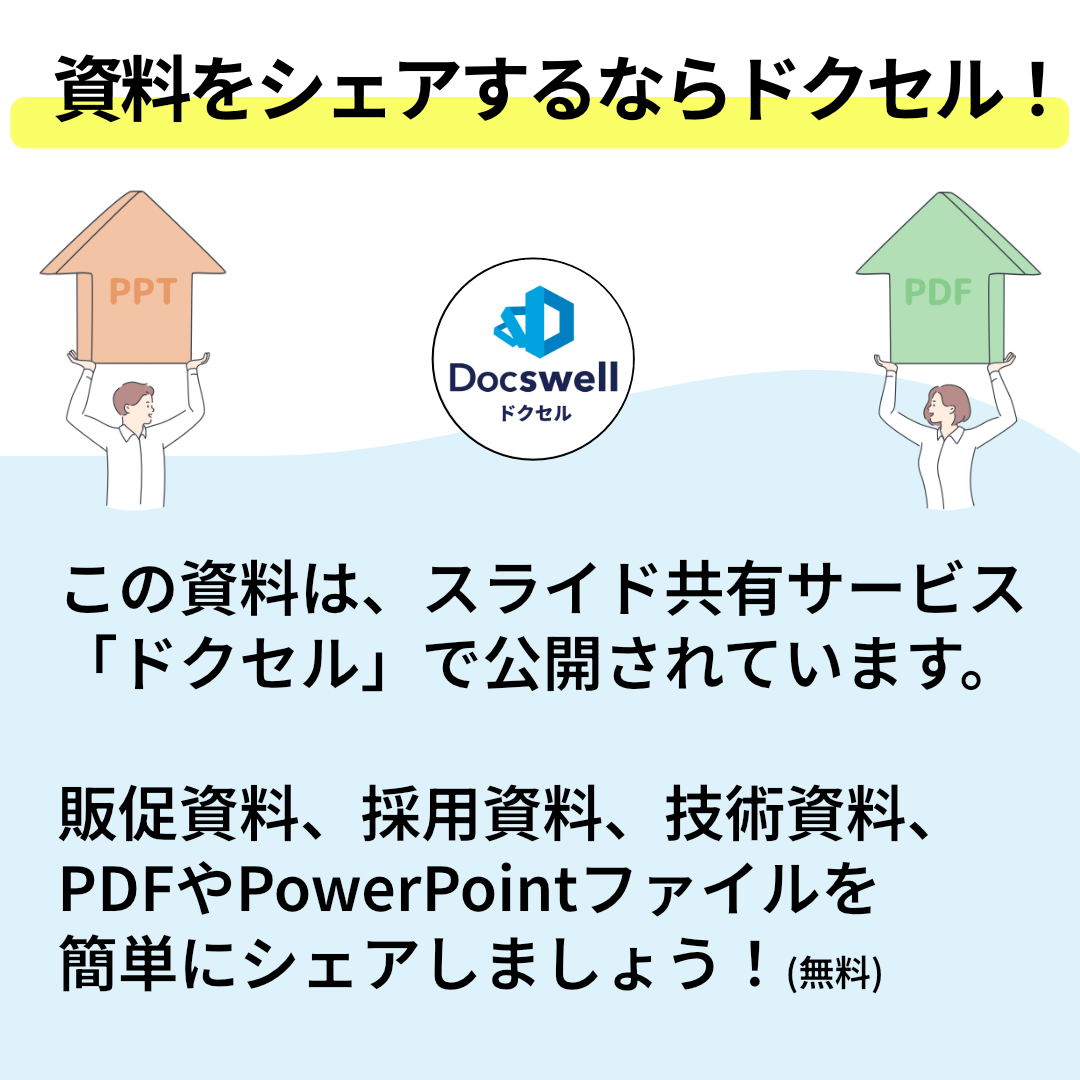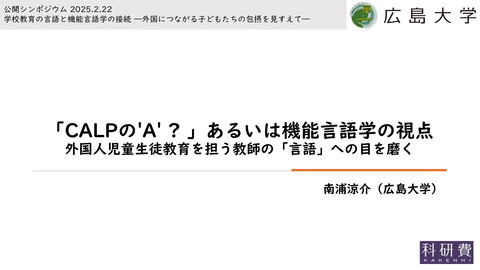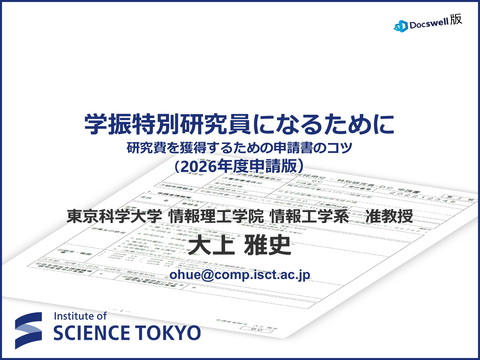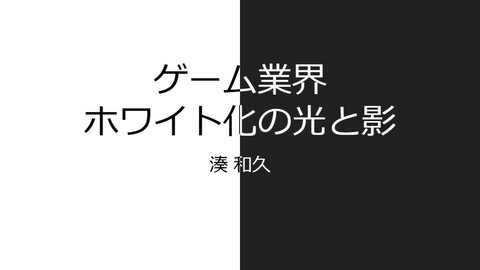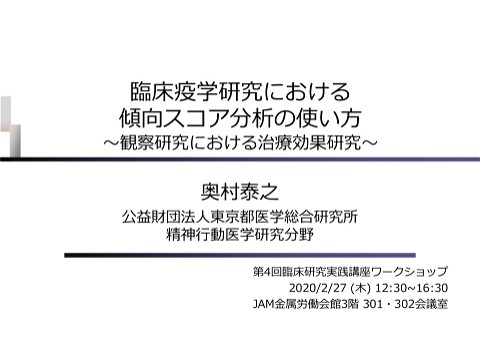外国人児童・生徒の教育課程デザイン論250801 発表資料 Khan, S. and VanWynsberghe ,R. (2024)
454 Views
September 06, 25
スライド概要
教育方法学・教科教育学という「一般的な教育」と,外国人児童生徒教育学という「特別な教育」をどちらも行っています。 このどちらもを同時に行う研究室は,日本の中ではほとんどありません。その結果,大学を含む多くの教育の場でこの両者は別々のものになってしまっています。
関連スライド
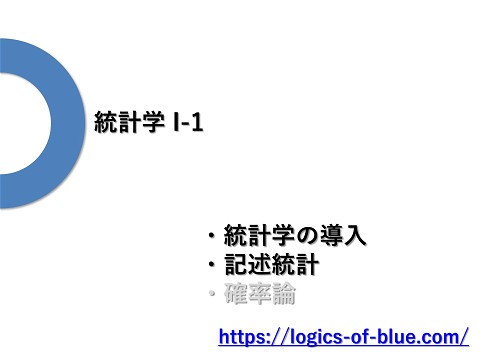
統計学I-1
 Logics of Blue
301.8K
Logics of Blue
301.8K
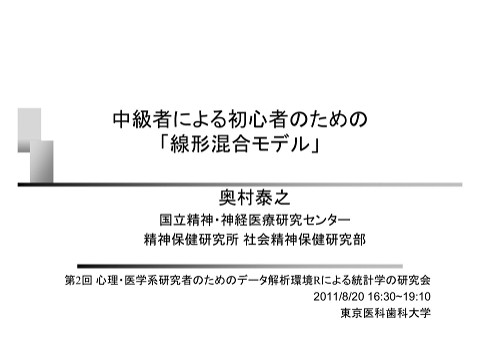
中級者による初心者のための「綿形混合モデル」
 奥村 泰之
223.8K
奥村 泰之
223.8K
各ページのテキスト
【お願い】このスライドは,広島大学 大学院人間社会科学研究科 教育科学専攻 教師教育デザイン学プログラムで開講している「外国人児童・生徒の教育課程デザイン論」(南浦涼介担当)の授業で行った受講大 学院生たちの発表資料です。 Trifonas and Jagger 2024 Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer のハンドブックのいくつかの章を選んで発表したものです。 教育的価値・資料的価値としてウェブでの掲載を行っていますが,いわゆる「論文」ではありませんので,論文等への引用や掲載は固くお断りします。 質問については広島大学南浦研究室(https://minamiura-lab.com/)までおねがいいたします。 Samia Khan and Robert VanWynsberghe(2024), Identifying Children's Funds of Knowledge as a Bridge to STEM ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 長谷川 智洋 陳 禹丞 1
1. 著者紹介 2. 論文構成・キーワード Agenda 3. 論文要約 4. 言語的文化的に多様な子どもの包摂への 示唆 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 2
01 著者紹介 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 3
1.著者紹介 Samia Khan Robert VanWynsberghe ブリティッシュコロンビア大学(BCU)教育学部教授 ブリティッシュコロンビア大学(BCU)教育学部教授 研究関心 (1)科学教育:教育学・人々がどのように学ぶか (K-16)・教師教育 (2)教育技術:視覚化・教室との統合 (3)研究方法:解釈と比較研究・ケーススタディと クロスケース分析・混合手法 研究関心 アダプティブ教育、成人教育、コミュニティエンゲージ メント、持続可能性のための教育、社会運動、教育社会 学、スポーツメガイベント ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 4
02 論文構成・キーワード ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 5
2.論文構成 『Identifying Children's Funds of Knowledge as a Bridge to STEM 』 •はじめに •STEMの知識基盤の概念的背景 • STEMの「知識の財産」カリキュラムとその影響のレビュー •研究方法 • 事例の選択 • STEM知識基盤の学校外カリキュラムの開発 • 学校外プログラムにおけるSTEM「知識の財産」カリキュラム •データ分析 • データ分析の信頼性 •結果と考察 • カリキュラムのために特定された子どもたちのSTEM知識源 • STEMの「知識の財産」プログラムが子供たちに与える影響 • 「知識の財産」カリキュラムを通じた子どもたちのSTEMの概念を学ぶ機会の獲得 • 「知識の財産」カリキュラムから学ぶ機会が学業成果に影響を与えた可能性 • 成績表データの縦断的分析 • 出席率に関する分析 •研究の結論と意義 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 6
2.キーワード 知識の財産(Funds of knowledge)・ 教育・家庭・子ども・STEM・持続可能性・ 科学・数学・技術・工学(STEM) ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 7
https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/1724/より引用 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 8
03 論文要約 Samia Khan and Robert VanWynsberghe(2024), Identifying Children's Funds of Knowledge as a Bridge to STEM ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 9
3.論文要約 はじめに 研究目的 北米の多文化的で「資源の乏しい」地域に暮らす子どもたちに対して、家庭に おけるSTEMの「知識の財産」カリキュラムがどのような影響を与えるかを調査 すること この事例における「カリキュラム」 「どのように、何を、誰のために学ぶのか」を探求するためのプロセス STEMの「知識の財産」 科学・技術・工学・数学といった体系化された分野に関連し、主に家庭や地域 社会の営みの一部として得られる知識や技能(Hogg,2011) 研究の目標 「知識の財産」に基づくカリキュラムが子どもたちのSTEM知識にどのような 貢献をもたらしうるのかを明らかにすること ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 10
3.論文要約 STEMの知識基盤の概念的背景 「知識の財産」: 家庭や個人の生活や福祉に不可欠な知識や技能の体系であり、歴史的に蓄積され、 文化的に形成されたもの(Gonzalezら, 2005) 子どもたちの「知識の財産」を学校教育の現場にどう統合できるか 「知識の財産」に基づく カリキュラムを子どもたち に提供した結果、教師や研 究者が家庭で特定した豊か な認知的資源を授業に組み 込むことで、子どもたちは 自身の知識を活用できる (Gonzalezら, 2005) 「学校のカリキュラムは、 教育と学習の営みにおいて 足場となる現実に適応させ ることができる」 (LlopartとEstebanGuitart,2018) ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 子どもたちの知識の財産 を承認することで、「子ど もたちの生活世界と科学の 授業との間の移行がスムー ズになる」 (BartonとTan,2009) 11
3.論文要約 STEMの知識基盤の概念的背景 ーSTEMの知識の財産カリキュラムとその影響のレビューー 先行研究の多くにおいて、子どもたちは自分自身の「知識の財産」を喜んで共有し、科学的なト ピックについて自信をもって自分の考えを表現するようになったと報告されている。 著者 対象者 Ayersら (2001) アリゾナ州の7・8年生 (主にヒスパニック系) 内容 建設業に従事する家庭背景を活かした「夢の家を建てよう」プロジェクトにより、 低学力層の生徒の数学への関心と自信を向上させた。 Barton & Tan (2009) 米国の低所得層地域の6年生 「食と栄養」単元に知識の財産を取り入れた授業で、生徒の授業への参加意欲が (アフリカ系・ヒスパニック系) 増加。おとなしい生徒も積極的に発言するようになった。 Seiler (2001) 「昼休み科学研究」で、ドラム演奏やスポーツを科学と結びつけた活動により、 (主にアフリカ系アメリカ人) 生徒同士の科学的な議論と語彙使用が促進された。 Zipin (2020) 都市部の高校生 9〜10年生 (多様な背景の生徒) 洪水経験をもとにした仮想的なSTEM授業で、生徒が個人的経験を社会文脈に結び つけ、成績不振生徒もテキスト読解や調査に積極的に関与するようになった。 先行研究の大半は、知識やカリキュラムの共同構築への参加機会に焦点を当てていた。 本研究の位置づけ 量的・質的データの両方を用いて、「知識の財産」アプローチが子どもたちの STEMに関する学習成果をどのように高めうるかを探る。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 12
3.論文要約 研究方法 「資産が乏しい(low-asset)」北米のある地域において、混合的手法による ケーススタディを実施 「知識の財産」と学業的・非学業的成果との関係を明らかにする 著者が考察が不十分だと考えている先行研究(Rios-Aguilar,2010) 212名のラテン系生徒を対象に、彼らの家庭の労働履歴、社会的相互作用、教育 的経験、言語使用などの「知識の財産」に加えて、社会的互恵性、家庭内活動の 頻度、親の教育理念、親の言語習得状況、英語リテラシーを重視した活動、スペ イン語リテラシーを重視した活動も調査し、それらの要素と標準化テストの得点 やGPA(成績平均点)といった学業成果とを重回帰分析によって関連づけた。 分析の結果、「知識の財産」は、生徒の学業成績や読解力の成果とは有意に関連 していなかった。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 13
3.論文要約 研究方法ー事例の選択ー • 人口約57万8,000人の北米の大都市「パークスタウン(仮名)」内の子どもたち の幸福度や社会的・経済的背景が低い地域を選定。 • 中国語を話す家庭の割合が高く(56%)、平均世帯収入は市全体の平均よりも 低い。 この地域の子どもたちの「知識の財産」を把握するために、コミュニティのリ ソース調査、地域住民との対話、家庭訪問を実施 明らかになった「知識の財産」に基づいて、課外授業・夏季プログラムを開発。 プログラム実施後に、子どもたちのSTEMに関する知識が評価された。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 14
3.論文要約 研究方法 ー学校外プログラムにおけるSTEM「知識の財産」カリキュラム開発ー カリキュラム検討グループ(Curriculum Study Group:CSG)がカリキュラム開発のために招集 CSGの構成員:地域の小学校管理職、地域に根ざしたNGO、地元大学の教職課程の学生、教育学・社会学の研究者、 小学校教員、学校制度内の地域ワーカー、サステナビリティの専門家。 • 5歳から12歳の地域内の子ども計47名がSTEM「知識の財産」カリキュラムに参加した。 • STEM 「知識の財産」カリキュラムは1年間にわたり実施された。 • • 放課後に1か月間にわたって2つの学校で、合計5.25時間と10.5時間提供された。 夏季課外プログラムも実施され、合計44時間行われた。 • プログラムに参加した子どもたちの多くは、学校で課題があると見なされた子どもたちであった。 分析対象(データ) 指導者の 振り返り (3名) 観察ルーブ リックの 記入と 記録写真 受講生を推 薦した教師 アンケート (5名) 子ども アンケート (47名) ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 保護者 アンケート (25名) 成績データの プログラム 前後の比較 (6名) 15
3.論文要約 データ分析 質的分析 量的分析 1. カリキュラムに参加した子どもに関わる あらゆる場面の情報を収集 2. コーディングの分類 • STEMに関わる「知識の財産」 (例:動物、昆虫、建設など) • STEM以外の「知識の財産」 (例:作文、宗教など) 3. コーディングの信頼性をIRR(相互評価者 間の一致率)やNvivo(定性分析ソフ ト)を使って高める 4. トライアンギュレーション(データの信 頼性を高めるために複数の視点から分 析)を実施 1. 6人の子どもについて、以下のタイミング で通知表の成績を比較 • • • プログラム実施の1年前 実施後の1学期後 2学期後 2. 通知表の評価方式の違いを考慮し、全て の成績を数字に換算(標準化)して比較 (幼稚園〜小学3年の成績は「できる・できない」などの達 成度ベースで科学がない、4〜7年生の成績はA〜Fなどのア ルファベットで評価) 3. 母集団の分布を仮定しないノンパラメト リック検定を用い、プログラム前後で、 子どもたちの成績が統計的に有意に変化 したかどうかを調査 • • ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 対象者が少なく(n = 6)、正規分布(平均的な 分布)が期待できないため、 特に数学(STEM科目)の成績の変化に注目。 16
3.論文要約 結果と考察-カリキュラムのために特定された子どもたちのSTEM知識群 目的:コミュニティで十分に活用されていないSTEMの知識の財産を特定し、共同で構築した「知識の財産」カリキュラム が、子どもたちのSTEM学習や取り組みに与える可能性のある影響について考察する。 やったこと: 1.特定された子どもたちの家庭の「知識の財産」について説明し、その後、そのコミュニティの子どもたちに提供され るカリキュラムに組み込んだ。 2.「知識の財産」カリキュラムが子どもたちのSTEM知識に与える影響の分析。2セクションデータ分析に基づく検討。 コミュニティ相談、家庭訪問、CSG、関係者インタビューで得られたデータをコード化し、テーマ分類し、重要な引用 とコミュニティからの写真、訪問やインタビューからの引用をテーマに分類し、包括的な知識基盤を特定した。 パークスタウンの都市コミュニティにおける学生たちのSTEM知識源: • 大工仕事 • ガーデニングと持続可能性 • 植物と植物生理学 • 食品栄養と健康 • ホームベーカリー • 薬膳スープとお茶に関する知識 これらの要素は、「知識の財産」として利用し、カリキュラムに取り入れるのは可能である。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 17
3.論文要約 結果と考察-カリキュラムのために特定された子どもたちのSTEM知識群 調査方法: 子どもたちの学校外活動への関与について、保護者アンケートの内容: 「放課後、定期的(4回/月)に子どもの学習を手伝っている(こと)」 数学、科学、ガーデニング、料理、デジタル(コンピューター)技術、物の作り方や機械の仕組み、持続可能な生活の仕 方など、14の選択肢/カテゴリーがあるが、これらに限定されない。 表1は、選ばれた回答の上位5つをまとめたものである。 ホームベーカリー事業と持続可能なガーデニングは、このコミュニティで発見された主な知識源のひとつである。 持続可能な生活 ガーデニング デジタル技術 物の作り方・機 料理 械の仕組み 36% 24% 24% 28% 20% 表1 放課後の子供の家事活動上位5項目 (n=25) p.953 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 18
3.論文要約 ホームベーカリー事業: 家庭訪問で、子供たちが放課後、家の外で模擬店をしていることを明かした。 具体:テーブル、椅子、お金を入れる箱、クッキーのお皿を持って外に出る。友達と一緒にクッキーを作る。それから、 時々お父さんも手伝う。 この知識は、お金の取り扱いを通じて通貨、交換、計算、象徴的価値の理解を促進し、広告活動やバザー販売を通じて起 業家精神のスキルを養うのに役立つ。 さらに、ある子どもは家庭訪問で、おもちゃ屋さんで買ったキャンディー作りキットを持っていることを話した。 この「知識の財産」から、材料の測定方法、化学物質の相互作用や反応について学んだことがあったのを推察される。 表1で、一緒に料理を作るのは、20%のが選ばれた。 祖父母と孫と一緒に料理とお菓子作りのが好きである。 子供がお菓子作りに慣れた後、自分のレシピを作ることになる。 異なる材料の比率を試し、最終的な製品を見ることで、数学的比例感覚をさらに発展させることができると推察された。 他には、栄養、食品科学、測定なども議論できる。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 19
3.論文要約 持続可能なガーデニング: 28%の保護者が、定期的に子供と一緒にガーデニング活動を行っている。ガーデニングは、1時間のセッションで4回、 他の家庭活動よりも多く取り上げられた。 「孫たちに、ミミズやミツバチなどの地球に良いことを教えるのが好きなんです。」 地域資源のスキャン、地域内の写真では、近所の家の屋上庭園、裏庭庭園などが、コミュニティ・ガーデ ンの証拠である。 「最も緑豊かな都市行動計画」:堆肥を増やし、コミュニティ・ガーデンの数を増やすようとする呼びかけ。 ガーデニング、植物の生態に関する基本的な情報を含む。 36%の保護者が、放課後で定期的に子供たちに「持続可能な生活」についての学習を手伝う。 教える内容:再利用、再製造、回収利用、地球温暖化・二酸化炭素の影響、節水、節電、公害、持続可 能性・非持続可能性について紹介する。 子供たちも基礎的な理解(自分で野菜・花を植える、公共交通利用等々)を持ってきた。 計画的に家庭の知識の財産を活用したガーデニング活動で、子供に植物生理学や持続可能な 学校菜園への取り組みをさらに教えるカリキュラムを構築することができる。 例えば:カリキュラムの園芸活動には、種まきなども含め、生存に必要な植物についての議論 子供たちの植物に関する知識を花植え活動で強化する。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 20
3.論文要約 結果と考察ーSTEM「知識の財産」プログラムが子供たちに与えた影響 目的2:STEM「知識の財産」カリキュラムが子供たちの学習と関連する概念の理解に及ぼす可能性のある効果を研究する。 「知識の財産」に基づいたカリキュラム構成が、家庭と学校の溝を埋めることがどのように促進される可能性があるの か? なぜ「知識の財産」に基づいたカリキュラム構成は重要なのか? 成果のまとめ: • 授業参加の増加、科学への興味、家庭とのつながりの深化が確認された。 • 子どもたちは自らの知識を活用して科学的に考える姿勢を見せた。 • 教員も子どもたちの理解や成長を実感し、教え方を柔軟に変化させた。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 21
3.論文要約 授業参加の増加、科学への興味、家庭とのつながりの深化 子供たちの学校外プログラム参加する前の事前アンケート: 大多数は「科学を使う仕事についてもっと知りたい」と答えた。 「家は3つの好きな場所のうちの一つ」と答えた子供は、16人中6人しかいない。 校外学習プログラム: コミュニティの知識の財産を基に構築され、カリキュラムはCSGの中で、また現職教師や教育者によって構築された。カリキュラム 作成に携わった2人の教育者が、放課後のK-7(幼稚園から中学1年の児童生徒)プログラムを二回(各5.25時間と10.5時間、1ヶ月 間)、校外のK-7サマープログラムを1回(44時間)実施した。合計60時間である。カリキュラムは教育者とアシスタントによっ て実施され、全プログラムのうち、合計47家族以上が参加した。このプログラムには、兄弟姉妹の参加も許可された。 食品に関する「知識の財産」の蓄積に基づいたカリキュラムの展開: 教師:「家で何を測ったことがありますか?」「親が料理している間に測るのを手伝ったことがあ る?」 学生:計量や調理に関する知識源につなげようとした。食品科学と計量知識を用いて、タンポポ茶の 活動でさらなる議論をできる。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 22
3.論文要約 授業参加の増加、科学への興味、家庭とのつながりの深化 弁当箱の調査活動: 教育者はすべての子供が弁当を持ってくるわけではないことに注目した。 弁当に関する知識の蓄積は… 「お弁当やスープをどのように保温するか?」という議論を引き起こした。 廃棄物処理場向けの食品廃棄物を分類する活動: 果物のシールを剥がすか、シール付きの果物を持参するよう指示され、食品の起源と行き先について疑 問を投げかけるよう促されました。 これらの例は、カリキュラムの活動を開発するために「知識の財産」がどのように利 用されたかを示しており、教育者の教え方が、子どもたちの生活と関連性を持たせ、 学習の機会を創出するものであった。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 23
3.論文要約 「知識の財産」に基づくカリキュラムを通じたSTEM概念の学習機会を得た 教育者たちは、日々の振り返りの中で自分たちの方略を共有するよう求められ、また、事前・事後のアンケートも記入し た。夏のプログラム最後三日間のカリキュラム校外研修に参加した。振り返り分析の結果、教育者の自由形式の質問に よって、子供たちの「知識の財産」をさらに探求し、強化することができたことが明らかになった。 1. 植物・ガーデニング活動における事前知識の活用 • 教師は「植物について何を知っていますか?」といったオープンな質問を用い、生徒の家庭での経験 (家庭菜園など)を引き出した。 • 子どもたちは植木鉢の底に穴が空いている理由を説明でき、水はけや植物の成長条件などの理解を深め た。 「家庭菜園などの経験を出発点として、植物の成長や水の管理についてのSTEM的理解を広げた。」 2. 食と測定に関する活動 • 子どもが家で料理の際に計量をしている経験を活かし、「家で何を計ったことがあるか」を出発点に活 動を展開。 • 蜂蜜などを使った食に関する活動を通じて、科学的探究や測定・比較の概念を学んだ。 「料理経験を通じて、測定や食に関する科学的探究を促した。」 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 24
3.論文要約 3. 昆虫・分解者に関する応用的理解 • 散歩後、子どもが「ミミズが人間も分解するの?」と発言し、分解者の概念が人間の死体にも当てはまると独自に類推。 • 教師はこのような発言を通じて、子どもの思考の深まりを把握できた。 「分解者の概念を身近な現象と結びつけて、子どもが応用的に理解し始めた。」 4. アーティファクト・バッグを用いた家庭と授業の接続 • 子どもは家庭から「夕食の象徴」となる物を持参し、それをもとに鳥と人間の食物連鎖を比較。 • この活動を通じて、食物連鎖・食物網の理解へと発展。 「家庭にあるものをきっかけに、生態系や食物連鎖の理解を深めた。」 以上の事例で、子供たちは気づいていなかったが、「知識の財産」カリキュラムを通し てSTEMの概念を学ぶことがあった。事後のアンケートでは、子供も「理科の新しい活動 はしなかった」と回答した。 「知識の財産」カリキュラムを通して、欠如アプローチ(教育の失敗の基礎を子供やそ の家族、文化に求める考え)から離れ、子供たちの既に持っている知識を大事にし、 STEMの概念を学ぶ機会を提供した。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 25
3.論文要約 子どもの変容と学習目標の接続 活動の参加によって、アーチーという子供が最初のエネルギーが高く不安も強く状態から成長して、家庭での知識を能動 的に学校の学習とつなぎ、鳥、植物、リサイクルに関する知識が向上し、自信をもって他者に説明できた。 不安のある子どもでも、「知識の財産」を活かしたカリキュラムを通じて、STEM理解と社会的な成長が見ら れることを示している。 チャンドラという子供は、友人関係に課題があるが、彼女を敢えて「空間的な推論を発達させる」ための学習 におけるグループリーダーに任命した。その学習過程で鳥の巣箱制作をすることになった際、当初兄弟と口論 をしていたが、最終的に協力し、巣箱を芸術性や創造性にも着目しながら完成させることができた。 地域や家庭にはたくさんのアートとの関連性があり、これらを活用することで空間的推理、数学、比率、割合、 視覚化、コミュニケーション能力などの州政府の学習目標などは十分に育つだろう。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 26
3.論文要約 成果と考察ー「知識の財産」カリキュラムから学ぶ機会が学業成績に影響を与える可能性 分析手法: • 事前・事後の通知表データ(成績・出席)を用いて、STEM「知識の財産」に基づくカリキュラムが学業成果に与える影 響を分析した。 • 定量的評価として、Wilcoxonの符号付き順位検定(ノンパラメトリック手法)を採用。 • 分析対象は、報告書提出に同意した6名の児童(学年K〜7)の成績および出席記録。 分析対象データと比較: 1. 対象期間: • プログラム実施前年度の成績 • プログラム実施後の学期1および学期2の成績 2. 比較項目: • 全教科平均点 • 数学の成績 • 欠席・遅刻回数 3. データ標準化: • K〜3年生の期待値評価(達成度)と4〜7年生の評定(A〜F)を変換して統合分析。(p.953) ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 27
3.論文要約 分析結果: 比較 検定結果 (Wilcoxon) 成績 P値 平均点の変化 全教科(学期1) 有意差なし p = 0.75 70.43 → 71.27 全教科(学期2) 有意差なし p = 0.25 70.43 → 75.70 数学(学期1) 有意差なし p = 0.89 78.33 → 77.83 数学(学期2) 有意差なし p = 0.11 78.33 → 84.42 数学においては平均点が上昇する傾向が見られたが、統計的な有意差(成績の激しい変化)は確認されなかった。 欠席数(前年ー学期1) 出席 平均 11.83 回 遅刻数(前年ー学期1) 平均 5.33 回 欠席数(前年ー学期1+2) 平均 9.41 回 平均 -1.33 回 遅刻数(前年ー学期1+2) 出席状況にも明確な有意差(明らかな関係性)は見られなかったが、このカリキュラムの参加を通して 一部児童に改善傾向があった可能性も示唆された。 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 28
3.論文要約 研究の結論: • 量的評価方法も、統計で 現したように、有意差が なしで、必ずしもすべて の「知識の財産」を評価 範囲内に入れたと言えな い。(出席数、遅刻数、成績) • 「知識の財産」から生ま れたカリキュラムの開発 は、子どもたちの態度変 容(参加・創造)、科学 への興味向上、家庭と学 校の連携に良い効果があ る。 • 教師は「知識の財産」カ リキュラムを実行する際 にも、学生達の成長がよ り注目でき、柔軟に授業 方略を調整でき、役割の 反省にも促す。 子どもたちが既に何ら かの知識を持っている 子どもたちは何 も知らない立場 欠如モデル 資源モデルに基づく STEM教育へ 脱却・変革 家庭と 学校の かけ橋 になる 新概念導入 持ち込みの阻 害になるかも 既存知拡張 家庭・地域におる教育の資源 (「知識の財産」) • 料理 • 園芸 • 建築 … 筆者作成 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 29
04 言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 30
4.言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆(授業前のまとめ) 1. 自然原理(理数教育)であるSTEMは一般化しやすく、異文化の人々との共通言 語となり、他者理解の一助となるのではないか 2. 外国人生徒の文化的な「知識の財産」をこれまで日本の教室空間において活用し てこなかったのではないか • 従来の日本の文化的な文脈に依存した日本の教育 • 例:豊臣秀吉・茶道 • STEAM教育(解釈を要する人文系の教科)の難しさ • 外国人児童の知識基盤をむしろ活用した授業ができれば • 例:ウクライナ人のクラスメイトについて 3. 家庭(知識の財産・学びの源泉)の重要性の再認識する必要があるのではないか • 言語力的な側面 • ローカルな文化的側面 • 思考力的な側面 4. 欠陥モデルから資源モデルへの転換が迫られているのではないか • 伸びしろ志向 • 例:言語能力の欠如によって親切心や判断力がなくなってしまう!? (うまく表現ができなくなる) ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 31
4.言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆(授業での議論を受けて) 1. これからの教育は「社会化」ではなく「個性化」をめざすべきではないか • 「正しい学力」という価値基準が席巻している世の中において • 評価基準の協同的な構築ができれば • 質的のみならず量的にも分析を行った意義(「正しい学力」へのアンチテーゼ!?) • アッサンブラージュに基づく教育目標と方法の生成は、絶えずに多様な現場をもとに変化し続ける 過程中に存在する 2.STEM/STEAM教育の包摂性(齊藤(2020)より) (1)定義の曖昧さが生む包摂性 「曖昧さにはリテラシー、ジェンダー、文化、民族、あるいは収入をベースにした差別化が起こることを無効にする期待 が込められているという見方もできる」(p.283) (2)Creativeな複数のアプローチと包摂性 「CreativeなSTEM/STEAM教育においては、解決策の構築はその可謬性を認めており、…複数の正解があり得る」 (p.287) (3)多様なステークホルダー参加と包摂性 「学習者は彼らの学校、地域のコミュニティ、県や国をまたいだ伝達可能な合理性の形成に関わる」(p.290) (4)多様な評価の包摂性 「個の学習を見取るという意味だけでなく、学習者のネットワーク、更にはステークホルダーまでをも含めた構成概念の 創発的な発露を見取る」(p.290) ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 32
参考文献 • Samia Khan and Robert VanWynsberghe , Identifying Children‘s Funds of Knowledge as a Bridge to STEM , Trifonas, P. P. and Jagger, P, Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer , 2024 • https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/1724/(最終閲覧:2025年7月26日) • 齊藤智樹『STEM/STEAM 教育の構成概念』,「日本教育工学会論文誌 」,44(3),pp.281-296, 2020 ©XXXXXCorporation All Rights Reserved 33