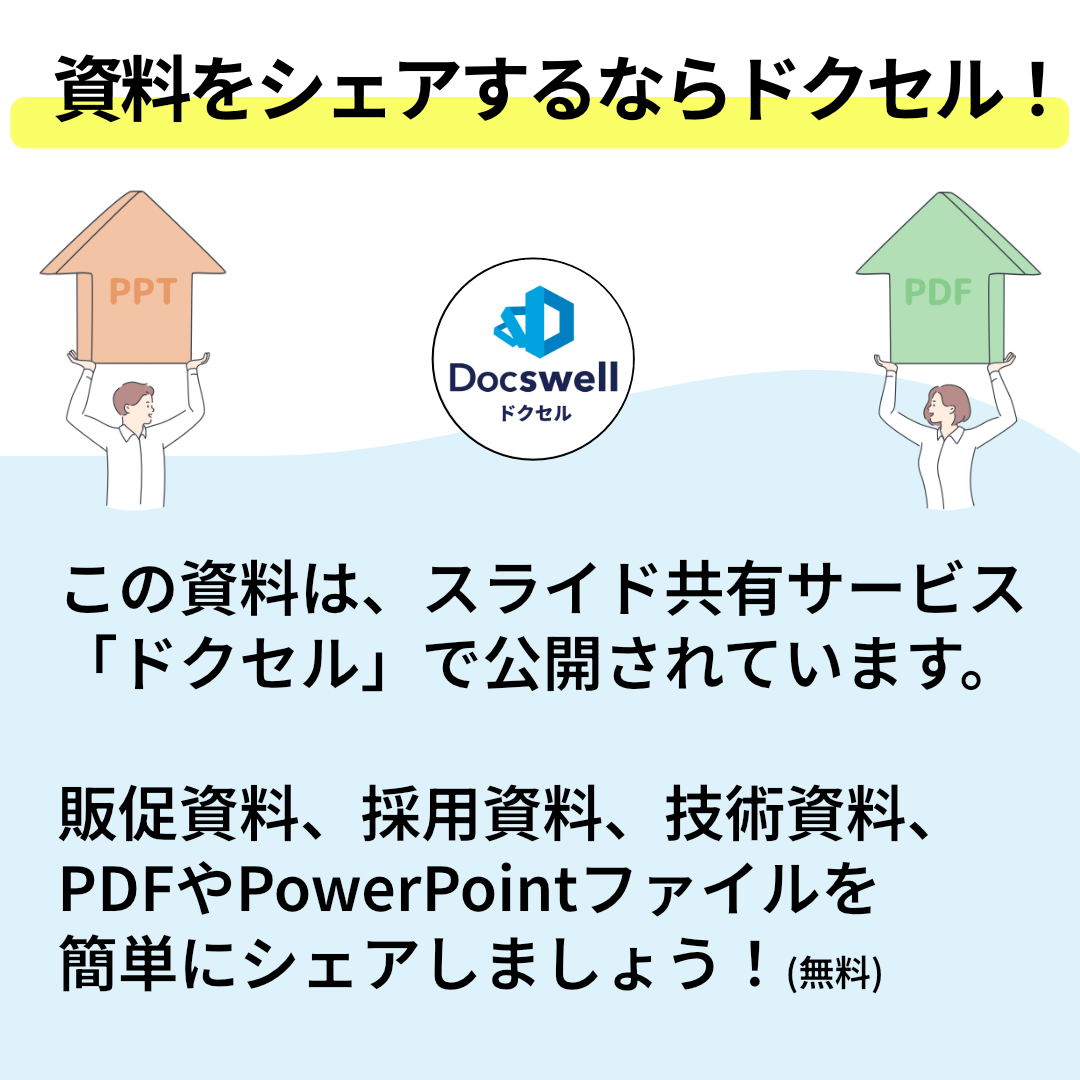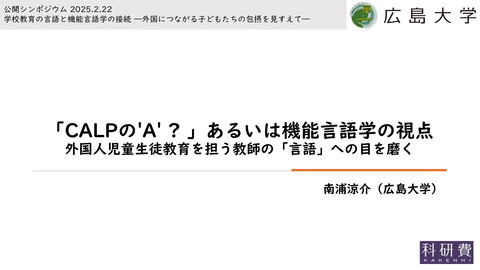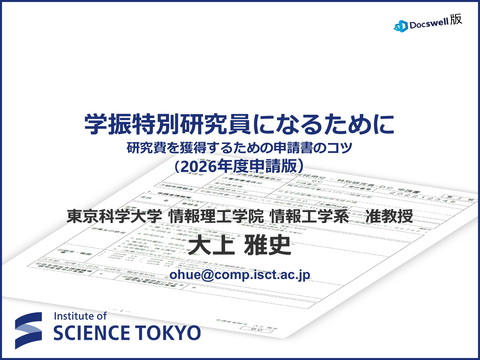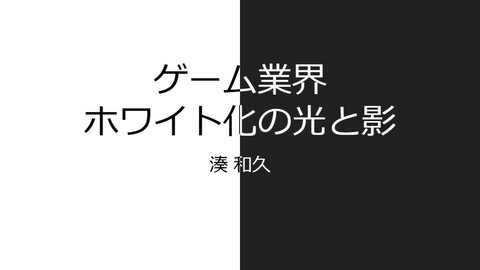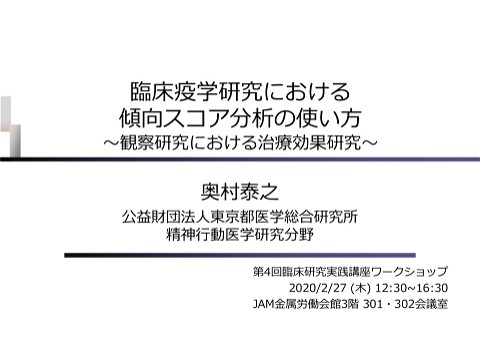2025 日本カリキュラム学会 自由2-6 南浦 発表スライド資料 広域交流型オンライン多文化共生授業の展開とそのカリキュラム的位置―多言語多文化化する学校の小片としての意図と意義―
773 Views
June 26, 25
スライド概要
教育方法学・教科教育学という「一般的な教育」と,外国人児童生徒教育学という「特別な教育」をどちらも行っています。 このどちらもを同時に行う研究室は,日本の中ではほとんどありません。その結果,大学を含む多くの教育の場でこの両者は別々のものになってしまっています。
関連スライド
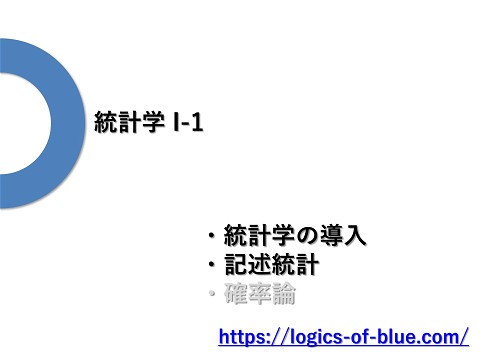
統計学I-1
 Logics of Blue
300K
Logics of Blue
300K
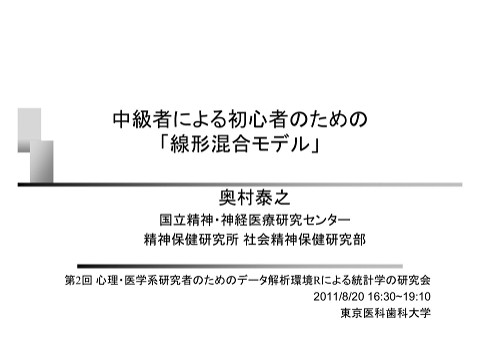
中級者による初心者のための「綿形混合モデル」
 奥村 泰之
222.1K
奥村 泰之
222.1K
各ページのテキスト
日本カリキュラム学会 (2025.6.22) 第36回花園大学大会 自由研究Ⅱ-6 広域交流型オンライン多文化共生授業の 展開とそのカリキュラム的位置 ―多言語多文化化する学校の小片としての意図と意義― 南浦 涼介(広島大学)
1 本発表の背景と目的 本発表の大きな目的 本発表は多文化・多言語の子どもたちを包摂するうえで鍵となる,偶発 性と関係性の中で生成変容する学校カリキュラムの生態学的側面を,広域オ ンライン多文化共生授業の実践と学校の関わりから論じる。 発表構成 1 本発表の背景と目的 2 研究の枠組み カリキュラム研究の系譜と新しい動き カリキュラムの生態学的アプローチの新たな展開 リサーチクエスチョン 3 広域オンライン多文化共生授業 DCCとしての多文化共生授業 授業の展開例 広島市立基町小学校の参加 校長の判断とカリキュラム的位置づけの分析方法 4 基町小学校の参加の学校的視点 学校が持つ背景的前提・理念 学校の良さを伝えることと学校経営 基町小学校の子どもたちの良さと授業参加との関わり 実際の授業参加と授業後の影響 次年度への方針への動き 5 考察 学校理念と道具的小片としての「多文化共生授業」 血流と骨格:状況的カリキュラム活用とその制度化 生態学的発想を取りこんだカリキュラム・マネジメント 6 意義 学校・子ども・教師・地域が「道具」を介して共生の観点を接続しあう 存在しない場をつくる/既存の場からのこぼれおちを止揚する場の創出 論点:「多文化共生」は学校カリキュラムの「骨格」になりえるのか?
1 本発表の背景と目的 背景と課題:外国人児童生徒の包摂とカリキュラムの課題 南浦(2023)言語的文化的多様性の包摂的カリキュラムの分析 • アコモデーション(目的・内容を変えない環境調整) • モディフィケーション(目的・内容・制度を再設計) に分類し日本の現状がアコモデーションに偏重していると指摘 南浦(2024)『外国人児童生徒受入れの手引き』の分析 • ペダゴジーの領域が日本語指導に集中 • 学校・学級全体での取組ではマネジメント領域が中心 必要なこと ①学校全体の カリキュラムとして ②ペダゴジーを ふまえ ③モディフィケー ションの視座から 構築する しかし,実際の日 本の学校における 計画主導型のカリ キュラム・マネジ メント下ではこれ らは困難 南浦涼介(2023)「学校の片隅を支える小さな教員とカリキュラムのつなぎ目─外国につながる子どもの教育の場から」日本カリキュラム学会第34回大会シンポジウム. 南浦涼介(2024)「『外国人児童生徒受入れの手引』の批判的検討─日本語指導から学校カリキュラムへの転換を見すえて」日本カリキュラム学会第35回大会自由研究発表.
2 研究の枠組み カリキュラム研究の系譜と新しい動き 工学的・線形的カリキュラム研究 生態学的・関係的カリキュラム研究 1940s-50s 目標-行動の原理による学習経験の組織化(Tyler) 1970s-80s ① 社会学の立場からカリキュラムによる社会化や階層の再生産 などのメカニズムを明らかにしようとする研究(Jackson, Bernstein, Whitty, Goodsonなど) ② カリキュラムのもつイデオロギー性、政治性、権力性を批判 的に暴露しようとする研究(Apple, Giroux, McLaren など) 1990s「逆向き設計」(Wiggins & McTighe) ③ 現象学を基礎としてカリキュラムを再概念化しようとする研 究(Pinerなど) 松下(2007) 2010sカリキュラム・マネジメント論 基本的にはカリキュラム論の主流的存在 2020年代 人-場-物質-生態など,環境と道 具,非人間などの関係も含めてカリキュラム を捉える動き(Jagger や Trifonas) アップル, M. W., 門倉正美, 宮崎充保, 植村高久(訳)(1986)『教育幻想とカリキュラム』アクト叢書 ジルー, H. , 渡部竜也(訳)(2014)『変革的知識人としての教師─批判的教授法の学びに向けて─』春風社. 松下佳代(2007)「カリキュラム研究の現在」『教育学研究』 74 (4), 567-576. Trifonas, P.P. & Jagger, S.(Eds) (2024). Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer.
2 研究の枠組み カリキュラムの生態学的アプローチの新たな展開 • ブロンフェンブレンナーによるマクロ-エクソ-メゾ-マイクロの 生態学的システム理論を起点 ↓ • 拡張された生態学的観点からカリキュラムを動態的に捉える • 空間的拡張,時間的拡張に加え,歴史性,制度などを含み込む • 人と社会の関係性のみならず,物質やテクノロジーとの関係性も視野に入れる (例 アクターネットワーク理論やアッサンブラージュ理論との融合) リサーチクエスチョン 1. 実際に,広域交流型オンライン授業多文化共生授業はどのような実践を展開したのか 2. 校長が率先して1に継続参加した小学校では,どのような判断でカリキュラムとして位置づけたのか? 3. 2の発想による位置づけは,カリキュラムとしてどのような特質と意義,及び課題があるか? Ouellette, M. A. and Gavin, D. A (2024). Flat (Packed) Affect: Theorizing Pedagogies of Seriality in Unboxing and Assembly, Trifonas, P.P. & Jagger, S.(Eds). Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer. Baruch B. Schwarz,B.B. Tsemach, U., Israeli, M., & Nir, E. (2025). Actor-network theory as a new direction in research on educational dialogues, Instructional Science, 53, 173-201.
3 広域交流型オンライン多文化共生授業 デジタル・シティズンシップ・シティとし ての多文化共生授業 24.6.29 言葉と学級づくり・地域づくり やさしい日本語 〜 や さ し い 日 本 語 の 「 や さ し 言葉と寛容性 さ」とは? 地域の多文化化 https://sip-dcc.hiroshimau.ac.jp/class_practice/class_practice-714/ 24.11.20 「外国の言葉が上手」とはどう 外国語コミュニケーション いうこと?〜みんなは外国語, における態度 話し上手? 聞き上手? 正確性<適切性 https://sip-dcc.hiroshimau.ac.jp/class_practice/20241120/ 25.1.29 みんなの言葉はあなたの言葉? 多言語の言語景観 あ な た の 言 葉 も , み ん な の 言 公共における優先性 葉? https://sip-dcc.hiroshimau.ac.jp/class_practice/class_practice20250129/ 社会言語学(とりわけ国際化との接点としてのリンガフランカや多 言語社会における言語と教育の観点)をもとに立案・作成 類似する発想に大山(2016),小栁(2021)など デジタルシティズンシップシティ 公共的対話のための学校 https://sip-dcc.hiroshima-u.ac.jp/about/
3 広域交流型オンライン多文化共生授業 デジタル・シティズンシップ・シティとしての多文化共生授業 授業の展開例 例 24.11.20「外国の言葉が上手」とはどういうこと? 導入 外国語をどれくらい話せる? 展開1 外国語の話し上手ってどういうこと? 新幹線の外国語放送を見てみよう 展開2 ALTの先生は日本語を話すときにどんな 気持ちかな? 展開3 基町小学校の校内放送を聞いて聞き上手 になろう 展開4 外国の言葉でコミュニケーションをとる ときに何が大切なのかな? デジタルシティズンシップシティ 公共的対話のための学校 https://sip-dcc.hiroshima-u.ac.jp/class_practice/20241120/
3 広域交流型オンライン多文化共生授業 広島市立基町小学校の参加 • 広島市内で最も多言語・多文化化が進む地域の小学校 • 南浦が「多文化共生」の2回目に授業参加を打診(授業内容に関わるた め) • その後,学校長の判断で「多文化共生」の第2回以降に連続参加 • 「社会科」の国際単元も参加 校長の判断とカリキュラム的位置づけの分析方法 1. 3回目の多文化共生授業が終わった2024年度末に1時間半の聞き取り (それまでも南浦が継続的に20年程度学校に関わる) 2. 校長の判断についての聞き取りをNVIVOを用いてコード分析と整理 3. 生態学的なカリキュラムの視点から意義を検討
4 基町小学校の参加の学校的視点 ①学校が持つ背景的前提・理念 本校の学校経営の根底にあるのは、どこの学 校もそうだと思いますが、人権教育です。 その人権教育も、やはりお互いを認め合って 高め合う、自分も他人も大切にする子供を育 てたい、ということが根底にあります。そし て、基町小学校は環境的にいろいろな学びの 場がたくさんある学校だと思っています。 素晴らしいところがたくさんあるのに、あま り世間には知られていない、と私は思ってい ます。実は来年度も学校の経営方針の重点と して、「基町小学校の良さを全開にする」と いうふうに先生たちに伝えているのです。そ の中の一つとして、基町小学校が東広島のオ ンライン学習に参加させていただくのは、と てもチャンスだと思いましたし、この学校だ からこそ国際理解学習をしっかりと積み上げ ていきたいと思っています。 学校の経営方針 今はそういう時代ではないと 思っていて、しかし、何をし たらいいか私自身もよく分か らず手探り状態でした この授業に参加させていただき、 これからの子どもたちに国際感覚 というか人権感覚をしっかりと身 につけさせるためには、どのよう な学習が必要なのかを学ばせてい ただこうと思った 新たな学習の手探り 昔であれば、外国に住む方をお呼びして、そ の国の生活や文化について話していただくよ うな学習が中心だったと思います 前は、おそらくこの学校も残 留孤児関係の方が多くて、中 国の方が多くて、そこには多 分大人の偏見もたくさんあっ たし、差別もあったし、大変 時代の変化 だったと思うのです。 今は(中略)多国籍化して、 LGBTとかそういう面でも脚光を浴びている 就労関係でいらっしゃる方も じゃないですか。だからマイノリティを大事 多かったり、世の中もそう にしていこうというのもたくさん出ていると 思うので、時代も変わったのだと思うのです。 なっているので。 昔は例えば中国の方に餃子をみんなで作って もらう、というようなことがありましたそう いうことを本当はしたいのですが、それがい ろいろな制約で難しかったりします
4 基町小学校の参加の学校的視点 ②学校の良さを伝えることと学校経営 本校の学校経営の根底にあるのは、どこの学 校もそうだと思いますが、人権教育です。 その人権教育も、やはりお互いを認め合って 高め合う、自分も他人も大切にする子供を育 てたい、ということが根底にあります。そし て、基町小学校は環境的にいろいろな学びの 場がたくさんある学校だと思っています。 素晴らしいところがたくさんあるのに、あま り世間には知られていない、と私は思ってい ます。実は来年度も学校の経営方針の重点と して、「基町小学校の良さを全開にする」と いうふうに先生たちに伝えているのです。そ の中の一つとして、基町小学校が東広島のオ ンライン学習に参加させていただくのは、と てもチャンスだと思いましたし、この学校だ からこそ国際理解学習をしっかりと積み上げ ていきたいと思っています。 学校の経営方針 基町小学校から広島市の日本語指導は始まっ ている。絶対に大事なこと。 分かれて少人数指導ができる時間割を来年度 必 は組みたいと思っている。 要 な 教 員 少し頑張って、11月に公開研究会をした の 確 教育委員会の方に認めていただいて、「素晴 保 らしい教育をしている」というふうに認めて くださったので、(日本語指導も)一人も欠 けることなく、これをつけてもらえました 学校の良さと行政的承認
4 基町小学校の参加の学校的視点 ③基町小学校の子どもたちの良さと授業参加との関わり 本校の学校経営の根底にあるのは、どこの学 校もそうだと思いますが、人権教育です。 その人権教育も、やはりお互いを認め合って 高め合う、自分も他人も大切にする子供を育 てたい、ということが根底にあります。そし て、基町小学校は環境的にいろいろな学びの 場がたくさんある学校だと思っています。 素晴らしいところがたくさんあるのに、あま り世間には知られていない、と私は思ってい ます。実は来年度も学校の経営方針の重点と して、「基町小学校の良さを全開にする」と いうふうに先生たちに伝えているのです。そ の中の一つとして、基町小学校が東広島のオ ンライン学習に参加させていただくのは、と てもチャンスだと思いましたし、この学校だ からこそ国際理解学習をしっかりと積み上げ ていきたいと思っています。 学校の経営方針 子どもたちには、特に最初の授業がそうだったのですが、 基町小学校の素晴らしさを子どもたち自身にも分かって もらえる良いチャンスだ 授業と学校方針のマッチング 地域の方などにインタビューをし たりして、そこから基町の良いと ころ、課題を解決するためにどう したらいいか。そして「自分は将 来こんな基町にしたい、そのため にこんなことをする」ということ を全員がまとめたのです その中で、基町の良いところに一 番に挙げたのは、「いろいろな国 の人がいる」ことでした 大人はそれを課題と思っている人 も多分まだいるのです。外国の方 を排除しようとされたり。 でも,子どもたちは入学した時か らそういう環境に育ち、全然言葉 も通じなかった友達とも打ち解け てコミュニケーションが取れるよ うになって6年間過ごし、「これが 自分たちの学校の良いところだ」 と感じてくれている 子どもたちの感じる「良さ」
4 基町小学校の参加の学校的視点 ④実際の授業参加と授業後の影響 みんなの言葉はあなたの言葉? あなたの言葉も,みんなの言 葉?(多言語の言語景観・公共 における優先性)の授業の後 木村先生が改めて指摘されて、校内 には多言語表示があるのです、図書 室前などに。それを子どもたちは普 通の景色として見ていました。 子どもたちの気づき 私たち自身も、あの授業の後 で、あまりにも不親切だった なと思ったことがあって、保 護者配布のプリントです。 学校と保護者対応 の変化 一応、リュウ先生(仮名:母語支 援の教師)がいらっしゃるので中 国語訳はつけて配るのですが、他 の方には何もしていなかった。 ルビ付きの日本語だけで対応して いて、それでいて「学校の方はあ まり協力してくださらない」とか 「伝わらない」とか、みんなで 言っていたのですが、それって違 うじゃないかと。 それで、英文訳もつけようという ことにして、1月末にあった新1 年生説明会の時に、全部中国語と、 実はネパールの方もベトナムの方 も英語は読めると分かったので、 つけて渡したら、説明のプリント 集も全部英語のを見ながら「分か る、分かる」と言ってくださった ので、これが抜けていたなと改め て思いました。
4 基町小学校の参加の学校的視点 ⑤次年度への方針への動き 今年は教育課程の中にどこか入れ ないといけないじゃないですか。 総合的な学習の3年生以上には、 多文化共生のオンライン事業を入 れているのです。 正規の教育課程への 位置づけ
5 考察 ① 学校理念と道具的小片としての「多文化共生授業」 多文化・多言語的地域の学校としての「国際理解」「人権」「共生」 は学校の目標像となっている 他方で,社会や地域の変化の中でかつてのような「中国帰国者の家 庭」の地域的資本を活かす国際理解教育は難しくなっている 学校の経営方針 新たな学校としての「国際理解」の視点を得よう とするときに広域オンライン多文化共生の授業が 「ヒント」となるという期待 時代の変化 新たな学習の手探り 子どもたち自身が自らの場や価値を再発見する場 としての確信 学校理念の実現のために必要な小片に
5 考察 ② 血流と骨格:状況的カリキュラム活用とその制度化 子どもたちが基町小ならではの「力」の獲得や再発見につながる また,保護者対応などの学校の取り組みのよい変化にもつながる 学校方針としての「良さの全開」の1つを形づくることで,学校の教 育課程として次年度(25年度)は正規に位置づける 学校の経営方針 授業と学校方針の マッチング 子どもたちの感じ る「良さ」 「子どもの成長方向-学校方針-学校の変 化」という学校の循環に位置づく(血流) 正規の教育課程(骨格)へ 子どもたちの 気づき 血流をめぐる栄養がそれを骨格化する 学校と保護者対応 の変化 正規の教育課程への 位置づけ
5 考察 ③ 生態学的発想を取りこんだカリキュラム・マネジメント 授業と学校方針の マッチング 必要な教員 の確保 子どもたちの感じ る「良さ」 学校の経営方針 学校と保護者対応 の変化 学校の良さと 行政的承認 子どもたちの 気づき 時代の変化 オンライン多文化 共生授業 新たな学習の手探り 正規の教育課程への 位置づけ 学校の方針(ビジョン)を中核 に,子どもの成長,保護者への 影響,良さの対外的承認と評価, 新たな学習の必要性 といった循環径路の中に オンライン多文化共生授業を 小片として乗せる
6 意義 学校・子ども・教師・地域が「道具」を介して共生の観点を接続しあう 多文化・多言語共生を微細に異なるニーズで 求めあう空間の内外が オンラインの道具を介して接続されることで 「教育的価値」を掘り下げる 多文化・多言 語化している 小学校 取り組みを知り 価値を学ぶ 取り組みを伝え 価値を再発見する 歴史的に 多文化・多言 語化してきた 小学校 共生をめぐる空間・時間・子ども・教師・学校・使用言語 と態度をオンラインによってネットワーク化され,相互の 深い学習をつくる(アクターネットワーク理論との関係性)
6 意義 存在しない場をつくる/既存の場からのこぼれおちを止揚する場の創出 工学的・線形的カリキュラム接近 生態学的・関係的カリキュラム接近 「多文化共生」というテーマの 位置づけにくさ 即興と文脈の中でテーマを位置づける 文脈の中で意味づけられる 「血流」の「骨格化」が生まれる ①学校全体の カリキュラムとして ②ペダゴジーを ふまえ ③モディフィケー ションの視座から 構築する
課題(論点) 「多文化共生」は学校カリキュラムの「骨格」になりえるのか? そもそもなぜ「骨格」とならないのか? 教育課程の時数に 位置づけにくい 広域交流型オンライン授業も「教科」(社会科)は参加校が多い 位置づけられたとしても 他方で「多文化共生」は参加校が少ない実態。 正規の教育課程の教科との関連づけは示しているが,少ない。 「総合的な学習の時間」 教科 領域 定められた 内容 が多い 重要だけど定めら れていない内容 学校の中の「目標」や「内容」をめぐるポリティクスの存在 「多言語・多文化の包摂」が「配慮・支援」を超えるためには 「教育課程のモディフィケーション」が本来は必要。 Khan, S., Vanwynsberghe, R. (2025). Identifying Children’s Funds of Knowledge as a Bridge to STEM. In Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Trifonas, P.P. & Jagger, S. , 943–66. New York: Springer.
主な参考文献 アップル, M. W., 門倉正美, 宮崎充保, 植村高久(訳)(1986)『教育幻想とカリキュラム』アクト叢書 大山万容(2016)『言語への目覚め活動─複言語主義に基づく教授法』くろしお出版. 小栁亜季(2022)「多言語共生に向けた言語教育の構想─英国におけるE. ホーキンズの言語教育の理論と実践」『教育学研 究』89(2), 65-77. ジルー, H. , 渡部竜也(訳)(2014)『変革的知識人としての教師─批判的教授法の学びに向けて─』春風社. ブロンフェンブレンナー, U., 磯貝芳郎, 福富護(訳)(1996)『人間発達の生態学(エコロジー)─発達心理学の挑戦』川嶋書 店 松下佳代(2007)「カリキュラム研究の現在」『教育学研究』 74 (4), 567-576. 南浦涼介(2023)「学校の片隅を支える小さな教員とカリキュラムのつなぎ目─外国につながる子どもの教育の場から」日本 カリキュラム学会第34回大会シンポジウム. 南浦涼介(2024)「『外国人児童生徒受入れの手引』の批判的検討─日本語指導から学校カリキュラムへの転換を見すえて」 日本カリキュラム学会第35回大会自由研究発表. ラトゥール, B. , 伊藤嘉高(訳)(2019)『社会的なものを組み直す―アクターネットワーク理論入門』法政大学出版局 Baruch B. Schwarz,B.B. Tsemach, U., Israeli, M., & Nir, E. (2025). Actor-network theory as a new direction in research on educational dialogues, Instructional Science, 53, 173-201. Carlos, A-U., and Infante, M. (2020). Assemblage Theory and Its Potentialities for Dis/Ability Research in the Global South. Scandinavian Journal of Disability Research: SJDR 22 (1): 340–50. Khan, S., Vanwynsberghe, R. (2025). Identifying Children’s Funds of Knowledge as a Bridge to STEM. In Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Trifonas, P.P. & Jagger, S. , 943–66. New York: Springer. Trifonas, P.P. & Jagger, S.(Eds) (2024). Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer. Ouellette, M. A. and Gavin, D. A (2024). Flat (Packed) Affect: Theorizing Pedagogies of Seriality in Unboxing and Assembly, Trifonas, P.P. & Jagger, S.(Eds). Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer. 本研究は,戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」採択事業 「デジタル・シティズンシップ・シティ: 公共的対話のための学校」の事業の一環を担ったものです https://sip-dcc.hiroshima-u.ac.jp/