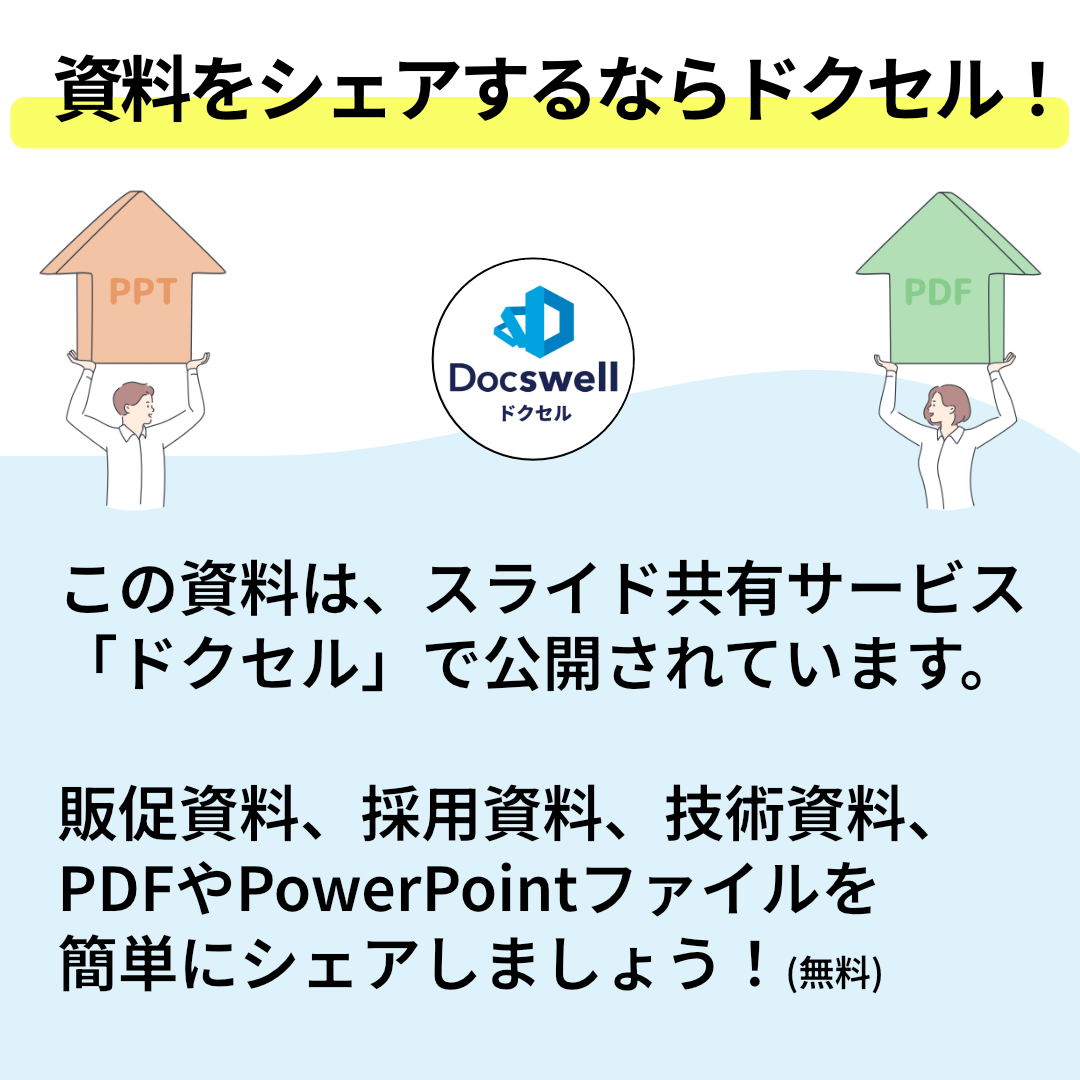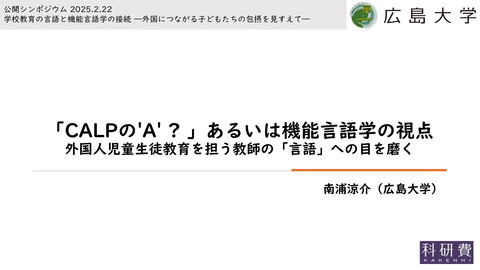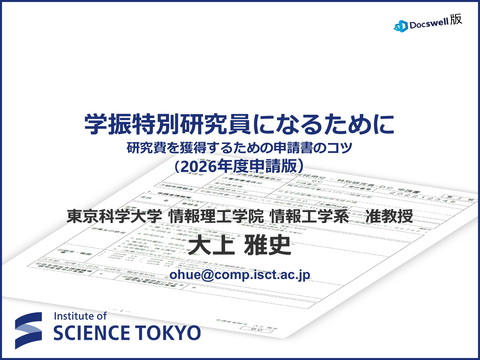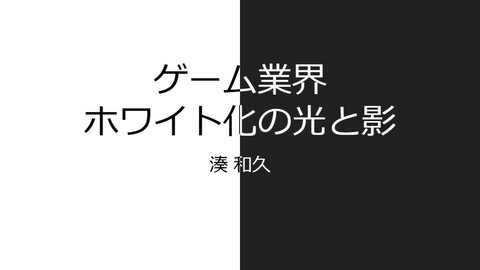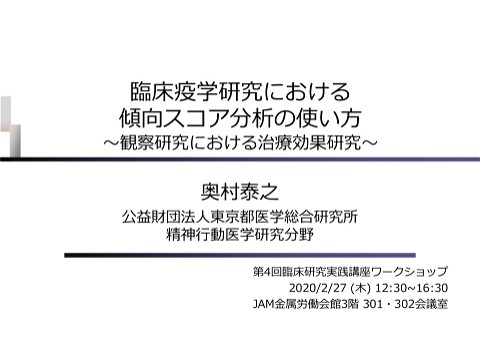関連スライド
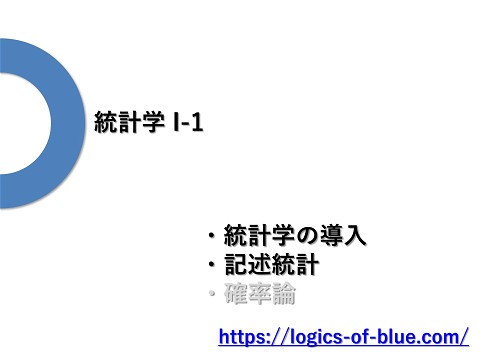
統計学I-1
 Logics of Blue
301.8K
Logics of Blue
301.8K
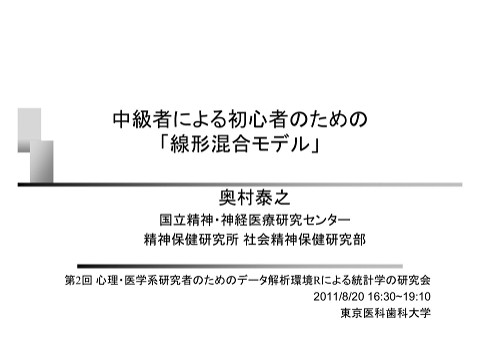
中級者による初心者のための「綿形混合モデル」
 奥村 泰之
223.8K
奥村 泰之
223.8K
各ページのテキスト
【お願い】このスライドは,広島大学 大学院人間社会科学研究科 教育科学専攻 教師教育デザイン学プログラムで開講している「外国人児童・生徒の教育課程デザイン論」(南浦涼介担当)の授業で行った受講大 学院生たちの発表資料です。 Trifonas and Jagger 2024 Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice, Springer のハンドブックのいくつかの章を選んで発表したものです。 教育的価値・資料的価値としてウェブでの掲載を行っていますが,いわゆる「論文」ではありませんので,論文等への引用や掲載は固くお断りします。 質問については広島大学南浦研究室(https://minamiura-lab.com/)までおねがいいたします。 第8.9回 外国人児童・生徒の教育課程デザイン論 Child's Play: Play as an Informal, Relational Curriculum of Childhood Noah Kenneally 発表日:2025年7月4日 発表者:ミ
発表構成 1. 著者紹介 2. Trifonas,P.P.and Jagger,P.(2024)Handbook of Curriculum Theory, Research,and Practice,Springer.について 3. 章の全体構成 4. 章の要約 5. 言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆 1
1. 著者紹介 N. ケネリー マックイーン大学:早期児童教育カリキュラム研究 助教授 【研究関心】 早期児童期のコミュニティにおける社会と社会正義の動態 に焦点を当てている 【研究テーマ】 早期児童期における子どもの権利の理解と実践 子どもが自身の社会世界について持つ視点 子どもの政治と早期学習・保育の政治学 創造・生産に関する課題 コミック研究 および創造的な研究手法と探求・分析実践 等 引用 https://noahkenneallyresearch.wordpress.com/ 2
2.Trifonas,P.P.and Jagger,P.(2024)Handbook of Curriculum Theory,Research,and Practice,Springer. について 【内容】 • 50カ国以上の理論家,研究者,実践者の研究成 果を特集 • 教育実践に与える影響を,地域的・国際的な視 点から議論 • カリキュラム分野で知られる議論の焦点や対立 点を捉える 引用 https://link.springer.com/referencework/10.10 07/978-3-031-21155-3 3
3. 章の全体構成 ■ 序論 ■ 社会的学習と社会化 ■ 関係性に基づくカリキュラムの理解 ■ 社会化:伝統的なモデルと子ども中心の再解釈 ■ プルデュー:ハビトゥスと実践 ■ 子どもの遊びの視点 ■ 遊びとしての子供の社会的実践:カリキュラム,社会化,関係性,およびハビトゥス 4
4. 要約 【序論】 〇本章の内容 ■ 児童社会学と関係性に基づく早期教育カリキュラム研究の枠組みに基づいて考察を進め る ■ 学校や教育の文脈を超えたカリキュラムに焦点を当て,非公式な学習と身体化された対 話に関する考え方を踏襲する ■ 社会学的には,ブルデューの「ハビトゥス」と「社会的実践」の概念と対峙しつつ,そ れらを再考する 社会化=社会的な実践に参加し,身体を通じて体験する 参加型で身体的な社会学習プロセスのこと →この文脈において,遊び=子供の「社会的実践」 遊び=子供時代における不可欠な要素 であり,彼らが特定の少数派の社会文 脈において子どもとして認識されるた めの定義的な活動 〇本章の着眼点 子どもが子どもとして成長し,社会の一員として形成される過程で,遊びが子どもの社会 的学習と所属感の形成を支援する側面に着目している 5
4. 要約 【社会的学習と社会化】 〇社会化のプロセス →大人によって子どもに対して行われる,子どもを社会生活に組み込むための文明化プロ ジェクトの一環 子どもの社会学では,避けられていた 理由:この枠組みで研究を行う研究者は,社会化に関して子どもを受動的な文 化的学習の需要者として位置付けるため,これと矛盾する子どもの積極的な社 会的行動者としてのイメージと根本的に対立するため ジェームズほかが子どものプロセスにおける積極的な役割を認める,より動的で参加型の社会 化として再構築する試みを行う ① 正式な教育の文脈外で起こる関係的なカリキュラム理解を通じて,社会的学習の概念を探 求 ② 伝統的な社会化モデルと新しいモデルを簡潔にレビューし,ジェームズ(2013)の子ども 中心の社会化モデルを例としてより深く考察する 6
4. 要約 【関係性に基づくカリキュラムの理解】 〇本章におけるカリキュラム 「学習者が社会的実践に従事する中で非公式に習得される学習内容」 →カリキュラムを物体や製品としてではなく,関係そのものの素材として捉えている 〇ロゴフ他(2016)による非公式な学習の主要な特徴 ■ 相互作用的(社会的相互作用と人間関係の中で発生) ■ 非指示的(明示的な指導の意図を持たない活動を通じて達成される) ■ 意味ある活動に組み込まれている(日常生活の領域とルーティン,コミュニティ内で発生) ■ 内発的動機付けと学習者の興味に基づく(一般的に外部から強制されず,学習者にとって関連性のない方法で課さ れることはない) ■ 支援が利用可能(学習者は社会的相互作用を通じて支援を得たり,活動自体の構造によって支援を受けたりするこ とができる) ■ 活動が外部的に評価されない(評価は活動自体に貢献するために行われ,活動とは無関係な目的のためではない) ■ 改善と革新(学習者は参加を通じてスキルを向上させ,既存のスキルや知識を磨くだけでなく,新しいアイデアを 生み出す) 7
4. 要約 〇関係的な教育アプローチの核心的要素→対話 〇エリオットの対話の概念 →会話や議論を指すだけでなく,言葉を超えた相互作用や交換を含む広範な概念 エリオットの 考え 対話は複合的であること 遊びは対話であること 内容 対話が言葉や文字に限定されないこ とを強調 遊びを相互的な対話と捉えると,特定の遊び のセッションに参加する多様な参加者が,会 話を豊かにし,形づくり,影響を与え,参加 者と要素の組み合わせに応じて現れる筋道に 沿って方向付ける 具体例 画像,グラフィックシンボル,映画, 砂場でのシャベルやバケツ,砂といった特定 ビデオ等の視覚的な表現形態やボ の素材との遊び,「学校」「家」「スーパー ディランゲージ,ダンス,その他の ヒーロー」といった概念を交換し役割やアイ 身体的な実践等の非言語的な表現形 デアを交わす想像遊び 態を含む 8
4. 要約 〇関係性に基づくアプローチを採用→「フライト・カリキュラム・フレームワーク」 フライト・カリキュラム・フレームワーク →学習は関係性に基づいており,関係性を通じて現れるという考えを提唱 教育者は,子どもたち,その家族,ほかの早期教育専 門家との間で強固で思いやりのある関係を育むように 奨励され,柔軟で応答性があり,養育的な「活気に満 ちた場所」としての早期教育コミュニティを創造する ことが求められている。 関係性構築の強調=子どもをコミュニティ の積極的な貢献者として認識 フライト→子供が資源豊富で能力のある存在 であるという理解を強調 子どもの遊びと積極的な参加を意味の構築に おける主要な方法論として位置づける一連の 目標に基づいている ☆この節での言いたいこと ① 学習と遊びを対話として理解することは,それらを能動的で社会的なダイナミクスと して捉えることを可能にする(ここでいう「社会的」とは,他者,環境,自己との複 合的,他方公的,他主観的な対話を包含する広義の意味) ② 関係性が学習の基盤であり,遊びが意味形成の重要なツールであるという理解に基づ 9 き,カリキュラム,社会化,遊びの概念を相互に結びつけることができる
4. 要約 【社会化:伝統的なモデルと子ども中心の再解釈】 モデル名 提唱者 内容 傾向 批判 機能主義的モ デル パーソンズ (1951) 社会化は出生から思春期の完了まで 続くプロセスとして理解され,大人 が子どもを,働き,目的を持ち,社 会に貢献する人間に形作ることで, 社会の安定を維持するプロセス 社会化を構造的な理解に 重点を置き,社会構造や 機関の支配的な力が人々 の生活を決定する役割を 強調している 構造化主体性のいずれかに重点を置く点は,解釈 社会学の分野が構造と主体性の定立的な理解から 離れ,両者が社会生活と子どもの発達に影響を与 える方法を説明しようとするより総合的な理論化 へと移行する中で,不十分で微妙な点があると批 判されてきた 行動主義モデ ル スキナー (1974) オペラント条件付けの概念を中心に, 子どもは経験と正の強化または負荷 の強化を通じて,適切な社会的機械 となるようにプログラムされる 社会相互作用 論的アプロー チ テンジン (1977, 2017) 子どもはより能動的な参加者として 捉えられ,社会的相互作用と言語習 得を通じて行動規範が内面化される クシンス キーら (2003)等 子どもと親が互いに社会化し合い, 特定の役割に適合するように互いを 形作る ブルデュー の理論 構造と主体性の概念の関係性を社会 生活の領域として強調 ジェームズ (2013) 子どもの社会化における積極的な役 割を前面に押し出すことで,社会化 概念の再構築を試みる 構造と主体英 の二分法を克 服する総合的 なアプローチ 主体性が強調され,社会 化のプロセスは個人間の 相互作用の中に位置付け られている 10
4. 要約 〇ジェームズの理論 …子供を自身の社会化プロセスの中核に据え,特定の実践や日常的な活動への関与を通じ て,彼らの社会生活を形成するプロセスに焦点を当てている …スマート(2007)の「個人的な生活の社会学」及び自身の研究を基に,社会化のプロセス を個人化 異なる子どもがそれらを異なるように経験することを強調し,個々の物語を語ることで, その違いをイギリスの社会における構造的・歴史的・政治的動向と結びつけて文脈化する 〇ジェームズにより行われた,子供の社会化体験の再理論化と分析における,基盤となる仮定 ① 子どもは大人と同様に,時折自身の生活を振り返る個人的な生活を持っている ② 子どもの生活は他者との相互作用の中で営まれ,他者の決定によって形作られるのと同じように,自 身の決定や選択によっても形作られる ③ 子どもの生活は身体的であり感情的である ④ 子どもの生活は,それらとの多面的な相互作用を通じて,構造や制度によって影響を受ける ⑤ 子どもの生活は伝記的であり,変化する歴史的,物質的,社会的環境とつながっている 子どもの経験を重視し,子どもが社会から分離された存在ではなく,物質的・概念 的に社会に深くうめこまれている多様な方法を示している 11
4. 要約 【ブルデュー:ハビトゥスと実践】 〇ブルデューの社会的生活の理解 社会的生活は合理的な思考ではなく,感じられる感覚に基づいた,無意識的,ほぼ無意識的, または忘れ去られたパターンが体に刻み込まれ,行動を通じて現れるもの 〇ハビトゥス 経験を通じて形成され,文脈,社会的地位,歴史に特有の,社会世界に対する内面化された 感覚のこと =身体化されたハビトゥスの中から,行動者は,適合し,意味を成し,または適切に感じら れる一定の戦略セットにアクセスできる 〇ブルデューによる社会実践のとらえ方 社会における実践をハビトゥスの反映であり強化するものと解釈し,芸術や職人技の一種と みなしている=ゲーム感覚 自信が属する分野でプレイする「ゲーム」の熟達に基づいて即興 的に行動し,選択し,戦略を立てて変化を生み出せる。 ※ただし,ハビトゥスの範囲内で 欠点 ハビトゥスがどのように形成さ れ統合されるかを考察していな い点 12
4. 要約 【子どもの遊びの視点】 目的①:子どもの参加者が生成したデータの一部を強調し,彼らの遊びに関する考えを考 察し,遊びを子どもの社会的な実践として確立すること とり上げる研究:「何が子どもを子どもたらしめるのか」という問いを探求したもの ① 章のアイデアの基盤となる研究プロジェクト 〇対象の子ども達:37名(うち28名が4~9歳・9人は10~11歳) :参加家族の形態は様々・子どもの性別も多様 社会学的研究において, 早期の幼少期と10歳未満 の子どもの視点が現代の 文献等で十分に代表的に とり上げられていないた め重要 参加家族の文化的背景も多様 A) 参加家族の親の大半は,家庭外で働いている B) 多くの親は自分の住宅を所持していた C) 大半は都市部またはその近郊に住んでいた。残りの参加 家族は,労働者階級の人口統計学的特徴に該当した 〇研究プロジェクトの進め方 芸術に基づく身体的な聴取という方法論的アプローチにより,子どもの頃,大人になること,親 になること,人間であることに関するアイデアを探求する物語的な会話に応答し,平行して生成 13 された複合的なアーティファクトが得られた
4. 要約 ② 子どもの遊びに関する研究の主な発見 〇研究プロジェクトにより得られた回答の分析 子どもと親の両方が指摘した主要なアイデアの1つ:遊びの重要性 例:生活の中の遊びの例という促しに答えて描いたもの ① ③ ② ④ 左図:Examples of play cartoons(p.40より) ① QUEEN LILY(6歳) 友人と一緒に田んぼを走り回って鬼ごっこをして いる様子 ② RA COON(8歳) 自宅の外で別の子どもと雪遊びをしている自分 ③ WILL(11歳) 子どもが成長するにつれた遊びがどのように変化 し,社会的意味や地位,相互作用の舞台となる可 能性があることを描いた漫画 ④ LARA(6歳) 自分が最も好きなことである,アート用品で遊ぶ 自分の様子 14
4. 要約 子どもによる遊びの捉え方 ■ 子ども達が大人と異なる点として重要なダイナミクス ■ いくつかの子どもは大人が遊びに参加する可能性を認めたものの,それは大人 にとっての余暇活動だと認識していた グリースハーバーとマッカーダル(2010)による遊びの主要な概念 ■ 楽しい・自然な・正常な・発達過程・子どもの無邪気さを反映する・すべての 子どもにとって普遍的な権利・活発で,身体的で,大声で,騒がしいもの 遊びが無邪気で,非合理で,軽率で,責任感のない,重要でないものとして 枠組み化されている =子どもの社会における従属的な地位を強化されている(能力の否定) 成人主体の 概念と対立 本来の子どもの姿 →周囲の世界に大きな影響を与える社会適応力のある主体であり,環境,文脈,人間関係によって形 作られつつも,それらを積極的に形作っている =ハビトゥスの社交力との明確な関連性であり,定義的な社会的慣習としての遊びが,プレイヤー達 に子ども時代の社旗的立場の境界線を親しみやすいものにしていく仕組みが徐々に見えてくる 15
4. 要約 ③ 社会化と社会学習を能動的かつ参加型の社会化プロセスとして理解する新興の 知見と対話させることで,子どもの遊びが,子どもが「子どもとして存在し, 子どもとなる」方法を学び,したがって子どもの社会的地位を確立する非公式 で非合理的な身体化されたカリキュラムであるということ 左図:Reading is play(p.42より) MRS CUPCAKE(9歳) 遊びの捉え方: 静かで表面上は受動的なもの 様子: 手は本を持ち,ページをめくっている 目は文字と画像を探索している 体は,感覚と姿勢の変化を通じて物語に 反応している →身体的な遊びの形態において,関係性 の中にある キャラクター,作者,本,制作に関 わった人,部屋,読むことを教えた人 16
4. 要約 〇これらの子ども達の様子からわかること 遊びは身体的な経験であるということ(活発か静的かを問わない) 遊びは社会的行動であるということ(他の子との関わり等の描写からわかる) →遊びは本質的に関係的なものであるということ 遊びを「社会的な学習や社会化行動」として,時間軸に沿って前進し,熟達や成人へ と向かう線形的ダイナミクスから,影響,注意,エネルギーが流れ,渦巻き,波紋を 広げ,拡散するネットワーク的ダイナミクスへと概念を転換する 17
4. 要約 〇発達心理学における遊びの捉え方 →遊びを子どもの成長と発達における重要な要素として評価してきた 人名 遊びの捉え方 備考 ピアジェ 子どもが同化と順応のプロセスを通じて新しい情報と思考/ 存在の方法を古いものに累積的に統合し,年齢とともにます ます複雑な思考が可能になるにつれて適応していく主要な場 ヴィゴツキー 遊びは子どもが生産的な社会的相互作用に必要な重要なスキ 子どもが社会的遊びを通 ルを学ぶ主要な空間 じて定期的に「発達の最 近接領域」に入る コルサロ 子どもは社会的構造,規範,基準を自身の経験と参照組みの なかで意味あるものとして再構成し適応させるプロセスにお いて,遊びが主要な方法として機能する(「解釈的再生産」 理論) 子どもは観察し参加する 情報,行動,役割を経験 の制約下で解釈し,社会 生活に参加する=ハビ トゥスの統合と即興的な 適応に類似 18
4. 要約 目的②:子ども達が遊びという身体的な社会的実践を通じて自分自身を子どもとして形成 し,子ども達が何をするか,どのように行動するか,そして世界の中でどのように空間を 占めるかを,身体と想像力に統合していく 〇子ども達は遊びが身体化された実践であり,ハビトゥスの構造を体現し,統合したり, 身体に刻み込んだりしながら,同時にそれらを現実に示そうとしている漫画 左図:RUBY running with her mom(p.44より) RUBY 遊びの捉え方:母親と関わり,繋がる手段 母親と遊びのレースをしている様子 RUBYは母親よりも早く走ることができる(価値が あると認識している) =子どもが大人よりも常に能力が低いとされる通 常の社会秩序に抵抗する空間を提供している 大人と子供の間の力関係を身体的な遊びの相互 作用を通じてシフトさせる行為 =子どもの従属を大人への従属として社会的に 強化されることに抗うための,非合理で即興的 な戦略 19
4. 要約 上図:GORILLA-ZILLA playing with a friend at recess(p.44より) GORILLA-ZILLA 遊びの捉え方:子ども達が互いと環境と繋がる手段/活発な活動 対立する概念: 学校での鬼ごっこ=規制されている 学校での「真のカリキュラム」に基づく学習に従事するためのリフレッシュの時間とし て遊びがある 20
4. 要約 左図:THE CAT’s drawing of girls playing(p.44 より) THE CAT 子どもの身体が遊びを通じて示す対話的,相互作用的, 関係的な側面および子どもの身体が示すこそもの年齢 に関する常識的な見方を強化する傾向的な活動が示さ れている 描かれているもの:子ども達がタイヤのブランコで一 緒に遊ぶ物語 第2のパネル:1つの身体に3つの頭で子どもが描か れている 遊びに参与することが関係性に参与することで あることを示唆 =子ども達の身体が協調的で狂暴的な活動に没 頭する,遊びの強力な「集まる」側面として理 解できる 21
4. 要約 【遊びとしての子どもの社会的実践:カリキュラム,社会化,関係性,およびハビトゥス】 〇非公式な学習の基準と子どもの文脈における遊びとしての社会的実践の関係性 ■ 遊びは相互作用的である その相互作用が他者,環境,または自己を対象とするかに関わらない ■ 遊びは内在的な動機付けに基づいている 学習や発達のために行われることもあるが,それ自体を目的として行われることもある 〇スキルと知識の構築は,遊びへの有機的な関与を通じて起こり,しばしば新たな発見につながる =遊びは少数派の世界文脈において子どもの社会的地位を示す行動や活動を身に付けるのを助ける 非公式な学習であると理解できる 〇子どもは遊びに積極的に参加し,遊びを子どもの社会実践として理解すると,その規範や基準に よって認識される子どもの役割に積極的に定着していく =それらに従う,抵抗する,またはそれらの中で遊びながら即興的に表現し体現する方法を模索す るプロセス 22
4. 要約 〇遊びのプロセス ① 子どもは,遊びを通じて「子どもの遊びの感覚」を統合し,社会的な子どもの立場を内 面化し,コミュニティ内の他者から子どもとして認識されるようになる ② 遊びを子どもの社会実践として行うことで,ハビトゥスを強化し再構築し,社会におい て子どもとして認識される特有の方法を強調する (ハビトゥスの視点から見る:子ども達は遊びを通じた実践的な行動を通じて子どもの社会 的立場に属するようになる) 〇子どもが遊ぶときに直面する内容 ■ 大人社会のルールに従うこと等→これらの内容を対処するために,子どもは思考する 〇本研究の成果 遊びを非公式で関係的な学習の形態,子ども達が子どもの社会的地位を身に着けるための非 制度的,身体的,実践的なカリキュラムとして理解する強い根拠を提供している 〇まとめ 遊びは社会的実践として,参加的で積極的な社会化であり,子どもが自分自身を子どもとし て形成する手段である 23
5. 言語的文化的に多様な子どもの包摂 への示唆 ■ 子どもの行う遊びは非公式なカリキュラムであるという観点から ☆子どもは「遊び」という非公式な場において学んでいるということ ☆つまり,子どもはただ遊んでいるのではなく,大人の知らない環境で学んでいるということ ■ 本来の子どもの姿という観点から ☆周囲の世界に大きな影響を与える社会適応力のある主体 ☆環境,文脈,人間関係によって形作られつつも,それらを積極的に形作っている 言語的文化的に多様な子どもを「話せるように手助けをしてあげないといけない,文化面への手 助けをしてあげないといけない存在」と捉えるのではなく,「教師が見えない場面でも学んでい ることがある存在」と捉えていく必要性があるという示唆を得られる。 24
5. 言語的文化的に多様な子どもの包摂 への示唆 ☆教師が言語的文化的に多様な子どもを包摂するためにできること☆ ■ できないと決めつけない →言語的文化的に多様な子どもは「遊び」という場で学んでいることが沢山ある。そ れを認識し,接していくことが大切 →出身国等に関してはその子ども達のほうが断然詳しいはず。その子ども達が詳しい と思われることをとり上げて,教室内でできた!と思えることを沢山経験させてあげ ることも必要。 ■ 教師自身も遊びに参加し,どのような遊びを子どもがしているかを観察する →遊びの場を観察することで,子ども達が何を学び,何が好きなのかが理解できるか もしれない。また,共に遊ぶことで信頼関係の構築も可能になる。 25
参考文献 ■ Noah Kenneally,“Child‘s Play: Play as an Informal, Relational Curriculum of Childhood” Handbook of Curriculum Theory,Research,and Practice,Springer,Trifonas,P.P.and Jagger,P,Reference work,2024, pp.29-50 ■ 「Noah Kenneally, PhD. | the professional website of Dr. Noah Kenneally, childhood researcher」https://noahkenneallyresearch.wordpress.com/ (2025年7月3日閲覧) ■ 「Handbook of Curriculum Theory, Research, and Practice | SpringerLink」https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3031-21155-3 (2025年7月3日閲覧) 26