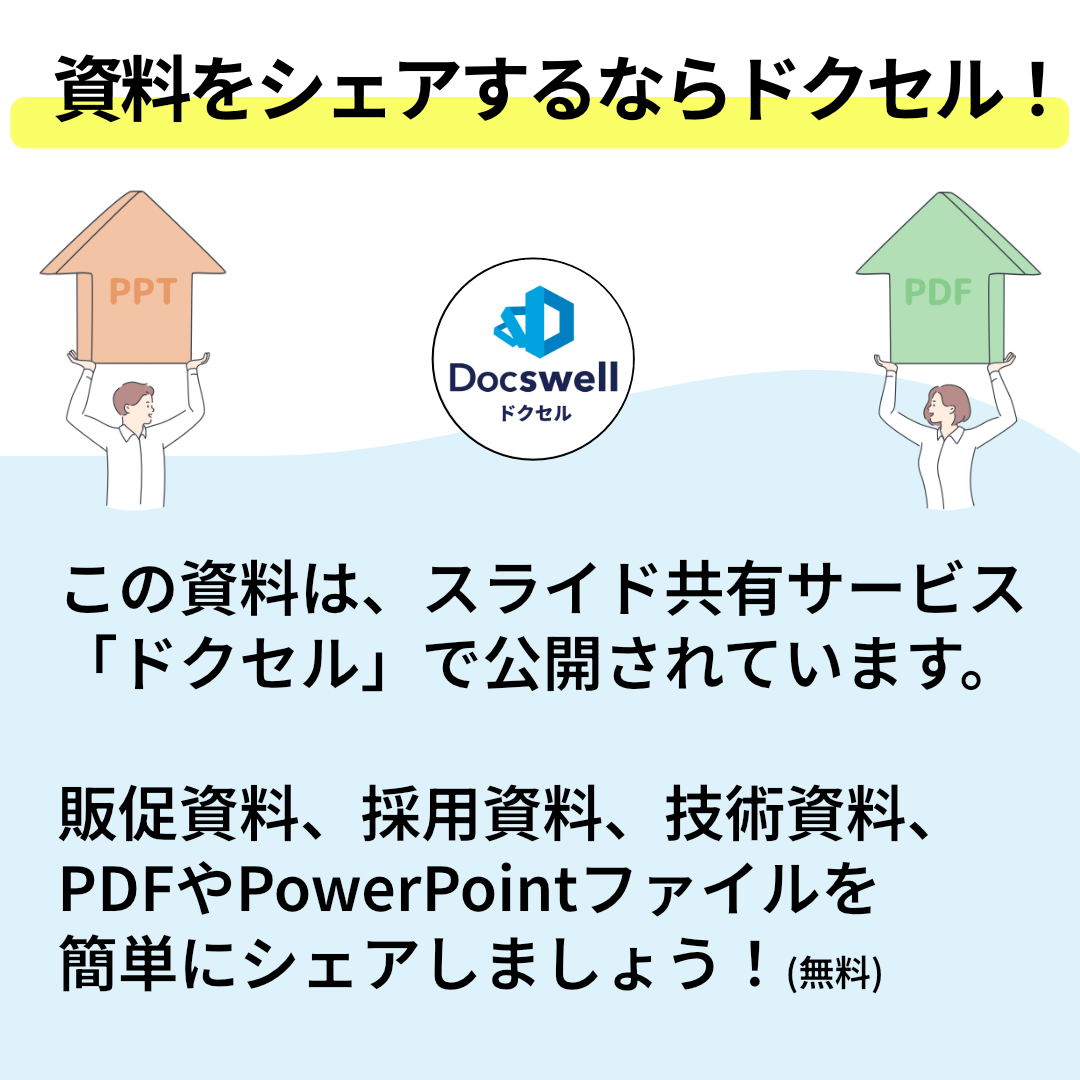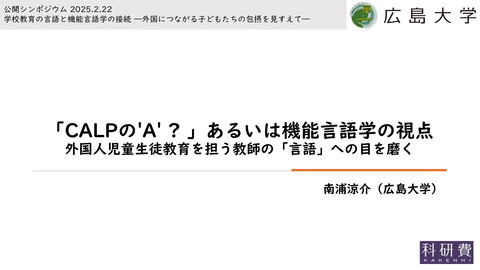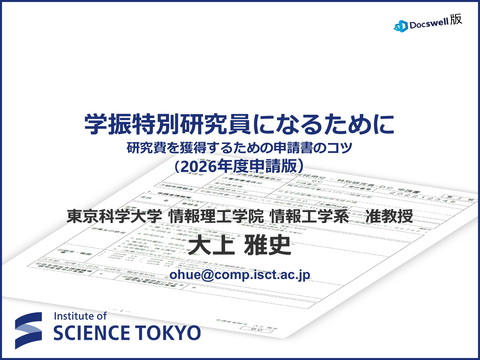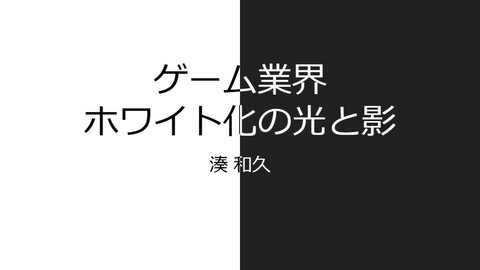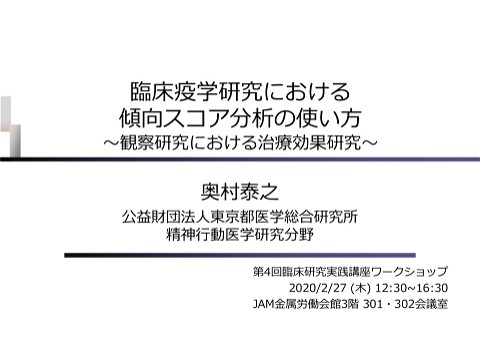外国人児童・生徒の教育課程デザイン論250725 発表資料 Kirchgasler, C. (2024)
405 Views
September 06, 25
スライド概要
教育方法学・教科教育学という「一般的な教育」と,外国人児童生徒教育学という「特別な教育」をどちらも行っています。 このどちらもを同時に行う研究室は,日本の中ではほとんどありません。その結果,大学を含む多くの教育の場でこの両者は別々のものになってしまっています。
関連スライド
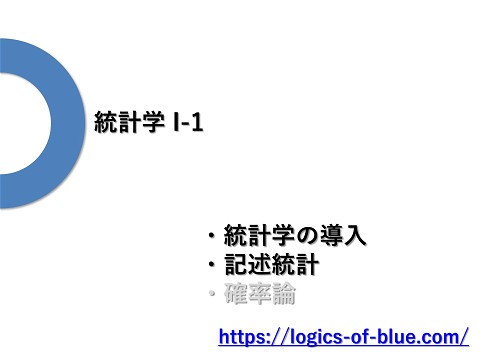
統計学I-1
 Logics of Blue
301.8K
Logics of Blue
301.8K
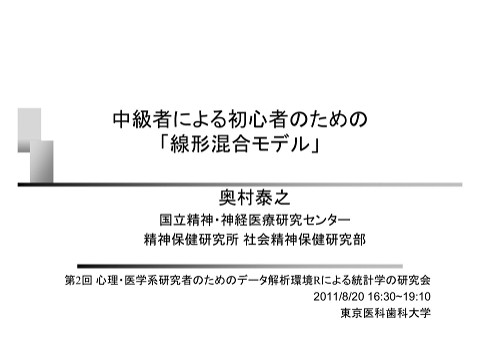
中級者による初心者のための「綿形混合モデル」
 奥村 泰之
223.8K
奥村 泰之
223.8K
各ページのテキスト
The Orders of Order: Curriculum Design and a Hauntology of Efficiency 順序のための秩序:カリキュラムデザインと 効率の亡霊論 著者 Christopher Kirchgasler 千田 成美 1
目次 • 筆者の紹介 • 序章 • インフラスペクトラルアプローチを用いたお化け屋敷としての カリキュラム ・組織としてのデザイン ・プロセスとしてのデザイン ・予測としてのデザイン ・デザインによる違い(結論) ・言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆 2
筆者の紹介 Christopher Kirchgasler • ウィスコンシン大学マディソン校、カリ キュラム&グローバル・スタディーズの助 教授 • アフリカ研究プログラムとホルツ科学技術 研究センター所属、運営委員 • 研究テーマ:国際教育研究、開発主義の研 究、植民地主義、発展主義、具体的な統治 方法などを検証。 3
序章 カリキュラムデザインの今日の問題 • カリキュラム:一般的に良い人生の基盤となる体系的な学習課程 を構築するための原則と手順。 ↓ 「良い人生」とは?カリキュラムを設計する際、どのような前提を 仮定しているか? • しかし今日、「生活には秩序が必要。カリキュラムデザインは単 に、それを実現するための適切な手順を決めること」 カリキュラムの手続きや実施に焦点が置かれている。 4
序章 カリキュラムデザイン自体を揺るがすには • 植民地主義・植民地化をヒント=占領支配プロセス、組織化と配置の実践 • 空間・・・占領や支配のプロセス+組織化・配置の実践 • 知識・・・宗教・言語・社会の支配 →生活を構成する条件+他の可能な秩序を排除しようとする搾取と暴力の 形態と密接に結びつく →デザイン=秩序、秩序=デザイン (知識は中立ではない、秩序にそぐわないものは排除) デザインは“どんな秩序(Order)をつくるか”という決定そのもの 5
序章 カリキュラム設計へのアプローチ法 カリキュラム設計 ×従うべき手続き→秩序の秩序 典型的・直線的・未来志向の目的論 →組織化・配置に先立つものに焦点 • これによりカリキュラムデザインの基盤に「取り憑いている」デザイ ン原理の亡霊を検証する。 6
インフラスペクトラルアプローチを用いた お化け屋敷としてのカリキュラム 7
ハントロジーとしてのカリキュラム ハントロジーとは • カリキュラム・デザインに「何が生きているのか」という問い • デリダは「マルクス主義を「ある」か「ない」ではなく、過去・現在・未来 に渡って現れ続ける予兆」 →幽霊のように今も存在、過去・現在・未来の私たちに影響し続ける。 ・・・ハントロジー カリキュラム・デザインの中に「他者、(大多数から漏れた人々(障害者、マイノリティ、 植民地の子供)」を内包していると考える視点、それをあぶりだす視点をくれる →カリキュラム秩序における別のあり方、可能性の裂け目 8
ハントロジーとしてのカリキュラム インフラスペクトラルアプローチでカリ キュラムに棲むお化けを見つける • Infra-spectralアプローチ: カリキュラムデザインは幽霊が住みついた家である その“幽霊”との出会いでカリキュラムの内実を探る 「カリキュラムがその規範や生き方の価値観に反対する差異や排除を いかに絶えずデザインしているのか」 9
ハントロジーとしてのカリキュラム カリキュラムデザインの秩序構造そのもの に迫る • 章の目的:制度や実践の設計合理性を支える秩序構造=デザイン思 考そのものを問うこと • 設計:単なる計画や構成ではなく、カリキュラムへの適応・不適応 の判断を支える秩序を構築する行為と捉える →カリキュラムは選別や追跡、特別支援、早期介入、職業的方向づけ などの正当化を可能にする秩序の形成に深く関与 10
ハントロジーとしてのカリキュラム 3つのカリキュラム設計の原理 • 進化的発達論(evolutionary developmentalism): カリキュラムを、個人がある自然な発達段階を通じて学ぶものと見なす 枠組み。 • サイバネティクス的プロセス(cybernetic processes): 学習者の行動を測定し、フィードバックを通して調整する自己制御的な モデル。 • 予測アルゴリズム(anticipatory algorithms): 蓄積されたデータに基づいて学習者の将来の成果やリスクを予測し、介 入を正当化する仕組み。 →これらは、教育を効率化するという名目のもとで、差異の管理と介入 の正当化を進めてきた。 11
組織としてのデザイン 12
組織としてのデザイン アメリカにおける20世紀初頭のカリキュラム設計の歴史 •産業主義と官僚制度・・・社会的効率のイデオロギーが普及 →子どもの教育に結びついた社会的な理想が→経済的な目的へと方向付けられた •教育本来の社会変革・啓蒙の可能性、力は抑え込まれる(経済的目的へと矮小化 ・学校教育はエリートの利益に支配) 子供の自然な発達 神聖なビオス(生命) 道具的合理性 近代のテクネ(技術) • この構図は「知識人が人類を抑圧する力から解放する役割」→人間 =政治の起源として神聖化している →「生命そのもの」が政治の対象になるようになった歴史的条件を見 落とす 13
組織としてのデザイン カリキュラム設計の歴史を問い直す •カリキュラムの歴史の問い直し:発達的な生命体としての子どもがどの ようにして制度の中に出現するようになったかを問う ↓ 20世紀の米のカリキュラムの歴史:「子どもの成長を生物学的進化に従 って管理するためのマニュアルやガイドが大量に生産された時代」 14
組織としてのデザイン 19世紀の生命の捉えの変化 • “生命”の概念=生命の内部性に着目、経験的で能動的な探究の対 象 • 構造的客観性:見えない法則を可視化 • 教育の目的:「罪深さを抑圧すること」→人類が種としての運命 を全うできるようその生命表現を導く 15
組織としてのデザイン 組織図が登場 • 内部構造の視覚化するため「組織図」 • ニューヨーク・アンド・エリー鉄道ダイ ヤグラム:鉄道を「生きた植物」として 可視化 • 構造を描く=統治可能を意味 →鉄道・工場・学校など: 成長・機能不全・死という共通原理により 組織化 それぞれ対象は共通目的を達成するため機 能を統合する必要があるもの 16
組織としてのデザイン 進化論的時間論が教育に影響を与える • 子ども時代:人種の差異を比較する空間として再構成 (文明化/後進的という理論を発展→科学的差別主義の条件を創出 →学校とカリキュラム:子どもの発達段階を基に人類の歴史の進化段 階を反映する必要があった 17
カリキュラムの変遷 19世紀 児童学 19世紀~20世紀初頭 統計的手法(ガウス分布)が登 場 目的:子どもの遺伝的な可能性を完成さ せること 目的:「文明的・科学的・合理的」 な人間にするため、「原始的・教条 的・迷信的な他者」から分離する態 度・習慣・感性を育てる 「先天的な特性」を特定するた め 設計:子どもの行動を図示→感覚的印象 の進行を追跡→それが将来の世代へ受け 継がれるよう可能性を記録 カリキュラム:「人種によって創ら れ、保存されたもの」 子どもの行動を段階的に習慣化させ ることが求められた 正常(平均)と逸脱(偏差)を 語れるように ホール:「ただし文明を継承進化できる のは白人だけ」 成長に失敗する人=原始的段階=劣っ た・未開な人 道徳的判断としても機能: 逸脱者は教育効率が悪い→隔離 発達の成功と失敗は「変化するニー と排除が正当化→カリキュラム ズ」をカリキュラムがどれだけ識別、 に組み込まれるように 対応できるかにかかっていた 18
組織としてのデザイン カリキュラムとデューイ カリキュラム改革:「子どもを救うこと」「国家を建 設すること」→人種的進歩を加速する必要条件を探す ように ジョン・デューイ 機能主義・進化論に依拠 「学校内外で得た学びが活かせていない」 ↓ 「大いなる浪費」を阻止する必要がある カリキュラム:社会における多様な「ニーズ」を効率 よく考慮することで調和のとれた発達を促す必要 19
組織としてのデザイン 無駄と効率が優生学へと 設計:「無駄」を防ぎつつ、社会的再生産を促進・向上させる環境 を整える必要がある 無駄や効率性への関心・・・進化論的な生命観に存在する ↓ これは次第に人種・性別・階級による差異の概念と結びつく 先天的能力に基づいて子どもを追跡・分離→優生学 20
組織としてのデザイン 現代のカリキュラム設計モデルに宿るお化け おばけ:生物学的な生命観とそれに不随する規範や価値観 生命のデザイン:自然な成長を足場にして組織化することで効率を上げて無駄をなくす カリキュラム設計の前提: 子どもと社会を結びつける、知識=蓄積的、遺伝的に成長する生命体、学び=環境に適応する 機能的行動の獲得、人間の「改善」を導く主体性 特徴 ・目的:正しい思考・感情・行動の習慣を育てること、失敗=「退化」、絶滅 への恐れを意味 ・逸脱者への介入の正当化=適者生存のため必要 ・現代の「効率的な健康・教育・福祉の改善」への呼びかけに取り憑いている 21
プロセスとしてのデザイン 22
プロセスとしてのデザイン カリキュラムへの批判的主張 カリキュラム内の無批判な規範や価値観が 白人・英語話者・健常者・中産階級・シスジェンダーの男性・異性愛者の経験、視点、 特権を優遇 △妨げる要因:ネオリベラリズム(報酬、市場の価値観)な どの外的要因 周縁化された人を中心・ニーズも応えるべき 23
プロセスとしてのデザイン 「ニーズを中心」の考え方は二項対立構造に取り憑 かれている 新自由主義下の 市場先導原則 カリキュラムは 学生・学校・地域社会の 近代化の弊害 自然な子供 ニーズを中心に! ニーズがいかにしてカリキュラム・デザイン、教育研究全体をも組 織化するようになったのか。 →サイバネティクスとシステム論 24
プロセスとしてのデザイン サイバネティクスとは • システムの制御と通信に関する研究分野、フィードバックや自己調整の メカニズムを探求する学問。 • 内的ニーズと環境的要因の理解のため、改善プロセスが利用 有機的ニーズ を把握 調整 環境的要因を 改善 • 有機的ニーズ:改善を導くシステムの構成要素の基盤 ・行動・成長・生命をデータとして捉えるように Galisonとウィーナー:「行動データを記録・保存・分析→情報パターンのズレを見出す→よりよい 結果を導く指標」=サイバネティクスの応用として主張 ・生命を「メッセージ、情報、プログラム(たとえばDNA)」という通信のパターンとして捉える ようになった 25
プロセスとしてのデザイン 教育やカリキュラムへも影響 ブルーナー:成長を促すためにはフィードバック=注意の訓練が必要 →「スパイラル・カリキュラム」 :情報を認識→コード化→記憶→呼び出すという人間の生理的能力を強化→心が改良・発達 従来のカリキュラム ↓ 「何を学ぶか」知識の伝達 ブルーナーのカリキュラム設計 真の学習:「どのように学ぶのか」を心の学びのプロセスとして模倣する つまりスキルの育成、能力の習得、生徒の熟達を支援することに焦点を当てるべき 「タイラー・ラショナル(Tyler Rationale)」カリキュラム・デザイン ・基準(スタンダード)を設定→学習経験を計画→成果を測定する ・フィードバックプロセスを循環、改善 26
プロセスとしてのデザイン 情報パターン・行動・目標駆動型のシステム重視 教育目標の具体的記述、完全習得学習、認知・情意・身体運動領域の分類に表出 →これらは子どもの発達を観察可能な能力基準で継続的に評価するとい う前提 →教育成果を定量的・測定可能な行動目標として設計・評価する流れを 強化 →適切なカリキュラムデザイン:“心のプロセス”に従うこと 27
プロセスとしてのデザイン 制度によって仕組まれたニーズ 生命(こう生きるべき、価値 判断)という概念に寄生・依存 サイバネティクス Step3 Step1 Step2 • 例 ジョージア州教育省の「継続的改善システム」 • 子どものニーズ「生きる、学ぶ、導く」ための準備状態」が中心。 • 「ニーズが家族、教育者、地域リーダー、政策決定者らをつなぐ」 • 「ニーズ」がフィードバックプロセスを導く原理 (準備状態を測定、基準から離れている児童を特定→介入→評価 28
プロセスとしてのデザイン お化け:ニーズは自然的でない • サイバネティクス的システム:“ニーズ”という概念がすでに植民地化(枠組みに支配) • 「ニーズ」は本来社会技術的な現象、「差異」を測るための基準 問題点1「ニーズについてこれまで聞かれてこなかった声や視点に応答」しようするとき、 →発達的ニーズという論理そのものが研究の対象となるべき人びとに、何が言えて何が言えないの かをすでに決定してしまっている 問題点2 不平等を再生産 • この理論はズレを測定し→補正→標準化する=不平等に対処しようとしている • 逆説:それらの不平等が“望ましい生”の規範として刻印されることを可能にしている条件への内 省を妨げる。 その結果「逸脱している人」ばかりに変化の責任を負わせる構造を再生産。 29
予期としてのデザイン 30
予期としてのデザイン 予期に取り憑かれている • 強度(量、速度、多様性)と偏在性=新しい生(予期)が可能に 現在 サイバネティクス的記憶 未来 予測 • 予測が現在を代表し、現在に介入する権限をもつ • 本章:今日のカリキュラム・デザインにおける「デジタル予期」の理念を、先に 議論した「サイバネティクス」「秩序化」の文脈によって「取り憑かせる試み」 である。 • 目的:「発達」の名のもとに、いかに“デザイン”が調整・管理を担っているか を明らかにすること 31
予期としてのデザイン データ化が当たり前? • 日常生活のデータ化は当たり前(世界銀行、ビル&メリンダ財団) 「テクノロジーが社会を良くする」=ユートピア的な見方 不平等の構造的な原因を見落としている 例”Jim Code“「テクノロジーが既存の不平等より客観的あるいは進歩的のように見せている」 =不平等の再生産 これだけでなく ・「生」・・・空間的・時間的境界そのものが変容 ・「社会」も変質・・・有機的発達・自己生成のシステム→最適化の対象と してコード化 32
予期としてのデザイン 例:Bridge International Academies • サハラ以南アフリカ諸国、インド • 低価格・営利目的の学校チェーン • スマートな教育システムを安価な技 術で設計 • 使命は「教育による貧困削減」 • 「学習成果」測定、 改善を Academy in a Boxで実現 • Bridge Community Schools - International Academies Worldwide 33
予期としてのデザイン 予期→最新、低価格、最適なカリキュラムが提供 • Learning Lab:世界の生徒の学習成果を収集→MVM(最小実行可能測 定)が可能:統計的に必要最低限のデータを収集し予測、フィードバッ クループを回す • MVMでカリキュラムデザインが適者生存競争にさらされる 例 教育実験(A/Bテスト) 成績への 影響測定 授業方法 変更 効果あり 改訂カリ キュラム 配信 • カリキュラム・授業計画は「入力―出 力システム」に • 教室は完全に標準化 • 目的:コスト効率が高く、継続的な改 善を迅速かつ大規模に実現 34
予期としてのデザイン Bridgeへの批判 人権ベース批判 「Bridgeが国家や民間の教育主体としての役割や義務を果たしているか否か」と いう観点から評価しているが・・・ ↓ 単に人々の自由を抑圧しているのではなく、「生命・人生そのもの」をデザイン している点を見落としている 「予期」のような変容が Bridgeによって「教育とは何か」「どのよ うに生きるべきか」という原理そのものが書き換えられている 35
予期としてのデザイン Bridgeは教育にとどまらない • 「1日2ドル以下で暮らす子どもと家族に関するデータ」→信用スコ アの算出、低価格の健康保険の提供を予測 顧客の好み、ユーザーの意図、生徒 の学習傾向 収集・記録・分析 価値や洞察、投機対象に Bridge って何者? 実店舗型の学校?企業?デジタル学習プラットフォーム? これらの区別に意味は? 36
予期としてのデザイン 新しい生のあり方を設計 • カリキュラムデザインの質:「効率性」という変化し続ける概念と常に 結びついている • 効率性は今や「生命そのもの」を最適化するための必要なデータとして 「バイオ資本」へと変換 • Bridgeのビジョン:未来完了形で語られる新しい生のあり方を設計 • 予測を重視、全ての可能な行動に意味づけする「関連付け・相関関係」の構築、予測に基づき行動で きる空間を作るためデジタルツールの普及、これらのシステムを「最適化」する義務 →予測不可能で常にリスクに満ちた未来をより正確に迅速に包括的に予測 することで、より効率的に生きていくためのデザイン秩序 37
まとめ:効率性とは • カリキュラム・デザイン:「常に最大限の効率性を追求する」=「良 き人生の実現に不可欠 • 効率性の必要性はデザインそのものの条件に内在 発達的効率性 サイバネティック効率性 予期的効率性 先天的な資質の段階的育 基準に対するパフォーマ すべての可能な行動の特 成、劣性要素の抑制の必 ンスのフィードバック、 定と最適化、潜在的なリ 要性 逸脱への介入の必要性 スクを事前に制限する必 要性。 38
まとめ ①幽霊:適切に発達的ではなく、フィードバックに柔軟に対応でき ず、予見可能なものとはならない、別の存在・思考・見方・行動の 仕方を排除するものである ②違いや排除は「常識」とされる方法で実施され、そこで生成され る「生のあり方」によって生じる ③デザイン行為=別の幽霊出現、自分・ましてや他人のため良い人 生を設計できないのでは、少なくとも前もった設計は不可能。 39
まとめ 幽霊と共存することから始める • ジャック・デリダ(1993)は、「生きること」を学ぶパラドックスについて • 未来を運命付けられたもの、フィードバックされたもの、または予期さ れたもの以外の未来を招き入れるために、カリキュラムはまず、「その幽 霊と共存することを学ぶこと」から始められる。 40
言語的文化的に多様な子どもの包摂への示唆 ・カリキュラムデザインは「特定の成功者、目標の達成」を前提として設計され る・・・そこから漏れ出る人が生まれる(お化け)ことを意識することが必要。 ・データ化されることで言語文化的に多様な子どもにばかり負担を強いるような介 入があたかも効果的で客観的であるように見える=正当化されてしまう課題 「お化け」への対抗論・・・教師が小さな価値を包摂する 小さな価値:「教室で偶発的に生み出された、言語文化的に多様な子ど もたちに対する、価値あるつぶやき・発想」 教師がこれをひろいあげ、価値づける=お化けも予想だにしない価値=対抗 になるのでは? ×小さな価値を「目標外だから」と除外、無視 41
参考文献 • Research – Chris Kirchgasler • サイバネティクスとは • サイバネティックスとは何?定義や応用分野などわかりやすく 解説! - ザッタポ 42