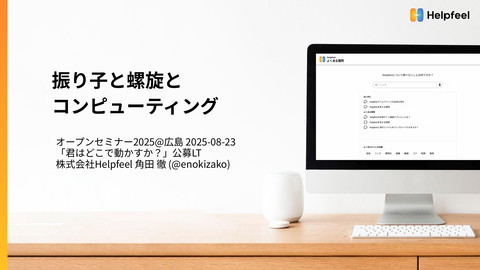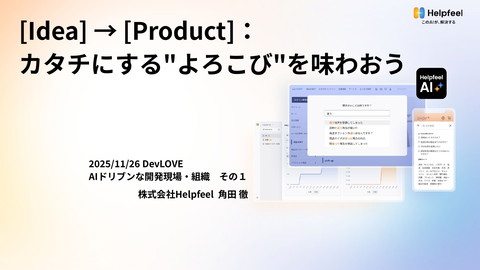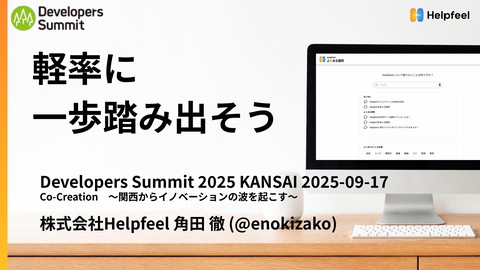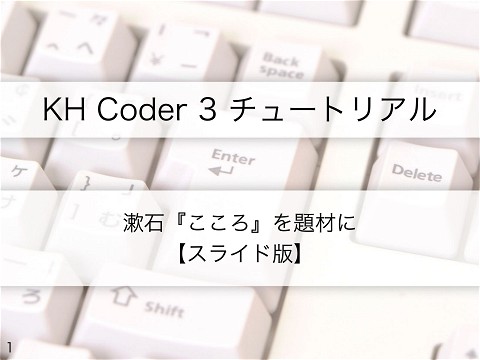enun vol.4 読解力の地図を描く
776 Views
November 21, 25
スライド概要
2025/11/20 engineer unite meetup vol.4 LT みんなの推し本、教えて!で行った書籍紹介です
島根県に生息しています。プロダクトエンジニアです。 株式会社Helpfeelでエンジニアリングマネージャーをやっています。ワークアット株式会社に所属しています。 コワーキングスペースenunでコミュニティマネージャーをやっています。
関連スライド
各ページのテキスト
2025/11/20 engineer unite meetup vol.4 LT みんなの推し本、教えて! 読解⼒の地図を描く 株式会社Helpfeel ⾓⽥ 徹
読めば分かるは当たり前? 読解⼒の認知⼼理学 ⽝塚美輪 読める⼈の頭の中には読解⼒の地図がある 私達が⽂章を読むとき、内容を理解するだけでなく、感動したり、 「それは違う」と思ったりします。こういう⼼の働きは、どのように 起きているのでしょうか。 https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480685131/ 2
about me enun : community manager Helpfeel inc, : engineer / unit leader / engineering office Work@ inc, : engineer / CTO 3
世は⼤テキスト時代! ● 現代において我々は⼤量のテキストを読み、書いている ○ プログラム⾔語、⾃然⾔語の両⽅で ● とにかく⼤量に読んで、⼤量に書いている ● うまくできてますか?僕は⽇々苦しんでいます ○ ⾃分はヒューリスティック(後述)な コミュニケーションを取りがちである ○ 割としょっちゅう読み違えている 4
そんなとき 同僚が「いま読んでる」といってたので興味を持ち⼿にとってみた 5
が 6
読解⼒を養成する本ではない ● 認知⼼理学の観点から、読解の複雑なプロセスを解明し、どうすればよりよ く読むことができるのかを考えます ● まずは、⾃分の読解⼒の現状や、⾃分が望んでいるような「読解⼒がある状 態」にどうやったらたどり着けるのか、その道筋を考えます ● ⾃分の読解のクセやつまずきを知って、読解⼒を⾼めるためにもっともよい 練習⽅法は何か選べるようになる事が重要です ● この本を通して、皆さん⾃⾝で練習⽅法を⾒つけたり、練習⽅法を編み出す ことができるようになってほしいと思います 7
おや、どうやらめんどくさいぞ? ● お⼿軽なコツとか具体的なスキルを教えてくれるわけではない ● だが、結論としてはよい本だった 8
なにがよかったか ● 読解 is なに?がわかった ● 「読解する」がわかると「読解させる」もなんとなくわかる ● 低いレイヤーの仕組みがわかると具体的な状況の理解が深まる ○ (完全に理解したとかなにかできるようになったとは⾔ってない) 9
では、さっそく内容 ● その前に注意 ● 書籍にない⾃分⽬線での意⾒を含みますのでご注意ください 10
そもそも読解⼒とはなんなのか?(いきなり結論) 11
3種類の読解 ● 表象構築の読解 ● ⼼を動かす読解 ● 批判的読解 12
表象構築の読解 ● 理解できた状態をつくること ○ 理解することを⼼理学では表象という⾔葉で表している ● これはふたつの段階がある ● テキストベース ○ ● 書いてある内容が整理され、頭の中に再現されている 状況モデル ○ 知識や推論も加えて、頭の中に世界が再構築されている 13
表象構築とは ● ⾃分の知識と結びつけた状況モデルの表象を構築すること ○ 情報は他の情報との関連の有無によって表現されるネットワークのどこかにある 14
表象構築の読解の先にあるもの ● 理解した、のその先にある⽬的地 ● ⼼を動かす読解 ○ ● 状況モデルに感情を加えてバージョンアップすること 批判的読解 ○ 状況モデルに論理を加えてバージョンアップすること 15
3種類の読解⼒の⽬的地 表象構築の読解 ⼼を動かす読解 批判的読解 表象 知識を⽤いた 状況モデル 状況モデル+感情 状況モデル+論理 現象 理解する 感動する、泣く 熟慮‧検討 正解の明確さ ある程度明確 不明確 場合により異なる 影響 知識変容 信念‧態度の変容 場合により切り離し 16
読解のための道具 17
ワーキングメモリ ● いわば⼼のメモ帳 ● コンテキストがここに載ることで読解できる ● コンテキスト is なに? ○ ⽂脈、前後関係、事情、背景、状況 ○ ⽂脈によっていろいろな意味を持ちます(再帰) 18
スキーマ ● スキーマ is なに? ○ 知識の枠組み、いわゆる常識 ○ 〜〜とはこういうものである ○ 経験や知識を整理したもの ● それが事実か、それが正しいかはまた別問題 ● スキーマはフィルターとして作⽤する(後述) 19
ワーキングメモリとスキーマは、あらゆる知的活動の道具 20
この整理でいろいろなことが説明できる ● ドメイン知識は膨⼤なコンテキストやスキーマの集合体 ● オンボーディングはコンテキストやスキーマの注⼊作業 ● 相⼿にあわせてコンテキストやスキーマを切り替えるのは本来難しい作業 ○ だからマネージャーとかリーダーはつらい(気がする) 21
マルチタスクの難しさと忘れることの重要性 ● コンテキストスイッチやスキーマの切り替えはコストが⾼い ● ワーキングメモリに載ってる膨⼤な情報を切り替える必要がある ○ ● マルチタスクが得意な⼈はこれが得意 転職とかリラーニング、アンラーニングとかこのへんの捉え⽅が有益 ○ うまく残す ○ うまく忘れる 22
で 23
読解にはふたつのアプローチがある ● ボトムアップ ● トップダウン 24
ボトムアップで読み解く ● ⽂字を読む ● ボキャブラリー 単語知らないと⾟いよねわかるわかる ○ ● ⽂法 ○ ● これも知らないと⾟いよねわかるわかる だが前提知識があると嬉しいという、それはそうの話なので割愛 ○ そして書く側で考えるとここで詰まらせないというのは重要 ○ ワーキングメモリについてもなるべくなら節約したいし 25
トップダウンで読み解く ● ヒューリスティックを⽤いた意味理解 ● ヒューリスティック is なに? ● ○ 経験則的 ○ より簡単で頭をつかわないでもできるやり⽅ ○ いってみれば時間や労⼒を節約できるやり⽅ ○ エネルギーを⼤量に消費する器官である脳は省⼒化が⼤好き スキーマを使って省⼒化する ○ フィルターする ○ 補完する 26
スキーマのリスク ● ⾮常に便利な道具だが認知バイアスに陥りやすいという罠もある ○ 偏⾒ ○ 思い込み ○ 確証バイアス ○ などなどなどなど 27
常識とは、18歳までに集めた偏⾒のコレクションである "Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen." 28
余談 ● 教科書や知らない技術の専⾨書が難しい理由はこのへんっぽい ○ ヒューリスティックが効きにくいのでボトムアップするしかない ○ ⽤語や概念で詰まるので、知識を注⼊しながら読解を進める必要がある ○ つまり状況モデルを構築するのに時間がかかる ○ 結局どこかで覚悟を決めないとならない瞬間は必ずくる 29
読解のための⽅略 30
読解⽅略 ● ⽅略とは ○ ⼼理学でよく⽤いられる⽤語のひとつ ○ なにか課題を達成したいときにとる思考や⾏動のこと 実際には我々は、トップダウンとボトムアップを 使い分けたり組み合わせて複雑な⽅略を駆使して読解している 31
⼤きく分けると3つに分類されるらしい ● 理解補償⽅略 ○ ● 内容学習⽅略 ○ ● 意味明確化、読みのプロセスコントロールなど 要点把握、質問⽣成、記憶など 理解深化⽅略 ○ 構造注⽬、既存知識活⽤など よく考えると、学校の国語の授業でやったなぁというやつらが並んでいる 32
さて 33
⼼を動かす読解が活躍するポイント ● 物語の⼒で説得する ○ ナラティブ、ストーリー ○ ⼼を動かす読解を引き出す ○ 悪い使い⽅もできてしまう 34
批判的読解が活躍するポイント ● 誤情報に対抗する ○ フェイクニュース ○ 疑似科学 ○ オレオレ詐欺 ○ 批判的読解で⾒抜いて切り離す 35
ここから感想とか考察コーナーです 36
読解してもらう⽴場として気をつけるべきこと ● ● 読解⽅略が効きやすい⽂章を作成する ○ 先⾏オーガナイザーを⽤意する ○ 結論から書く ⽂章や⽂の命題を明確にする ○ 述語、助詞に気をつける ○ ねじれを避け構造をシンプルに保つ 37
内容以外にもできることはたくさんある ● 段落や⽂字サイズ、箇条書きといった⾒た⽬を整える ● 相⼿の持つコンテキストを理解して適切に利⽤する ● ○ 過度に読み⼿のスキーマを頼らない ○ 事前にコンテキストを共有する 話す場合はもっといろいろある ○ 周囲の環境 ○ 声のトーン ○ ⾝振り⼿振り 38
AI 39
もしそれがアヒルのように⾒え、アヒルのように泳ぎ、アヒルのように鳴くのなら、 それはおそらくアヒルである "If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck." 40
AIは読解⼒があるか ● AIは⼈間とは違う ● が、⼈間の⽂章を学習し、振る舞いを学習している ● ⼈間と同じやり⽅がある程度通じるかもしれない 41
できること(個⼈の感想です) ● 状況モデルの構築はしてくれているようにみえる ○ むしろ⼈間より得意なんじゃないだろうか ○ 事前に学習した膨⼤な知識を⽤いている ○ ただしコンテキストが許す範囲で 42
できないこと(個⼈の感想です) ● ⼼を動かす読解は苦⼿ ○ ● 批判的読解も、もともと苦⼿ ○ ● というより、勝⼿にやってもらってはむしろ困る 明⽰的に指定しないとやってくれないことが多い 批判的読解は、適切なプロンプトを与えれば上⼿な場⾯もある ○ Chain of Thought、Tree of Thoughtが取り⼊れられ、Reasoning modelsになった ○ 適切なプロンプトを与えることである程度できるようにはなっている 43
もちろんではあるが、できることには 的確に伝えられれば という前提はつくのだけれど (そこは現状、⼈間相⼿とあまりかわらない) 44
ありがとうございました! ⼤テキスト時代を乗り切りましょう! 45