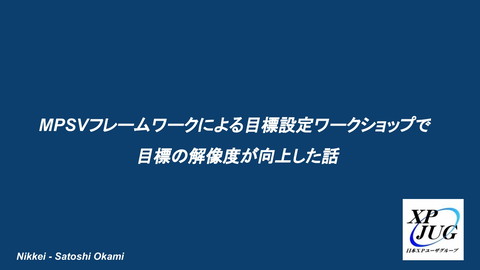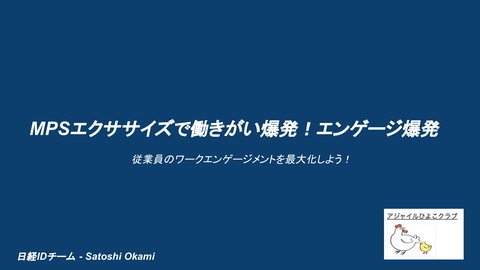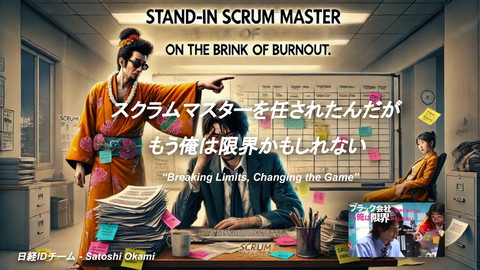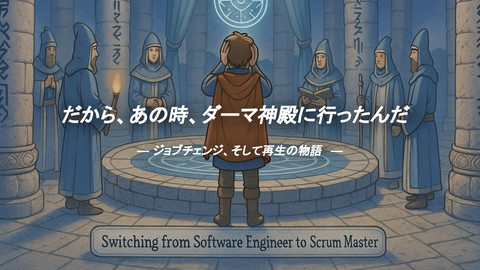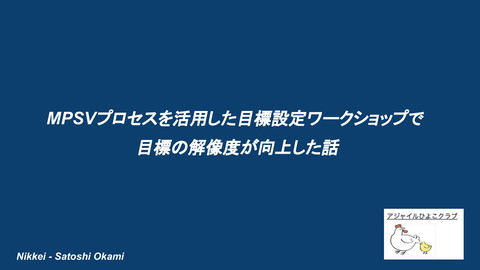カメラオフ・ミュートでも、荒波を超えてく
645 Views
October 04, 25
スライド概要
本資料は「スクラム祭り2025」で発表した内容です。
オンライン会議では、カメラオフ・ミュートにより表情や非言語情報が失われ、沈黙やすれ違いが頻発します。
本発表では、そうした「言葉しかない世界」で生まれる不確実性をどう乗り越え、チームが成果を出し続けられるかを探りました。
・不確実性の正体:「個」に由来するズレ(集中阻害・属人性・文化摩擦・コミュニケーションの違い)
・沈黙はデータ:“考え中の間”“作業の間”“準備の間”をゼロにする設計
・実践例:事前準備の徹底、火種のストック、心理的安全性を育むファシリテーション
・成果:会議時間20%削減、雑談の復活、チームの自律性とシェアド・リーダーシップの醸成
文化はルールではなく「水脈」。
しなやかに流れるチームデザインの実践から、未来の組織づくりのヒントをお届けします。
好きなときに好きなことに対してコミットしています。月に40、50冊の本を分野に関係なく読んでいます。ソフトウェアエンジニアしてますが、知の探索が専門領域です。 https://after12am.carrd.co/ 過去スライド https://speakerdeck.com/after12am
関連スライド
各ページのテキスト
カメラオフ、ミュートでも、荒波をサーフしていく 言葉だけの世界で、どう “水脈 ”を設計するか? Nikkei - Satoshi Okami 1
今日お話しする全体像 1. チームビルディングの不確実性 ― 認知のズレ、属人化、コミュニケーションの違いが生む不確実性 2. カメラオフの不確実性を乗り越える ― “考え中の間” “作業の間”、間を減らして、連続性を取り戻す 3. 成果の“水脈”を発見する ― 成果の表層下に隠れた行動・文化・意思決定の層を読み解く 4. 文化を“流れ”として育てる ― 不確実性にしなやかに即応する、水脈型チームデザインへ 2
ズレの発生源は、チームではなく“個”にある。 成果 不確実性は“個”から生まれる 形成期 混乱期 統一期 機能期 そのズレが、やがて“荒波”となってチーム に影響を与える。 主な要因 🕒 集中の阻害 頻繁なコンテキストスイッチ 負荷の偏り 能力・スキル差 /業務負荷の偏り 🧠 属人性 承認プロセス・意思決定・ 役割 の属人性 🧬 文化的 な摩擦 暗黙知/価値観の違い/ JTC的構造 🗣 コミュニケーションの違い ズレの大きさ ズレの種類 形成期 混乱期 統一期 機能期 発言量・頻度/カメラオフ・ミュート 3
“個”のズレがチームに与えた荒波 ズレの種類 🌊🌊🌊 過去のズレの具体例 🕒 集中の阻害 🌊🌊会議が多く開発時間が確保できない /プランニング残業 負荷の偏り 🌊🌊フルスタックやめたい 🧠 属人性 🌊🌊🌊POがスケールしない/フロントエンド増やしたい 🧬 文化的な摩擦 🌊🌊AI活用の温度差/モブプロやめたい /社員と協力会社の “見えない壁” 🗣 コミュニケーションの違い 🌊🌊🌊カメラオフ・ミュート(非言語情報の欠如)/空気になる人 カメラオフ、言葉しかない世界で起こる “荒波”とは? 4
その沈黙、合意ですか?不在ですか? 認知のヒント 起こること 😐カメラ ON/リアル会議 🫥 カメラ OFF/ミュート 表情・声色・身振り 言葉しかない世界 - 意見を 引き出せる - 意見が 伝わる - 合意してるかわからない - 発言しない 人が“消える ” - 沈黙時のファシリテーションに困り果てる 沈黙のたびに、「沈黙は、承諾とみなします」の声。 5
誰にも聞けない。GPTにすがる日々が、はじまる。 ファシリが怖かった。本当はスクラムマスターなんてやりたくなかった。 6
会議中の“考えない時間”をゼロにする 👉 沈黙はデータ=“準備不足”や“低解像度”を示す信号では? 👉 会議の場で、「今ここ」に集中してもらうには? 👉 “考え中の間 ” “作業の間 ” “準備の間 ” をどう埋める? 沈黙は“間”として現れる。正体は、準備不足だったのかもしれない。 7
“間”を埋めるために実践していること 👉 PRレビューを 可能な限りして 、誰が何を知っているかを把握し、 “火種”を持つ 👉 誰が何を知っているかの知識を活かして、名指しで問いかける 👉 資料は事前に目を通し、すぐ着火できるよう準備し、 “考え中の間 ”をゼロにする 👉 会議の冒頭で、ゴールを明確に共有する 👉 話してほしい内容は、会議前に依頼し、 “考え中の間 ”をゼロにする 👉 同じ種別の会議でも、内容に応じて時間配分を柔軟に調整する 👉 デモ依頼や資料提示を事前に依頼し、 “準備の間 ”をゼロにする 👉 議論の火種探しに集中 し、タイムボックスを意識して場をマネジメントする 👉 会議前に事前記入できる項目は全て記入し、会議中の “作業の間 ”をゼロにする 👉 参加者の声のトーンや言い淀みに注意を払い、 話し手の心情 を見極める 👉 会議資料は、ブラウザのタブをグループ化、会議中の “作業の間 ”をゼロにする 👉 「すごいっすね」「さすがっすね」、称賛 で相手の気分を上げて、意見を引き出す 👉 視点を(括弧書き)で示すことで、議論のラリーを減らし、一気に深める 👉 名指しで、合意確認や意見・発言を求め、特定の人だけに話させない 👉 会議は生き物。場や人が変われば、進め方も変わることを理解し、超準備する 事前準備の工夫 会議中の工夫 8
“間”を埋めるための実践例 👈Hawkeyeは日経の障害管理ツール。会議 前に事前記入できる項目は全て記入する。 ☝ ゴールを説明し、何を達成したら終了となるの かを明確にし、会議に集中してもらう。 👈再発防止策は、障害対応中に話題に上がることはよくあ 👈 障害説明は、ポストモーテム前に記入可能なので事 前に記入し、会議中の “作業の間 ” をゼロにする。 るため、「問いかけ文」として記載しておく。 ☝会議は生き物。場や人が変われば、進め 方も変わる。タイムボックスは変更可能。 ☝事前に担当者名を記入しておくことで、プレッシャー ☝ デモ依頼や資料提示、話してほしい内容は、 を与えるとともに、考え中の間をなくす。 会議前に依頼して、 “準備の間 ” “考え中の間 ” をゼロにする。 ☝ 会議資料は、ブラウザのタブをグループ化、 ☝視点を(括弧書き)で示すことで、会議中の会話のラ 会議中の “作業の間 ”をゼロにする。 リーを減らし、会議時間を短くする ☝会議は生き物。会議体や状況に応じて、アジェンダや 注釈など全て更新していく。会議の後は 1人PDCA。 9
沈黙の“間”が消え、雑談の“間”が生まれた 会議時間の削減(定量的効果) 会話と関係性の変化(定性的効果) - 2024年度: 19.7% 会議時間を短縮 - 1日がかりのプランニングが、 1時間区切り+休憩可能に - 2025年度: 12.6% 会議時間を短縮(継続中) - 会議の合間に、 1年ぶりの雑談が自然発生 - 1時間ごとに 10分休憩を導入し、集中力と回復を両立 - 12人参加のデイリーが、 10分で完了する仕組みに進化 - 1on1で、メンバーの生産性が向上したとの報告を上司より 報告を受けた 10
“議論”の前に“考える”準備を整える 慌てて会議の場で考えさせ、沈黙は生ませない。 場を整え、「今ここ」に集中してもらう。 それが私の仕事だった。 スクラムマスターの “準備”が、チームにバフをかける。 11
2024年の日経IDチームの成果 2024年6月 Google社主催パスキーハッカソン 2024年6月 社内カンファレンス優勝 2024年7月 Passkey テストライブラリ OSS公開 2024年9月 パスキーをテーマにNikkei Tech 2024年12月 FIDO Tokyo Seminar 2024年12月 Engineering Vision 賞 12
積み上げてきた成果 2024年12月 「Engineering Vision賞」 2024年06月 「第4回 社内カンファレンス 優勝」 2023年12月 「CDIO賞」 2022年12月 「デジタル事業統括奨励賞」 2022年05月 「第2回 社内カンファレンス 3位」 2021年04月 「第1回 社内カンファレンス 優勝」 ※ チャレンジは省略、表彰のみ記載 13
成果は“氷山の一角”にすぎない 表層|成果(インクリメント、表彰、ジョブ・クラフティング) 2021~ 2019~ 2024~ 中層|行動(シェアド・リーダーシップ) 2020~? 深層|文化(本流もあれば、支流もある水脈設計) 2019~ 最深層|意思決定(集団的知性、MPSV目標設定ワークショップ) 2019~ 2024~ ※ 集団的知性は、前職のチームでも稼働実績あり。属人性を減らし、引き継ぎ不要な構造を構築できる。自走するチームに不可欠。 14
意思決定の構造が、行動の質を変える “人間は、他人から言われたことには従いたくないが、自分で思いついたことには喜んで従います。 ” 「いい質問」が人を動かす p9 谷原 誠 👑 トップダウン型 🤝 集団的知性型(シェアドリーダーシップ) 意思決定の軸 リーダーの承認が必要 チーム全体で “話し合って決める 動機の源泉 外発的(命令・ルール) 内発的( 自分で決めた・納得したこと ) 行動の性質 指示待ち/受動的 自走/能動的 ※ 障害対応などではトップダウン型が有効な場合もある。状況やフェーズに応じて意思決定構造を最適化する。 決め方が変わると、会話の質が変わる。日々の対話が共創になる。 15
集団的知性は、設計できる。どうやって? 👉 チーム全体で“話し合って決める”ようにする 👉 相談事や提案は、特定の個人ではなく“チーム”に対して行う 👉 PRの“必須レビュアー”をなくして、2 approves でマージできる 依存させるのは “個”ではなく、 “チーム”に。 上下関係を生まない構造が、平等な対話と自律性を育てる。 16
自律が成果を育てるシェアド・リーダーシップ ❓「シェアド・リーダーシップ」とは何か? 👉 一人一人が自分の得意を活かしてチームを牽引する。 一人ひとりの得意が、成果への伏線になる。 17
「価値の源泉」を可視化するMPSVワーク 👉 MPSVフレームワークによる目標設定ワークショップで 目標の解像度が向上した話 MPSVフレームワーク 18
MPSVワークで、“何に資本を注ぐか”が見えてくる ※ 2025年 5月 日経 IDチームの目標設定ワークショップ 価値が“視える”ようになったとき、 貢献の起点 が見えてくる。 19
成果を生む役割の掛け合わせは一つじゃない 🧙 私は「チームにバフをかける」役 Aさん・Bさん・Cさんは「テックリードや勉強会をリード」 🤝 Dさんは「他チームとの調整役」として外部との接続役 👉 それぞれが強みを活かし、自走し、自然にリーダーシップが分散する 「バフ × 技術 × 調整」、役割の掛け合わせが、チームの成果をスケールさせる。 20
文化は、ルールではなく水脈である 👉 ルールは「明示的に決めるもの」文化は「明示しなくても行われる振る舞い」 👉 自分のペース(支流)で本流に合流できる文化 👉 水が低きに流れるように、環境変化にしなやかに即応する 🔷 外的要因によって発生した問題 🔶 内的要因によって発生した問題 ・AIバイブコーディングの技術トレンド変化 ・モブプロやめたい、フルスタックやめたい ・新メンバー加入による文化の摩擦 ・カメラオフにしたい ・会議多すぎ問題 ・キャッチアップ速度、取り組みの温度差 ルールではなく、水脈のように。分かれ、合流しながら流れ続ける文化。 21
ルールと文化の違い 22
チーム紹介(日経ID担当年数とても長い) 表層|成果 7年目 5年目 9年目 中層|行動 5年目 6年目 4年目 8年目 深層|文化 12年目 13年目 4年目 チームの居心地に影響 社員5名、協力会社 様7名、フリーランス1名 最深層|意思決定 👉 所属の違いは、無意識に上下関係を生みやすいため、話に入れられない雑談はしない会話 設計や、自律性を育むためには “全員合意型”の意思決定プロセスが重要 チームの居心地に影響 23
ご清聴ありがとうございました。 Nikkei - Satoshi Okami 24
未来を共につくる人材募集 日経は、競争ではなく協力しながら、楽しく挑戦でき る仲間を探しています。 インフレが進む世界で、日経 は社員に 安心 × 安定 × 成長 を約束します。 一緒 に、未来をつくりませんか? 25
自己紹介 岡見 慧 担当:スクラムマスター、ソフトウェアエンジニ ア、ワークショップデザイナー 趣味:バイク。沖縄で素潜り。息止めベスト5 分3秒。 ポートフォリオサイト :https://after12am.carrd.co/ 26