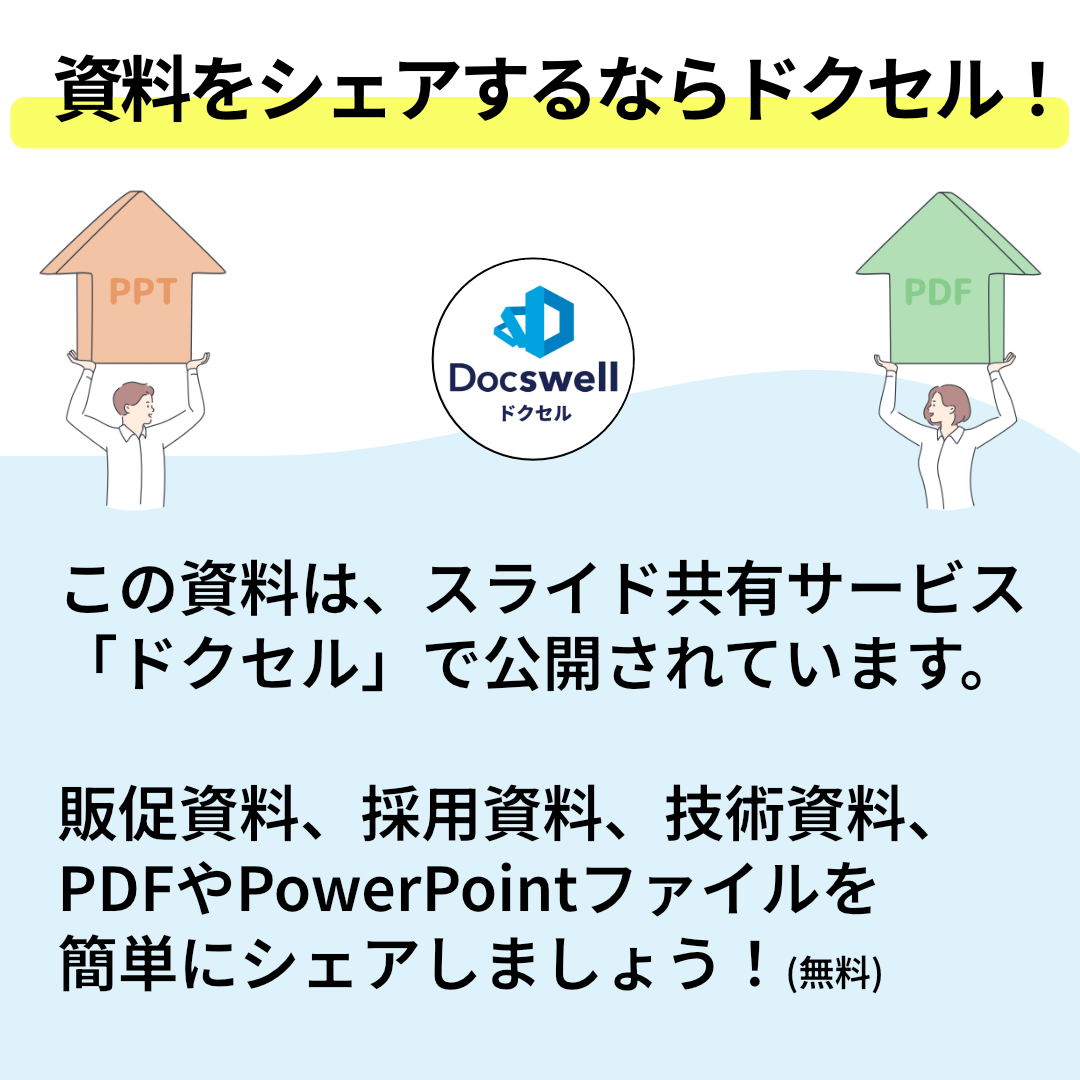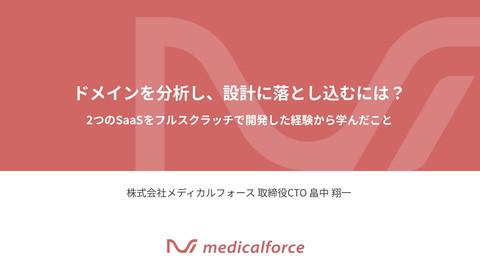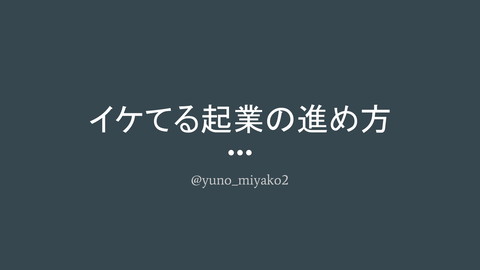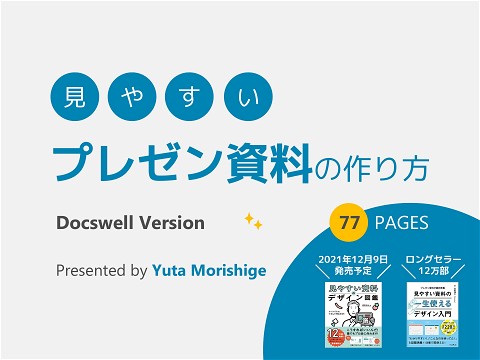Medicalforce Core Action_ver.1.0
14.3K Views
June 03, 25
スライド概要
関連スライド
各ページのテキスト
Core Action ver.1.0
Core Actionにかける思い 企業の経営競争力の源泉はヒト・モノ・カネであり、その中でもヒト(組織)は最も再現するのが難しく、 それ故に強い組織を作ることは最も強固なモート (= 構造的競争優位性)を築くことといえます。強い組 織が強いプロダクトをつくり、顧客満足を生み、市場に大きなインパクトを与えます。 メディカルフォースが美容医療市場で確固たるポジションを確立できたのは間違いなく強い組織があっ たからです。今後複数の産業でプロダクトやサービスを通して産業の成長を生み出すためには組織の 力が欠かせません。僕たちの組織が正しい骨格を保っていることが産業の成長のきっかけをつくること を信じて、正しい行動指針で会社を経営します。
AtomicSoftware Core Action 4つのCore Value(HRT・We・感動・Punk)を 高い次元で体現していくために共通して持つべき行動指針であり、 事業・組織・仕事に関する意思決定を行うための軸。 “アトミックソフトウェアらしさ”を表現したもの。 今の事業・組織フェーズに合わせて特に重要視しているものを選定。 3ヶ月に1度の頻度で見直しを実施。
AtomicSoftware Core Action
問題の解決を待つのではなく、自ら動く 「誰かがやってくれるだろう」という姿勢では組織も個人も成長しない。 小さな一歩でも自ら動くことで、周囲を巻き込み、チーム全体の成果を最大化できる。 例えば、「問題の提示だけして解決に向けた提案や行動を行わない」、「問題に対して自分は動かず他の人にのみ行動を 求める」などはせずに、常に「自分にできることは何か?」を問い続けよう。
できない理由から始めるのではなく、 できる理由から始める 困難に思えることも、「できる」と信じた瞬間に道は開ける。 「難しそうだ」「無理かもしれない」と立ち止まるのではなく、「どうすればできるのか?」と視点を変えることで、 新たなアイ デアや突破口が生まれる。 特に、過去にうまくいかなかったことや新しい取り組みを始めるときなど、達成までの道筋が描きにくいことに対して “できな い理由”を列挙してしまうことはよくある。 そんな時こそ“できる理由”から始めよう。
すぐやる、必ずやる、できるまでやる 意思決定を行ったら、すぐに取り掛かろう。 その積み重ねが会社に大きなスピード感をもたらす。 決まったことは絶対にやろう。 どんな意思決定をしても、遂行しなければ意味がない。 結果が出るまで粘り強く取り組み続けよう。 一つひとつをやり切ることこそ、会社の組織力・業績へと繋がる。
同意せずとも決まったらやる 反論は意思決定の前まで。決まったら、賛成・反対に関わらず、実行する。 職種、立場関係なく、多様な意見を元にした意思決定は大切であり、そのために異論を発言しやすい環境を作ることも大切 である。ただし、”チームとして”の最終的な結論は一つ。 複数の意見を取り入れることはあるかもしれないが、すべての意見が取り入れられるとは限らない。 そのような場合において、「反対だからやらない」ではなく、「反対でもやる」というスタンスを大事にしよう。
モメンタムは全員でつくる モメンタムとは「自分たちはできるんだ」という 組織効力感や勢いのこと。 その組織効力感や勢いを生み出すために、組織の目標達成に向けて、「自分 が組織の目標達成を引っ張るんだ」という気概を持とう。 そして、組織や仲間の成果や行動を能動的に把握し、 それらを積極的に賞賛しよう。 Good MTGで積極的に発⾔し、 場をつくる。 誰かのSlack発信に スタンプやコメントする。 仲間の⼩さな成功を祝い、 ⼠気を⾼める。 計画的なリスクを恐れず、 挑戦を歓迎する。
70%の情報と 30%の直感 意思決定に必要な情報が100%揃うことはない。揃っているのだとしたら意思決定が遅すぎる証拠である。 意思決定自体に正解はなく、行った意思決定を正解にするのが大切。 会社の業績やカルチャーは、大小様々な意思決定の積み重ねの結果。 良い意思決定は早い意思決定であり、良い会社は意思決定が早い。
意見と人格は別 意見をぶつけること、率直なフィードバックを行うことは人格否定ではない。 意見の正しいぶつかり合いは建設的な議論を生み、率直なフィードバックは透明性と信頼を向上させる。 その結果、物事は正しい方向に進み、より良い成果につながる。話し手も受け手も、意見そのものに意識を向けよう。 このタスクの進⾏が遅れているのは、 管理⽅法に問題があるからではないか? この⼿法はリスクが⾼い。 良い解決策とはいえないのではないか? 私は無能だと⾔われている。 私の判断⼒が信⽤されていない。 進⾏管理の⽅法を⾒直すことを 求められている。 リスクを低減するための対策を 考えることが求められている
三方よしの視点で最適な行動を選ぶ 顧客の視点に立つことはもちろん、その行動が自社の利益につながっているか、また、産 業にとって良い影響を与えるものか考える。 例えば、顧客から患者のためにならない機能開発を要望された場合、 それに応えることは自社利益には繋がるかもしれないが、 顧客 産業のためにならないため、やるべきではない。 三⽅よし ⾃社 産業
顧客の要求の根っこをつかむ 顧客の要求の「根っこ」とは、顧客が口に出した問題や困っていることではなく、 その背景にある目的(なぜそれをやりたいか?)のこと。 それを把握するために適切な質問を繰り返し、 顧客の要求の「根っこ」に対して適切な提案をすることが重要。 例: 「xxxという機能を開発してほしい」という顧客の要望における課題は「 xxxができないこと」ではない。 「なぜその機能が必要なのですか?」「なぜその運用だと不十分なのですか?」など質問を重ね、 「yyyという目的があるから」まで聞き出すことが根っこをつかむということである。
目的から逆算して達成までのステップを決める 全ての仕事には目的が存在するが、その多くが達成までに時間を要する。 遠くの目的をがむしゃらに追いかけても誤った方向に進む恐れがあるため、 具体的な達成基準とそこまでのステップ・時期を逆算し、明確化することが必要。 そして、その延長線上で“今何をすべきか”を捉えよう。 ⽬ 新規事業成功の蓋然性を証明する 的 いつまでに何の数字を実現するか STEP 7 STEP 6 STEP 5 STEP 2 STEP 1 5ヶ⽉後までに1件デリバリーが済んでいてその全体像が⾒えている 4ヶ⽉後までに3件以上受注が発⽣している 3ヶ⽉後までに提供価値とニーズがハマり、セールスプロセスが進むことを証明できている STEP 4 STEP 3 6ヶ⽉後までに顧客に商品のデリバリーが3件済んでいること 2ヶ⽉後までに5件商談を⾏い、FBを踏まえて価値の磨き込みができている 1ヶ⽉後までに顕在層アプローチの⽅法が確⽴できている 来週までにはアプローチ開始できている ということは今は価値の整理と並⾏して資料やアプローチリストの準備をできていないといけない 以上のようなステップを決めることが重要。
隣の組織の業務プロセスを語れるようにする 他組織の業務プロセスを語れるほど他組織について解像度を高めることで、自組 織においても他組織においても適切な行動ができるようになる。 他組織の業務プロセスを語れるとは、 他組織 貢 献 ⾃組織 業務フローを知っているというだけではなく、 どの業務にどれだけの時間がかかっているか、 その過程で苦労するポイントはどこか、 解決に向けて動いていることなどを知ることである。 他組織 ⾃組織 その上で自組織としては、他組織の負荷を軽減するような工夫や、 他組織の成果に繋がるような情報提供をしよう。 全体最適
適応のために検査し、 検査のために透明性を上げる スピードこそ会社にとっての最大の競争優位性である。 スピードとは「どれだけ速くゴールに近づけるか」。 スピードを上げるのに必要なのが「どれだけ無駄なことをしないか」と 「どれだけすぐに軌道修正できるか」である。 これらを実現するためにはスクラムの3本柱である「透明性」 「検査」「適応」が重要。 問題があった時にすぐに軌道修正をしたり、 無駄を省略するといった「適応」を日々する必要があり、 「適応」のためには熱心かつ頻繁に現状の課題や 問題点を把握する「検査」が必要。 そして検査を行うために誰の目からも検査できる 「透明性」が不可欠。
誰かの言葉ではなく自分の言葉で語る 自らの言葉で語ることでチームにも自分にも納得感が生まれ、その納得感が行動の質と速度を最大化させる。 ビジョン、事業戦略、チーム方針、個人目標といった自らの関わる全てのことに言えることである。 なぜそれを目指すのか、それを達成するとどういう影響や成長があるのか、 達成する上でのボトルネックは何なのか、どのような動きをすれば達成に近づけるのか、 これらに自らの納得感を持たせ、語れるようになろう。 ビジョン 事業戦略 ‧チームにも⾃分⾃⾝にも納得感 チーム⽅針 ‧⾏動の質と速度を最⼤化 個⼈⽬標 etc.. ⾃分の⾔葉で語る
即レス 仕事における信頼関係は即レスによって生まれる。 メディカルフォースが定義する即レスとは「即反応を示す」こと。完璧な答えを即用意することではない。 人は不確実なことに不安を覚えるため、反応がないと発し手の不安は増し続け、結果的に不満に繋がる。 質問の答えがわからないこと、時間がなくて対応できないことであっても「確認して XX時までに返します」 「Yさんに聞いてください」「今日中の確認が難しいので明日午前中には返します」と具体的な反応を返して あげることはできるはず。 作業に集中するためにコミュニケーションをシャットアウトしたい場合は、その意思を示すことが重要。 社内に対しても、社外に対しても、円滑で気持ちの良いコミュニケーションで信頼関係を築こう。
全ての事項のネクストアクションを明確化する 「わからない」状態なのであれば、わかるようにするための一歩を考え設定すべきであるので、 ネクストアクションを明確にできないことはありえない。 ネクストアクションの生まれない議論はただの雑談である。 意見の衝突を恐れずに発言する。 議論の終わりには、何を・誰が・いつまでにやるのかを明確にした上でログを残し、行動につなげよう。