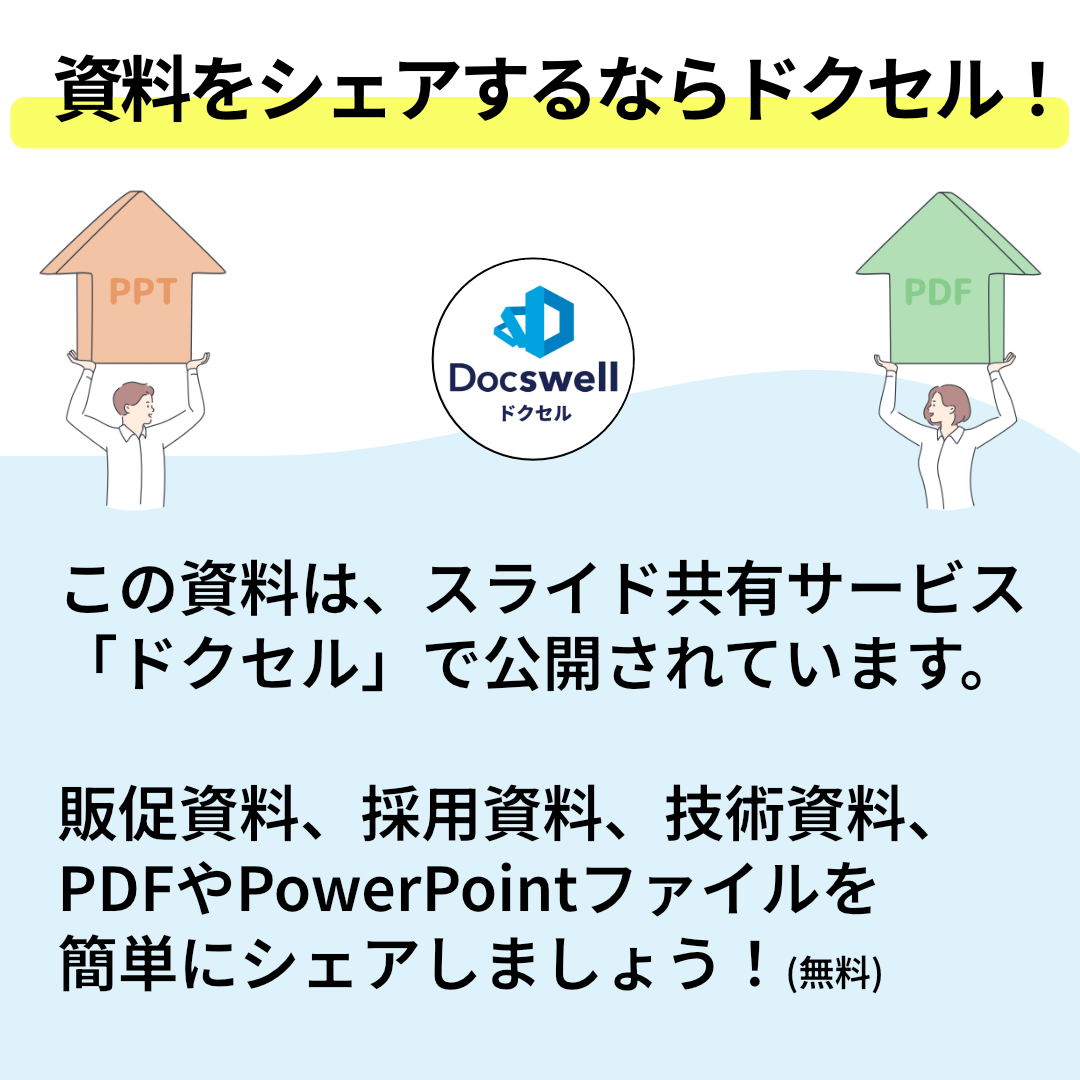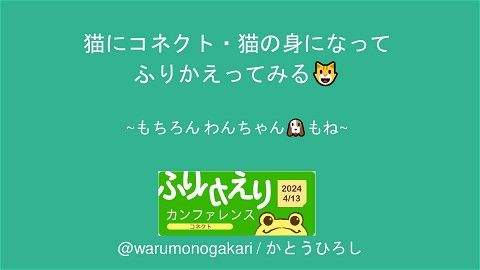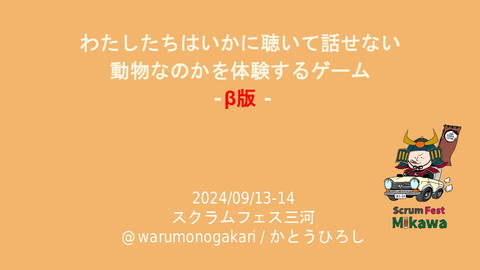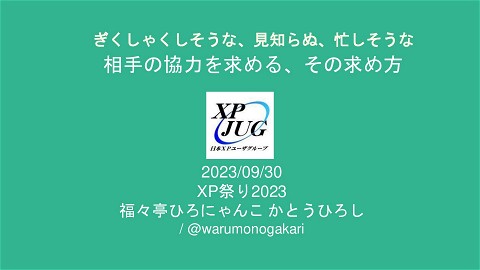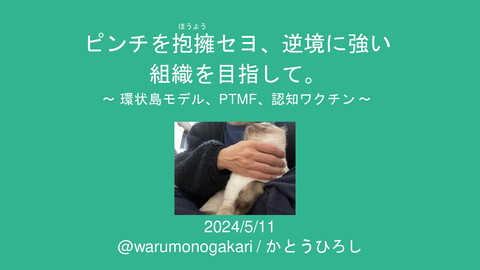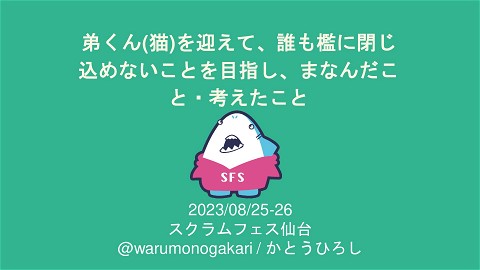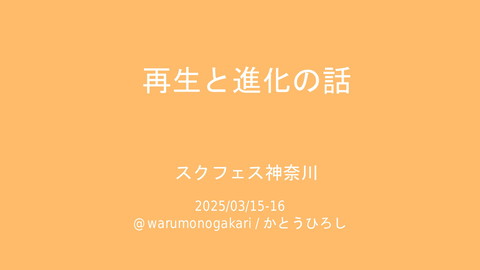2025XP・スクラム祭り_大部屋開発の再生と進化
182 Views
October 04, 25
スライド概要
2025/10/03-04で行われたXP祭り・スクラム祭りでお話した資料です。
妻の批判はアドバイスをモットーとする CSM/CSPO・ブリーフセラピスト。 世のため人のため、大変な逆境下でもめげず人間らしい知性を宿した組織とは何かを探究しています。 老後は猫の置物を作ったり、歴史モノをかいたりできればと思っています。書いている内容は所属・関連する組織とは一切関係ありません。
関連スライド
各ページのテキスト
大部屋開発の再生と進化 - - – 再生編 – わたしが見聞きし体験したウォーターフォール、XPと スクラム、そして大部屋開発と愛 XP祭り・スクラム祭り2025 2025/10/03-04 @warumonogakari / かとうひろし
今日お話しすること ⚫ アジャイル開発25年、その前の時代から今まで ベイトソンの学習階梯(かいてい)から見た各手法 の特徴 ⚫ 大部屋開発で体験した「愛に基づく協働」 ⚫ ⚫ 次の25年に向けて、一緒に考えたいこと 「まだ見えていない未来」への探求をご一緒に
今日この時間をどう過ごしたいか おおよそ35年 今までやってこれた感謝の気持ちを込めて恩送り コミュニティから学んで職場に還元した、ほんの数例 マシュマロチャレンジ Fearless Change ふりかえり実践会 できるだけ自分語りではない 現在そして未来に持ち運べる本質的な要素を 次世代のリーダーにお裾分け共有したい
ところで、おまえ誰よ? • 妻の批判はアドバイスをモットーとする CSM / CSPO /ブリーフセラ ピスト • エンジニアリングマネジャー / チームビルディング / ふりかえり / Management3.0 / 実践LeSS • 世のため人のため、大変な逆境下でもめげず人間らしい知性を宿した 組織とは何かを探究 簡単な履歴書: むかしむかしむかし(1991~2001) さる大きなSIer勤務 ・機械学習・文字認識の研究、OCR製品開発~技術移転 ・データ分析、ソフトウェアメトリクスに関する調査研究 むかしむかし(2001~2006) 関東・関西のさる複合機メーカ子会社勤務 ・複合機・オプションプリントコントローラーの試作~製品開発 ・共通化プラットフォームアーキテクト・開発リーダー及びマネージャ むかし(2006~) メーカ会社勤務 ・組み込み系 Network部ソフト設計リーダー ・Network部ソフト開発チーム エンジニアリングマネージャー ・Network部品質評価マネジャー いま(2025〜) 愛知県製造業支援 / スクフェス三河運営員
ところで、おまえ誰よ? • 妻の批判はアドバイスをモットーとする CSM / CSPO /ブリーフセラ ピスト • エンジニアリングマネジャー / チームビルディング / ふりかえり / Management3.0 / 実践LeSS • 世のため人のため、大変な逆境下でもめげず人間らしい知性を宿した 組織とは何かを探究 居場所 むかしむかしむかし(1991~2001) さる大きなSIer勤務 ・機械学習・文字認識の研究、OCR製品開発~技術移転 (SIer、研究屋) ・データ分析、ソフトウェアメトリクスに関する調査研究 IT業界 メーカ むかしむかし(2001~2006) (ソフト屋) 関東・関西のさる複合機メーカ子会社勤務 ・複合機・オプションプリントコントローラーの試作~製品開発 ・共通化プラットフォームアーキテクト・開発リーダー及びマネージャ メーカ(野中論文(The New New Product むかし(2006~) メーカ会社勤務 Development Game))にのっている、ソフト屋) ・組み込み系 Network部ソフト設計リーダー ・Network部ソフト開発チーム エンジニアリングマネージャー ・Network部品質評価マネジャー コミュニティ:スクフェス三河 いま(2025〜) 愛知県製造業支援 / スクフェス三河運営員
ここ35年で筆者 が体験した開発手法 90年代 2010年代 ▲Takeuchi,Nonaka The New New Product Development Game (1986年) 2000年代 ▲アジャイルソフトウェ ア開発宣言(2001年) ▲ W.W.Royce Managing the ▲ W.S.Humphrey Development of Large Software Managing the Software Systems(1987年) Process(1991年),CMM 2020年代 25年 ▲ 清水吉男 要求を仕様化 する技術・表現する技術 (2005年),XDDP 来年でアジャイルソフトウェア開発宣言から四半世紀 ウォーター → XP→ スクラム フォール → 大部屋開発 筆者:ありがたいことにいずれも経験
今日お話しすること ⚫ アジャイル開発25年、その前の時代から今まで ベイトソンの学習階梯(かいてい)から見た各手法 の特徴 ⚫ 大部屋開発で体験した「愛に基づく協働」 ⚫ ⚫ 次の25年に向けて、一緒に考えたいこと 「まだ見えていない未来」への探求をご一緒に
まず、ウォーターフォール W.W.Royce Managing the Development of Large Software Systems より Automotive SPICE https://www.ncos.co.jp/products/mobility/development/consulting/a_sp ice.htmlより
ウォーターフォール まあまあ、憎まれている 光と、人の渦が…と、溶けてゆく。…あ、あれは憎しみの光だー 機動戦士ガンダム第42話「宇宙要塞ア・バオア・クー」より
ウォーターフォールの本質的課題 複雑なソフトウェア開発を 複雑なまま捉えるのではなく 認知負荷を下げ 単純化した形でとらえる
ウォーターフォールの本質的課題 複雑なソフトウェア開発を 複雑なまま捉えるのではなく 認知負荷を下げ 単純化した形でとらえている ややもすると、バブル型理解 でとどまりがち 犬神家の一族(1976年)より よーし、わかった! でも、現実は複雑なまま...
ウォーターフォールの本質的課題 失敗パターン① 基本設計段階 「何をやるか」で迷走 ⚫ ⚫ ⚫ 要件が曖昧 ステークホルダーの合意が取 れず 設計方針が定まらない 要求・要件分析 基本設計 アーキテクチャ設計 総合テスト 結合テスト 詳細設計 コーディング 単体テスト 結果:時間の浪費、プロジェクト遅延の始まり
ウォーターフォールの本質的課題 失敗パターン② 統合・結合段階 実際には依存関係が複雑 要求・要件分析 一気に結合しようとして... ハマる 基本設計 アーキテクチャ設計 結合テスト 詳細設計 • 想定外の相互作用 • インターフェースの不整合 • パフォーマンス問題 総合テスト コーディング 単体テスト
ウォーターフォールの本質的課題 失敗パターン③ テスト工程 統合・結合での問題が表面化 さらなる遅延 炎上プロジェクトの完成 品質 vs スケジュール vs コスト 全てが破綻 要求・要件分析 基本設計 アーキテクチャ設計 総合テスト 結合テスト 詳細設計 コーディング 単体テスト
ウォーターフォールの本質的課題
炎上からの脱却 必死の対応策: • メンバー間距離短縮 → 毎日朝会・昼会・夕会 • 「一気に結合」で絡んだ糸をほぐし直し →少しずつ段階的に結合 • 仕様確定のため顧客確認・レビュー繰り返し → 早期のフィードバック 火消し部隊の皆さん
繰り返される過ちと炎上 悪循環
繰り返される過ちと炎上 機動戦士Gundam GQuuuuuuXより いつも。。彼プロジェクトを殺してしまう
過ちからの脱却へ これを最初からやればいいじゃん
過ちからの脱却へ これを最初からやればいいじゃん クライスラーC3 Project Kent.Beck, Chrysler goes to extremesより 実際にやってうまく行った
過ちからの脱却へ XP・スクラムの誕生 eXtremeの意味の中には、炎上中のeXtremeな対応 という意味もあったかと思う(知らんけど)
開発手法変遷のまとめ ウォーターフォール → 失敗 → 炎上対応 → アジャイル 25年経った今 XP・スクラムは確かに成果を上げた でも、何かが足りない...
今日お話しすること ⚫ アジャイル開発25年、その前の時代から今まで ベイトソンの学習階梯(かいてい)から見た各手法 の特徴 ⚫ 大部屋開発で体験した「愛に基づく協働」 ⚫ ⚫ 次の25年に向けて、一緒に考えたいこと 「まだ見えていない未来」への探求をご一緒に ここまで目標8分
ベイトソンの学習階梯 Gregory Bateson (1904-1980) 学習階梯(かいてい)の話 ⚫ 学習 I ⚫ 学習 II ⚫ 学習 III レベルが上がるほど困難
ベイトソン ゼロ学習:ゼロ学習の特徴は 反応の特定性にある。そこで は一つの決まった反応が正し かろうと間違っていようと、 修正されることはない。 学習Iとは:反応が一つに定ま る定まり方の変化、すなわち はじめの反応に代わる反応が、 所定の選択肢群の中から選び 取られる変化である。 学習IIとは:学習Iの進行プロセス 上の変化である。選択肢群そのも のが修正される変化や、経験の連 続体が区切られる、その区切り方 の変化がこれにあたる。 学習階梯(かいてい)の話 学習IIIとは:学習IIの進行プロ セスに生じる変化である。代 替可能な選択肢群がなる系そ のものが修正される変化がこ れに相当する。 後で例示で説明(一旦赤文字のみ) 学習IVとは:学習IIIに生じる変化、 ということになろうが、地球上に生 きる(生成体の)有機体がこのレベル の変化に行きつくことはないと思わ れる。ただ、進化のプロセスは、個 体発生のなかでIIIのレベルに到達す るような有機体を生み出しているわ けであるから、これに系統発生を組 み合わせた全体は、事実IVのレベル に踏み込んでいると言える。 この後すぐに例をあげて説明(一旦赤文字のみ)
ベイトソン 学習階梯 イルカの芸の例 ゼロ学習:芸を仕込もうとも、ただ首をかし げるのみ 学習I:特定の文脈において、試行錯誤を通じ て正しい反応を学ぶ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ジャンプ → 報酬 回転 → 報酬 尾びれで水面を叩く → 報酬 輪くぐり → 報酬 各行動は独立したものとして学習され、文脈に 応じた適切な反応を身につける 各行動をすると、各々報酬(魚)がもらえる
ベイトソン 学習階梯 イルカの芸の例 学習II:異なる文脈に共通するパターンを学習 し、「学習の仕方を学ぶ」 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ パターン認識:「昨日やった同じ行動では報酬がもら えない」 メタルールの把握:「新規性が評価される」という上 位ルール 学習方法の変化:既知行動の組み合わせや変形を試行 期待の調整:「何をすれば良いか」から「どうすれば 新しいか」へ イルカの発見:トレーナーや観客が求めているのは「特 定の行動」ではなく「新しい行動」である 「新しい行動」=既知行動の組み合わせや変形でよい
ベイトソン 学習階梯 イルカの芸の例 学習III:突然、完全にオリジナルな行動が爆発的に出現 「与えられた課題を解く」存在から、「新しい課題を 創造する」存在へと変化 創造的行動の具体例 ⚫ ⚫ ⚫ 水槽から飛び出し、1.8mの舗装を滑ってトレー ナーの足首をタッチ 逆立ち入水→正常姿勢→円泳ぎ→ジャンプの連 続技 水槽仕切りの飛び越え、未知の尾ひれ技など トレーナーの予想を超えた、訓練で作り出すことが不可能だ と思えることをやり出す
学習観の進化 学習III 新しい学習観 「芸を創る」 創造そのものを学習する。 学習システム自体を変革する能力。 トレーナーと観客にとっての 「イルカはこんなもの」という枠組みを 超える 観客・トレーナー:イルカはプールサイドに上がって走り回らない (という思い込み) イルカ:プールサイドにあがって子供達と走り回る(ことが実はできる) これが芸になるんだー(という発見)
学習観の進化 学習III 新しい学習観 「芸を創る」 創造そのものを学習する。 学習システム自体を変革する能力。 トレーナーと観客にとっての 「イルカはこんなもの」という枠組みを 超える 信頼関係の枠組は残る 「イルカはやさしい動物で危害を及ぼ さない」
ウォーターフォールと学習階梯 ウォーターフォール バブル理解でスタートしがち • 同じ失敗パターンの繰り返し • 根本的な改善に至らない • 炎上対応に追われる あ〜、大変だった。。 再びバブル理解に戻る 学習I はできても、学習IIまではなかなか至らない
XP・スクラムと学習階梯 XP・スクラム 学習I:継続的な修正(TDD、リフ ァクタリング) 学習II:レトロスペクティブ、各種 ふりかえり 炎上対応を最初からやる 透明性・検査・適応 Wikipedia エクストリーム・プログラミングより スクラムとは~要求の不確実さに対応するための フレームワーク オージス総研より https://www.ogis-ri.co.jp/column/agile/agilescrum01.html 厳しい現実への適応が可能になった
XP・スクラムの限界? でも、学習IIIまでは至りにくい • スプリントレトロスペクティブ • 各種ふりかえり •プロセス改善・継続的改善 適応はできるが... 創造そのものを学習するには「何か」が足りない
今日お話しすること ⚫ アジャイル開発25年、その前の時代から今まで ベイトソンの学習階梯(かいてい)から見た各手法 の特徴 ⚫ 大部屋開発で体験した「愛に基づく協働」 ⚫ ⚫ 次の25年に向けて、一緒に考えたいこと 「まだ見えていない未来」への探求をご一緒に ここまで目標25分
大部屋開発のはじまり 中心メンバの招集 トップの説明 何がどうなっていてどこに持っ ていくと売れるのか、概略・重点 ポイントの共有 例)プリンタ • サイズ 小さいKIOSKの売り場では • 紙の厚さ さる国の医療レシートは。。 • 欧州公共機関には置いてもらうにはやっ ぱり省エネ
大部屋開発のはじまり 中心メンバの招集 大体課長かちょっと下 最初は3人〜6人 老若男女いろいろ(元気でちょっと若め) 多種多様なメンバ メカ代表 搬送担当 自転車乗り 商品企画 帰国子女 子育て大変 ハード代表 基板担当 電子工作大好き ソフト代表 Net担当 時代劇オタク
大部屋開発のはじまり 適切なPower構造 • 外部環境の認知 • トップの健全な危機意識 • 現場への信頼 中心メンバの招集 トップの説明 たのむよ 部長さん方がガ タガタ言ってき たらふってくれ 「現場に任せたいこと」と「トップがやること」の なんとなくの共通理解の形成
苦境の階層的共有 中心メンバの当初 ⚫ より大きい組織の代表として責務 例)ソフトGの一部の代表→ソフト全体代表 今まで持っている自分の知識や経験では 受け止めきれない →必然的に周囲の協力が必要 ⚫ 多種多様なメンバというと聞こえはよいが。。 メンバ同士「オマエは何を言っているのダ」 帰国子女 x 英語ダメ男、体育会系 x 文化系時代劇オタク。。 話す言葉の速度、調子、関心事。。 →全てが違う、一言一言が噛み合わない
苦境の階層的共有 中心メンバの理解 とても向き合いにくい問題 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 誰がどれだけやれるのか、やるのかわからない けど、問題はそこにある たまたまお互い自分たちが拾ってしまっただけ トップの苦境も聞かされている 重要な任務を任されている実感 たのむ よ ガタガタ言 ってきたら ふってくれ 「ああ、(お互い)大変だよな」 みんながみんな、それぞれの苦境に立つ
毎週ミーティング 毎週、起こったことからふりかえって、お金を計算して、 宿題を設定して、来週までにどうしようかと相談 安井義博 「ブラザーの再生と進化」を参考 ときには合宿、必要に応じ新メンバを巻き込む
段階的な巻き込みプロセス 少人数 → 部門横断 → 全社展開 ⚫ ⚫ ⚫ 最初:商品企画、メカ、ハード、ソフト ↓ 営業部門、品証部門、生産技術、カスタマー部門 ↓ 関係する全部門 スケールするのは、多種多様な「人種」 (言葉や思考、価値観が異なる)
で、TypeC になる 中心となるメンバは企画の最初から生産3ヶ月まで見届け 最後の最後まであきらめず何かあれば納品先の倉庫まで行ってリワーク
新メンバ巻き込み時の現実 ミーティングの空気は張り詰めて いる(というか、怒られる) • 過去のプロジェクトで助け合え なかった恨み • 不信感の持ち込み • 緊張状態 きれいごとではない現実
感情的衝突 新メンバからの強い難詰 中心メンバ: 「いろんな感情がわき上がる」 「反論したくなる」 でも... 重要な任務を任されている責任 感から 「聴く」ことを憶える
転換の瞬間 (1)赦し 「聴く」を優先 過去の行動で悪かった点について 「あのときはゴメン」(軽い感じで) 「すまなかった」(息を吐くように) 赦しを乞う
転換の瞬間 (2)ペース変化 会話の質的変化 早口のやりとり(紛糾) ↓ ゆっくりのペース ↓ 沈黙も出てくる 1時間〜90分のミーティングで 10分〜15分くらいで変化
転換の瞬間 (3)沈黙を聴く 会話の質的変化 沈黙の出現 「沈黙を聴く」ことの重要性 • • • 相互理解が深まる瞬間の共有 単なる無音ではない 意味のある静寂
愛?の出現 場の質的変化 • 雰囲気が明るくなった感じ • エネルギーが上がってくる • 場が暖かくなる 身体で感じる変化
関係性の修復?再構築? ミーティング終了後 対立していた当事者が 穏やかに雑談をしている 周囲も「よかった」と感じて 場が暖かくなる
心の底からの理解 「聴く」ことで心の底からの理解 をする みんながみんながそれぞれ お互い苦境に立つことを 心の底から感じ始めたとき 「じゃ、どうしていこう?」 たの むよ いつしか「わたし(たち)はこんなもの」の枠を超え出す (ちょうどプールサイドを歩き出す のように。。)
ずっとひっかかっていた謎のプロセス 話の通じない同士が集まる ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 向き合いにくい問題をまず「聴く」 強い感情の表現と相互やりとり 身体的リラクゼーション 和解?の瞬間としての「愛」 関係性の修復?再構築? 心の底からの理解 さらに話の通じない同士が集まって増える(怒られる)・・ (以下、繰り返す) これって一体なんなんだろう?
オープンダイアローグに出会う オープンダイアローグ 複雑なメンタルな危機を多種多様な対話で解消する うまくいった場合のプロセス ⚫ モノローグからダイアローグへ ⚫ 強い感情の表現と相互調整 ⚫ 身体的リラクゼーション ⚫ 治癒の瞬間としての「愛」 仮説:オープンダイアローグ ≈ 大部屋開発 危機の熔解の瞬間を、思い込みの熔解・和解の瞬間 と置き換えれば一致 (大部屋開発の場合、毎回そうではない。炎上のままも)
愛の定義 〜オープンダイアローグより〜 • 優しさ、同感、思いやり、育み • 安心感、心強さ • 深い情動的つながり • 相互の情動的共鳴 (mutual emotional attunement) ヤーコ・セイックラ フィンランドユヴァスキュラ大学心理学部名誉教授 臨床心理士。家族療法士 愛はダイアロジカルな場で発生する Seikkula & Trimble (2005) "Healing Elements of Therapeutic Conversation: Dialogue as an Embodiment of Love”
トップ たの むよ は何をしていた? 結果とか成果物ではなく、暖かく愛情を持って 炎上熱量と巻き込み状況で様子をうかがっていたらしい 腹心を通してたまに助言? 「まあまあまあ、もう少し様子をみましょ、もう少し様子をみましょ。。」
野中先生のcontrol by love “The New New Product Development Game”より さりげない管理(subtle control) 自己管理、ピアプレッシャーによる管理 そして愛による管理(control by love) ここでも愛が。。 大部屋開発で(たまに)生まれていた状態 ロジックや力による統制ではない 愛に基づく協働ではなかったか
今日お話しすること ⚫ アジャイル開発25年、その前の時代から今まで ベイトソンの学習階梯(かいてい)から見た各手法 の特徴 ⚫ 大部屋開発で体験した「愛に基づく協働」 ⚫ ⚫ 次の25年に向けて、一緒に考えたいこと 「まだ見えていない未来」への探求をご一緒に
もちろん、持ち運べないことがある 昭和な時代ならではで パワーハラスメント(力関係による決定) ⚫ 排他的決定プロセス ⚫ タバコ部屋での決定 ⚫ 飲み会での当事者不在の意思決定 ⚫ ハードワーク(長時間労働依存症) ⚫ 法令・規則・ルールの精神の(ややもすると)否定 ⚫
時代を超えて持ち運べることも 愛に基づく協働 たまたま拾ってしまった、向き合いにくい問題を拾う ピンチをチャンスと捉え直すチームワーク モノローグからダイアローグへの転換プロセス ⚫ 苦境の階層的共有と相互理解 ⚫ 「沈黙を聴く」場づくり ⚫ スケールする多種多様な「専門家」 「専門家」の協働による問題解決 リモートワーク時代でも コンプライアンス重視でも AI(LLM)の出現下でも
まだ見えていない未来 アジャイル25年の成果を踏まえた次世代開発手法 まだ見えていない でも... イノベーション創出には学習IIIが不可欠 学習IIIには「愛に基づく協働」がきっと必要 たのむよ
まだ見えていない未来 「愛に基づく協働(control by love)」状態の実現を 一緒に考え 一緒に実践していきませんか そのさきに 次の25年があるんじゃないか 恩送りの想いを込めて
これで今日の話はおしまい ありがとうございました