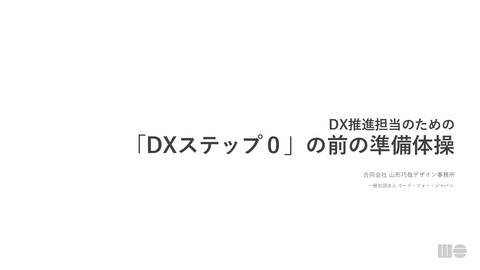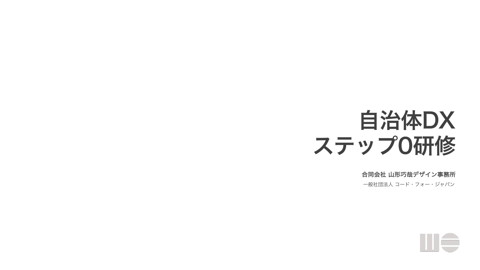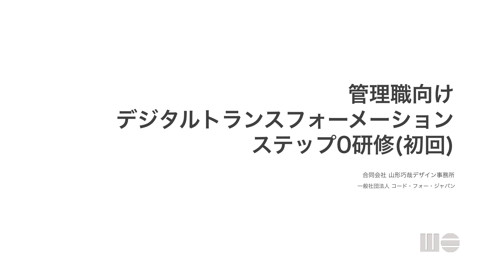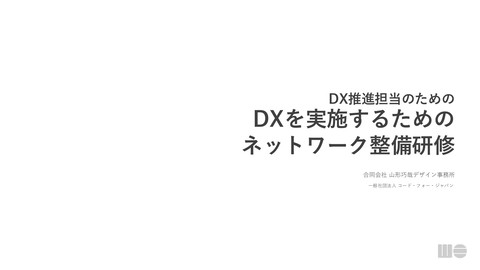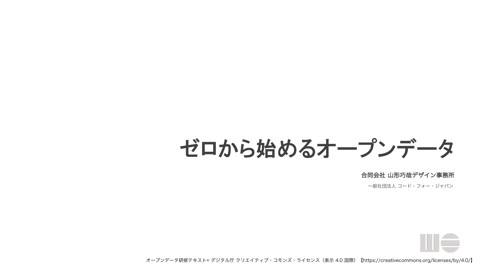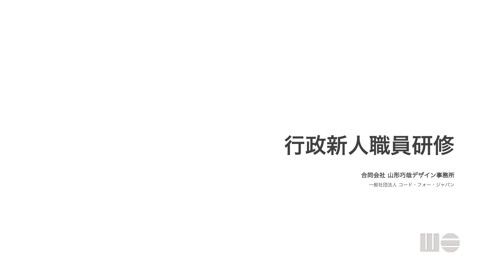2025JIAM小規模でもできるDXのコツ
8.7K Views
August 30, 25
スライド概要
## 「小規模でもできるDXのコツ」要約
### 研修の目的と対象
* デジタル化と人口構造の変化を踏まえ、自治体業務と住民サービスを刷新する共通認識を持つことが目的。
* 対象は自治体DX推進担当者や管理職。異動でDX担当になったばかりの人、庁内の機運を高めたい人向け。
---
### DXの基本的な考え方
* **デジタル化は目的ではなく、まちづくりの手段。**
* DX = 業務プロセスや文化、住民体験を根本的に変革。
* 「デジタル=ITの社会融合」。AI・IoT・データ連携などを含め社会全体を変革。
---
### 社会変化とDXの必要性
* スマホ普及により生活は大きく変化、行政は遅れが目立つ。
* **Society5.0(人間中心の超スマート社会)** 実現にはDXが不可欠。
* 背景課題:高齢化・人口減少。2040年に生産年齢人口が半減し、人海戦術が通用しなくなる。
---
### 自治体DX推進計画
* **時限DX**(標準化・オンライン化・BPR等の必須対応)
* **継続DX**(オープンデータ活用、AI・RPA導入、テレワーク推進等)
* 計画と進捗管理が重要。補助金などの活用にもつながる。
---
### 課題と対応
* 多くの自治体の課題は「財源不足」と「人材不足」。
* 実際は「本当に足りない」と「変わりたくない」の両面が混在。
* 重要なのは **整理と行動**。小さなところから始めること。
---
### ゴールとロードマップ
* **2050年**:持続可能で幸福な社会。
* **2040年**:超高齢化社会を乗り越えることが最大課題。
* **2030年**:そのための準備期間として制度・サービス・インフラを刷新。
#### 行動ステップ例
1. 半年以内:庁内で議論・スケジュール可視化
2. 1年以内:変革案の提案・概念実証
3. 2年以内:導入・検証・改変
---
### 成功のポイント
* \*\*「忙しい」「お金がない」「うちには無理」\*\*をやめる。
* クラウドや生成AIなど新技術を積極的に活用。
* モチベーションを高める設備投資(良いPC・クラウド環境)が効果的。
* 小規模自治体ほど柔軟にDXを進めやすい。
---
### 結論
* DXは「街に住み続けるための手段」。
* 地方自治の目的は住民の福祉の増進。デジタルはその実現のツール。
* オープンな気持ちで、みんなで協力してDXを進めることが必要。
関連スライド
各ページのテキスト
小規模でもできるDXのコツ JIAM Day1 山形巧哉 合同会社 山形巧哉デザイン事務所 一般社団法人 Code for Japan
Hello, Iʼam 北海道、函館近郊に位置する森町という小さな町で公共領域の空間の 研究調査を行っている。行政や教育現場での実務経験を数多く持ち 比較的小規模な市町村での公共政策を一緒に考えていきます。 座右の銘は「まあすわりなよ」 合同会社 山形巧哉デザイン事務所 代表 北海道森町 政策参与 (一社) Code for Japan (株)HARP エグゼグティブアドバイザー 山形巧哉 やまがたたくや (一社) 北海道オープンデータ推進協議会 理事 / (一社) モリラボ 理事 (一社) データクレイドル (法人会員) 国際大学GLOCOM 客員研究員 / 公立はこだて未来大学 アソシエイト デジタル庁 オープンデータ伝道師 幹事
私の考え方 • 小さな街の行政出身なので、言語がより住民に近い視点で、かつ、庁内政治も理論より寝技が多かったです。 その上で今は理論も重要だなと感じています。 奉職 【 1998 】 はこだて未来大学と クライアント仮想化に関 庁内クラウド する実証実験 構築・運用開始 【 2011 】 オープンデータ公開 【 2013-4 】 町内学校 サーバーレス フルクラウド化 【 2019 】 ・・・ 【 2010 】 庁内システムの 仮想化を開始 【 2012 】 町内学校 シンクライアント化 LOD実証実験 【 2021 】 GIGAスクール導入 【 2018 】 ひぐまっぷの実証実験 森町退職 総務省ICT地域活性化大賞優秀賞受賞 森町復帰 【 2025 】
今回の総合研修について ー 目的とターゲット 目的 • 本講義は、受講者の皆さんが、加速するデジタル化と人口構造変化を踏まえ、自治体業務と住民サービスを抜本 的に刷新し、未来志向で組織全体が“今すぐ動き出す”共通認識を持つ契機とすることを目的とします。 ターゲット • 自治体DXを推進していく推進課の管理職や担当者向けに構成されています。 • 異動等で推進担当になったばかりという方 • 推進していく上で役所内の機運情勢を高めるための納得感を自身が持てていない • DX担当者を育成するためにどう話をしていけば良いかわからない
今回の総合研修について ー 研修の目標 目標 • 受講後には皆さんがデジタルトランスフォーメーション実現に向け、庁内で課題と方向性を共有し、計画の中長 期的視点と、すぐにでも着手できる短期アクションプランを作成できるようになることを目標にしています。 • 共通認識の形成を説明できる • 具体的なアクションの可視化ができる • 「まずは試す」マインドの定着
今回の総合研修について ー ワークについて 講義の中ではワークも入ります • • ワーク中は • 年功序列は一旦横においてください • 相手の意見を否定・批判しない • 質より量 • 自由な発想で変なアイデアでもOK • 他の人のアイデアに乗っかる 意見を言う時は端的に • 結論:〇〇だと思う • 理由:なぜならば • 具体:たとえば • 結論:だから〇〇だと思う
本日一番大事なこと オープンな気持ちで、みんなで、たくさん話、笑いましょう!! 普段声を出すのが苦手だなって方も、今日は自分の中で今年一番しゃべったなというくらい話してください。
午前講義
講義について ー 話の流れ • デジタルと地域社会 • 社会がデジタル変革する理由 • では、我々はどうするのが良いか • 事例紹介 • まとめ
先に話の結論 私たちは デジタル化が目的では無く まちづくりが目的 街に住み続けるためにデジタル「も」 みんなでどんどん活用しましょう!
デジタルと地域社会
わたしたちの日常 • 私たちは日常的に、多くのデジタルサービスを利用して生活しています • あまりにもスムーズに移行してきていますが、昭和・平成の時代から比べると大幅に生活スタイルが変わってい るはずです 映画やテレビ番組 オンラインショッピング ソーシャルメディア(SNS) エンターテイメント 購買 コミュニケーション ストリーミングサービスによって根 本的に変わった 対面購買の基本概念が大幅に変化 個人間はもちろん、ブランドや企業 が顧客と直接コミュニケーションを 取る手段も変化
これらサービスはすべてスマホで完結 大幅にサービスの概念が変わっている デジタル・トランスフォーメーション 世の中的には実施され、実装されている
では、そもそもデジタルトランスフォーメーションとはなんであるか • 一般的にDXとは… • 業務プロセス・文化・顧客体験を根本から変えること • 従来の業務モデルや戦略を再構築し、 効率化・価値創造し、顧客満足度や競争力を向上させること ↑確かに変わったが・・・なんとも説明しづらい・・・ ので、デジタルを横に置いといて トランスフォーメーションの例を確認しましょう
狩猟社会 農耕社会 工業社会 情報社会 超スマート 社会 Society1.0 Society2.0 Society3.0 Society4.0 Society5.0 縄文時代 江戸時代 明治・大正・昭和 平成 令和 車輪 エンジン IT 文明は常に「なにか」をきっかけにトランスフォーメーションしてきた 今回は『デジタル』を使ったトランスフォーメーション (だが、ITとデジタルは何が違う?) デジタル
情報社会 超スマート 社会 Society4.0 Society5.0 平成 令和 デジタル IT+ AI・IoT・データ連携・DXなどによるテクノロジー の社会融合 デジタル ITの社会融合 現代の「デジタル」とは、包括的な技術とその 応用を表すためのものであり、テクノロジー自 体だけでなく、それが社会に与える影響を指す 用語となっている
工業社会 情報社会 Society3.0 Society4.0 明治・大正・昭和 平成 『寿司』も「大将に注文」から「寿司ロボット」や「回転配膳」「タブレット注文」に変わり・・・
ここまで大幅に世の中が変わったのは とある、要因があると僕は考えています
これは僕がDXの話をするようになった 2016年当時の資料 (東京の地下鉄) 2006年 2016年 この2枚にどんな差があると思いますか? 左 Business Subway by Mike Murry Follow is licensed under CC BY-SA 2.0 右File:電車内スマホ 2016 (30334955280).jpg by tilex is licensed under CC BY 2.0
みんなスマホ 9年前の時点ですらこうだった
2025年6月に行った紫波町までの電車内 東京だけじゃ無い。みんなスマホ
これまでのネット手段の変異 2005 人生初スマホ Gmailが出たり mixiをはじめたり 2000 初めてネットで買い物 定額接続があたりまえに 1999 携帯電話でネットが (すこし)見れるように ADSLも出始める 1998 インターネットを始めた頃 ネットはまだ珍しい存在 ダイヤルアップからISDNへ 情報通信白書 © 総務省 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 4.0 国際)
2005 人生初スマホ Gmailが出たり mixiをはじめたり 2000 初めてネットで買い物 定額接続があたりまえに ネットは「職場か家で」 1999 携帯電話でネットが (すこし)見れるように ADSLも出始める ネットショッピングする人も 増えたよねという印象 1998 インターネットを始めた頃 ネットはまだ珍しい存在 ダイヤルアップからISDNへ 情報通信白書 © 総務省 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 4.0 国際)
2005 人生初スマホ Gmailが出たり mixiをはじめたり 2007 iPhone登場 2000 初めてネットで買い物 定額接続があたりまえに 1999 携帯電話でネットが (すこし)見れるように ADSLも出始める ネットは一気にスマホ時代へ (国内ではいわゆる3Gサービスもスタート) 1998 インターネットを始めた頃 ネットはまだ珍しい存在 ダイヤルアップからISDNへ 情報通信白書 © 総務省 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 4.0 国際)
スマホ保有率 2011年 29.3% 2012年 49.5% 2013年 62.6% 2014年 64.2% 2015年 72.0% 5年間で約43%増 3.11後、スマホの普及でLINE やSNS普及率も一気に向上。 スマホが当たり前の世界に 情報通信白書 © 総務省 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 4.0 国際)
改めて写真でみると味わい深い 2006年から2016年の10年は大進化 2006年 2016年 2025年 2016年から2025ではあまり変わらないようにも見えるが・・・ スマホが当たり前になっただけで世の中変わってない??
時代はもっと変わった スマホ以外の スマートデバイスも当たり前に 情報通信白書 © 総務省 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 4.0 国際)
世の中のサービスも『デジタルありき』になった
こうしてみると普段から利用したり目にしているものばかり 世の中はこのように変わったが 我々は、我々の仕事を「ちゃんと」変えられているのか
行政DXの現在地
例えば役所で文書を作成する 例えば役所の広報活動 工業社会 情報社会 超スマート 社会 工業社会 情報社会 超スマート 社会 Society3.0 Society4.0 Society5.0 Society3.0 Society4.0 Society5.0 明治・大正・昭和 平成 令和 明治・大正・昭和 平成 令和 タイプライター パソコン 生成AI マスメディア ネット マルチチャンネル CPU データ CPU データ ワンソース・マルチユース もちろんこれらもDXだが各論である。区市町村としては総論を把握する必要がある
自治体DXとは何か デジタル社会形成基本法 により作成された デジタル社会の実現に向けた重点計画 を自治体として実現する取り組み これはなんのため? ※デジタル・ガバメント実行計画は2021年12月に廃止
デジタル庁 https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program
自治体DXとは何か 重点計画において特に自治体が重点的に取り組む べき事項を整理、具体的に示したもの 自治体DX推進計画 推進計画に示される取組みは、スケジュール感な どで2つに分類し眺めると面白い 時限と継続 • 各団体においてDXを進める前提となる考え方 • BPR の取組の徹底 • 自治体におけるシステム整備の考え方 • オープンデータの推進・官民データ活用の推進 • 自治体DXの重点取組事項 • 自治体フロントヤード改革の推進 • 自治体の情報システムの標準化・共通化 • 公金収納における eL-QR の活用 • マイナンバーカードの普及促進・利用の推進 • セキュリティ対策の徹底 • 自治体の AI・RPA の利用推進 • テレワークの推進 • 自治体DXの取組とあわせて取り組むデジタル社会の実現に向けた取組 • デジタル実装の取組の推進・地域社会のデジタル化 • デジタルデバイド対策 • デジタル原則を踏まえた条例等の規制の点検・見直し
自治体DXとは何か 時限DXには具体的な「手順書」が存在する • 全体手順 • • 推進計画 推進手順書 標準化共通化手順書 • • 自治体におけるDXの実施のための手順 自治体の情報システムの標準化・共通化 オンライン化手順書 • 自治体フロントヤード改革の推進 • セキュリティ対策の徹底 • デジタル原則を踏まえた条例等の規制の点検・見直し • BPR の取組の徹底 標準化共通 化手順書 全体手順書 (地方公共団体 情報システム の標準化に関 する法律) オンライン 化手順書 (デジタル手続 法)
自治体DXとは何か 特に時限DXはスケジュール感がしっかり出ているので、庁内実施スケジュールを定め進捗管理をする。計画を立て、 進捗管理を行うことで現状の把握も行いやすくなり、また、良い補助メニュー等が出た時に瞬発力が生まれる。 スケジュール管理は2種類必要。俯瞰して見て考えられるものと各論の作業タスク
自治体DXとは何か 2020年12月に自治体DX推進計画が策定されてから、どの団体でもやらなければならない時限DXを着実に進めて いると、現段階で出来上がっている成果の順序は以下のとおりである。 • 自治体DX推進計画の作成 • オンライン申請拡充や窓口業務改革 • • BPRの実施も含む 条例・規則の改正 • 押印見直しも含む • 自治体情報システムの標準化・共通化に関する何らかの取り組み • セキュリティポリシーの見直しやネットワークの再設計に関する取り組み 区市町村においては、現段階で自団体の進捗と見比べ、状況判断することをお勧めしている。
これらが理解できていれば 自治体DXはカンタン!
休憩(15分)
ロジックをしっかりと組む
2020 問題・課題の整理 2020年総務省実施のアンケートも、株式会社グラ ファーが2024年11月に公表した行政デジタル化実態調 査レポートでも、自治体の課題は以下の2点が多い。 • 財源不足 • 人材不足 総務省 令和3年情報通信白書より引用 2024 いつまでも課題が変わっていない 引用: グラファー 行政デジタル化実態調査レポート https://graffer.jp/govtech/articles/govtech-digitalization-report-2024
問題・課題の整理 財源不足 人材不足 今更、言ってもどうしようもない。 やれる範囲でやるしかない。 そもそも人は足りない。 また「デジタル人材 is 誰?」の定義 をしないと議論にならない。 (仮設) 不足というのは ”本当に足りない”と ”実は変わりたく無い”が 交差しているのでは無いか 総務省デジタル人材の育成ガイドブックも参照 やるべきことは整理。人が足りないから整理ができないなどを言い続けるとなにもできない。また高度なBPRなど から始める必要もない。 本当に足りないのか、変わりたく無い理由を言ってしまってるだけなのか わかる範囲から整理を開始する
問題・課題の整理 本当に足りないが判明した場合 実は変わりたく無いが判明した場合 なんとかしてください なんとかできる可能性があります 外部からできることはほぼありません。 役所内でなんとかするしかありません。 根強いアナログ主義や、えもいわれぬ不安感が要因の 場合は、職員のモチベーションやマインドを少し上向 きにするだけで変わる可能性があります。
なぜ世の中のサービスは変わった(っている途中)のか 社会はなぜデジタル化を進めるのか 数値化・可視化できるビジネスケースを根拠に、 投資判断とロードマップを策定していると推測 される l 顧客体験の向上 l コスト/業務効率化効果 l データ活用によるビジネス価値最大化 では、役所はどうなっているのか 社会の変化と共に確認してみる
引用: Wayback Machine https://web.archive.org/web/20011113233431/http://www.yahoo.co.jp/ 引用: Wayback Machine https://web.archive.org/web/20110203020759/http://www.yahoo.co.jp/ 引用: Yahoo!Japan 主流ビジネスOS:Windows XP 主流ビジネスOS: Windows 7 主流ビジネスOS: Windows11 • • • 2001年(24年前) 2009年(16年前) 2021年(4年前) • 一般家庭でもネットが普及 • ネットが当たり前に • スマホが主流 • 多くの人がパソコンを購入 • スマホやSNSの登場 • キャッシュレス決済普及 役所 役所 役所 • ワープロからパソコンへ • 神エクセル氾濫 • • 神エクセル降臨 • • 電子メールの普及 インターネット利用前提の調 査の増加 ・・・ 社会全体は着実に変化しているが、行政サービスや内部業務はこの20年進化していない(新型コロナウ イルス感染症対策により一定進んだが、それでも?)
コンセプトとして『Society5.0』 デジタルと現実が融合した 経済発展と社会課題解決を同時に実現する “人間中心の超スマート社会”を目指す カーボンニュートラルやムーンショット計画など、Society5.0の担保条件が2050年 を目標年としていることから、2050年がしばしばセットで語られる 令和3年3月26日に閣議決定された第6期科学技術・イノベーション 基本計画では、我が国が目指すべきSociety 5.0の未来社会像を 「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するととも に、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」と 表現しています。 この社会を目指す背景として 高齢化/人口減少問題も大きい 引用: 内閣府 https://www8.cao.go.jp/cstp/society5̲0/
高齢化/人口減少問題といえば・・・2040年 • 団塊ジュニアが65に達し高齢人口のピーク • 生産年齢人口が現在の半数に • 困ったら人海戦術というこれまでの常識が通用しない 率先したデジタル活用が必須 民間サービスの変化は 2040年に向けたサービス設計 であるとも言える 出典: RESAS(https://resas.go.jp/population-composition)
2040年を目指すのは良い これでは現時点の『高齢者』が 置いてきぼりになっているのでは? 確かにその懸念は残るのも事実 ではあるが・・・?
70歳以上 2,007.8万人 2,889.2万人 近年日本の 人口分布 7,395.2万人 70歳未満 9,546.2万人 1,417.3万人 出典:人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)-全国:年齢(各歳)、男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級)、男女別人口
ネット利用 可能な人数 70歳未満 70歳以上 8,499.0万人 1,547.2万人 出典:2024 総務省 情報通信白書
さらに今はスマホの時代 LINEヤフー社の調査によると • 「スマホ」でのインターネット利用者は、15〜 79歳全体で90%。「PC」での利用者は36%と なった。 • 15〜79歳全体の構成比としては前回調査同様 「スマホのみ」の利用者が最多で55%となった。 • 「スマホとPC」の併用は35%、PCのみの利用 者は1%となった。 多くの人々がスマホでネットを利用中なので、何らかの デジタルサービスを利用できそう 引用:LY Corporation 【LINEヤフー】〈調査報告〉インターネットの利用環境 定点調査(2024年下期)https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/016997/
総務省 2025年8月27日公表
現在のニーズにも 実は 合致している
まずデジタル変革における我々のゴールを逆算してみる • 2050年に幸せに暮らしていたい • • 『幸せな地域、豊かな環境、平和な世界』であるこ とを見据えたい(があまりにも先で抽象的だ) だが、先に訪れるのは2040年「超高齢化社会」 • 2040だけでは無く、そこから数年ある高齢者と生産 年齢人口の大きな差も問題 • この時期には私たちが生産年齢世代にサポートを 受け始める時代に? 誰がやるでは無くみんなでやる必要性 私たちは、 (未来の人々だけではなく)私たちのために 2040年に向けた準備を行う必要がある なん の いつ 準備を まで に?
だが2040年は遠い。当面は2030年を目標にしてみると良い(だろう) • 2040年と言っても想定しきれないのも確か。もう少し 手前の目標設定をしてみてはいかがか。 • 明確なドキュメントとしてまとめられていないが 「2030年ごろに顕在化する社会・経済の構造的課題」 としての2030年が多く語られる。 • • 2030年展望と改革 タスクフォース報告書 • 経済産業省 「未来人材ビジョン」 2050 技術変革がもたら す明るい未来 2040 超高齢化社会問題 解決のアプローチ 時間軸としてもちょうど良い 2030 2040年のインパクトを乗り越えるために 2030年からトップスピードで動ける準備 『制度・サービス・インフラ・業務手法』 全てを2030までに刷新・整備する= 準備 問題解決に向けた 準備期間 2025
じゅん-び【準備】 物事をする前に、あらかじめ必要なものを そろえたり態勢を整えたりして用意をする こと 準備とは、2030年時点ではさまざまなことが実装されているという意味です
準備のために具体的アクションプラン・短中期ロードマップをつくってみる • 計画作りが目的化してはいけないが、組織内の目線 を合せのため何らか指標はあった方が「やりやす い」だろう • • 例: • Step1 (半年以内):今日の話をふまえてマ ネージャー間の話し合い。スケジュールの可 視化 • Step2 (1年以内):良い変革案を出し合う。そ して概念実証を繰り返す。 • Step3 (2年以内):導入、効果検証、改変、さ らなる準備へ 一気に5年分を細かく作るのではなく、抽象的に、た だし、まずは目先でやることの解像度を上げていく ことも大事。 なによりも大切なのは 『行動に移す』こと
準備には内部事務も含まれる。しっかりと目をむけましょう ペーパーレス AI コミュニケーション 紙はすでに軽い確認のために 存在するもので、全てデータ ファーストになっている ChatGPTなど、生成AIの登場 で大幅に社会が変わりつつある チャットやクラウドの登場で 大幅に業務方法が変わった 時代的には『今』こうなっています
業務インフラの整備もかなり重要 • セキュリティにも配慮 • 庁内NWのモダン化を進めるべく、多くの情報を取得しておくのが大切 • α・βという枠だけでは無く、どうすれば庁内のデータが守られるのかを議論する必要あり 衆議院地方自治法の一部を改正する法律案より引用 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb̲gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309031.htm Google Cloud 鹿児島県肝付町事例より引用 https://cloud.google.com/blog/ja/topics/customers/kimotsuki-town-goes-full-cloud-for-secure-operations 日本マイクロソフト 北海道伊達市事例より引用 https://ms-f1-sites-03-ea.azurewebsites.net/en-us/story/1553645444005667592-date-city-hokkaido-nationalgovernment-microsoft-365-ja-japan
整備には思い切りが大事 実はクラウドはもう常識の範囲内であり、クラウドに加えて・・・ • • ちゃんと良いパソコンを買う • かっこいいパソコン(一番大事)=モチベーションアップ • 持ち運びしやすいラップトップ型(13-15インチ) • 行けるならSIM入り 外付けの大きなディスプレイも買う 結果としてPCの性能差は作業効率の差につながる。繋がらないというならば、他の業務に無駄が「多すぎる」とい う証左である。
整備には思い切りが大事 役所外がどうなっているかも見よう • 役所の常識が社会の常識とは限らない • • 企業がどのような整備、職員教育を実施しているかインタビューしてみるのも大切。また自分の目で見てみ る。 小さな自治体ほど最先端に行きやすい • 多くなればそれだけ数が必要になる。クラウドなどはライセンスフィーがかかるため小さいほうが導入しや すいメリットもある
弓道は丹田の意識 BMXも丹田の意識 基礎は 軸を立てる土台である
蛇足ですが もし、庁舎内に 「DX用語がわからない」 という方がいたら おすすめの本です
まとめ
本日話したこと • デジタルと地域社会 • • 社会がデジタル変革する理由 • • 我々の生活は変化しており、デジタル技術はより身近である 幸せな2050年を迎えるために、まずは2040年の超高齢化社会のインパクトを乗り越える必然。もちろん時 代の変化に伴うニーズもある。 では、我々はどうするのが良いか • 2040年のインパクトを一気に乗り越えるため、2030年を目処に準備をする
私たちは確実に変わらなければならない • 素養としてデジタルの知識を得た人材がこれからどんどん入ってくる • 当然社会は着実にデジタルを起点とした変革が連続する • これまでの当たり前を疑い、時代のスタンダード皆で考え・変化していかなければなりません • とにかく基礎体力(知識も時代に合わせてアップデート) • そのためには次の3つの発想をやめ、明日からでも変化をしていきましょう! • いそがしい・お金がない・うちの職場には向いていない
もっとみなさんを「あおる」ならば・・・ 本日話している要素はすべて今の高校で学べますw • 情報社会の特徴や現状 • 現代社会における問題とその解決手順 • 情報社会における法律と制度 • 情報セキュリティ • 情報通信を利用したコミュニケーション • データの扱い方や活用方法 変わりましょう。変わらないとまずい。
改めて自分がブレーキになってしまっていないかも「常に」確認する 狩猟社会 農耕社会 工業社会 Society1.0 Society2.0 Society3.0 縄文時代 江戸時代 明治・大正・昭和 赤旗法(1985-1896) ChatGPT 19世紀後半の英国。馬車関連業者の権益を保護するために自動車を規制。 郊外では6km/h、市街地では3km/hの速度制限。自動車は、赤い旗を持って車両の55m前方を歩く。 赤旗法 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』を筆者改変
ということで本日最後の質問です 地方自治は誰のために、ですか?
地方自治法第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを 基本として、地域における行政を自主的かつ総合 的に実施する役割を広く担うものとする。
結論 私たちは デジタル化が目的では無く まちづくりが目的 街に住み続けるためにデジタル「も」 みんなでどんどん活用しましょう!