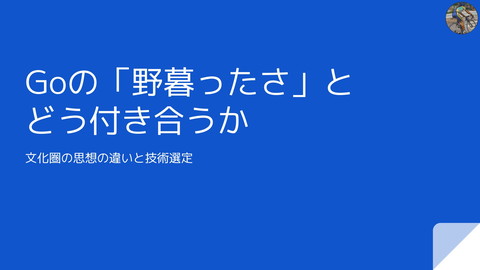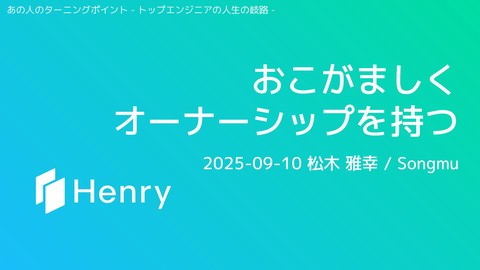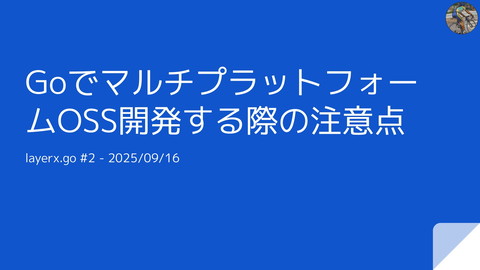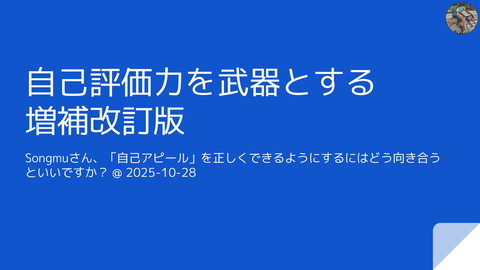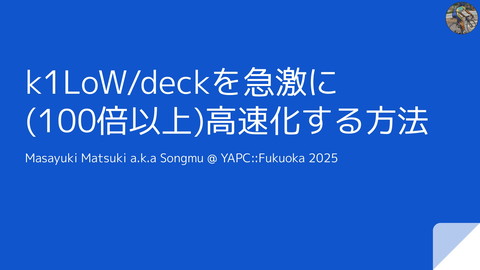自己評価力を武器とする
77.6K Views
September 26, 25
スライド概要
GitHubber, OSS作家。Tech SaaSのPdM、スタートアップ取締役CTOや外資スタートアップのIC等を経験後現職。好きな言語はGoとPerlと中国語で雑なOSSを200以上量産している。3 times ISUCON winner. 著書「みんなのGo言語」共著他。Podcast https://oss4.fun
関連スライド
各ページのテキスト
自己評価力を武器とする LAPRAS レジュメブラッシュアップ講座 @ 2025-09-24
自己紹介 松木 雅幸 (@songmu) ● フルサイクル開発組織支援 / OSS作家 ○ ○ ○ ● ● ● ● 株式会社ヘンリー フェロー MOSH株式会社 技術顧問 株式会社DELTA 技術顧問 200+ OSS Developer / 3 Times ISUCON Winner 入門監視 付録C 執筆 「みんなのGo言語」共著者 Podcaster: ○ 趣味でOSSをやっている者だ
これまでのキャリア エンジニア採用自体には10年以上関わっています。 それぞれの立場の経験からお話します。 ● ● ● ● ● ● エンジニア経験 転職経験 人事評価マネージャー経験 採用面接官経験 経営者(CTO)経験 人事経験 市場価値スコアが技術力スコアに比して低い → 私もレジュメのブラッシュアップが必要…
給与と価値 企業側の力学と思惑を理解する
給与とは企業にとっては投資である ● ● 会計上は「コスト」であることの問題点がピープルウェアに書かれている その人が将来的に出してくれるであろう価値の「期待値」に対する投資 ○ ○ ● 給与より「価値」が上回るという期待がある ○ ● だから新人にもいきなり安くない給与を払う 新卒の場合は多くは長期投資である ■ 投資なのだから回収できずに退職に至ることもある 価値は単純な金銭的利益とは限らない スキルに対して支払われているわけではない ○ その人がどういう成果と価値を出してくれそうかに着目している
給与と賞与の違い ● ● 給与は未来の期待値に対して支払われる 賞与は過去の成果の分配 ○ ● 賞与が無い会社もある ■ 給与で十分に報いているという考え ■ 無配当株みたいなもの 歩合(インセンティブ)は成果に対する報酬 ○ ○ 成果を金銭換算しやすい場合に有効 単純労働のアルバイトなどもこれに近い
給与は目標達成に対するご褒美ではない ● ● 当人が出してくれるだろう価値への期待値の現れ 成果による昇給も「将来の期待値」に対して行われる ○ ● 目標達成しても成果が価値に繋がっていないのであれば評価されない ○ ○ ● 「今季の成果からして、今後も継続的に成果を出してくれるだろう」 目標設定はあくまで「計画」なのでそれ自体確実ではない ■ 目標設定が絶対的に正しいと思うのは「アジャイル」ではない 結局その上で出てきた成果と価値に対して評価される ■ 評価制度が機能していない場合も多いが… 偶然の要因が強そうな大きな成果に対しては昇給ではなく賞与で報いる
「価値」とは誰かにとっての幸福である ● お金ではない ○ ● 誰にどのような幸福を与えるかが企業のレゾンデートルとなる ○ ● 組織や個人によって物差しが異なり、定める必要がある 本当に「世の中」に良い影響を与えられているかは問いかけるしかない ○ ● 世の中に何か良い影響を与えられているか 自己完結できない 継続的な価値創出のために合理性が必要 ○ 経済合理性は大事
直接的・間接的な様々な「価値」がある 「三方良し」の精神。その上でどこに重点を置くかが企業哲学となる。 ● ● ● 世の中が幸せになること 顧客が幸せになること 社員が幸せになること 企業としては従業員のそれぞれの営みが全て何らかの価値に繋がっていると考 えたいし、そういう組織作りをする。
具体的な成果と抽象的な価値 ● ● ● 「アウトカム」と「バリュー」と書かれることも 成果は定量的で価値は定性的とも言える 成果が価値にどう繋がるかの解釈には 企業理念 が反映される ○ ○ ○ ある意味恣意的 議論を尽くす・納得性を高める必要性 永遠の課題
企業側の思惑 ● 価値に見合わない投資はしたくない ○ ● 企業の価値創出に貢献してくれる人を採用したいし評価したい 投資のリターンを最大化したい ○ ○ その人が最大パフォーマンスを発揮し、雇用し続けられる適正な給与を払いたい 少し露悪的に言うとその上で最低限の報酬にしたい
市場価値や相場 ● 企業は適正な報酬を払いたい ○ ● 企業側も個人側も市場価値をベースに交渉することになる ○ ● 社員が満足に暮らせ、モチベーションを保て、転職されない 職種やレベル感に応じた相場が存在する 相場に満たない場合 ○ ○ 当人はモチベーションを保ちづらくなり、転職リスクが高まる 新規採用が難しくなる
市場価格高騰の落とし穴 ● 職種間の市場価格格差は否応無しに社内にも持ち込まれる ○ ○ ● 企業が市場価値の高い職種への入札競争に付き合いすぎるのもリスク ○ ○ ● 社内格差がモチベーション問題を引き起こすことも 頭が痛い問題 消耗戦になり限界もある ITエンジニアで市場価値を上回る給与を優位性にできる企業は一握り 企業はコスパの良い人材を探す「マネーボール」戦略をとりたい ○ 自社に価値をもたらせられる職種の人に、市場価格より高い報酬を支払う ■ それが優位性や競争力になる
企業だって給与は満足に支払いたい(はず) ● ● ● 従業員の幸せを望んでいるし、良い成果を出した人を労いたい意識もある モチベーション高く仕事してもらった方がパフォーマンスも出る 成果を出している人に報酬を出さないと採用市場でも不利になる ○ ● 成果出している人を安い報酬で雇っていると同等以上の人を雇えない 雇用創出の社会的責任もある そうじゃない会社からはさっさと逃げましょう。
評価制度の重要性 ● 価値を出した人を適正に評価する・評価される状況を作る ○ ● 評価の場は「具体的な成果」と「抽象的な企業文化や価値観」との接合面 ○ ○ ● それがどのような「価値」を生み出したのかを確認する場 価値創出の定義は曖昧であり、企業によって異なる 価値を議論する 組織学習・経験学習 の場 ○ ○ ● 自分たちにとって優秀な社員のモチベーションを毀損しない 各自が「価値」を解釈・説明するトライをする それが、組織の生産性を高める とは言え、時間をかけすぎるのは良くない ○ ○ 省力でやりつつ、なあなあにはしない やらないで先延ばしにしすぎると組織へのダメージが大きくなる
組織側: 評価基準を明確にする ● ● 会社にとっての価値とは何なのか・どういう人を評価するのか 評価基準に一貫性が乏しいと信頼を失う (人間と同じ) ○ ● 必ずしも定量化する必要はなく、価値観と文化が大事 ○ ○ ● MVVを各人が継続的に意識して解釈、認識合わせをする どういう人が評価されるかには「会社の個性」が出る 社員に成果説明の機会を与える ○ ● 変わる場合は説明する責務がある それを省力に実行できる仕組みを提供する 社員を適正に評価することがモチベーション向上や成長に繋がる ○ 言うは易し…
個人側: 成果や価値を説明可能になる ● 評価制度の有無とは実は関係ない ○ ● 目標設定は自分の成果を説明可能にするための一つの手段 ○ ○ ● 目標設定をやりたくない気持ちもわかるし、成長のために常に有効だとも限らない 状況が変化して意味がなくなった目標に固執しても意味がない ○ ● 目標を達成することでどういう価値を会社にもたらせるのかまで意識したい 会社の価値観を理解する 目標設定は評価に関わらず成長速度を上げるための有効なツール ○ ● 自分の成果を書き留めておくの大事 (忘れてしまう) 目標を破棄して、別の成果を出した方が評価は高くなるケースも 目標の達成度ではなく 「成果」で語る
自己評価スキルと言語化スキル 評価に向き合う
適切な自己評価と言語化 ● 自分の成果や価値の説明を試みることは重要 ○ ○ ○ ● 説明することで成果への理解度が上がる フィードバックサイクルが速くなる 説明能力・抽象化力・再現力が高まる これは転職でも社内評価でも重要なスキル
評価はエライ人の仕事でしょ? ● 「高い給与をもらっているんだから」それがあなたの仕事でしょ? ○ ○ ● でも残念ながら「他人の評価力に期待しすぎ」 ○ ● 人を評価するのはとても難しい 期待するのは良いが、期待通りにならなかったことは自分で受け止める ○ ● その通りで評価は大事な仕事 だから「ワタシのやることではない…?」 暗黙的に期待して勝手に裏切られたと感じて感情を損ねるのは建設的ではない エライ人だって多くは適正に評価したいと思っている ○ ○ 「無能で十分説明されることに悪意を見いだすな」ref. ハンロンの剃刀 ■ 「無能」は言葉が強いが、人間は常に未熟である 上司は全然スーパーマンではない
評価を他人に委ねない ● 自分がアピールせずとも評価してくれる? ○ ○ ● 「マネージングアップ」して自分から働きかける ○ ○ ● そんな幸せなことは稀有なので、その状況に恵まれているのであれば大事にする 評価して欲しいのであれば、そのための努力をする 「この成果は価値に繋がっていますよね」 何が価値なのかは曖昧だし流動的なので細かくすり合わせする 様子見はアピールの労力とのリスクリターン上穏当な選択肢ではある ○ ○ 期待値以上のリターンが得られる確率は低くなる それで期待に届かなかったことを嘆くのはナンセンス
適切なアピールは実は周りも嬉しい ● 会社やマネージャーと自分達は一対多の関係 ○ ○ ● 適切に成果説明してくれるとマネージャーはめちゃくちゃ助かる ○ ○ ● マネージャーの可処分時間が増える 評価の精度が高まるし、他のメンバーを評価する時間も捻出できる ■ 自分にも周りの同僚にとっても嬉しい 察してもらおうとしない ○ ● メンバー以外のステークホルダーもいるし、事業を見るのが主 経営者やマネージャーは忙しい・度量が求められる 少なくとも「察してもらえなかった」ことにガッカリするのは愚か 同僚を称賛する・アピールに協力することも大事 ○ これは「自分がより働きやすく」する為でもある
現場のキーマンを会社が外してしまう問題 ● なんであの人辞めさせちゃったの…? ○ ○ ● 「会社は現場が見えていない」 ○ ○ ● マネージャーはあなたが思っている以上にスーパーマンではない そこに期待しすぎるのもまた無能である 自分たちがその人の価値を説明できていれば、問題を回避できたかもしれない ○ ○ ● その通り! 現場を見ることはマネージャーの仕事の一部にすぎない キーマンを外したのは無能だが、そこに悪意を見いだしても仕方がない ○ ○ ● 評価されないので転職してしまう、みたいな話も SNSで定期的に話題になる「ごんぎつね」的逸話 同僚を称賛することの重要性 会社の判断が正しかった可能性もある その上でコミュニケーションが成り立たないこともある ○ 価値観がどうしても合わないのであれば転職等を考えましょう
アピールすること 自己評価して説明して精度を上げる
アピールは程々に ● ● ● あまり労力をかけずに勝手に評価が上がって行って欲しいですよね 打算的になりすぎないほうが幸福度が高いという話もある 心が濁らない程度にやる
アピールしたくなさ 分かります ● ● ● あまり目立ちたくない・チャラチャラしたくない プレゼンスばかり高くて技術力が皆無の中身が無い人間になりたくない 職人肌の潔癖さと裏腹の斜に構えた冷笑主義 ○ ○ ● 身の丈に合わないアピールすることはカッコ悪い 目立ってばかりのヤツはダサい 文化的な背景もあるかも ○ ○ 「アピール・自己主張するな」という教育 それでいてアピールして評価されている人を見るとズルく見える
何故アピールを厭うのか ● ● 疲れる・メンタルが削られる 必要以上のアピールしている人がバカに見える ○ ● 苦労してアピールしても見合うかが分からない ○ ● 自分もバカに見られたくない 評価されなかった時のダメージも大きい 出来ればアピールせずともいい感じに評価されたい ○ ○ 様子見は傷つかない賢い選択肢ではある ■ ローリスクローリターン ただし、勝手に期待して勝手に失望しないこと
人間は思っている以上に失敗を恐れる生き物である ● 特性として受け入れるのが良い ○ ● 経験を積んだ専門家ほど、失敗や自分の弱みを見せることを恐れるようになる 「失敗を恐れていない」と言う人の多くは「弱い自分の開示」を恐れている
「錯覚資産」という苦い嫌な言説 ● ● 人生は運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている 早くアウトプット・アピールした人のほうがフィードバックサイクルが速く回る ○ ○ 錯覚資産をレバレッジにして成長機会を多く得た人の方が成長が早い 最初に実力差があっても結果的に実力も逆転してしまうケースも多い
「過大評価よりも過小評価を恐れる」 ● 私が尊敬しているスーパーエンジニアの言葉だったはず ○ ● 控えめな人は過小評価を恐れたほうが良い ○ ● 出典はネット上に残っていない アピールしすぎる失敗よりも、 アピールしないことによる失敗を恐れた方が良い 評価して欲しいのであれば頑張る ○ 今の評価で程良く満足しているのであれば別に頑張らなくても良い ■ ただ、それが持続的かどうかは気にかけた方が良いかも
他者からの評価を受け入れる 社会生活においては他者からの評価によって、あなたの社会上の人格が決まる ● ● ● 自己評価を評価してくれる他者がいないと自己評価も成り立たない 他者からの評価はその人から見た「一面の真実」であることは受け入れる そこには常にギャップがあり、時には痛みを伴う ○ ○ そこのしっぺ返しがアピールに前向きに取り組みたくない理由でもあるが… ■ 自分自身への期待値を高くしすぎないのも大事 ■ ここも期待値コントロール ギャップは受容しても良いし、ある程度は受容する必要がある
自己評価と他者評価のギャップ ● ギャップを解消したいなら自らアクションをする ○ ○ ○ ○ ● 自己評価を高くしすぎるとギャップに苦しむ可能性は高まる ○ ● 自己評価を見直して現実に合わせる 研鑽して実力を上げる アピール方法を改善する より良い適切な評価をもらえそうな環境に移る 低く設定することによるギャップに苦しむケースも。ref. インポスター症候群 ギャップの痛みの解消が自己成長に繋がるのは事実 ○ ○ 痛みが少ない位置に自己評価を留めるのも1つの選択だし、その見極めは大事なスキル 人生における仕事やキャリアの優先度は人によって異なる
アピールは疲れるし大変だが大事 ● ● めんどくさいし否定される恐怖もある 自己評価を外に問いかけないと、正しい自己評価に繋がらない ○ ● ● ● ● 自己満足に留まってしまう 自分に合った無理の無いアピール方法を見つける 適切に主張しないと期待値以上に評価してもらえることはなかなかない フィードバックサイクルを多く回したほうが精度も実力も上がりやすい 程々にしておくのも本人の選択 ○ リスクリターンを考えてやる
あなたの価値は何か 適切な自己評価と説明能力が望ましい職務機会を生む
スキルの絶対的値段は存在しない ● ● 市場価値や相場はあるが、結局「価値」の話になる 残念ながら同一スキル・同一給与ではない ○ ○ ● 同等の実力のプロスポーツ選手であっても所属チームで倍以上の年俸差があることも いわんやビジネスパーソンをや、である 高く買ってくれそうな企業に売り込むのも戦略の一つ ○ ○ 活況な業界を渡り歩く 裕福なプロスポーツチームに所属するのと似たような話
スキル購買モデル ● 企業がスキルを買い、価値に転化する ○ ○ ● その価値転化ロジックを理解できるとキャリアの可能性は広がる ○ ○ ● そのスキルを価値に転換する型が企業内で定まっている場合 個人は汎用スキルを高いレベルで保持しているだけで十分高く買ってもらえるケースも 逆に理解できていないと社内のビジネスモデル変化時に評価されなくなるリスクも高まる 汎用スキルであれば転職でカバーはできる スキル購買モデルに個人が依存しすぎるのはリスク ○ ○ ○ 特に単一スキルの場合 受容できるリスクであれば良い キャリアアップを志向するならブロッカーになる可能性は高い
誰がスキルを価値に繋げるか ● 企業にスキルを価値に繋げてもらう ○ ○ ● スキル購買モデル 企業は「価値に繋げられそうなスキルを持っているか」を見る 個人でスキルを価値に繋げる ○ ○ ケイパビリティ 企業は「スキルを価値に転じた経験があり、再現できそうか」を見る グラデーションではあるがケイパビリティに自覚的な人の方が企業からの評価 は高くなるし、キャリアの応用も利く。
企業は具体的な成果から あなたの価値を評価する 「振る舞いから実力を想像する」とも言える。表出したモノからしか評価でき ないし、評価してはいけない。 ● ● 成果として語れるエピソードを持つ 自分のやったことが、どのような成果を生み、価値に繋がっていたか ○ ● やったことの羅列ではなく、成果と価値に繋がったストーリーを語れるか 技術スキルも保持を表明するだけでは片手落ち ○ ○ ○ そのスキルを身に付けた背景 スキルを活用した経験 そのスキル自体の強みや価値を説明できるか
あなたの価値はなんなのか自問する スキルや特性や振る舞いが世の中にどう良い影響を与え得るか、与えていたか ● ● ● ● 自分がどう考えてどういう行動をしたか 自分がやったことの意義を理解していたか その結果どうなったのか ケイパビリティの説明は定性的で良いが、アウトカム説明は定量的に
外に問いかける ● 「自分の成果はこれで、自分にはこういう価値がある」 ○ ● 「どう思いますか?」を率直にぶつける ○ ○ ● 伝えて相手とすり合わせる 会社もそういう機会を十分に用意すべき 自分の価値を説明することで、自分の価値への解像度も上がる ○ ○ ● つたなくて良いから説明の場数をこなす 何事も説明することで理解度が高まる 自己成長につながる 会社の価値観や評価基準への理解度も深まる
同僚や先輩や上長の力を借りる ● フィードバックをもらう ○ ○ ● 社会人歴の浅い人に会社のバリューストリームの理解は難しいケースも ○ ○ ● 自分の強みは何なのか 自分の行動がどのような成果や価値に繋がっているか 残念ながら情報格差も存在する 透明性高くありたいが… マネージャーはメンバーの成果の言語化に協力する ○ チーム力・組織の力の向上につながる
体外発信がやりやすいエンジニアはお得 ● 自分の価値を社外にも問える ○ ● ● セカンドオピニオン的 自分を評価してくれる人が見つかることも 好きでやってることが評価につながることも
会社側の評価力の重要性 ● 会社側も社員を適切に評価できることは強みになる ○ ● 評価は結局納得感 ○ ● それぞれが労力を払わずともいい感じに評価できるのが理想 評価制度を定めないのも1つのやり方 ■ ただ、給与の差があるのであれば、暗黙的に評価がなされているということ ● 経営者の一存で決める方法は経営者が評価しているということ ● スタートアップ初期は全然それで良いと思う ■ 全員同一給与であれば評価が無いと言えるかもしれない ● ただ、それは全員が同じ価値を出していると全員が信じきれるかどうかにか かっており、スケールは難しそうに思う 会社側も試行錯誤して悩んでいることも多い ○ 完成形はないし、会社も常に未熟である
まとめ
自己評価力を磨き続ける ● ● ● ● ● 曖昧な「価値」を意識する 自分の価値は何なのか、どういう価値を創出できるのか ちゃんと周りに問うて説明能力を鍛える 他人が決めた値段ではなく、自分で値付けできるようになりたい 私もできているとは思っていない
(宣伝)このスライドは k1LoW/deckで作られました ● k1LoW/deck ○ ○ ○ MarkdownからGoogle Slideを生成するツール 私もメンテナとしてアクティブに開発に関わっています 是非ご利用下さい!
(宣伝) スポンサー募集 色々OSSを開発・メンテナンスしています。$1のワンショットでも嬉しいの で、活動を支援してくれると嬉しいです。 ● GitHub Sponsor ○ ● https://github.com/sponsors/Songmu ghq handbook ○ ○ https://leanpub.com/ghq-handbook https://zenn.dev/songmu/books/ghq-handbook
- https://www.google.com/url?q=https://github.com/sponsors/Songmu&sa=D&source=editors&ust=1758889584906521&usg=AOvVaw1n8sx9jFV5LKs6Br0xankl
- https://www.google.com/url?q=https://leanpub.com/ghq-handbook&sa=D&source=editors&ust=1758889584906820&usg=AOvVaw08MOBfXEe-vuECi_1LHHAA
- https://www.google.com/url?q=https://zenn.dev/songmu/books/ghq-handbook&sa=D&source=editors&ust=1758889584906962&usg=AOvVaw0OuiQkEexmbM2oSIY4hdCj