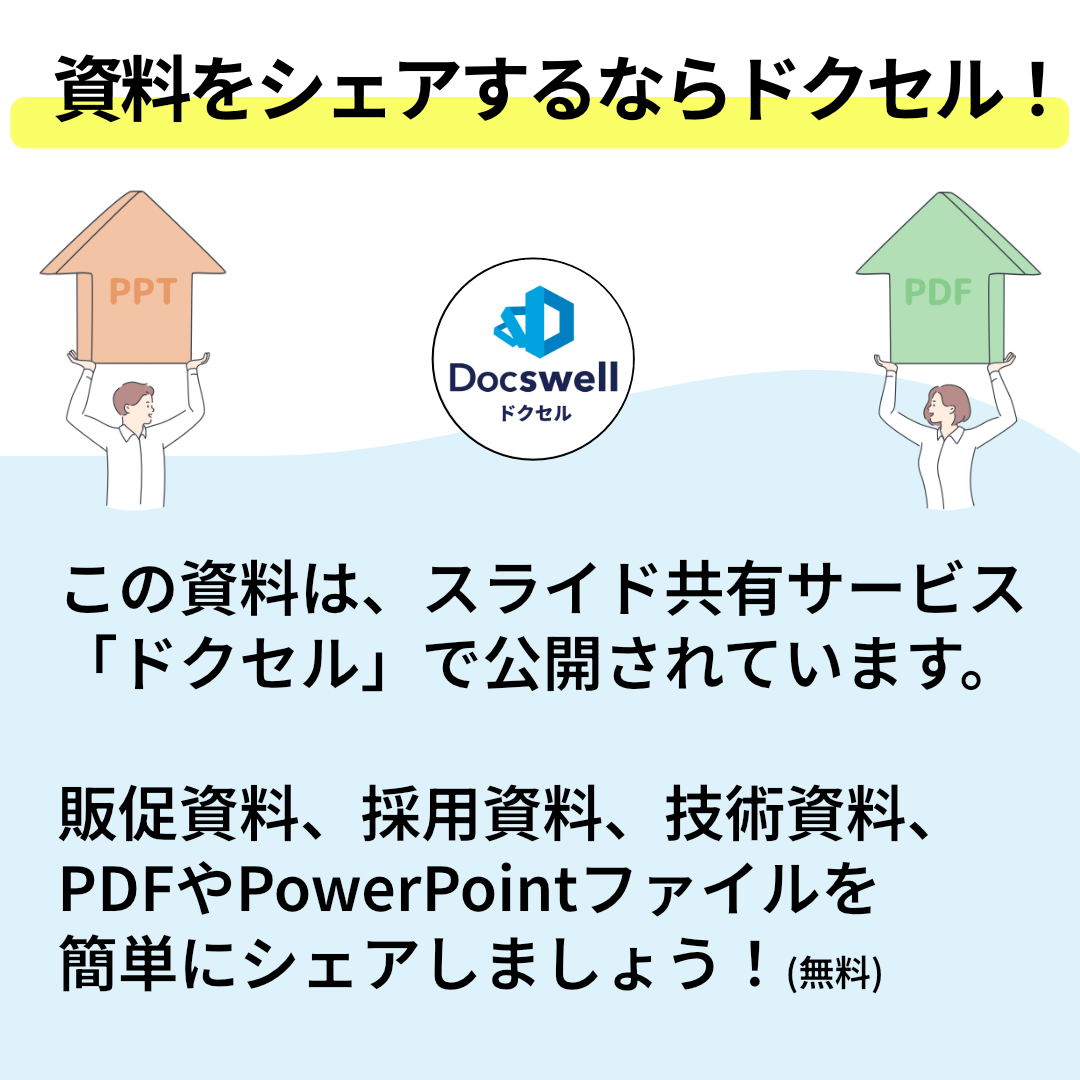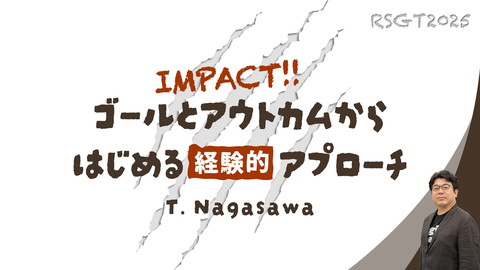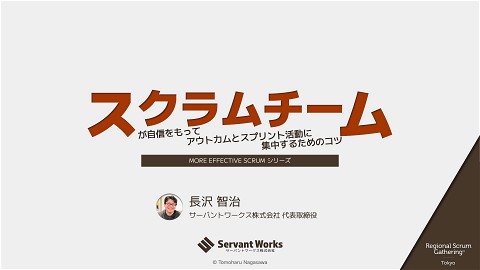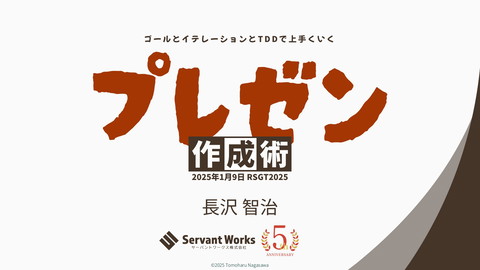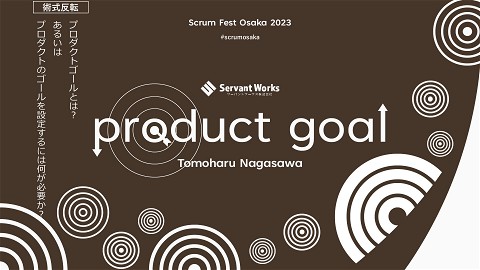Agile Kata 2.0 (Japanese)
633 Views
June 11, 25
スライド概要
アジャイルのカタの旧バージョンのホワイトペーパーです。現行版とは異なりますのでご注意ください!!!
サーバントワークス株式会社 代表取締役/アジャイルストラテジスト/アジャイルコーチ/エバンジェリスト プロフェッショナルスクラムトレーナー(PST) Agile Kata Pro 認定トレーナー DASA DevOps 認定トレーナー EBMガイド、カンバンガイド、フローシステムガイドなど多数を翻訳 監訳:『More Effective Agile』『Adaptive Code』『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』『アジャイルソフトウェアエンジニアリング』 翻訳: 『EBM実践ガイド: アジャイルマネジメントフレームワーク』『プロフェッショナルアジャイルリーダー』 執筆: 『Keynoteで魅せる「伝える」プレゼンテーションテクニック』 講演や支援のご相談はぜひお気軽に(ご相談は無料です)!
関連スライド
各ページのテキスト
2. 0 バ ージ ョン ビジネスアジリティの実現へ
ビジネスアジリティの実現へ バージョン 2.0 2022年3月31日 ニューヨーク Joe Krebs 日本語翻訳 長沢 智治 agilekata.org 2
はじめに 武道に起源を持つ「カタ」は、意図的に反復練習を行うことで、ある形式を習得するものである。ビジ ネスにおいては、継続的改善の基礎となるカタのパターンがある。カタを実践することで、企業文化を 転換するための新しい習慣やスキルを身につけることができる。これらの基礎となるカタは、「改善の カタ」と「コーチングのカタ」と呼ばれる。これらの起源はトヨタのモノづくりにある。 「アジャイルのカタ」は新しいものであり、基礎となる2つのカタを中核とし組織変革を推進するもの だ。さらにアジャイルのカタは、方向性を示すアジャイル宣言(アジャイルソフトウェア開発宣言)と アジャイルリーダーシップのスタイルを結びつけるもので、基礎となるカタを拡張している。これによ り、アジャイルのカタを自己管理、自律したチーム、価値に基づく計測、コラボレーションツールと手 法、アジャイルコーチングの姿勢に関する新鮮な見方といった重要な関心事と間接的に繋げている。 背景 アジャイルのカタの目的は、アジリティを高めることである。アジリティを高めることは、① 個人、② チーム、③ 組織内のより大きなグループに対して影響をもたらす。これらの3つすべてに共通している のは、人々の振る舞いを変え、新しい習慣を作り出すということだ。新しいことを学び、社内の特異な 状況に直面し、それに加えて、人々と仕事をすることがアジリティの導入を複雑なものにしている。 「探索-把握ー対応」は複雑さに対して効果的に対処する適切な手法であり、決まりきった解決策やテ ンプレートがあるわけではない。このため、アジャイルのカタでは、改善のカタを中核として「探索ー 把握ー対応」を行うことで、変化をうまく乗り切るためのパターンを提供する。10年以上にわたって繰 り返し実証されてきた改善のカタは、アジャイルのカタの支えとなっている。アジリティを高めるに は、アジャイル宣言から読み取ることができるアジャイルの定義に、より注目する必要がある。アジャ イル宣言における価値基準と原則は、アジャイルのカタの方向性を示しているが、同時に、アジャイル のカタを実践している最中にも、その価値基準と原則を適用し続けることを意識させている。それはど ういうことだろうか。 まず、アジャイル宣言の価値基準と原則が変革の最中に適用され、従っていると、その選択したプロセ ス自体がアジャイルになる。我々の経験によれば、ほとんどのアジャイル変革のプロセスは、特定のア ジャイルプロセスに従っているわけではないのである。「計画に従うことよりも変化への対応を価値と する」の記述は、アプローチそのものがアジャイルでなければならないことに気づかせてくれる。組織 のアジリティを達成する場合にも言えることだが、変革の取り組みの当初から、改善の最終状態が明確 に定義されているわけではないだろう。仮に組織のアジリティを高めることに注力しないと判断したと しても、それでやることがなくなったというわけではない。 次に、アジャイルのカタを実行しているときに用いる手法や解決策は、我々が築きたい文化を描写する ものであるべきだ。例えば、トップダウン型のリーダーシップスタイルなコマンドコントロール環境で アジャイルのカタを実行しているとしよう。どのようにしたら自己管理と自律したチームの文化が生ま れてくると期待できるのだろうか。アジャイルリーダーシップと自己管理、感情知性(EQ)、エンパワ ーメント、グループコラボレーションを促す手法は、アジャイルのカタを実行する際の重要な要素とな る。 3
大枠としては、カタとアジャイルは、アジャイルのカタの2つの主要な要素であると言える。このホワ イトペーパーの目的は、アジャイルのカタを紹介し、経験を共有し、アジャイルのカタへ取り組むこと を促すことにある。現在、我々はアジャイルのカタの3つの異なる活用法を模索している。アジャイル のカタそのものを紹介する前にそれらを見ていこう。 1. アジャイル変革 2. 組織的な改善 3. アジャイルチーム 1. アジャイル変革 このアジャイルのカタは、組織をアジャイルに変革していくためのマクロのレベルでの指針を示すパタ ーンである。多くの企業は、グローバル市場のスピードがますます速くなっていることに自らを適応さ せるために、より機敏になることが求められている。変化の頻度とは、ビジネスの世界での進化によっ て引き起こされることが多いかもしれないが、自己組織化や自律したチームでの仕事を含む新たなリー ダーシップスタイルへの反応が引き起こすこともある。アジャイルのカタは、これらのニーズに対応し ており、組織が完全なビジネスアジリティへと移行するためのアプローチを提供する。アジャイルのカ タは、ゴール設定、実行、インパクトの計測を行なうことで、リーダーがコミュニケーションを図り、 有意義な変化を推進するのに役立つ。アジャイルのカタは、リーン生産方式、アジャイルのムーブメン ト、サーバントリーダーシップにおける数十年の経験に基づいて構築されている。 2. 組織的な改善 ミクロのレベルでは、アジャイルのカタは、アジャイルチームがレトロスペクティブ後や組織的な障害 物に反応するための継続的な改善活動を推進するのに役立つ。スクラムのようなアジャイルプロセスの フレームワークは、課題を明らかにし、プロセスの改善点を見つけ出すのに優れているが、アジャイル チームには、それらの課題や改善点を効果的にやり繰りする方法についての指針は持ち合わせていな い。アジャイルのカタは、組織的な改善点を具体的で、透明性があり、計測可能なものにする活動を並 列に行うことで、このギャップを埋めることができる。 3. アジャイルチーム 最も抽象的に改善を考えるとするならば、ある新しいプロダクトの機能とは、そのプロダクトの改善点 と捉えることができる。つまり、ある機能を持たないということはビジネスにとっての問題であり、そ の機能を作ることでその問題が解決する。創造性が高く、自己管理されたチームは、非常に効果的に問 題を解決できる。それゆえ、プロダクト開発の取り組みを、一連の問題提起や機能依頼に落とし込んで みてはどうだろうか。アジャイルのカタは、一番高いレベルでの実験と自己管理の自由を享受するチー ムにとって、非常に軽量なアジャイルのプロセスとして機能する。 4
アジャイルのカタ 中核 アジャイルのカタの中核をなすのは、10年以上前に発表された「改善のカタ」である。この改善のカタ には、以下に示す4つのステップがある。 改善のカタを実践することで、時間の経過とともに新しい習慣を生み出し、改善を計測可能なものにす る。改善のカタは、あらゆる改善活動に対して共通するパターンだ。最初の3つのステップは短い計画 づくりの活動であり、4番目のステップは反復的なアプローチで実行することに焦点を当てている。 1. 方向性やチャレンジを理解する(Understand the Direction or Challenge) 2. 現状を把握する(Grasp the Current Condition) 3. 次のターゲット状態を設定する(Establish the Next Target Condition) 4. ターゲット状態に向かって実験する(Experiment Toward the Target Condition) 方向性あるいはチャレンジとは、定義されたビジョンに向けた一歩であり、北極星のように人々を導け るものである。チャレンジはビジョンよりもさらに具体的で、文字通り必ずしも容易に、あるいはすぐ に達成できるものではない。改善のカタの強みのひとつは、現状を定義するためのステップがあること だ。多くのチームが、現状を顧みることなく、すぐに解決策を模索したり、すぐに実装したりしている のではないだろうか。現状を把握するためには、計測が必要となる。確かなデータがなければ、自身の 改善が効果的であったことを後でどのように知ることができるだろうか。自身がどこにいるかがわかれ ば、次にどこにいたいのかを定義することが可能だ。改善のカタでは、次のターゲット状態を設定する ことでこれを実現している。現状とありたい姿の差分を定義できれば、実験を行うことができる。実験 は、困難な道をたどることもあるが、それだけアプローチが創造的であることも示している。定期的に 実験を振り返る反復的なアプローチは、非常によい方法である。 5
アジャイル宣言 アジャイル宣言の12の原則を示すアイコン アジャイル宣言は、2001年以来、我々のコミュニティ全体に方向性を示してきた。アジャイルのカタの 実践者が方向性、現状、次のターゲット状態などを決定するときには、アジャイルの価値基準と12の原 則が拠り所となる。これらの原則とは、実験を行う際の基準となるもので、例えば、「意欲に満ちた 人々を集めてプロジェクトを構成します。環境と支援を与え仕事が無事終わるまで彼らを信頼します」 や「シンプルさ(作らなくて済む量を最大限にすること)が本質です」(※訳注: 原典は、「ムダなく 作れる量を最大限にすること」とあるが、英語原文に合わせて訳者にて変更している)がある。 アジャイル宣言の12の原則は、現状や次のターゲット状態を計測する際にも用いることができる。例え ば、「ビジネス側の人と開発者は、プロジェクトを通して日々一緒に働かなければなりません」や「情 報を伝えるもっとも効率的で効果的な方法はフェイス・トゥ・フェイスで話をすることです」がある。 これらは、進捗を計測するために原則を用いるほんの一例にすぎない。 アジャイル宣言では、価値に関して「計画に従うことよりも変化への対応を」のように、左記の価値よ りも右記の価値を適切とする明確な立場をとっている。記載されているそれぞれの価値を計測すること は難しい場合もある。アジャイル実践者に(左記のことがらよりも右記のことがらに価値をおくとい う)方向性を与えているが、具体的にどうデータを数値化するかが決められないからだ。 一方で、価値基準の背後にある原則は計測可能な指標となる。「チームがもっと効率を高めることがで きるかを定期的に振り返り、それに基づいて自分たちのやり方を最適に調整します」という原則を例に とると、調整の回数を計測することで価値あるアウトカムを作り出せる。チームが何回振り返りを行な ったかを計測することはアウトプットにすぎない。アジャイルコーチは、価値を計測する指標の種類に 焦点を当てることが多い。例えば、エビデンスベースドマネジメント(EBMgt: Evidence-BasedManagement)だ。 EBMgtは、アジャイル実践者がアウトカムやインパクトに基づいた指標に焦点を当てるのに役立つ。し かしアジャイルのカタの文脈では、EBMgtもひとつのツールにすぎない。他の方法もあるだろう。全般 として、価値に焦点を当てることは、アジャイルのカタの実践者が作業の効果性を計測するいくつかの 意味のある指標に集中するのに役立つ。 6
アジャイルのカタにおけるリーダーシップとコーチング 製造業では、コーチングは部下である学習者と直接仕事をするマネ ージャーによって行なわれる。その関係性は、個人同士による直接 的なものになる。アジャイルでは、グループで働くため、自己組織 化された自律したチームの環境を推進している。この違いは重要で あり、アジャイル原則の「最良のアーキテクチャ・要求・設計は、 自己組織的なチームから生み出されます」として現れている。 アジャイルのカタを支持し、アジリティを推進するアジャイルコーチとは、チームと日々のコーチング サイクルにおいて、コーチングのカタから派生した次の5つのコーチングの質問を用いて探究するもの だ。アジャイルのカタの文脈では、コーチングの対象は一個人ではなく、チームである。 ターゲット状態は何か? 現在、実際の状況はどうなっているか? 今、どの障害物(ひとつだけ)に取り組んでいるのか? 次のステップからどんな期待をしているか? 改善したことをどれだけ速く確認できるか? これらの質問は、チームにおける会話のきっかけとなるはずだ。コーチングサイクルが20分を超えない ように、アジャイルコーチがファシリテーションを行う。アジャイルコーチは、2つ目の質問の後、上 記の質問に戻る前にさらに明白にするための4つの質問をすることもできる。これによりチームが取り 組んでいる障害物についてチームとともに深く掘り下げることができる。 1. 前回のステップとして計画したことは何か? 2. 何が起こると期待していたか? 3. 実際に起きたことは何か? 4. 学んだことは何か? コーチングサイクルの間に、アジャイルコーチとチームは、ストーリーボードを用いて作業を振り返る ことになる。チームは、障害物に取り組むためにいくつかの実験を必要とすることがほとんどである。 それゆえ、ひとつの障害物を日々のコーチングサイクルで複数回にわたって対処していくこともある。 7
アジャイルスターターのカタ アジャイルのカタを始めるための前段階での障壁や余計な活動は存在しないので、いつでも始めること ができる。アジャイルのカタとは、最初から最後まで行うような方法論ではないからだ。アジャイルの カタを組織的な改善に用いようとするリーダーは、スクラムのような既存のプロセスを阻害することな く、アジャイルのカタを実践し、その恩恵を受けることができる。アジャイルチームやアジャイル変革 にも同じことが言える。 アジャイルのカタは、既存の開発プロセスを壊すことなく、チームを個別のチャレンジに集中させるこ とができる。その一方でアジャイルのカタの結果は、既存のプロセスに影響を与えることになる。それ はもちろん、より高度な組織的なアジリティにつながるため、望ましいことである。 タイミングだけでなく、アジャイルスターターのカタには、新しいチームをこの新たな働き方に適応さ せるための一連の基本的な活動が盛り込まれている(※訳注: アジャイルスターターのカタとは、アジ ャイルのカタの始め方を示したもの)。経験豊富なアジャイルコーチは、プラクティスを拡張する前 に、チームが基本的なプラクティスを繰り返すことを支援するものだ。これはダンスを習うときと同じ で、新人のダンサーは、基本ステップの流れから始めて、より複雑なステップを加えていく。基本を疎 かにしたり、基本に留まりすぎたりすると、アジャイルのカタの結果が中途半端になる可能性がある。 アジャイルコーチは、チームとともに高い成果を目指し取り組むことになる。また、新しいチームのキ ックオフにアジャイルスターターのカタを用いることになる。 アジャイルのカタの解説に基づいてステップ・バイ・ステップで実践することは、非常によい出発点と なる。最初に扱いやすいチャレンジに焦点を当てることで、最初のアジャイルのカタのサイクルがさら にわかりやすいものとなる。 まとめ アジャイルのカタは、アジャイル、リーン、リーダーシップのそれぞれのコミュニティでよく知られて いる実証済みのパターンに基づいて構成されたプラクティスである。そのカタは、アジャイル変革、組 織的な改善、プロダクトチームにおける支援を求めるすべての人のための言語となることを意図として いる。アジャイルのカタは、繰り返すことで、組織をより高いレベルのビジネスアジリティへと導き、 変化へ反応することから変化を主導することに移行できるハイパーパフォーマンス企業へと変貌させる ことができる。 アジャイルのカタを採用している組織は、個人とチームが本来発揮できる能力に着目し、その結果とし て、従業員満足度とエンゲージメントが向上し、アジャイルな文化が醸成されていく。アジャイルのカ タ自体は、規範的なものではない。それぞれの企業が独自の手法を取り入れるのに十分な余地と創造性 を残している。 8
ライセンス Agile Kata © 2022 Joe Krebs クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示-継承 4.0 国際) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Joe Krebsによる「アジャイルのカタ(Agile Kata)」は、CC BY-SA 4.0 のもとに許諾されている。 謝辞 Nils Oud 、 Daniel Hettrick 、 Mary Poppendieck 、 Tom Poppendieck 、 Pat Guariglia 、 Alexandre Boutin、Christian Capart、Evan Leybournには、このアジャイルのカタの進化の過程で時間を割いてフ ィードバックをいただいた。多大な感謝の意を表したい。また、アジャイルのカタをダウンロードし、 質問や激励のコメントをくれた方々にも感謝している。ありがとう! 参考資料 「カタ」という用語は、単数形、複数形で用いられる。本文中では固有名詞として表記している。 『Toyota Kata』 Mike Rother [邦訳]『トヨタのカタ』 マイク・ローザー 著、稲垣公夫 訳 『Cynefin』 David Snowden 「アジャイル宣言」https://agilemanifesto.org/ 『What Makes a Leader?』 Daniel Goleman 『Open Space Technology: A User’s Guide』 Harrison Owen [邦訳]『オープン・スペース・テクノロジー』 ハリソン・オーエン 著、ヒューマンバリュー 訳 「EBMgt」 https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_management 『The Wisdom of Crowds』 James Surowiecky 翻訳 このホワイトペーパーは、英語版を日本語に翻訳したものである。日本語翻訳は、長沢 智治が担当し た。また、以下の方々に翻訳レビューをお願いした。 佐々木 俊亮、花井 宏行、河原田 政典、伊藤 宏幸、佐藤 竜也、石沢 ケント、的場 聡弘(順不同、敬称 略) 翻訳に関する連絡先: 長沢 智治 ([email protected]) 9